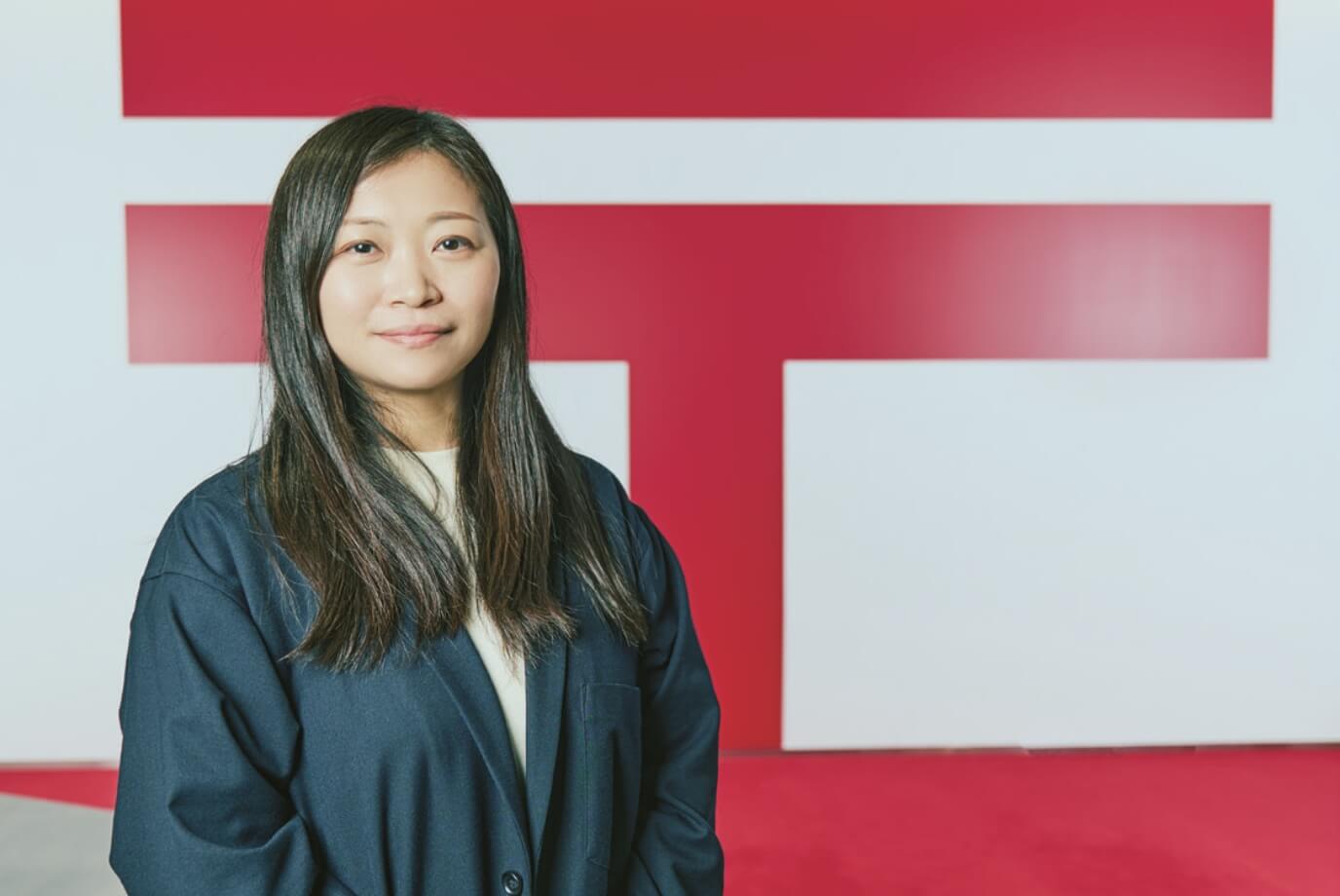Works 183号 特集 Z世代 私たちのキャリア観 自分らしさと不安のはざまで
対談 どうする? Z世代の「育て方改革」
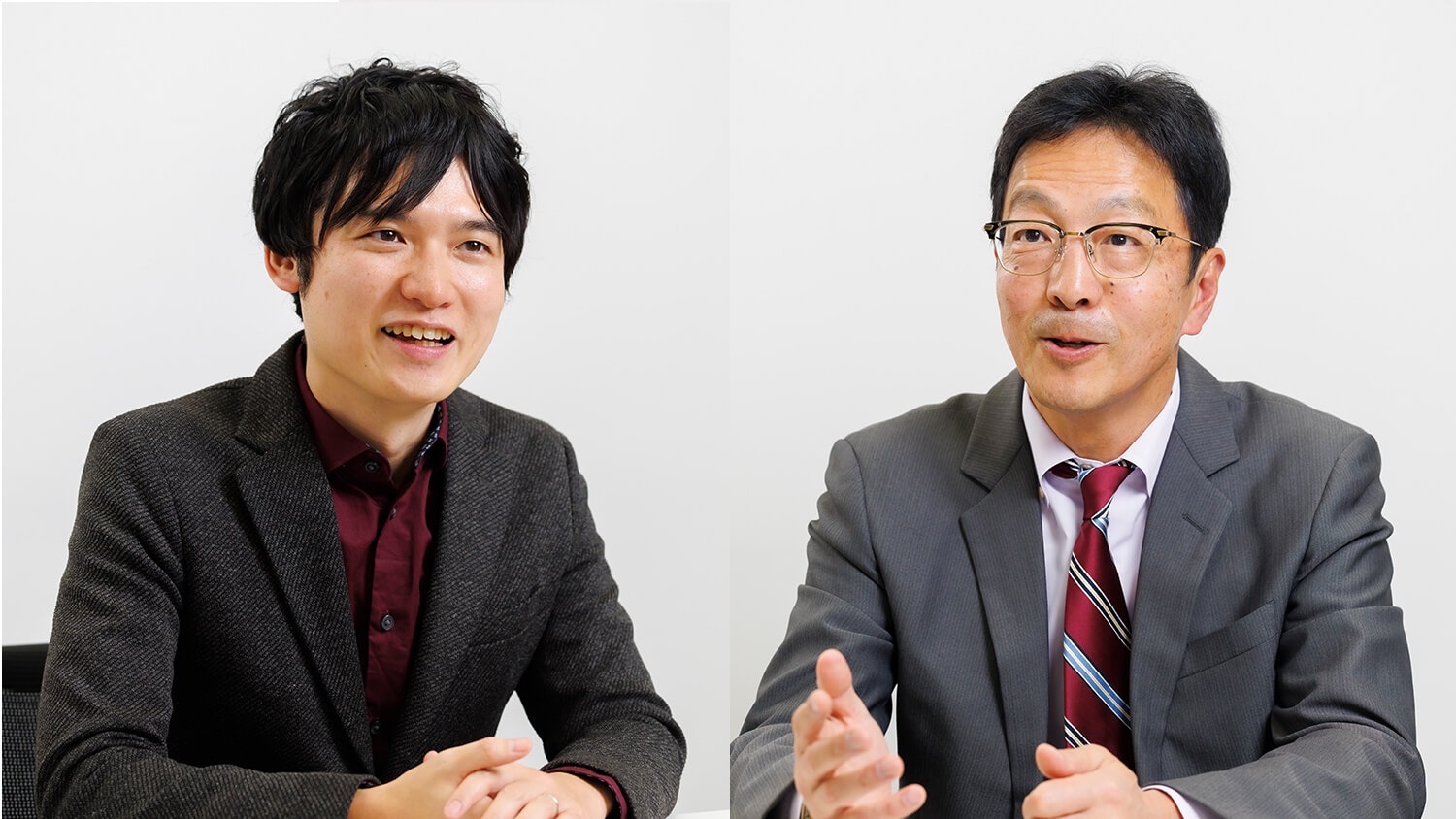
「部下を叱れない」「育て方がわからない」―――
上司が戸惑う一方、「ここでは成長できない」と職場を見切る若手が増えている。
「イクボス」伝道師・川島高之氏、『ゆるい職場』著者の古屋星斗が考える育て方改革とは。
「ゆるい職場」を見切る若手たち
古屋:法改正や社会規範の変化を背景に、労働環境は急速に改善する一方、新入社員の離職率が上昇しています。「叱られたことがない」「このままでは成長できない」……。「仕事がきついから辞める」のではなく「ゆるい職場」でキャリアに不安を感じ、転職に踏み切る。「不満型転職」ではなく「不安型転職」が増えています。
川島:管理職からは「部下の育て方がわからない」という悩みをよく聞きます。

いかに「関係負荷」を高めずに「質的負荷」を高めるか
古屋:まず、「Z世代は◯◯だ」と一括りにしないほうがいいと考えています。Z世代を対象にした仕事に対する意識調査でも、多くの項目で二層化が顕著です。さらに掛け合わせによって、主流派なき多様化が進んでいます。
これまで多くの日本企業は、白紙状態の新卒を一括採用し、OJTで育成していましたが、若手のキャリアのスタート地点も、経験や志向も多様化する今、彼ら・彼女らのライフキャリアを把握できないことを前提とした「育て方改革」が必要です。
川島:入社時研修にせよ部下指導にせよ、完全個別対応の時代ですね。
古屋:もう1つ、育成の難しさの複雑性を高めるのは、負荷の掛け方の難しさです。私が2021年に行った調査で、仕事の量による「量的負荷」と仕事の中身に関する「質的負荷」、上司などとの人間関係による「関係負荷」と、新卒1年目〜3年目の成長実感の関わりを分析しました。すると、質的負荷は成長実感にプラス、関係負荷はマイナスという結果が出たのです。関係負荷を高めずに質的負荷を高めるという非常に難しい舵取りが求められています。
川島:辞められたら困る、ハラスメントになるという恐怖から、部下に厳しく言えない一方、上からは相変わらず「昭和」な指示が下りてきて板挟みになっている。こうした管理職を支援しなければなりません。
「外で育てる」「横の関係で育てる」一社に閉じない育て方改革
古屋:育て方改革のポイントは2つあり、「外で育てる」「横の関係で育てる」ことです。若手の育成は、一社に閉じるべきではありません。大手自動車会社でも2020年前後から出向研修を導入しています。越境プログラムを提供する企業による「レンタル移籍」を導入する企業も増えています。
川島:私自身、MBAを学びましたが、それよりも実際にマネジメント能力を鍛えられたのはPTAでした。社内の序列や文脈が通用しない組織で、人を動かし物事を進める経験を管理職自身がしたほうがいい。「MBAよりPTA」が私の常套句です。
また2014年に私は、経営者や管理職として意識してきたことを「イクボス」の定義と10カ条にまとめあげ、世に出しました。定義は、(1)部下の仕事と私生活をともに応援する、(2)ボス自らワーク・ライフ・ソーシャルを楽しむ、(3)成果には厳しくこだわる、です。上司自身が家事や育児などを主体的にやり、PTAや地域活動などソーシャル活動に参画し、充実したワーク・ライフ・ソーシャルを見せることが大切です
古屋:ある日系大手企業の若手は、出向先のベンチャー企業で仕事に厳しい指摘を受けた。初めての経験だったそうですが、その経験をさせてくれた自社に感謝しているそうです。
川島:以前は親だけでなく、子どもを叱ってくれる近所の年配者や、マナーを教えてくれる商店街のオジチャン・オバチャンなどがたくさんいました。そう、地域総ぐるみでの次世代育成です。職場も同じで、上司だけが1to1で部下を育成するのではなく、部外・社外・そして地域やNPOなどのソーシャルで若手や次世代を育成することが大切かなと思います。
古屋:大阪商工会議所が主催する若手社員キャリアデザイン塾の塾長をしていますが、業種や企業規模の異なる約50社から若手社員が参加しており、社外の人材と交流するなかで、さまざまな気づきを得ています。若手育成を職場の問題に閉じるのではなく、横の関係で学ぶコミュニティの形成が今後、重要になると感じます。職場での関係負荷を高めずに質的負荷を高めていく1つの方法かもしれません。
社外に目を向ける若手は「離職予備軍」か?
古屋:「外」を経験した人材は、自社へのエンゲージメントが高まることがわかっています。ただ離職率も高まるのが悩ましいところです。
自律的な若手ほど、組織に不満を持つのではなく、よりよい機会を求めて転職する。これを「ポジティブ転職」と呼んでいます。対義語は「ネガティブ在職」で、不満を持ちながら組織にしがみつく。ポジティブ転職を防ごうと自律的な社員のキャリアを制約するより、ネガティブ在職を減らすことこそ喫緊の課題ではないでしょうか。

上司だけでなく部外・社外・ソーシャルで若手を育てる
川島:部下を越境させることは、経営者や上司にとって覚悟の要ることです。本業がおざなりにならないか、離職してしまわないかと心配して、機会を与えず囲い込みたい気持ちも痛いほどわかります。しかし、部下を越境させる覚悟を持ったほうがいいです。そのためにも上司自身が仕事一本足打法から脱却し越境する必要がありますね。
古屋:まったくです。若手にとって「いい上司」とは、「できる人」よりも「変な人」かもしれません。組織の保守本流で職場の仕事ができて評価されている人より、社内外にネットワークを持ち、面白そうな仕事をしている。自分自身、越境している人がロールモデルになりやすい。
会社のメンバーシップも多様化していきます。副業や兼業、インターンシップ経験者、アルムナイなど、フルタイムでコミットはしていないが、会社に魅力を感じて、なんらかの関わりを持つ関係人口ならぬ「関係社員」がいるはずです。マーケティングにおけるファンコミュニティの考え方を人材領域に応用して、「関係社員」を増やすことが競争力に直結する。ジョブ型でもメンバーシップ型でもない、いわばハイパーメンバーシップ型組織です。複層化するコミュニティで育成する設計が重要になっていくでしょう。
Text=渡辺裕子 Photo=今村拓馬


小林 浩
NPO ファザーリング・ジャパン 理事
慶應義塾大学卒業。三井物産入社後、系列上場会社の社長に就任し「イクボス式経営」で利益8割増、時価総額2倍、残業4分の1に。“元祖イクボス”として多方面で活躍中。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ