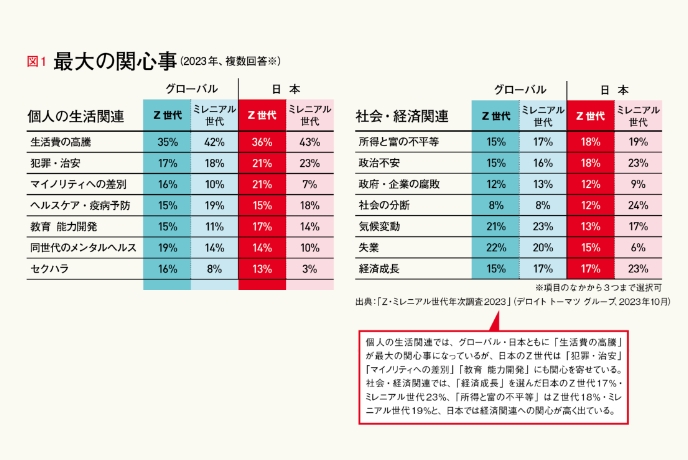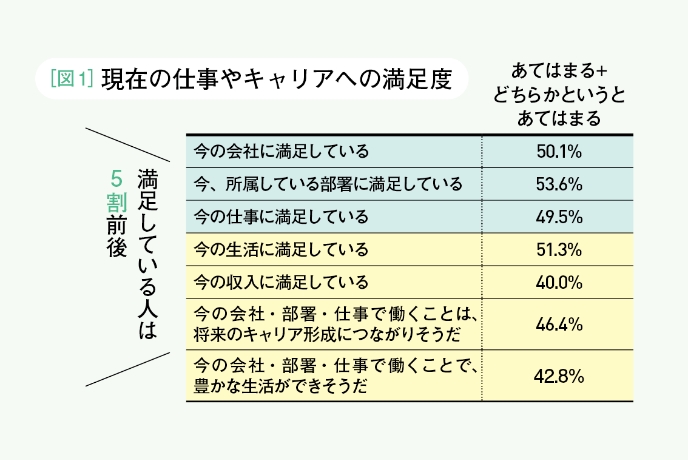Works 183号 特集 Z世代 私たちのキャリア観 自分らしさと不安のはざまで
Z世代が抱える「絶望」とは
可視化された差別や格差とどう戦うか──竹田ダニエル

アメリカではイスラエルのガザに対する攻撃に、若者を中心に抗議の声が高まっている。2024年の米大統領選にも、こうした若者たちの考えが大きな影響を与えそうだ。Photo=AFP=時事
アメリカのZ世代は、資本主義が加速するなかで、インターネットによって可視化されるようになった差別や格差を子どもの頃から身近に感じている。
Z世代が抱える「絶望」の根源とは何か。
1997年生まれ、アメリカ在住のライター・研究者の竹田ダニエル氏に聞いた。
アメリカのZ世代はポスト9.11の世代で、人格形成に重要となる学生時代や就職の時期に、新型コロナウイルス感染拡大に伴うロックダウンを経験しました。貧困層の有色人種のエッセンシャルワーカーが亡くなったり、経済優先で国民が置き去りにされたりするニュースをスマホで見るなど、インターネット上であらわになった差別や格差を知っている世代です。初の黒人大統領が誕生し、同性婚が合法化されるなど、人種やジェンダー、セクシュアリティにおいても多様性が前提にある社会を知っている世代ともいえます。
1946〜1964年生まれのブーマー世代が体感した「アメリカはすごい」というアメリカンドリームもまったく実感できない。ブーマー世代は真面目に働けば家を建てられ、老後は安泰だという感覚がありましたが、学生ローンや不安定な雇用形態に苦しむZ世代にそのような感覚は皆無です。こうしたことを背景に、多くのZ世代は「仕事を真面目に頑張れば人生がうまくいく」という従来の価値観に大きな違和感があります。
もちろん、こうした感覚を持つのはZ世代に限りません。インターネットの普及で情報が「橋渡し」され、世代間の情報量のギャップが少なくなり、年齢によって「世代」を区切ることがナンセンスになってきました。こうした「Z世代的価値観」は世代を超えて共有されています。
劣悪な労働環境に声を上げる若者
生活費高騰、テックバブルは終焉
私が住むカリフォルニア州では、道を1つ挟むと住んでいる人々の経済状況はまったく異なり、生まれながらにして格差があると強く感じます。
2022年11月には、UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)やUCSD(カリフォルニア大学サンディエゴ校)など、カリフォルニア州内の10大学に所属する4万8000人の大学院生やポスドクが、低賃金と劣悪な労働環境を変えるべくストライキを行いました。アカデミアの労働者では、アメリカ史上最大規模のストだったといわれていますが、鉄道労働者やスターバックスの従業員などからも同様の動きが出ています。米全土において、今、すぐにも「変化」が必要で、そのための行動を取らなければならないという緊迫感を、若者たちは強く抱いています。
日本の人からは、しばしば「なぜアメリカの若者は声を上げるのか」と聞かれるのですが、UCB(カリフォルニア大学バークレー校)の学生の10人に1人がホームレスだったり、事件に遭っても警察がまったく助けてくれないどころか市民に差別的な危害を加えたりする、と想像してみてください。アメリカでは、声を上げなければならない必然性があるのです。
実際、私の友人たちの就職は、高学歴であってもとても厳しいです。昨今のインフレによって家賃や生活費は高騰していますが、よい大学を出れば仕事があるという状況ではない。たとえ就職しても、経営者の判断でいつ解雇されてもおかしくない。2019年ごろまでは、シリコンバレーでテック関係のスタートアップ文化が盛んでしたが、今やテックバブルは崩壊し、ブームは去りました。ロサンゼルス・タイムズ紙などの有名メディアでも有色人種のジャーナリストが解雇されるなど、マイノリティが「居心地が悪い」と感じる出来事も続き、絶望的なムードが蔓延しています。
自分たちなりの「幸せ」追求
日本社会に感じる閉塞感
資本主義が加速するなかで、このような「絶望」を抱える多くのZ世代は、「会社に忠誠を尽くす」という従来のライフスタイルを受け入れることができない。会社に入っても労働者を監視するカルチャーがあったり、「お互いが敵」と感じられるために同僚を信頼できなかったりする、というのはよく聞く話です。
興味深いのは、Z世代には「生活のために仕方なく仕事をしているが、あくまでお金のためなので頑張らない」というニヒリズムがある一方で、「短い人生をどう楽しめばいいのか」、そして「社会によりよい変化を及ぼすにはどうしたらいいのか」という問いが混在していることです。自分たちなりの「幸せの基準」を追求しようとしている、ともいえます。
翻って日本の状況はどうでしょうか。日本では、集団に帰属することの喜びや重要性が子どもの頃から教育段階ですり込まれています。その陰でマイノリティや女性が社会的弱者であることが、アメリカに比べると見えづらくなっているように思えます。日本の女性の友人からは、企業でパワハラを受けてからジェンダー問題に自覚的になったという話も聞きますが、こうした差別は「そちら側」に立っていない特権的な立場にいるマジョリティの日本人にとっては、「あまり関係がないこと」と認識されているのではないでしょうか。もう1つ、日本で閉塞感を感じるのは、社会的に許容される価値観に多様性がなく、成功への道筋に1つのはしごしかかかっていないように見えることです。私自身は、日本とアメリカ両方に住んだ経験があり、どちらにも良いところと悪いところがあることは身をもって体感します。だからこそ、客観的な視点で両者の文化や社会を分析し、「完璧な社会は存在しない」ということを理解しながらも、よりよい社会を目指して活動を続けたいと思っています。
Text=川口敦子
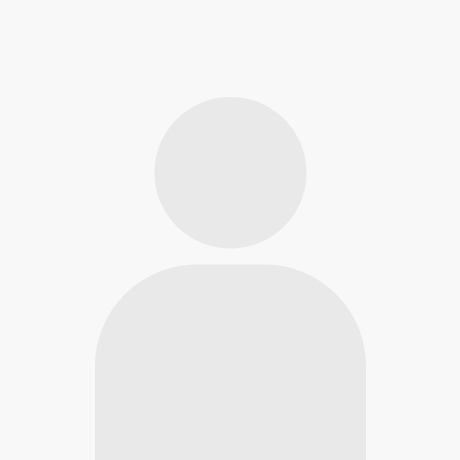
竹田ダニエル
ライター・研究者。
1997年生まれ、カリフォルニア州出身、在住。「カルチャー×アイデンティティ×社会」をテーマに執筆し、リアルな発言と視点が注目されるZ世代ライター・研究者。著書に『世界と私のA to Z』『#Z世代的価値観』(ともに講談社)。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ