Works 186号 特集 あなたの会社の人的資本経営大丈夫ですか?
丸井グループ/本質的な問いに向き合い 10年かけて「 人的資本」を拡大
丸井グループは2005年に青井浩氏が代表取締役社長に就任して以降、「人的資本経営」という言葉が登場する前から、人材にフォーカスした投資や施策を推し進めてきた。青井氏が経営危機を通じて「挑戦する人材」の必要性を痛感したことが、その原点にある。
青井氏は昨今、人的資本経営という言葉を耳にするようになって、「これは我々が経営危機で苦しい時期に、やってきたことだ」と思い当たっているという。
「当社が今でいう人的資本経営に至ったのは、会社がつぶれるかもしれないという局面で、当社の存在意義に向き合わざるを得なかったからです。創業家の3代目である私自身の生きる意味も、会社の立て直しとは切り離せませんでした」
同社は青井氏が社長に就任してほどなく、経営危機に直面。2009年3月期と2011年3月期には赤字転落も経験した。
「真っ暗なトンネルを手探りで歩いているような状態」だった当時の青井氏にとって、唯一のよりどころは「世の中の働き手が『こうあってほしい』と思える働き方はどのようなものか」という本質的な問いだった。自問自答の結果、「一人ひとりがやりがいを持って働き、世界や社会に貢献する」ことに行きついた。
「私欲ではなく、みんなが共有できる普遍的な価値を基盤に行動や戦略を展開すれば、自分なりに納得して取り組める。それがすごく大事でした」
社員にやりがいを感じてもらうには、やらされる仕事ではなく自ら創造性を発揮し、やりたいことに挑戦してもらう必要がある。そのためには企業風土や文化から作り直さなければいけないと考えた青井氏は、当時はまだあまり注目されていなかった働き方改革や、自律的なキャリア形成を促す人事制度改革に着手した。
「結果的には組織を変えるのに、10年くらいかかりました」
成果主義で壊れた 信頼関係を取り戻す
青井氏の就任前の2003年、同社は成果主義を導入し、人事制度も大きく変更した。青井氏は就任後、この制度変更によって社員と経営陣との信頼関係が、決定的に破壊されてしまったことをひしひしと感じたという。社員との信頼関係なしに、組織は価値を生み出せない。このため7年に及んだ経営危機の間も人員削減はせず、退路を断ち、歯を食いしばって立て直しに取り組んだ。社員にも頻繁に「仕事を通じて皆さんが幸せになれる組織を作りたいので、協力してください」といったメッセージを送り、信頼関係を少しずつ再構築していった。
もう1つの大きな課題は、現場が新しいことにチャレンジできなくなっていたことだった。業績至上主義に陥り、人材は利益を出すための「パーツ」として、既存事業で売り上げを高めることだけを評価されていた。小売業の売り場では長い間、同じメンバーが同じ品ぞろえの商品を、同じ売り方で販売していた。
「経営環境は非常に速いスピードで変わっているのに、当社は変化に追いついて新しい領域を切り開くことがまったくできなくなっていた。その結果、既存事業はどんどん陳腐化してジリ貧になっていました」
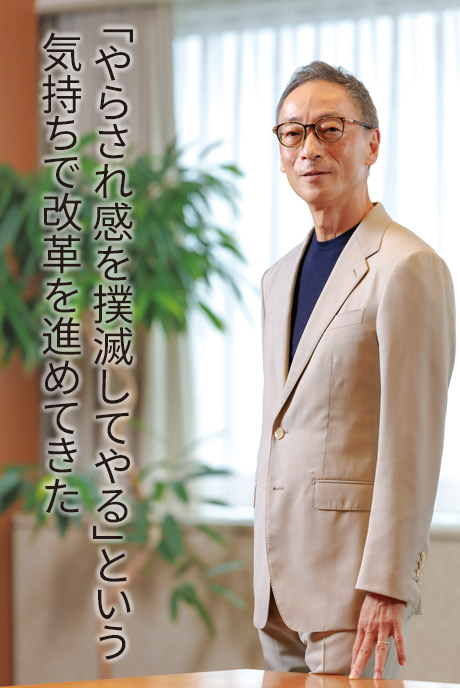
丸井グループ 代表取締役社長
代表執行役員CEO
青井 浩氏
青井氏は店舗を回るうちに、新人が多数配属される雑貨売り場などに比べて、ベテラン社員が多い子ども服、紳士服などの売り場ほど、十年一日のやり方が踏襲されていることにも気づく。「社員が長く同じ職場に留まり、変化への対応能力を低下させてしまった職場と、変化が常態化し、社員もそれを楽しめるようになった職場のどちらがより多くの価値を生み出せるか。それは明らかに後者です」
2013年、社員を小売りからカードへ、カードから物流へ、など事業をまたいで異動させる「職種変更」の人事制度をスタートさせた。社員に希望のキャリアを自己申告してもらい、ポストが空いたときは希望者のなかから適性に合う人を充てる。これによって、多くの異動に社員本人の希望が反映されるようになった。
当初はベテランを中心に「門外漢が来たら生産性が落ちる」といった反発もあった。新人を受け入れる習慣がないため、マニュアルすら存在しない職場も多かった。しかし、まったく別の職場から社員が異動してくることで、「なぜこんな作業があるのか」「無駄じゃないか」という新しい視点がもたらされ、仕事の見直しや新しいアイデアにつながった。
これまでに全社員の約8割が職種変更を経験し、調査に対してそのうち86%が「異動を通じて成長できた」と回答している。新卒の採用面接でも「グループ内に多様な職種があり、いろんな経験ができそうだから」という志望理由が聞かれるようになった。
「個人の成長にも会社の進化にもつながる施策のヒントは、現場にありました」
変化に対して後ろ向きな人もいるが、育児や介護などの特別な事情を除けば、「同じ部署に留まり続ける」という選択肢は、現時点では存在しない。異動した人が楽しく働き成長する姿を見せることで「自分も挑戦してみようか」と思ってもらうことを目指している。
また異動直後で仕事に不慣れなうちは、前の職場で得ていた評価を得られなくなるリスクがある。このためバリューとパフォーマンスの二軸評価制度に変更、評価が異動の妨げにならないようにしている。
評価制度改革に対し不信 社員100人で2年間議論
青井氏は職種変更の仕組みと並行し、人事評価制度の見直しにも取り組んだ。2003年に導入した成果主義は、自律的に行動する組織風土の醸成には、そぐわない内容だったからだ。
従来の制度では、給与・賞与に加えて昇進昇格も個人の成果に左右され、部下の育成やほかのメンバーへの貢献などは評価されなかった。しかし、たとえば小売りの現場では、販売だけでなく自社カードの会員獲得や在庫管理、売り場づくりなどさまざまな仕事があり、職場のメンバーがそれぞれの強みを発揮して成果を出すことが重要だ。このためメンバーへの貢献や新しい価値の創造といった評価軸を加えた、新たな人事制度を導入しようとした。
しかし、「成果主義を導入した2003年の人事制度改革で多大な不利益を被ったというトラウマから、社員は新制度の導入に懐疑心を抱いてました」(青井氏)。
トップダウンで制度を導入しても、社員の納得感は得られないと考えた青井氏は、「新制度を導入するかどうか、みんなで決めてください」と社員にボールを投げた。CHROの石井友夫氏が中心となり、新たな評価制度について議論する会議体を立ち上げたのだ。
会議は手挙げ方式で、役職も年齢も異なる社員約100人が参加した。月1回ほど全員で話し合い、その結果を職場に持ち帰って意見を募り、その意見をさらに会議で議論することを、1年半~2年繰り返した。
議論を通じて組織全体へ、新しい人事制度への理解が少しずつ広まっていった。そして大半の社員の合意が得られたと判断した2017年、制度を導入した。

丸井グループ
専務執行役員 CHRO
石井友夫氏
石井氏は、「制度の方向性を示したのは青井でしたが、社員が2年間試行錯誤し、ボトムアップで必要性を理解していった。あの2年がなければ、たとえ制度が入っても『やらされ感』満載で、評価者である管理職も動かなかったのではないでしょうか」と話す。
青井氏自身、社長になる前の約20年間は上司の下で働く立場だった。「私は部下だった時代、『やらされ感』がすごく嫌だったので、社長になってからも社員に『社長にやらされた』とは言われたくなかった。だから個人的には『やらされ感を会社から撲滅してやる』という思いで、一連の改革を進めてきました」
エンゲージメントが向上 10年経って実感したリターン
一連の取り組みによって、社員が主体的に動く風土が次第に醸成され、世の中になかった新しい仕事やサービスも生まれるようになった。
たとえば新規事業として「アニメ事業部」が発足。アニメやアーティストなどとコラボレーションした自社カードは「好きを応援するカード」として、多くの会員を獲得している。
石井氏は「誰しも好きなことには没頭できる。アニメが好きならアニメに関わることを『仕事』にしてしまえば働くことへの高揚感が高まり、会社の利益にもポジティブな影響をもたらすのではないか」と話す。
社員のエンゲージメントの指標も向上している。「自分の役割を認識している」社員の割合は、10年前の30%台から80%へ、自分が職場で尊重されているという心理的安全性の数値も、30%台から64%に上昇した。
石井氏は人事の役割を「『自律的な組織を作る』という経営戦略が提示されたとき、自律的な組織とはどういう状態かを因数分解し、やるべきことを明確にする」ことだと説明する。
ただエンゲージメントの上昇は、働き手の環境改善を示す指標ではあっても、現時点では企業利益との因果関係が明確に証明されたわけではない。石井氏は「当社は10年以上、人への取り組みを続けたことで新規事業などが生まれ、それを人的資本の『リターン』と位置付けられるようになりました。人的資本が企業にもたらすリターンは、何年も経った後に振り返って初めてわかるのではないでしょうか」と語った。
Text=有馬知子 Photo=今村拓馬

青井 浩氏
丸井グループ
代表取締役社長
代表執行役員CEO

石井友夫氏
丸井グループ
専務執行役員 CHRO


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ