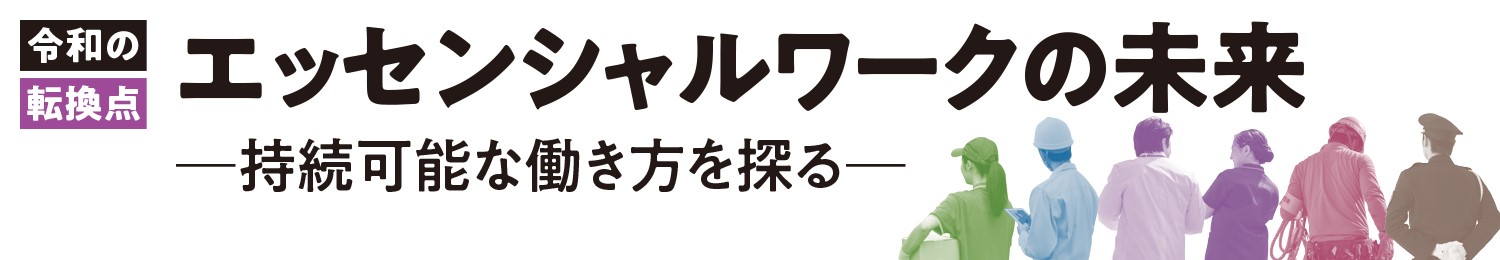
生活者目線の発想が生む経済の好循環――すかいらーくホールディングス・谷真会長
労働供給制約下だからこそ好循環への発想の転換が可能になる。DXで業界をリードする外食大手「すかいらーくホールディングス」の谷真会長が重視するのは、多様なプロ集団が導く生産性向上が起点の新しい好循環だ。新時代の経営と日本社会のあり方を考える。(聞き手:リクルートワークス研究所 古屋星斗) 株式会社すかいらーくホールディングス 代表取締役会長CEO 谷 真 氏(写真右)
株式会社すかいらーくホールディングス 代表取締役会長CEO 谷 真 氏(写真右)
好循環の起点は生産性向上にあり
古屋:日本の経済政策の要諦は長年、「失業者を増やさない」ことでしたが、目下の最大の課題は働き手不足です。働く時間を増やしたいのに「働き控え」をする人たちの問題をどうするか。さらにはどうやって生産性を向上し、賃金の引き上げにつなげていくか。本来こうした政策課題と向き合わねばならないのに、働き手が男性正社員だけだった時代の流れを引きずっているものが多いと感じます。企業でも家族手当がある会社はまだまだ多いです。
谷:今は手当を減らして基本給を上げていく時代ですからね。収入の増加分を消費に回し、経済の好循環を生む世帯を増やさないといけない。問題は政府も含め日本の中枢にいる人たちが、終身雇用制に象徴される高度経済成長期の成功体験を引きずったままデフレに突入したことです。このため個々の働き手のスキルを上げ、人材の流動性を高めていく方向に踏み出せないまま来てしまった。
古屋:完全にルールが変わっている。
谷:発想の転換が必要です。コストを削減すれば利益が出て会社を存続できるという、企業の存続だけを目的化したデフレの時代が30年続きました。この時代は終わった、と考えるべきです。なぜなら、コスト削減で利益を出せるのは潤沢な内需に支えられてこそ成立するからです。高齢化に伴って内需そのものが失われるなか、内需の恩恵を受ける最たる業界である飲食業はどうやって生き残りを図るのか。そう考えれば、生産性が最も大事なのは明白です。デフレ時代の生産性向上といえば、人も投資もとにかく「削る」という発想でした。その結果、名目上の生産性は上がっても海外企業との競争に勝てなくなった。本来の生産性と真剣に向き合わなければ、グローバルな価格競争や開発競争から取り残されていくだけです。
古屋:グローバルな戦いに踏み出すためにも、生産性向上は何によってもたらされるのかを真剣に考える必要があると。
谷:そうです。企業のオペレーションは各部門の作業の難易度と工数、作業の全体量で数値化できます。ここに焦点を当て最大限の効率アップに取り組まない限り、グローバルで戦える価格を提示できません。生産性を高めることで付加価値が上がる。そうすれば価格転嫁でき、賃上げができる。この循環の起点が生産性です。そのためには徹底した現場主義で人と向き合うのと並行してDXを進める必要があります。日本経済全体にとっても、生産性向上から賃上げに至る循環をあと5年は続けるのが至上命題でしょう。
古屋:近年の分析で、高齢化率の上昇と世帯数の増加はほぼパラレルで進行することがわかってきました。ご高齢者は単身世帯が多いですから。75歳以上人口の割合のピークはまだまだ先とされていますから、日本ではこれから30年間は世帯数が減らない。そうなると、介護サービスもインフラ整備も効率悪化は避けられません。こうした生産性の押し下げ圧力が強まるなかで、構造的な働き手不足が加速化していくのがこれからの日本の現実です。こうした点も踏まえ、どういった視点で生産性をマネジメントしていくべきだとお考えですか。 谷:生産性には生活者目線と企業目線の二つの視点があると考えています。世帯数が増え、とりわけ単身世帯が多くなるなか、ライフスタイルも多様化しています。仕事以外にも家事をこなし、趣味も楽しむ忙しい人たちが増えています。そうしたなか、余剰時間があっても近所に働き口がなかったり、勤務体系がフィットしなかったりする人たちに、より柔軟に働いていただける機会を提供しようと生活者目線の発想で導入したのが、「スポットクルー制度」です。これは、すかいらーくグループの店舗で働く全国9万人のクルー(従業員)が今契約している店舗以外でもスポット勤務できる制度です。例えば、普段は「ガスト」で勤務している人が「バーミヤン」で2時間だけ勤務に入ったり、普段は都内の「しゃぶ葉」で働く北海道出身の大学生が帰省中に北海道の「ガスト」で働いたりもできます。企業目線を生活者目線に近づけることで生産性の高い社会を実現していくこのシステムは、私たちから日本社会への提案でもあります。
谷:生産性には生活者目線と企業目線の二つの視点があると考えています。世帯数が増え、とりわけ単身世帯が多くなるなか、ライフスタイルも多様化しています。仕事以外にも家事をこなし、趣味も楽しむ忙しい人たちが増えています。そうしたなか、余剰時間があっても近所に働き口がなかったり、勤務体系がフィットしなかったりする人たちに、より柔軟に働いていただける機会を提供しようと生活者目線の発想で導入したのが、「スポットクルー制度」です。これは、すかいらーくグループの店舗で働く全国9万人のクルー(従業員)が今契約している店舗以外でもスポット勤務できる制度です。例えば、普段は「ガスト」で勤務している人が「バーミヤン」で2時間だけ勤務に入ったり、普段は都内の「しゃぶ葉」で働く北海道出身の大学生が帰省中に北海道の「ガスト」で働いたりもできます。企業目線を生活者目線に近づけることで生産性の高い社会を実現していくこのシステムは、私たちから日本社会への提案でもあります。
恩恵を受けた世界をのぞきたくなる
古屋:DX推進でもリードされてきましたが、これも経営戦略の一環という位置付けですか。
谷:従業員の意識付けという意味で転機になったのは、本部のDX推進で導入した「困りごと解決プロジェクト」の影響が大きいと思います。元々は「DX推進」を掲げていたのですが、現場が他人事だった。しかし「困りごと」を解決するというミッションへと変更した結果、そのプロジェクトの成果によって「仕事が簡単になった」「ミスが減った」「仕事量が減った」という実感のこもった声があちこちで聞かれました。すると組織のなかに、こうした恩恵をもたらしてくれた指導的な立場の人たちの意識や考え方を共有しようという感情が芽生えます。自分が恩恵を受けた世界をのぞきたくなるわけです。のぞいてみると、「こういう仕事をしているんだ。自分も参画したい」という能動的な意識が働き、それが資格取得や社内勉強会の参加につながる。資格をとった人はそのスキルを使って、より高度な課題に挑戦したいと考える。こうした流れで現場の「困りごと解決」の輪がどんどん広がったのが実態ですから、私だけがリーダーシップを発揮したというよりも、従業員が主体的に意識変革した結果がさまざまな成果につながったと考えています。
さきほどの生活者目線を従業員目線に置き換えれば分かりやすいと思います。企業側の都合で上から目線で生産性を押し付けるのではなく、従業員の多くが「こういう世界があるのなら自分も仲間になりたい」と思う仕組みや環境を整えれば、ものすごいスピードで共感の輪が広がっていきます。
古屋:従業員を「生活者」と重ねる視点は今後の日本を考えるうえで重要です。全ての働き手は生活者や消費者でもあるわけですから。谷さんはどのような意識で「生活者」という言葉を使うようになったのですか。
谷:飲食業に限らず、良い商品を提供し続ければお客様が集まる、というのは1980年代までの話です。家電の買い替えもあまりしなくなりました。内需が行き渡ったこの時代に人々が求めているのは生活に潤いをもたらす「何か」です。そう考えたときに必要なのは、生活者一人ひとりの感情の内側に入っていく経営志向です。それができなければ会社の成長は望めません。 古屋:サービスやシステム開発にあたっても生活者視点、すなわち働き手の視点を大事にされていますね。例えば、配達員専用アプリの開発に際して、リーダーの執行役員自らが現場の仕事を体験したい、と「Uber Eats」の配達員として働かれたエピソードも耳にしました。こうした現場を重視する組織文化はどうやって醸成されたのですか。
古屋:サービスやシステム開発にあたっても生活者視点、すなわち働き手の視点を大事にされていますね。例えば、配達員専用アプリの開発に際して、リーダーの執行役員自らが現場の仕事を体験したい、と「Uber Eats」の配達員として働かれたエピソードも耳にしました。こうした現場を重視する組織文化はどうやって醸成されたのですか。
谷:私たちの現場主義は建前ではありません。第三者が見ると、「なぜそんなことを?」といったことにもとことんこだわります。例えば、「クリーンアップタイム」というシステムがあります。社内のデータアナリストが売上との相関関係が最も強いオペレーションを調べたところ、テーブルのお皿を下げるスピードだとわかりました。そこで、従業員がお皿を下げるべきタイミングを画面表示で「見える化」するシステムを開発・導入した結果、増収につながりました。これも現場起点の着想が実を結んだ一例です。現場の課題や問題意識が明確になれば、それをどう解決していくかという段階に進める。そこにDXをはめ込んでいくイメージです。
古屋:きわめて重要なポイントです。DXは「DXをすること自体」が目的化する傾向に陥りがちですが、売上と相関関係の強い作業の検証から始まる「生産性のキーファクターの発見」がDXのフックになるわけですね。また、DX推進と並行して専門人材の育成強化にも着手されていますね。
谷:高度経済成長期は配置転換を繰り返し、オールラウンドの「何でも屋」を育てる人事が主流でした。組織の中枢で全体を見渡せる人材は必要ですが、これからの時代は高度プロフェッショナル人材をどれだけ育てられるかが企業の底力になります。そのために今尽力しているのが、店舗マネジャーの高度人材を育成する人事制度です。所定の資格を取得すると難易度に合わせて給与を引き上げるなど、専門人材を評価する態勢を強化しています。自力で売上や利益を上げられる店舗マネジャーには店舗経営の権限委譲も進める方向です。今後は本部のデータアナリストといった専門人材にも上級エキスパート職をつくり、給与をアップしていきます。プロフェッショナル集団への移行が経営力強化に直結すると考えるからです。高度経済成長期は会社が敷いたレールに従っていれば良かった。しかしこれからは、自分の意思と裁量で収入もキャリアもアップさせていく時代です。
社会問題の捉え方を変えるとき
古屋:冒頭でも少し触れましたが、働き手が貴重な資源になりつつある日本で行政に求められるものは何だとお考えですか。
谷:まず頭のなかの構造を変えないといけない。例えば、国会で議論になっている「103万円の壁」の問題。行政機関の方々と話をすると、「学生の本分は勉学なんだから、そんなに働いてもらっては困る」というのが本音のようです。しかし今は半数超の55%の大学生が奨学金を受給し、社会人になっても返済に苦慮しているのが現実です。高度経済成長期のように国が強制的にキャップをはめる考え方は改めるべきです。
政府にとっての売上高は税収です。税収を伸ばすには経済を成長させる以外にない。にもかかわらず、「年収の壁」や在職老齢年金といった労働力を縛る前時代的な手法がまかり通っています。ほかにも、65歳以上で週20時間以上働く人を採用すると、自社で健康保険組合を有する場合は、1人あたり高額な納付金を国に納めなければならない、といった問題もあります。そうなると、企業は優秀な高齢者を採用できず、結果的に生産性の低下につながります。税の集め方には課題が山積しています。
古屋:働いた分だけ年金が減る在職老齢年金制度の根底には、高齢者が働き続けることで若者が失業する事態を避けるという前時代的な発想があります。今は高齢者が働き続けても若者の求人を補いきれない働き手不足の状況が地域の現場で起こっていますから、発想の転換が必要としか言いようがありません。
谷:副業についても国は推奨する一方で、一日複数の会社で通算して8時間を超えて働くと、後から雇用した企業は25%の割増賃金を払わなければならない。こうなると企業は採用や契約に後ろ向きにならざるを得ません。さまざまな旧来的な発想でつくられたルールが新しい経済への転換のふたをしている状況です。戦後の日本社会は分厚い中間層に支えられて発展してきました。しかし今は中間層がやせ細り、富裕層と貧困層の分断が顕在化しています。インフレについていけない中間層が増えるのは日本の民主主義にとってもリスクです。分厚い中間層が幸せに暮らせる社会を取り戻す必要があります。
古屋:社会が転換するなかで、しっかりと働ける、しっかりと収入を増やせる、そんな環境をつくっていかなくてはなりませんね。本日はありがとうございました。
■谷 真 氏 プロフィール
株式会社すかいらーくホールディングス 代表取締役会長CEO
1977年旧株式会社すかいらーく入社。2000年ニラックス代表取締役社長、2007年同社長兼すかいらーく執行役員を経て、2008年すかいらーく代表取締役社長に就任。2018年すかいらーくホールディングス代表取締役会長兼社長を経て、2023年同社代表取締役会長CEO(現在)。
執筆:渡辺豪
撮影:平山諭


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

