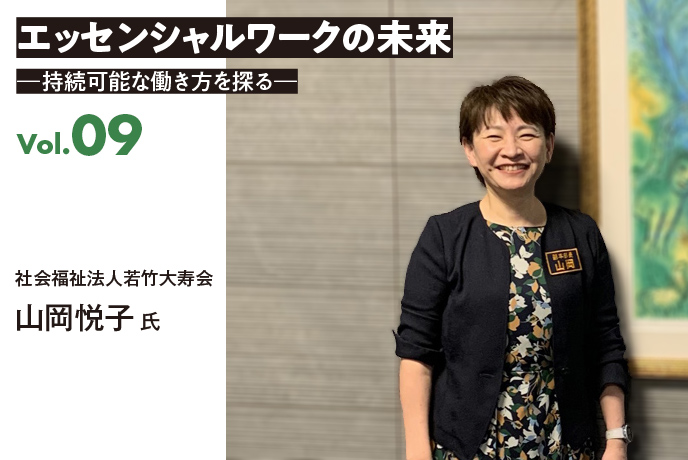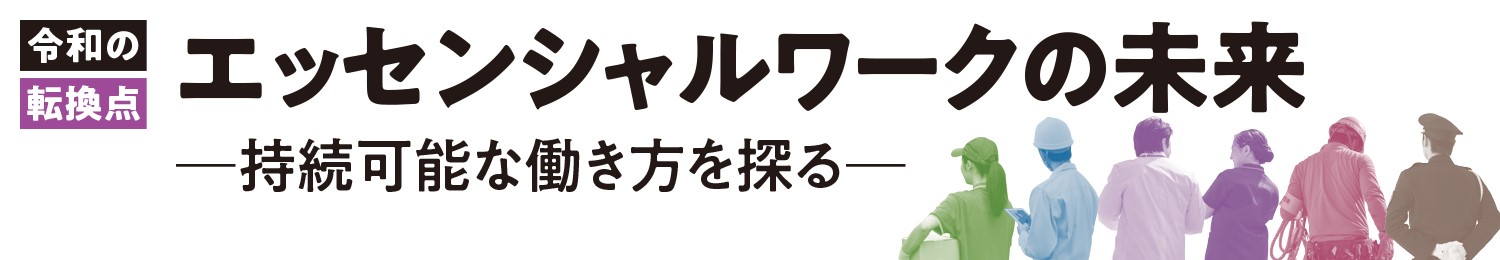
働き手の「困りごと解決」が企業を強くする――すかいらーくホールディングス
労働供給制約下において最重要ポイントとなる自動化や機械化。デジタル・トランスフォーメーション(DX)の推進で業界をリードしてきた外食大手「すかいらーくホールディングス(HD)」の軌跡をたどると、現場の働き手の困りごとや課題がイノベーションの突破口になった実態が浮かぶ。IT部門を担う平野曉執行役員へのインタビューで、テクノロジー活用戦略と表裏一体の人材活用戦略に迫った。(聞き手:リクルートワークス研究所・古屋星斗主任研究員) 株式会社すかいらーくホールディングス執行役員
株式会社すかいらーくホールディングス執行役員
マーケティング本部マネージングディレクター
平野 曉 氏
店舗系DXは現場で使えないと意味がない
――すかいらーくHDのDX戦略について聞かせてください。
平野:当社のDXは主に3領域あります。一つは、お客様へのサービスや従業員の生産性向上を含む店舗系DX。もう一つが本部のDXを推進する「困りごと改善タスクフォース」。さらに、アプリの開発・管理などCRM(顧客管理システム)に関わる分野です。
――アプリといえば、コロナ禍前に配達員向けアプリを開発・導入されましたね。
平野:注文ごとに自動的に配達ルートが表示される「配達員専用アプリ」を導入したのは2019年です。これは店舗系DXに含まれます。
――このアプリを開発したプロジェクトメンバーの顔ぶれ、規模を教えてください。
平野:ITの専門家以外にすかいらーくのコールセンターの責任者や店舗マネジャー、営業サイドから宅配の責任者、あと当時財務担当だった私も含め総勢10人弱です。
――宅配分野は未経験のメンバーも多かったのでは?
平野:そうですね。そのため、宅配専業の業者やデリバリーに力を入れている各社の協力を得てヒアリングを重ねたうえでプロトタイプ(製品モデル)を開発しました。その後、プロジェクトメンバーが実際に「Uber Eats」の配達員として働いたり、他社の研究も行いました。アプリの操作性については、当社の宅配現場で使い勝手を確認しながら改善を図りました。
――平野さんご自身も配達員の仕事を経験されたとか。プロジェクトメンバーが配達員に、しかもリーダー自らが、というのは驚きました。
平野:店舗系オペレーションのDXは「現場で使えないと意味がない」というのが基本です。配達員専用アプリ導入前は、ホワイトボードに時計の絵を描き、宅配に出る時間と帰店時間の予測を書き込んだり、壁に大きな地図を貼り出して基本ルートを数日かけて覚え込んだりしていました。
――アプリ開発にはどれぐらいの期間を要しましたか。
平野:宅配受注システムの検討を起点にすれば、店舗への試験導入まで約半年といったところでしょうか。ベテラン配達員が多いため配達ルートの自動表示は当初、「そんなの見なくても大丈夫だよ」と敬遠されがちでしたが、そのうち「あれがなくては困る」という声が広がり重宝されるようになりました。
――配達員の確保にもつながっていますか。
平野:誤配送のクレームが減り、現場からは働きやすくなったとの意見ももらっています。初期のトレーニング期間も大幅短縮でき、即戦力の投入がスムーズになりました。
イノベーションの種は現場に転がっている
――どのような問題意識でDXを推進されてきましたか。
平野:「お客様の立場に立って考える」という基本思想のもと、店舗中心経営のベースにあるのは「お客様のストレスをいかに減らすか」ということです。この視点に立って、経営の柱の一つとしてDXを活用していく、という谷(会長)の号令で進めてきました。例えば、デジタルメニューブック(セルフオーダー端末)の導入も従業員の省力化というより、お客様が従業員を呼ばなくても自分のペースでオーダーできればストレス軽減につながる、と考えたのがきっかけです。
――働き手不足の課題の中なかでもとりわけ注目しているのは、機械化や自動化への転換が困難な対人サービスの省力化投資です。しかし今おっしゃったことは、省力化がそもそもの問題意識の発端ではなかったということですね。
平野:省力化は副次的な産物と言えるのかもしれません。例えば、「ガスト」で今注力しているフレンチコースメニューは、従業員がお客様の食事の進捗に合わせてお皿を下げたり、調理してお出しするタイミングを図ったりしています。こうした機械には代替できない、きめ細かい対人サービスにはしっかり労力を傾ける一方、それ以外の部分は効率化を進めていく。セルフレジの導入もこの認識に基づいています。
――リクルートワークス研究所の調査でも、飲食店でのサービスについて「飲み水やお茶、飲み物はセルフサービス」で90.3%、「配膳はロボットやベルトコンベアなどのシステム」で85.3%、「注文はオンライン」で75.3%が、それぞれ「来店をやめることにつながらない」や「気にならない」「むしろそのシステムの方が良い」と肯定的な回答をしています。気になるのは顧客接点の対応にメリハリをつける御社の判断の根拠です。例えばセルフレジの導入に際し、レジで釣り銭を手渡しで受け取るサービスに客は価値を感じていない、といった知見をどうやって把握されているのですか。
平野:当社はドリンクバーを日本で初めて導入しましたが、これもお客様ご自身のペースで利用いただく方がお客様が心地よく飲食できる、との発想でスタートしています。全てはこの「お客様の視点で何が望ましいか」を考えるサービス志向に由来すると思います。
――宅配プロジェクトのチームに店舗マネジャーなども加わっているとのことでしたが、店舗系DXに現場の知見を活かせるのは強みだと考えておられますか。
平野:そう思います。当社には店舗オペレーションに長けた人材が多くいますが、そのトップクラスがプロジェクトメンバーに選ばれます。そこにITに詳しいメンバーがタッグを組むことでうまく補完し合えていると思います。
――ITと店舗の専門家がそれぞれの領域を超えて議論できるよう、チーム内で決めているルールなどはありますか。
平野:ルールというよりも、「現場を改善する」という目的意識の共有が大切だと思っています。ITのメンバーも店舗のオペレーション改善にコミットするのは面白いと感じたようです。現場の些細な課題や問題意識に大きなヒントが隠されている、という感覚は社内で共有されていますね。
――人手不足が顕著な業界には現場に詳しい「現場参謀」のような方たちがいて、ITエンジニアやコーポレート人材とともに現場の課題をイノベーションの種として吸い上げ、高いパフォーマンスを発揮されているシーンをよく見かけます。
平野:確かに、イノベーションの種は現場に転がっていると思います。例えば、デジタルメニューブックは2週間ぐらいでつくったものを一部の店舗で試験的に導入して課題を拾い、その都度改良を重ねて対象店舗を拡大していきました。現在4店舗で試験導入中の入店案内システムも同様の流れです。導入店舗を広げるたび、現場で見つかった新たな課題に対処し改善を図る。この繰り返しで店舗系DXを進めています。
――配膳ロボットはグループ全体で3,000台の導入を完了されています。このロボットも頻繁にアップデートを繰り返されたのですか。
平野:いいえ。音声を変えたぐらいで、ほとんどアップデートせずに利用を続けています。ロボットの動線にも変化はありません。変化といえば、お客様と従業員の双方が利用に慣れたことで、ロボットが運ぶべきものと人間が運ぶべきものを明確に区別できるようになりました。そういう意味ではロボットの進化というよりも、ロボットの特性に合わせて人間が進化した面があると感じます。
――これは大きなポイントです。配膳サービスといってもテーブルに料理を並べることまではロボットにはできない。そのタスクを装備するには膨大な開発コストがかかってしまう。でも客がロボットの特性に慣れ、少しだけロボットを助ける関係が成立すれば、この課題はクリアできます。こうした関係性を築く仕掛けはどこにあるのでしょう。
平野:やはり外観が「ネコ型」という点が大きいと思います。当初はネコ型以外も含め3種同時に店舗導入したのですが、最終的にネコ型に絞りました。
――ネコちゃんだと通路を譲ったり、席を引いたりしてあげる気になりますからね。店舗設計もロボットフレンドリーにしていく流れはありますか。
平野:一部店舗では、調理してすぐに届けられるよう配膳ロボットが厨房前まで入れる設計にしています。人とロボットが共存しやすい環境づくりは意識していますね。
――配膳ロボット導入後、従業員の歩行数が42%少なくなった、というデータも公表されています。高齢従業員も働きやすくなったのでは。
平野:その効果も大きかったですね。加えて、従業員が配膳以外のサービスに時間を割けるようになったことも大きなメリットです。店内を回ってお客様の困りごとを把握するのはホールスタッフの大事な仕事の一つですから。
――点心の業態では「アツアツ小籠包」というプロジェクトもスタートしています。こういうユニークな提案はどこから生まれるのですか。
平野:小籠包の食べごろは調理後4分以内とされています。「いかにして出来立ての小籠包を提供するか」という課題は現場から上がっていました。それを念頭にプロジェクトメンバーの一人が、スマートグラス(メガネ型のウェアラブル端末)を使ってみてはどうか、と提案したのがきっかけで動き出しました。料理が仕上がるタイミングをフロアスタッフに伝達できるようになれば、さまざまなサービスに応用できると考えています。
「困りごとならいくらでも話せるよ」
――IT部門を担う平野さんのチームメンバーのキャリアパスについて教えてください。
平野:IT部門は「店舗と工場周り」「本部周辺」「お客様サイド」「インフラ」を扱う4グループに分かれています。キャリアパスについては本部周辺を担当している富名腰ディレクターに直接、話してもらいましょう。
富名腰:メンバーのキャリアでいいますと、プロパーが8割、中途採用者が2割です。中途採用者はITベンダー出身のエンジニアが中心で私もその一人です。プロパーは店長経験者がIT部門に異動してくるコースが基本です。パソコン好きでITにマッチしそうな適性の人が選ばれています。コロナ禍前後から社内の働き方が変化し、デジタル化が進んだことで多様なチーム編成になりました。業務部門とIT部門の間には大きな壁があるのが通例ですが、当社は混成チームがさまざまなプログラムに取り組んでいるため、ITによるシステム構築だけでは細かなサービスには手が届かないのは当然という認識が業務部門に浸透しています。IT部門にはサポートできるところを手当てしてもらえばいいという理解が広がった結果、IT部門の仕事もやりやすくなりました。
――本部のDX推進は「困りごと改善タスクフォース」と呼ばれていますね。
富名腰:当初は「DXプロジェクト」という名称でした。各部門の役割を明確化し、無駄をなくすという発想で立ち上げましたが、これがよくなかった。DXというと縁遠いと感じてしまう人が多いのですよね。従業員全員が幸せになることを第一に考え、「困りごと改善タスクフォース」に名称変更したところ、「困りごとならいくらでも話せるよ」という方向に社内の空気ががらりと変わりました。社外人材も活用して年間何百もの案件に対応し、解決できることがどんどん広がっています。ITパスポート取得者は年間約30人もいて、IT企業みたいになっています。部署横断的に延べ400人ほどが参加する自主勉強会では毎週社外から講師を招いたり、他社のベンダーさんを訪ねて話を聞いたり、エクセルの使いこなし術も共有したり。会社のサポートがなくてもみんな自発的に参加しています。
――自動化やDXは現場の困りごとや課題に向き合うことで切り拓かれていく、と私たちも考えています。
富名腰:今まで現場で「困りごと」と認識されていた「やりたくないこと」が、DXの推進によってやらなくて済むようになる。省力化によって無駄に気付く。こういった経験の積み重ねが従業員の幸せにつながると実感できたのは大きな収穫だと思います。
――働きがいを感じられる、といった声も聞かれますか。
平野:IT部門はこの2年間で一人も辞めていません。台湾などの海外子会社でも日本国内のシステムを導入したいという声が高まっており、グローバル競争力につながる手応えも感じています。
■平野 曉 氏 プロフィール
株式会社すかいらーくホールディングス執行役員/マーケティング本部マネージングディレクター
1994年中央監査法人に入社(公認会計士)。アクセンチュア株式会社 シニアマネージャー、SAS Institute Japan株式会社 BPM事業本部マネージャー、クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社(現IQVIA サービシーズ ジャパン株式会社)経理財務本部シニアディレクターを経験。2015年4月旧株式会社すかいらーく入社後、財務本部ディレクターを経て、2019年1月よりIT本部デピュティマネージングディレクター、同年9月より執行役員、2020年1月よりIT・マーケティング本部デピュティマネージングディレクターを務め、同年7月にIT本部マネージングディレクターに就任。2022年9月より現職。
執筆:渡辺豪
撮影:平山諭


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ