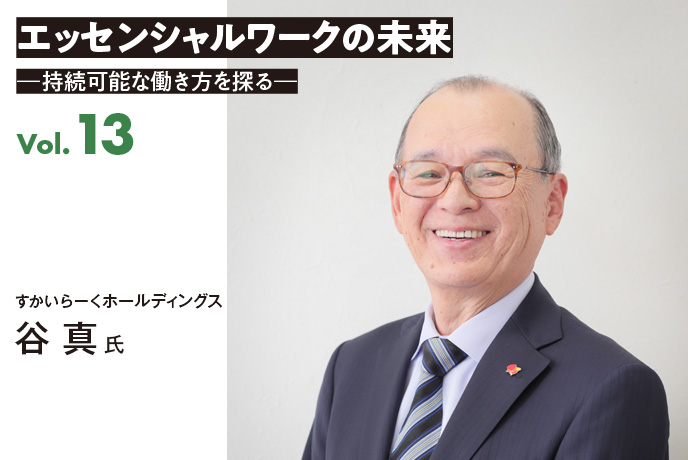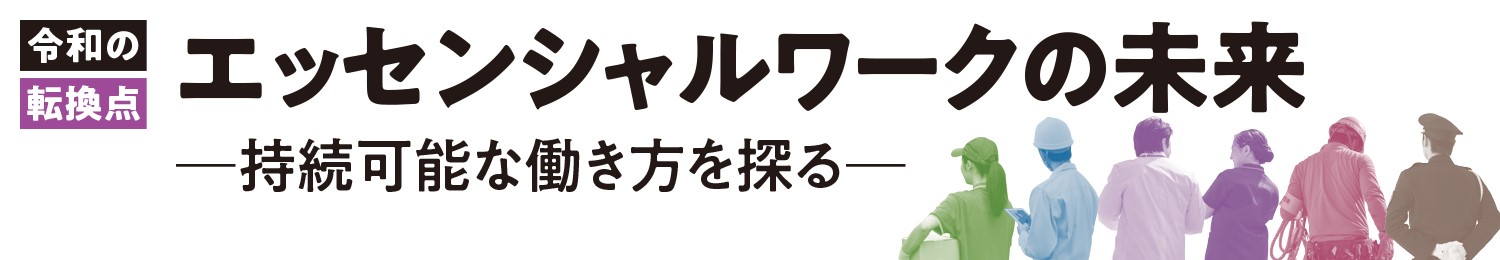
賃上げと労働時間削減をセットで実現 顧客に値上げ求め原資を確保――両総グランドサービス
バス運転士は2030年、約3万6,000人もの不足が予測されるなど、人手不足の深刻化が見込まれている。コロナ禍で事業基盤が揺らいだ後に一転、インバウンド需要が急増するなど経営の乱高下にも見舞われるなか、どのように人手不足を乗り切ろうとしているのか。空港利用者の送迎サービスなどを展開する両総グランドサービスの川島孝之社長に聞いた。

株式会社両総グランドサービス
代表取締役社長 川島 孝之 氏
コロナ禍で離職が増加 時間外労働の上限規制も人手不足に拍車
――現在予想されている人手不足が、現実味を帯びてきたという感覚はお持ちですか。
バスやタクシーの運転手は、コロナ禍による事業者の経営悪化と時間外労働の上限規制適用(2024年問題)が減少に拍車を掛けており、団塊世代が現場から完全に退出する頃には、ドライバーの減少率はかなり大きくなると思います。当社を設立した約40年前、ドライバーの平均年齢は20代でしたが、今は50代後半くらいになっています。採用についても2010年頃までは、相当数の応募があり書類選考と二次面接で人数をかなり絞り込んでいましたが、今は当時の5分の1くらいに減ったように感じます。
――コロナ禍では空港利用者が激減したと思いますが、困難な時期をどのように乗り切ったのでしょうか。
コロナ禍による乗客の急減で、売り上げは一時期、前年比75%減という厳しい状況に陥りました。しかし過去にリストラを実施したとき、残った従業員への打撃が大きかったことなどから、今回は雇用を維持しました。雇用調整助成金を利用しながらワークシェアをして最低人数を出勤させましたが、賞与も出せず、収入減を理由に離職した人もいました。
経営的な余力が失われたため、定年後のシニアの待遇改善もできなくなり、定年退職者が嘱託に移行せず退職してしまう事態も起きました。このためコロナ禍が収束すると、ドライバーが減った状態でインバウンド需要に応じるという、非常に難しい対応を迫られることになりました。
――インバウンド需要の急拡大に加えて、時間外労働の上限規制も適用されるなか、どのように必要な人手を確保していますか。
2024年問題については、事前にドライバーの拘束時間の変化などを算出し、どの程度人員が足りなくなるかを予測していました。それをもとに不足する人材の補充策として、内勤者や管理職の免許保有者に一時的に乗務してもらうことを考えたのです。内勤者には飛行機の発着ピークである朝方と午後2~5時の時間帯に、スポットで乗務してもらい、同時に朝の内勤者数を増やして事務所内の業務も滞らないよう配慮しました。内勤者の半分以上はバス乗務が可能ですし、乗務計画を組んでいる立場として、自分が乗れば不足が埋まることがわかっているので、乗務についても納得してくれました。
これ以上人手不足が進んだら、時短勤務のドライバーの採用も検討せざるを得ないかもしれません。しかし異なる勤務形態を作ることで、フルタイムのドライバーが不満を抱く恐れもあり、現時点では短時間勤務の制度は設けていません。主婦(夫)パートを採用したいという気持ちもなくはないですが、主婦(夫)が働きやすい10~14時の時間帯は発着ピークから外れており、需要も少ないためあまり効果的ではないと思います。
残業時間が半分以下に 値上げ応じない顧客との取引は断る
――2024年問題で長時間労働の抑制が求められる一方、残業代が減るとドライバーの生活が打撃を受ける懸念もあります。どうすれば残業削減と収入確保を両立できるでしょうか。
以前はドライバーが、朝と午後のピークを1人でカバーし、1日の拘束時間が10時間を超えてしまう日もありました。ホテル送迎の業務は待ち時間が多く、実際の運転時間は2~3時間と、肉体的な負担は比較的軽い一方、飛行機の遅れなどでイレギュラーな残業が生じる日もあり、月間の時間外労働が著しく長くなる人もいました。このためコロナ禍前から、残業削減は大きな課題となっていました。
そこで2024年問題も踏まえて2019年に「5カ年計画」を策定し、賃上げと労働時間削減にセットで取り組み始めました。基準内賃金を上げれば残業代のベースも上がり、時間外労働が減っても手取りはさほど変わりません。コロナ禍の間は計画が止まりましたが、収束後に3年分を一気に取り戻し、最終的に残業を概ね週20~40時間に減らすことができました。
――労働時間を削減するには、顧客の理解も不可欠だと思いますが、どのように交渉を進めたのでしょうか。
お取引先には、2024年問題に伴いバス運行の効率化が不可欠なことをご説明し、ダイヤ改正などを実施しました。ダイヤを変えればお取引先側から、さまざまな対応を求められることもあります。交渉はかなり大変で、ご理解を頂くまで半年かかった取引先もあります。
またダイヤ改正と同時に、取引価格の値上げもセットでお願いしました。しかし、なかなかお取引先のご理解が得られず、苦労しました。
賃上げの原資は、お取引先からいただくしかありません。政府も2023年、燃料費の高騰などを理由に、貸し切りバスの下限運賃を引き上げています。こうしたなかで、値上げにご理解いただけないお取引先には、ご契約の更新が困難なことをお伝えせざるを得ませんでした。
――取引をやめるというのは、経営に影響を与えかねない思い切った判断ですね。
今はインバウンド需要なども旺盛で、需給バランスを考えても、適正な対価を求めるチャンスだと考えました。当社のお取引先の大半が、発注者と直接契約する「直請け」であることも、交渉力を高めたと思います。中間業者が入らないので、値上げ分をまるまる賃上げなどに充てることもできました。
残念ながらご契約の更新ができなかったお取引先が「やはりお願いしたい」と戻ってきたこともあります。信頼できる事業者をということで、改めてお選びいただいたのだと思います。大変ありがたいことです。
全取引先の4割を占める外資系のお取引先については、総じて交渉がスムーズでした。外資系のお取引先は円安が進む中で、ドル換算の支払い価格が下がり続けているので、ご理解いただきやすかったのだと思います。
ドライバーの年収500万円超 外国人ドライバーの採用拡大も
――ドライバーの待遇は現在、どのようになっていますか。
ドライバーの平均年収は500万円を超えています。また2025年から、年間休日も段階的に増やして、週休2日に近づけようとしています。今は4日勤務の後1日休みというサイクルで、月7日程度休みがある計算ですが、いずれ4日勤務で2日休みのサイクルを実現したいと考えています。中堅・中小は収入面では大手に及ばないので、労働環境に魅力を感じてもらえるよう、労働環境改善に取り組むつもりです。
――大型2種の規制が変わり、最短で19歳から免許を取れることになりました。新卒の採用強化も視野には入れていますか。
規制が変わって、若者の門戸が広がることは歓迎しています。ただ当社に関しては、お客様へのきめ細かいサービスを一番のセールスポイントにしているので、ある程度社会経験を積み、人間的に成熟した人の方が合うように思います。
また当社に応募してくる人の多くは、ある程度長く働ける制度があることに魅力を感じていると感じています。現在はシニア雇用の制度を変更して、65歳の定年を迎えた後も一定の待遇を維持しながら働け、ドライバーの最高齢は72歳です。ただ加齢に伴い運転のリスクは確実に高まるので、70歳以降は契約期間を半年~3カ月に変え、健康で無事故無違反であることのほか、普段の仕事ぶりや顧客の意見なども踏まえて、個別に更新するかどうか判断しています。
――ドライバー確保に向けた新たな展望はありますか。
外国人ドライバーを積極的に受け入れていきたいと考えています。当社は事業の8割が空港関連で、航空会社とのやり取りや契約などで、日常的に英語が使われています。このため外国人労働者にとっては馴染みやすい環境だと思います。航空会社のクルーなどを送迎する場合も、日本語は流暢でなくとも、英語さえ話せれば意思疎通はできます。英語が通じやすい労働環境をアピールして採用を有利に進めたいですし、今後は組織として、外国人労働者を受け入れる仕組みも整えていくつもりです。
――ドライバーの人手不足に加え、残業の上限規制、コロナ禍、原油高騰などの課題が重なるなか、残業削減と賃上げの改革を進め、さらなる人員確保の仕組みを検討されているのですね。ありがとうございました。
聞き手:岩出朋子
執筆:有馬知子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ