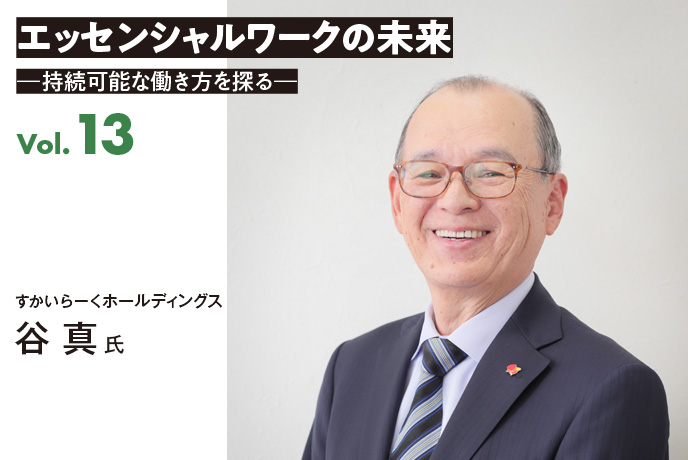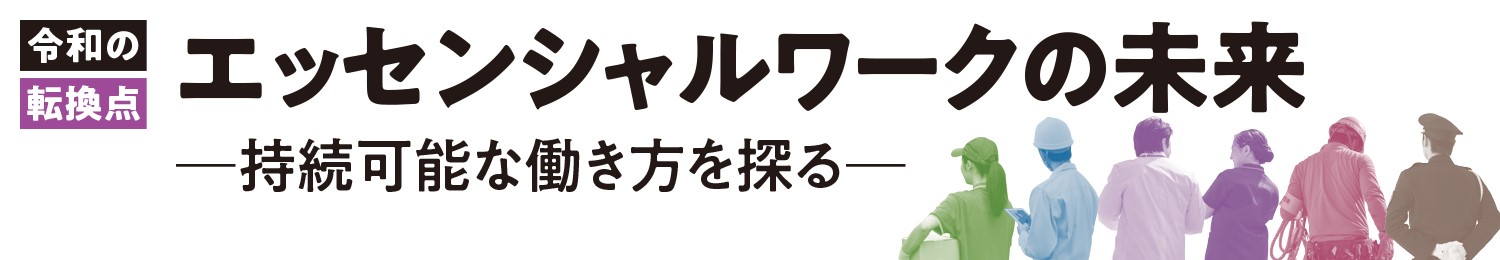
ロボット活用、技能実習生の長期育成で人材不足に対抗――グローブシップ
ビルメンテナンスのグローブシップは、ロボットを活用した省人化に加え、外国人材の長期育成と登用によって人手不足に対抗しようとしている。設備投資や人材育成のコストをかけてでもこうした施策に踏み切った背景とその効果について、ロボット導入と人材管理、それぞれの責任者にたずねた。
 グローブシップ株式会社 常務執行役員 諸橋 勝悟氏(写真左)
グローブシップ株式会社 常務執行役員 諸橋 勝悟氏(写真左)
グローブシップ株式会社 FMDX開発事業部長 佐々木 靖氏(写真右)
 グローブシップ株式会社 常務執行役員 諸橋 勝悟氏(写真左)
グローブシップ株式会社 常務執行役員 諸橋 勝悟氏(写真左) グローブシップ株式会社 FMDX開発事業部長 佐々木 靖氏(写真右)
ロボットと人の「ベストミックス」が大事――FMDX開発事業部長・佐々木靖氏
――ロボットを導入するという意思決定に至ったのは、どのような経緯からでしょうか。
一番の理由は、清掃スタッフを採用しづらくなったことです。オフィスの清掃は早朝に行っているイメージが強いと思いますが、当時は早朝勤務スタッフの採用が難しくなりつつあり、比較的採用しやすい深夜帯の募集に力を入れていました。しかし深夜帯での採用も難しくなり、加えて都内の複数エリアで大規模な建築計画が進められていたため、今後ますます人手を確保できなくなるのではないか、という懸念が強まりました。さらにコロナ禍もあり、清掃ロボットの導入で状況を打破しよう、という経営層の意識が高まったのだと思います。
――どのようなプロセスで導入していったのでしょうか。
2019年当時、日本に業務用の清掃ロボットはほとんど存在せず、海外製品もサイズが大き過ぎるなど、導入が難しそうなものばかりでした。家庭用の清掃ロボットをオフィスで試したこともありましたが、一般の家庭と比べてオフィスは清掃範囲が広く、業務用としての導入は実現しませんでした。
同じ時期、ソフトバンクロボティクス社の清掃ロボット「Whiz」の使い勝手や性能を検証してほしいという依頼があり、当社の多くの現場で検証を繰り返しながら、多くの改善点をフィードバックしました。メーカー側もきめ細かく対応してくれて、次第に品質、性能ともに向上したのです。このため当社も十分業務に実装できると判断し、本格導入に至りました。
2020年には機能をアップデートした「Whiz i アイリスエディション」も投入し、当社から他社への外販も始めました。販売したWhiz シリーズは現在、全国で約300台が稼働しています。また2024年4月からは除塵に加えて床洗浄もできるPUDU社の清掃ロボット「CC1」の取り扱いを始めています。
2020年には機能をアップデートした「Whiz i アイリスエディション」も投入し、当社から他社への外販も始めました。販売したWhiz シリーズは現在、全国で約300台が稼働しています。また2024年4月からは除塵に加えて床洗浄もできるPUDU社の清掃ロボット「CC1」の取り扱いを始めています。
清掃ロボットは「自走する掃除機」 機械と人の組み合わせに苦労も
――現場に清掃ロボットを導入するにあたって、どのような苦労がありましたか。
当初はビルの関係者に清掃ロボット導入のお話をすると、安全確保のため人を立ち会わせるよう求められました。しかし、人が立ち会うなら省人化にはなりません。また清掃スタッフも、自分たちの仕事をロボットに奪われるのではないかという不安があったようで、導入に否定的な意見もありました。しかし清掃ロボットの認知度が高まるにつれて安全性への不安が解消され、清掃スタッフにも仕事が奪われることはないと理解が進んで、逆に効率的な運用方法を考えてくれるようになりました。
ただ現在も「清掃ロボットを導入すれば単純にコストが下がる」と考えるお客様は少なくありません。清掃ロボットはあくまで自動で移動が可能な掃除機であって、全ての問題を解決できる存在ではありません。自分でドアを開けて部屋から部屋へ移動することも、自分でエレベーターに乗ることもできません。壁を傷めないよう壁際を避ける設計になっているため、その部分は人が清掃する必要もあります。清掃ロボットは省人化、効率化に非常に有効ではありますが、人と清掃ロボットをうまく共存させる仕組みをつくることで、その力を最大限に引き出せるのです。
――具体的にロボットをどのように活用し、それによってどんな課題が見えてきましたか。
まずは清掃ロボットにできること、できないことをスタッフが理解することが大切です。スタッフは清掃ロボットを清掃場所まで移動させ、ロボットが床清掃を行い、ロボットが稼働している間は、水回りや机の下、壁際など清掃ロボットができない場所の清掃をします。壁際や机の下だけなら、大型掃除機でなくハンディクリーナーのような軽い掃除機を使用できるので、スタッフの負担も軽くなります。床掃除を機械に代替させ、空いた時間にスタッフが別の場所を担当することで、人員の削減や美観が向上するといった効果が出ています。
ただし、人と清掃ロボットの効率的な役割分担をつくるには、清掃範囲や時間帯、スタッフの人数などの条件をパズルのように組み合わせる必要があり、単純化できないのが難点です。生成AIにデータを読み込ませても、なかなか有効な提案は出てきません。結局、現状ではベテランの知見に頼るのが最も効果的で、属人性から脱しきれていないことも課題となっています。
――FMDXチームの体制や、ロボット開発にどのように関わっているのかを教えてください。
現在、FMDX開発事業部は総勢14人で、このうち清掃ロボットに関わるのは4人です。現場出身の社員が多いですが、異業種から中途入社した人もいます。ロボットの運用は予定通りの結果が出ないことも多いので、めげずに何度でも取り組めるポジティブさが必要です。幸いそういうメンバーがそろっていると思います。
例えば最近のトラブルでは、ごみの量が想定より多く、モーター周りに細かいごみが詰まって止まってしまいました。また女性用化粧室では、落ちている髪の毛が多過ぎて清掃しきれず、モーターの回転数を細かく変えてテストを繰り返しました。ロボットがカーペット敷きの床をいつも同じルートで曲がると、カーペットがこすれて薄くなってしまうので、タイヤの道筋を分散させられないかなども検証しました。検証結果や要望は、開発に役立ててもらえるようメーカー側にも共有しています。
他にも、エレベーターにロボットが自動で乗降できる仕組みの導入にも取り組んでいます。ロボットが自動で他のフロアに移動できるようになれば、作業効率が大幅にアップすると期待しています。
時代に合わない法制度 社会の偏見解消も課題
――今の法制度や社会の仕組みなどについて、変えてほしいことはありますか。
ビルメンテナンスに関する法律の多くは、数十年前に制定されて以降、ほとんど見直されていません。例えばオフィスには2カ月に1度、環境測定が義務付けられていますが、築10年未満のオフィスの多くは、温度や湿度などが常にモニターされています。センサーやカメラも進化するなか、点検方法に関する規制も見直していいかもしれません。
またこれは社会の問題ですが、清掃や警備の作業に従事する人は下に見られがちで、カスタマーハラスメントも受けやすい仕事だと感じます。しかしこうした人たちは、社会にとって必要不可欠なエッセンシャルワーカーです。ロボットやIoTを扱うことで、少しでも偏見の解消につながればうれしく思います。
またこれは社会の問題ですが、清掃や警備の作業に従事する人は下に見られがちで、カスタマーハラスメントも受けやすい仕事だと感じます。しかしこうした人たちは、社会にとって必要不可欠なエッセンシャルワーカーです。ロボットやIoTを扱うことで、少しでも偏見の解消につながればうれしく思います。
技能実習生にも、長期雇用の道を用意――常務執行役員・諸橋勝悟氏
――外国人材を積極的に受け入れていますが、採用にあたり留意していることはありますか。
当社は2018年から、ミャンマー人技能実習生の受け入れを始めました。戦略的に採用地域を絞り込み、企業イメージを根づかせることで、優秀な人材を集めようとしています。また受け入れにあたっては、現地の送り出し機関に「丸投げ」せずに当社の社員が現地に行き、生活環境・教育内容を確認するとともに、来日後のサポート体制などを丁寧に説明しています。
また技能実習生には長く活躍してもらうことを期待し、キャリアプランを示しています。5年の実習期間が終わる頃には、仕事のスキルも向上するとともに、当社の企業風土も身に付き、大事な戦力に成長しているからです。このため実習終了後も、特定技能1号の在留資格を取得し、社内でキャリアを積む道を用意しています。外国人材を長期的に働いてもらう大切な人材として受け入れていることが、成功につながったと思います。
また技能実習生には長く活躍してもらうことを期待し、キャリアプランを示しています。5年の実習期間が終わる頃には、仕事のスキルも向上するとともに、当社の企業風土も身に付き、大事な戦力に成長しているからです。このため実習終了後も、特定技能1号の在留資格を取得し、社内でキャリアを積む道を用意しています。外国人材を長期的に働いてもらう大切な人材として受け入れていることが、成功につながったと思います。
――外国人材を登用する仕組みも整えていると聞きました。
このほど外国人の女性2人が、課長代理に昇格しました。うち1人はミャンマー人で、技能実習生たちのチューターとして、また日本での「お母さん」的存在として生活指導はもちろんのこと、公私ともに親身に相談に乗ったり、会社の方針などを伝えてくれたりしています。今回登用したのは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働く正社員ですが、今後技能実習生が育ってくることを考えて、リーダー候補として育成し管理職へ登用する仕組みも設けています。
また、現在ミャンマーは軍事政権下でもあり、採用リスクを分散する必要があると考えて、2024年からはインドネシア人技能実習生の受け入れも始めました。送り出し地域も、ミャンマー人技能実習生と同様、戦略的に選んであえて都市部から離れたスマトラ島に決めました。
このほど外国人の女性2人が、課長代理に昇格しました。うち1人はミャンマー人で、技能実習生たちのチューターとして、また日本での「お母さん」的存在として生活指導はもちろんのこと、公私ともに親身に相談に乗ったり、会社の方針などを伝えてくれたりしています。今回登用したのは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働く正社員ですが、今後技能実習生が育ってくることを考えて、リーダー候補として育成し管理職へ登用する仕組みも設けています。
また、現在ミャンマーは軍事政権下でもあり、採用リスクを分散する必要があると考えて、2024年からはインドネシア人技能実習生の受け入れも始めました。送り出し地域も、ミャンマー人技能実習生と同様、戦略的に選んであえて都市部から離れたスマトラ島に決めました。
――政府による外国人労働者の受け入れ政策については、どのように考えていますか。
外国人材の受け入れは、不法就労との兼ね合いもあって規制緩和のさじ加減が難しいことは理解しています。しかしそれでも、特定技能1号から特定技能2号へのハードル(難度)は高過ぎると感じます。在留資格そのものを緩和すべきとまでは言いませんが、これから外国人の労働力を活用しようとするのであれば、難度の高い資格・技能試験等をクリアさせるために、国・企業が足並みをそろえて、日本語習得や技能のサポート体制を充実させる必要があると思います。
執筆:有馬知子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ