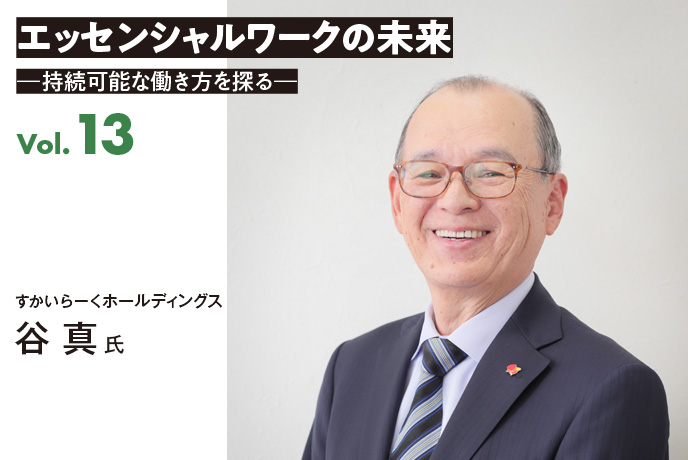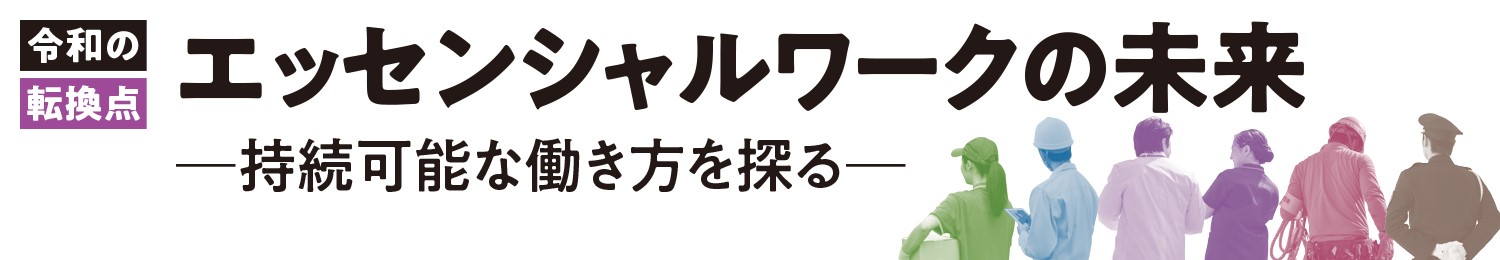
組織改革通じ人材確保の基盤を整備 業務集約通じて「全体最適」を目指す――ヤマト運輸株式会社
労働供給制約の中、運輸業のドライバー確保は今後、社会的にも重要な課題になると予想される。ヤマト運輸では、組織や制度の改革を通じて人材確保の基盤を整えると同時に、採用や業務集約などの面で現場の実情を踏まえた工夫を凝らしている。人事戦略を統括する常務執行役員の石井雅之氏と人事部長の齊藤純氏に、足元の人手不足感と取り組みについて聞いた。 ヤマト運輸株式会社 常務執行役員(人事、人材開発 統括) 石井雅之氏(写真右)
ヤマト運輸株式会社 常務執行役員(人事、人材開発 統括) 石井雅之氏(写真右)
ヤマト運輸株式会社 人事部長 齊藤純氏(写真左)
膨大な人員管理が課題 年功から職務へ人事制度を変える
――少子高齢化の進展、ECサイトの利用拡大といった変化が起きるなかで、どのような人事戦略を構築していますか。
石井:当社は、新たな付加価値創出に向けた最適な人材ポートフォリオの構築や、多様な社員の働きやすさと働きがいの向上など、経営戦略と連動した人事戦略を推進しています。その中でキャリア採用による体制強化や教育研修体系の整備、また働きやすい職場環境整備への投資など、学ぶ意欲を高めてスキルと知識の向上による社員の成長を目指しています。また当社の社訓の一つに「ヤマトは我なり」という言葉があり、社員一人ひとりが「自分はヤマトを代表している」という意識を持って自ら考えて行動する「全員経営」の精神が創業以来受け継がれています。この精神を原点に企業理念を具現化するべく、社員の成長を事業拡大に結び付ける共成長の関係を築こうとしています。
――人材確保のためには、具体的にどのような施策に取り組んでいますか。
石井:当社にはセールスドライバーだけでも約6万人の社員が在籍しています。毎月入退社が発生するために全国各地の拠点では採用・退職に関わる実務や勤怠・労働時間の管理など、労務管理に膨大な労力を要しています。多数の人材を確保し、活躍いただく前提として、社員を定量的・定性的に把握し管理するための全社的な人材管理の仕組みを強化することが必要となりますので、これを課題として取り組んでいます。
またセールスドライバーの人事制度に年功要素が強い点も課題です。公平性や仕事の魅力、そして採用競争力を高めるには、職務を起点にした制度に変える必要があります。セールスドライバーの平均年齢は40代の半ばでミドル層も多く、今後の高齢化の進展を想定すれば、スピーディーに制度を変革することも大きなテーマです。
職務を起点とした制度を機能させるには、人材を正しくアセスメントし、配置や昇進に反映させることが重要です。計画されている多くの施策に優先順位をつけ、ボトルネックをつくらないようにしながら人材を底上げすることが課題です。
役職者の底上げがカギ 人手不足感は地域差が大きい
――組織に変化を促すためのポイントは、どこにあると考えていますか。
石井:人材マネジメントのカギは、所長など事業所の運営を支える役職者の方針理解度や、スキルおよび知識を高めることだと考えています。当社の役職者には面倒見は良いものの、トップダウン型で部下を管理する人が多いと感じます。しかし社員の価値観や上司への期待値も多様化するなか、こうしたやり方は時代に合わなくなっています。マネジメントスタイルを多様化、多能化させ、部下一人ひとりに柔軟に向き合って、対話型のマネジメントを行うようにすることが、結果的にセールスドライバーの働きやすさや働きがいも高めると考えています。
――ドライバーの人手不足感について、現状を教えてください。
齊藤:ドライバーは主に長距離ドライバーと、各地域で配達を担うセールスドライバーに分かれ、2024年に乗務員に労働外時間の上限規制が課せられた際に、人手不足が懸念されたのは長距離ドライバーでした。この分野については、業務を委託するパートナー会社を増やすことで、長時間労働を抑制しつつ必要な人員を確保しています。
一方、セールスドライバーは不足感にかなり地域差があります。九州や北海道、北信越地方では必要な人手を確保できていますし、委託ドライバーに協力いただくことで安定したサービス提供ができている地域もあります。一方、関東、関西、名古屋といった都市部は共働きなどで日中不在の家庭が多く、再配達や夜間配達の需要が大きい。このため1回で配達が終わることの多い地域よりも多くの人手が必要となり、特に関東地方は不足感が強まっています。
現場主導で人手確保に工夫、業務の集約も
――将来的に予想されるドライバー不足に、どのような対策を講じようとしていますか。
齊藤:自社ドライバーならではの強みを発揮する部分は、顧客と直接会って荷物を預かる集荷の部分です。このため集荷を自社ドライバーに、配達業務を委託ドライバーに任せるといった業務分担を進めようとしています。
また私の前任地である福井県では昨年、復職者や転職者の採用、事務員からセールスドライバーへの職種変更などによって、セールスドライバー数の減少を年間数名程度に抑えることができました。福井市内のセールスドライバーを、本人の了承を得て社宅も用意したうえで、人手の足りない滋賀県境へ異動してもらったこともあります。採用できる地域でセールスドライバーを確保し、不足する地域へと配置する取り組みも、全社に広げる必要があると考えます。
――採用の工夫に加えて、組織として変えるべき部分はありますか。
齊藤:拠点の大型化、集約化に着手しています。福井県で試験的に、同じ営業所の3つのグループを1つにまとめたところ、オペレーションが効率化され首都圏と同等の生産性を維持できるようになりました。また福井県内を統括する主管支店の7つの課を一室に集めたことで、トラブルが起きた際には課長たちがその場で話し合って迅速に結論を出せるようになり、セクショナリズムも解消しました。
当社には各地域で事業を運営する「主管支店」が全国に約90ありますが、主管支店の業務を一つ上のレイヤーである「地域統括」に集約する動きも始まっています。組織の壁を崩して、部や課、主管支店ごとの個別最適から全体最適に変えることで、生産性が高まり必要な人員も10人から7~8人に減るといった効果が期待できます。
――石井さんは製造業出身ですが、他業界の視点で物流業界を見たとき、業種の違いによる気付きはありますか。
石井:製造業は、省人化を進めて人を介在させないプロセスをつくり上げ、安全性や品質、生産性を高めるというのが基本思想です。一方、運輸業においてはドライバーが不可欠な職種であり、人材の質を高め差別化を図るという考えがベースにあります。実際に当社はそれによって差別化に成功し、成長してきました。ただその分、人材と機械の最適バランスを目指す考えが希薄になり、省人化のための投資が少ないように感じます。業務のどの部分を人が担い、どこを機械が担うべきかを経営層が明確化し、もっと積極的に社員に伝える必要があるでしょう。「人だからこそ担える役割」をドライバーに伝えることは、エッセンシャルワーカーとしての自分の仕事の価値を再認識し、エンゲージメントを高めることにもつながると思います。
認識されない教育の重要性 現場と本社の意識に乖離
――齊藤さんは、最近まで福井県を担当するエリアの責任者をされていたとのことですが、現場の改善に最も必要な取り組みは何だと考えていますか。
齊藤:本社の考えが十分現場に伝わらず、両者に乖離が起きていると感じます。例えば本社の人事は、教育による人材育成が重要だという考えを再三打ち出していますが、現場にはあまり響きません。セールスドライバーはハンドルを握って収入を生み出すことが最優先で、非稼働時間は極力つくらないという考えが浸透しているからです。この結果、現場には育成を疎かにしてきたひずみも現れているので、必要な育成投資をぶれずに実行し、かつての強いヤマト運輸を取り戻さなければいけない、と強く思います。現場の教育を進めるには、主管支店長、所長ら役職者の理解も不可欠で、現場と本社の距離を縮めるのが、両方を知る私の役割だと考えています。
――労働人口減少の中、インフラの維持という社会課題にどのように取り組んでいくお考えでしょうか。
石井:1社でできることには限界がありますが、政府や業界団体と連携すれば、できることは広がります。政府も物流業界のさまざまな課題を認識しており、幹線輸送サービスの自動化のようなプロジェクトを主導していますし、当社も多くのプロジェクトで協働しています。国や業界と一緒に物流全体を変えることは、最終的には消費者のメリットになります。当社としても今後の協業を通じて社会の変化をいち早くキャッチし、事業や組織、そして人材のポートフォリオを変えていく必要があるでしょう。
――社会課題解決のための政府や業界団体との連携、エッセンシャルワーカーとしての価値を高めるための人的資本投資の継続など、新しい取り組みを進められているのですね、ありがとうございました。
聞き手:岩出朋子
執筆:有馬知子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ