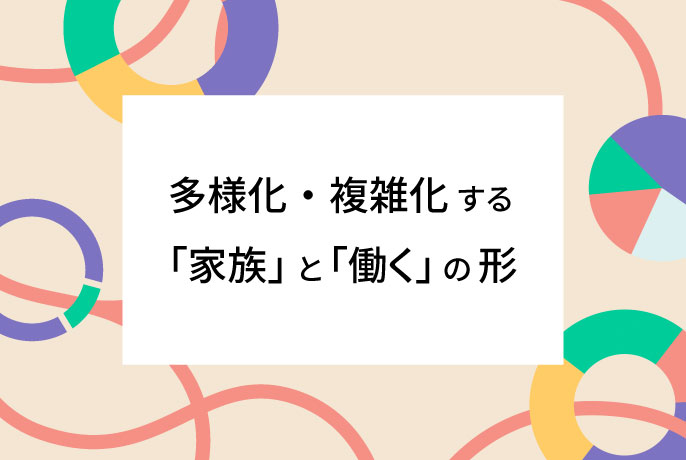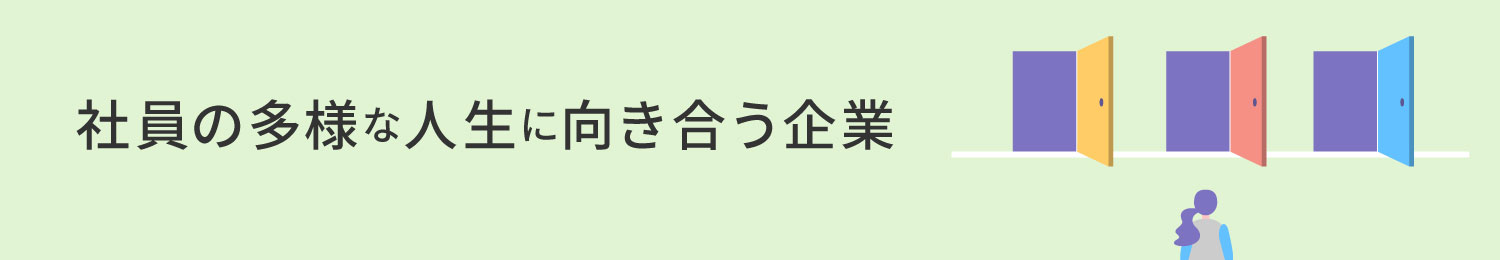
「努力した人が報われる職場」が前提 社員自ら働き方を選択し、納得して働く
 富山県高岡市の金属メーカー、CKサンエツは、社員が4つのパターンから働き方を選べる制度を設けるなどして、GPTW Japan「働きがいのある会社ランキング」に8年連続で入賞した。一方で仕事に力を注ぐ社員には、賃金や育成投資を手厚く配分し「努力して働くほど報われる」組織も実現している。釣谷宏行社長にこうした組織を作った目的や、経営にもたらす効果などを聞いた。
富山県高岡市の金属メーカー、CKサンエツは、社員が4つのパターンから働き方を選べる制度を設けるなどして、GPTW Japan「働きがいのある会社ランキング」に8年連続で入賞した。一方で仕事に力を注ぐ社員には、賃金や育成投資を手厚く配分し「努力して働くほど報われる」組織も実現している。釣谷宏行社長にこうした組織を作った目的や、経営にもたらす効果などを聞いた。
努力するほど報われるのが「働きがい」 家族の価値観を尊重
-努力した人、成果を出した人に、教育資源や賃金などを手厚く配分するという方針を徹底して打ち出しています。取り組みの狙いは何でしょうか。
自由主義社会においては、努力した人とそうでない人への配分に差がつくのはある意味で当然のことです。社員たちは、労働力の市場で競争しているのですから。才能や生い立ちによるハンディなど、努力が及ばない領域で後れを取ってしまう人は救済すべきですが、できるのに努力を出し渋った人の配分が減るのは仕方ないことと思います。当社は採用面接で「本気で働く気はある?」と正直に伝えます。「仕事は大変でも自分の力を試したい」という人を迎え入れることで、安易な離職も抑えられています。
「働きがいのある会社」ランキングでは、「働きがい」に「働きやすさ」を含めていますが、私が「働きがい」だと認識しているのは「努力するほど報われる」ことです。働きやすい職場環境の整備も大事ですが、努力の結果として、多くの人に感謝され、社会的な評価も所得も高まり、自己実現につながるなどさまざまな意味での「対価」を得られることこそ「働きがい」だと考えています。
-子育てや介護を担う社員が一時的に働く時間を制限し、配慮すべき事情がなくなったら再び仕事に力を注ぐ、といった働き方も可能ですか。
もちろん可能です。人手不足の企業では、長期の育休取得などに難色を示すケースもあるようですが、当社では、ある程度人材を確保できていることもあり、きちんと休んで万全の態勢を整えてから復帰してほしいというのが基本的な考え方です。何事も中途半端はいけません。本気で育児をするためには、きちんと長期の育休を取得すべきです。今も管理職の男性が、数カ月間休んで父親の介護に当たっていますし、男性社員の育休申請がたった1週間だと「1年取ったらよい」とはっぱをかけることもあります。また育休を取る女性にも「たとえ3年間でも4年間でも育児に専念してきても、戻る席は用意するよ」と伝えています。
-社員の仕事と家庭のバランスについて、どのような考えで臨んでいますか。
各家庭の持つ家族観に、社会や企業が介入してはいけないと考えています。女性が出産後も働くのは本人にとっても社会にとってもいいことだ、というのは一つの価値観にすぎず、妻は子育て、夫は仕事に専念するという役割分業も、その逆の役割分業も、夫婦双方が納得しているなら認められるべきです。一方で当社には、出産後もベビーシッターを活用するなどして、育児をしながら残業をこなしている社員もいますし、そうした外部労働力を利用できるように、十分な年収を社員が確保可能なようにしています。ちなみに、昔から富山は3世代同居が多い土地柄でもあり、祖父母の協力を得て共働きしている社員もたくさんいます。
2024年6月には、出産・育児を経て復帰した30代の女性社員が取締役に就任しました。彼女には産前同様に仕事をオファーし、できることをやってもらっていますが、たいていの仕事は断らずに引き受けています。ただ子どもが病気のときなどはすぐ帰宅することもあり、臨機応変に対応しています。
働き方を4パターンから選択 仕事ぶりを賞与に反映
-社員の価値観を尊重する働き方とは、具体的にはどんな仕組みでしょうか。
「働き方選択制度」を設け、社員に毎年①仕事最優先、②仕事優先、③私生活優先、④私生活最優先、の4つの選択肢から希望する働き方を選んでもらいます。育児や介護などで私生活優先の働き方をした場合は、その分を賞与で調整します。当社は2025年度の年間賞与を平均300万円支給する予定ですが、①の働き方をして600万円もらう人もいれば、④の働き方をして140万円に留まる人もいて、実際に受け取る金額には非常に大きな差があります。ただ140万円でもこの地方ではトップクラスの賞与金額ですし、雇用が不安定になるわけでもありません。また④を選択していた人が、生活に制約がなくなったときに①や②に戻ることも可能です。
-選択制度は、職場ではどのように運用されているのでしょうか。
上司は、例えば製造工程で不良品が出るなどして残業が必要になったときは、①を選んだ人から順にお願いしていきます。急な仕事を頼んだときに、次々と「僕は無理です」「今日はできません」と断られ続けると、引き受けようと思っていた人まで働く意欲を削がれてしまいます。何より、声をかける上司の方が、精神的にやられてしまいます。選択制度があることで、仕事が発生したときに真っ先に声をかけてほしい人と、事情が許せば引き受けたい人、全く声をかけないでほしい人が事前に分かるようになり、上司の精神的負担も軽くなりました。
さらに「あいさつしたら何点」「欠員をカバーしたら何点」「残業を引き受けたら何点」といった職場の評価項目ごとの配点を掲示しています。一般社員は1点取ると賞与が2万3000円上がると決まっていて、5点取れたら11.5万円アップする計算です。例えば①の働き方をした人が、残業を引き受けたり欠員をカバーしたりして、その評価項目を全うしたら5点満点を付けるという形で運用しています。このほか、会社の方針に沿って仕事をしているか、教育プログラムに参加したかなども3カ月ごとに評価しています。
-「努力が報われる」ことによって、社員の仕事に対する意識はどのように変わりますか。
適切な評価表(項目と配点)を公表しておけば、社員は何をすれば評価(収入)が上がるか、明確に理解できるようになります。「有効な不良対策をすれば評価が高まる」ということが分かっていると自然に、例えば不良が発生したとき、自分から原因を徹底的に追究し再発防止策を講じるようになります。それが組織人としての自立だと思うのです。評価表は、社員が点数の意味を考え自ら動くという、自立に向けた共通認識を醸成するための一覧表だと思っています。
多様な社員を適材適所で配置し「ばらつき」を吸収
-評価に対する社員の納得感や透明性を高めるための取り組みはありますか。
管理職が部下の働きぶりをきちんと評価できるよう、評価者研修を実施しています。また、社員自身の自己採点と会社の評価点に大きな差が出た評価項目があれば、面談を通じて差異分析し、お互いの主張を擦り合わせます。社員も、上司からどこを直せば何点上がるというフィードバックを受けることは、次回の賞与金額アップの参考になるので重要で、耳に痛いことを言われても是正のモチベーションにつながります。逆に言えば、本人にとってメリットのない抽象的な面接は「説教」か「パワハラ」でしかないと思います。
シビアな評価についていけず離職を希望する人もいました。しかし他社の賃金水準や職場環境を知るとたいてい辞意を翻し、「この会社で頑張ろう」と覚悟を決める人が多いようです。一度離職した人が数カ月後に、再入社を希望してくることもあります。新入社員と同じ待遇からの再スタートになるのですが、「それでもいい」と入ってきて猛烈な努力をして成績を上げ、離職前と同程度の水準に戻す人もいます。
-釣谷さんがこうした仕組みを取り入れたのは、どんな経緯からですか。
私は前職が銀行勤務でしたが、その後、当社に転じると、多くの社員が成果に関係なく年功序列で昇進・昇給していて、これはおかしいと思いました。
このため自分が社長になってからは、学歴や年齢に関係なく結果を出した人を3カ月ごとに評価して、昇進させたり、賞与を多く分配したりする仕組みに変えました。給与には年功序列的要素を残しましたが、年収に占める賞与の比率がどんどん高まり、今では、新入社員が50代のベテラン社員より多くの賞与を得るケースもあります。
当社では、賞与の金額は会社の業績に連動せず、会社が赤字のときも下げません。会社の業績が悪くても努力した社員にはきちんと報いる。業績の良し悪しは社長の責任ですから。社員のせいにしてはいけません。
地方企業である当社に入社する人で三拍子も四拍子もそろった万能の人材は、私も含めて、めったにいません。このため各自の持ち味を活かした適材適所を実現することで、互いの不十分なところを補い合わなければいけないのです。でも、完璧な人材が少ないことが、かえって多様な人材を活かす仕組みを作ることにつながっているように思います。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ