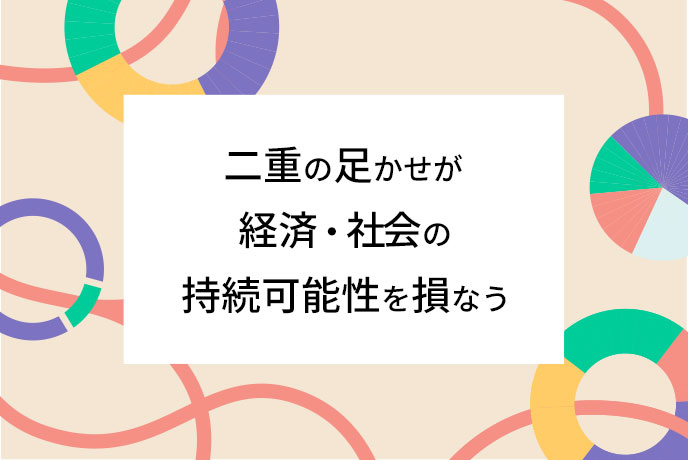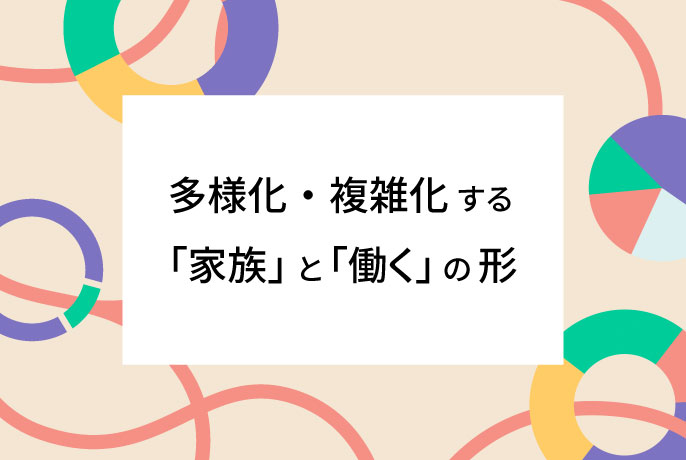諦めず長期的な視野で取り組む姿勢が、時代に応じた制度への転換に必要
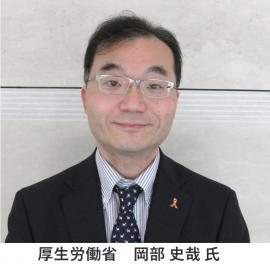 短時間労働者や共働き家庭の増加をはじめ、「家族」と「働く」の選択が変化・多様化するなかで、個人の生活や働き方を支える制度のあり方について改めて議論される場面が増えている。厚生労働省で長く社会保障政策に関わってきた大臣官房参事官の岡部史哉氏に、今起きている社会の変化に社会保障制度が対応していくために、どのような視点が必要かを聞いた。
短時間労働者や共働き家庭の増加をはじめ、「家族」と「働く」の選択が変化・多様化するなかで、個人の生活や働き方を支える制度のあり方について改めて議論される場面が増えている。厚生労働省で長く社会保障政策に関わってきた大臣官房参事官の岡部史哉氏に、今起きている社会の変化に社会保障制度が対応していくために、どのような視点が必要かを聞いた。
社会的にカバーすべきリスクの範囲は、時代に応じて変わる
―岡部さんは厚労省で年金課長などを歴任され、年金政策などに長く関わってきました。現在の社会保障制度をどのように見ていますか。
厚生年金制度は第二次世界大戦中の1942年、賃金水準が比較的均等で労働形態が定型的なブルーワーカーを主な対象と想定して創設された経緯から、時間単位で労働を管理していた時代の仕組みを引きずっているといえます。今や働き方は多様化し、労働時間と働き手が生み出す成果との相関関係は、昔に比べて希薄化しました。パートタイマーの増加に伴い、近年は適用対象者が週30時間以上働く人から週20時間以上働く人に拡大するなど、適用対象を大きく変えた面もあります。
社会が個人のリスクをどこまでカバーすべきかは時代によって変わり、今の仕組みが永久に正しいわけではありません。4600万人を超える被保険者が影響を受けるので慎重に行う必要はありますが、被用者保険の基本的な考え方を見直す時期が来ていると思います。
―具体的にはどのような見直しが考えられますか。
例として被保険者が死亡した後に配偶者に給付される遺族年金について、30歳以上で夫を亡くした女性の場合、その後未婚なら終生、遺族厚生年金を受け取れます。一方、男性は妻の死亡時に55歳を超えていないと受給権は生じないというように、男女間で大きな差があります。
社会保障制度はライフスタイルに中立的であることが重要で、制度が人生の選択を変えるようなことがあってはなりません。男女格差の是正も必要です。
このため2025年の年金制度改革に向けて、65歳未満の配偶者については、受給期間を5年の有期給付に変える案が審議会で議論されています。年金財政に与える影響はほとんどありませんが、実現すれば家族への保障をどこまでカバーするか、という制度の土台となる考え方を変える、大きな転換点になります。ただ激変緩和措置として20~30年単位の移行期間を設け、長期的に変えていく必要はあるでしょう。
20年越しで進められた適用拡大 諦めずに議論を続ければ社会の理解を得られる
―社会保障制度はこれまで、時代の変化に応じてどのように変遷してきたのでしょうか。
1992年に育児・介護休業法が施行されると、早くもその3年後には厚生年金保険法が改正され、育児休業中の厚生年金保険料を免除する規定が設けられました。賃金という所得を得ている人を対象とする厚生年金制度に保険料免除を設けることには議論もありましたが、当時は少子化が社会問題化しつつあり、団塊ジュニア世代が社会に出るまでに、仕事と育児を両立しやすい制度を整えて出産を後押ししようとしたわけです。その後も両立支援の諸制度が徐々に整えられた結果、女性の就労は当初の想定以上に進みました。もしこのような制度の見直しがなければ、出生率は今より下がっていた可能性があります。
また1990年代、長期不況で正規就労できない若年者やパート就労する専業主婦が増えたことなどから非正規労働者が増加し、フルタイム労働を前提とした厚生年金制度では対応できない労働者の所得保障が課題となりました。このため2000年代初頭から適用拡大の議論が始まり、紆余曲折を経て2012年の改正で、複数の要件を設けた上で、所定内労働時間が週20時間以上の短時間労働者も適用対象となりました。その後、企業規模の要件が順次緩められ、2025年の年金制度改正に向けては撤廃に向けた議論が行われています。
両立支援の制度も厚生年金保険の適用拡大も、10年、20年取り組みを続けた結果、その必要性について社会の理解を得られるようになりました。社会の関心はどうしても即効性の高い施策に偏りがちですが、長期的な視点で考えるべき政策については、たとえすぐに実現することが困難であっても、長く時間がかかろうが諦めず、議論を続けること、実現に向けた取り組み続けることが大切だと考えています。
―今後、取り組むべき課題はありますか。
企業に雇用されているパートタイマーは既存の枠組みでカバーできますが、企業に従属的に働く人でも被用者でないフリーランスへの対応は、現行制度では技術的に非常に難しい面があります。しかしこのような働き方をする人への所得保障も重要な課題です。「雇用」とは何かという根本にも関わる難しい問題ですが、議論を続けていく必要があると思います。
またデジタル技術の発達で地理的な障壁が低くなるなか、これからは海外の企業に雇用され、日本国内でリモート勤務するといったケースも増えてくるでしょう。日本政府はこの労働者を日本の社会保険に加入させ、米国の企業から保険料を徴収できるのか。このように、変化の早い現代世界においては今の制度が想定していない問題がもぐらたたきのように出てくるものです。
情報発信を通じて女性の意識に訴えて、第3号被保険者を減らす
―第3号被保険者制度の今後のあり方について、お考えはありますか。
そもそも1986年に第3号被保険者制度が作られたのは、専業主婦の困窮を防ぐためでした。制度改正前には専業主婦に年金加入義務はなく、妻を扶養するための加給分が夫の厚生年金として支給されていたため、離婚をしてしまうと年金もゼロになり、生活が困窮するといった事態が生じかねなかったからです。このように「婦人の年金権の確立」を目的に創設された第3号被保険者制度に対しては、一定以上働くと手取りが減る、という認識によって就業調整を招いているという批判が強くあります。
ただ男女の役割分担意識が薄れ、女性の労働参加が進んだことで、ピーク時には約1000万人に上った第3号被保険者数は、2023年には700万人を切るまでに減りました。第3号被保険者が減って第2号被保険者が増えれば、女性が将来受け取る年金額が増えることに加えて、年金制度を支える力が増すことで全体の給付水準も上がる。個人と制度の双方にとって望ましい変化だといえます。
社会保障制度は経済の活力を損なわないよう、働くことを後押しするよう設計することが重要です。一方で第3号被保険者制度の廃止については、慎重な議論が必要なことも事実です。当初の目的である「婦人の年金権」を保障するために代わる方策をどうするのか、医療保険の被扶養者制度も廃止するのかという課題を解決する必要があります。一方で今後を展望したとき、第3号被保険者が自然に減っていくトレンドも変わらないでしょう。この流れのなかでは、厚生年金に加入した方がキャリアも築けて生涯収入も年金も大きく増えるという情報を発信することで、第3号被保険者であることは「お得」だという意識を変えて就業調整せずに働くよう自然と促すことが重要だと考えています。
社会制度は悲観的に作るが、若い世代の意識変化には期待
―正社員同士の共働き世帯が増える一方、専業主婦世帯の所得が相対的に低下し、子どもを持ちづらくなっているという指摘もあります。こうした層への手当てとして、何が考えられるでしょうか。
欧州諸国には、病気で働けない人への現金給付制度を設ける国が多くあります。同時に移民などを対象とした就労支援にも力を入れて取り組んでいます。このように国が置かれた環境と国民の選択によって必要な制度はさまざまです。
人口減少局面にある日本では専業主婦のうち、働きたくても働けない人を見極めて経済的支援を強化するとともに、働きたい層の就労をサポートすることが望ましいかもしれません。ただし日本の公共職業訓練の現場には、個人差の大きい専業主婦を手厚く支援する余裕は少ないですし、財政がひっ迫するなか、経済的な支援にも制約があります。公的部門・民間部門を分けて考えるのではなく、公共職業訓練と教育機関による職業教育、そして民間企業による職業訓練がうまく連携して相乗効果をあげることが必要でしょう。
―単身世帯も増加していますが、彼ら彼女らが豊かさを感じながら生活できる環境整備に向けて、必要な取り組みはあるでしょうか。
男性の正規労働者については、現行制度で対応することを前提に、単身の非正規労働者に関しては、厚生年金の適用拡大を進めて老後資金を確保することが大事です。また60代に働けるかどうかで収入も年金受給額も大きく変わるので、シニアが長く働ける就労環境を整備する必要もあります。
女性については、社会保障よりも雇用の現場で、賃金や処遇のジェンダー格差を解消することに尽きます。ただ就業率のM字カーブが過去20年間で急速に解消し、20~30代のジェンダーに関する意識は男女ともに大きく変わってきています。今の子ども世代が将来、労働市場に出てきたら、さらに変わるでしょう。社会制度は悲観的な見通しに基づいて作るべきですが、若い世代の意識の変化については、期待を込めてある程度楽観的になってもいいのではと思っています。
(注)発言は個人的な見解で、所属する組織のものではありません。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ