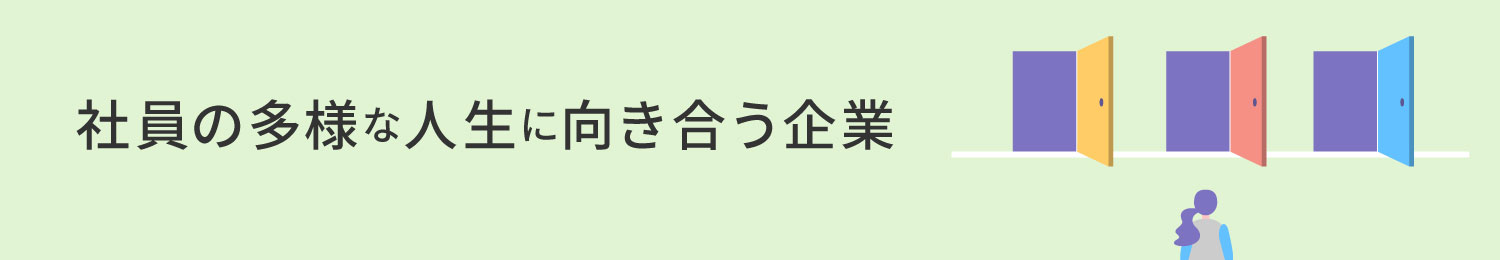
デジタルの力を借り、成果を出しやすい職場を作る 多様な人材前提に働き方を構築
 給排水設備のメンテナンス、設計、施工、コンサルティング業務を担う富士水質管理は、DXを通じた生産性向上に加えてリモートワークの導入といった多様な働き方を実現し、2024年には東京都による「Tokyo Future Work Award」を受賞した。専務取締役の白山達也氏、総務・経理部 部長の山村誠氏はいずれも異業種から同社へ転じ、改革を推し進めている。2人に改革の目的や成果について聞いた。
給排水設備のメンテナンス、設計、施工、コンサルティング業務を担う富士水質管理は、DXを通じた生産性向上に加えてリモートワークの導入といった多様な働き方を実現し、2024年には東京都による「Tokyo Future Work Award」を受賞した。専務取締役の白山達也氏、総務・経理部 部長の山村誠氏はいずれも異業種から同社へ転じ、改革を推し進めている。2人に改革の目的や成果について聞いた。
社会インフラ、支え手不足は深刻 人を集めるため働きやすさを高める
-一連の取り組みを始めたきっかけは何だったのでしょうか。
白山:当社は、空港や公共施設の給排水設備の保守管理を事業の柱としており、人手不足でこのままでは立ち行かなくなる、というのが改革のきっかけです。埼玉県八潮市の道路の陥没事故が大きなニュースとなっているように、インフラを維持することの社会的な重要性は高まっています。
この仕事は、五感を使って異臭や異音などを察知しなければならないので、ロボットや人工知能に代替できず、将来的にも市場価値が高い職種です。にもかかわらず3Kのイメージが強く、求人を出しても応募が少ない。八方ふさがりのなか、まずは多様な人が活躍できる、働きやすい環境を整えようと考えました。それによって社会の注目が集まれば、蛇口をひねればきれいな水が出るのが当たり前、という生活を裏で支える人材に、もっと光が当たるのではないかという思いもありました。
-白山さんの目指す「働きやすい環境」とは、どのような職場でしょうか。
白山:「働きやすさ」には手厚い福利厚生や快適な職場環境など、さまざまな要素があります。生産性の高い人はこうした恩恵を成果に還元できますが、なかには環境に甘えてしまう人もいる。当社では女性やシニアも含めた多様な従業員が、技術の力も借りながら短時間で高い成果を出して早く帰れる、といった状態を「働きやすい職場」と定義しています。
建設業界はテクノロジーの導入が遅れており、いまだに会議や打ち合わせにオンラインツールを使わずホワイトボードや電話、ファクスを使っている企業も珍しくありません。当社も私が入社した3年前は男性職場で、業務の大半が紙ベースでした。紙の作業をデジタル化したところ残業やミスが減り、リモートワークも可能になりました。
私の前職はIT業界で、国籍も年齢も違うメンバーが一緒に働くのが当たり前でした。デジタルスキルと多様な職場という2つの経験は、改革の上でも役立ったと思います。
3年かけて新システムを定着 表彰制度が切磋琢磨も生む
-DXに着手したときの、社員の皆さんの反応はいかがでしたか。
山村:4年前にDXを始めた当初は、抵抗もありました。販売関連のシステムを刷新したときは、従来のシステムに「使いづらい」と不満を漏らしていた従業員が一転して「前の方が良かった」と。しかし新システムによって、売り上げや請求額、原価などがクリック一つで集計できるようになると、営業所の作業が格段に楽になりました。さらに一目で数字を把握できるようになったことで、管理職や経営層も効果を実感するようになりました。それでも組織全体にシステムが定着するまで、足掛け3年はかかったと思います。
-DXと同時に、組織人事改革も進めてきました。
山村:「働きやすい職場」を実現するには、ゴールを設定し評価も明確化して、働き手の力を引き出す必要があると考えました。このため1on1を導入し、目標設定やフィードバックなどのコミュニケーションを充実させました。2023年からは売上高や受注件数、業務改善など多角的な視点で社員を評価し、表彰も始めました。その結果、従業員のモチベーションが高まり、良い意味でライバル意識を持って切磋琢磨する人たちも出てきました。
当社は従業員数70人程度で一人ひとりの顔が見えやすく、施策への反応を通じて、従業員それぞれの働くスタンスのようなものも見えてきました。トップダウンで施策を打って失敗したら変える、というトライアンドエラーで物事を進めやすい規模だったことも、幸いしたと思います。
-一連の取り組みが、採用や業績に直接的な成果をもたらした部分はありますか。
山村:時間外労働を一定の範囲内に抑えつつ1人当たりの担当物件数を増やすことができて、生産性は確実に高まっています。売上高も年率5~6%増と堅調に伸びています。
以前は大規模マンションや商業施設などの仕事が来ても、人手不足で受けられないことがありましたが、最近はそういった事態も解消されつつあります。今後、新規顧客の開拓に取り組めれば業績の伸びしろもあると思います。
「できない」のは「やらない」だけ 女性・高齢者活用には課題も
-中小企業からは、1on1やテクノロジーの導入は難しいという声も聞かれます。できる職場とできない職場の違いはどこにあると思いますか。
山村:違いは「やるかやらないか」に尽きると思います。できない理由を並べる企業には、まずやってみてはどうか、とお伝えしたいです。ただ白山や私が、前職で新しいことに取り組んだ経験を還元できたことは、当社のアドバンテージといえるかもしれません。
当社も、取り組みが100%うまくいっているとはいえません。勧めてもリモートワークをしたがらない従業員もいますし、中小企業には自動化するより手作業の方が早い仕事もあります。DXを推し進めることと得られるメリットとのバランスには、日々悩んでいるところです。
またこの仕事は24時間の緊急対応が求められますが、重いマンホールのふたを持ち上げるのが難しいことなどを考え、女性社員やシニア社員を緊急対応から外している営業所もあります。しかし男女、年齢に関係なく働いてもらうには、こうした制約を乗り越えることが不可欠です。先日、重たいものを扱うところなど危険が伴う場所を洗い出したところ、さほど多くないことが分かりました。「危険を伴う業務なので女性社員やシニア社員には難しいのではないか」とイメージだけで業務を限定していたわけです。ケアすればよいポイントが分かったことで、女性社員やシニア社員の働く余地が広がりました。また、今後はパワーアシストのような技術を導入する必要もあると考えています。
-健康管理や環境整備などには取り組んでいますか。
山村:健康経営は今や、企業に求められる最低水準の取り組みと言っても過言ではありません。当社も保健師と契約して、健康診断の結果に対してアドバイスをもらったり、運動不足や食生活に関する情報を提供してもらったりしています。また一定の運動能力が求められる仕事なので、シニア社員には契約更新のときに「片足立ちで目をつぶる」などチェックを実施し、事故リスクを回避しながら長く働いてもらおうとしています。
環境整備についても、点検場所に照明が足りない、手すりがなくて危険だといったことは安全衛生委員会で共有し、建物の所有者や管理会社に改善を提言しています。場合によっては当社独自で対策を講じることもあります。
多様化と高齢化で、従業員も「どう生きるか」考える時代へ
-従業員が社外で活動した結果、人脈が広がるなど、仕事にプラスの効果をもたらすこともあるのではないでしょうか。
山村:現時点では事業とプライベートの社外活動の隔たりは大きく、偶然、事業の要請と合致することはあっても、積極的に紐づけるイメージは持ちづらいのが本音です。
ただ私も含めて誰しも年を重ねれば、仕事以外の人生を考える必要が出てきます。また従来の日本企業は、同質性の高い人を集めることで成長してきましたが、今は従業員の価値観も多様化しています。特に当社のような中小企業は、さまざまなバックグラウンドの人がいて、考え方もまったく違います。このため組織も「従業員は一人ひとり違う」ことを前提に「チーム」を構築しなければいけないし、高齢化の中で従業員も、自分はどう生きていくかを改めて考えなければいけない。その中で、従業員の社外での行動が事業の枠組みに合えば、活用の道が開けるのではないかと考えています。
-仕事以外の活動に対する企業としてのスタンスは、改革が始まる前と後でどのように変化したと感じますか。
山村:改革が始まる前は、仕事以外の活動に対して積極的に関与することはなく、どちらかといえば受け身の姿勢でした。ただし、当時から従業員が自身の裁量で業務を調整できる仕組みは一定程度提供していました。例えば、点検担当者には社用車を貸し出し、自宅近くの駐車場を借り上げることで、直行直帰を可能にしていました。
現在も、趣味のための休暇を特別に推奨することはしていませんが、リモートワークやデジタル技術の活用を進めたことで、仕事以外の活動を尊重する姿勢がより明確になってきました。今後も、従業員が仕事にやりがいを感じつつ、プライベートも充実させることが、最終的に企業の成長につながるという好循環を目指していきます。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

