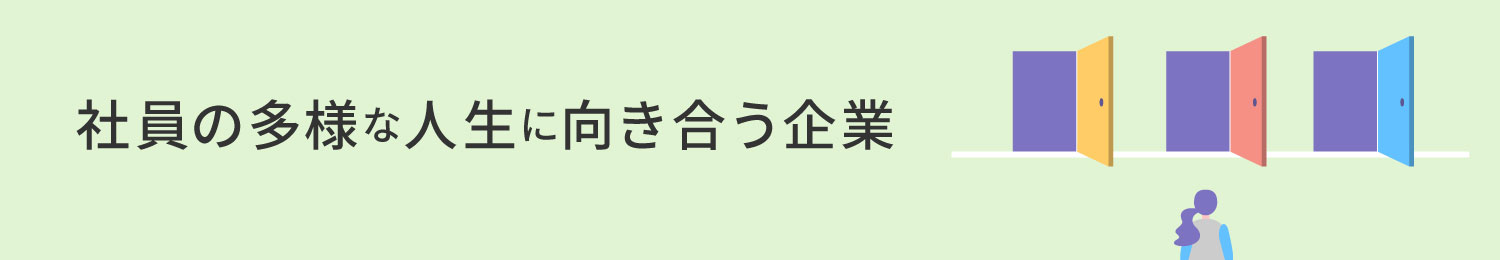
「残業なし」「週3日勤務」「販売職の土日祝休み」――選べる働き方を導入、地域活動も推奨
 明太子を製造・販売するふくや(福岡市)は、社員が残業なし、週3日勤務、土日祝休日固定など働き方を選べる仕組みを導入しているほか、地域活動への手当も支給している。支援部 人事課 課長の山中崇彦氏に、こうした取り組みのきっかけや効果を聞いた。
明太子を製造・販売するふくや(福岡市)は、社員が残業なし、週3日勤務、土日祝休日固定など働き方を選べる仕組みを導入しているほか、地域活動への手当も支給している。支援部 人事課 課長の山中崇彦氏に、こうした取り組みのきっかけや効果を聞いた。
「地域への恩返し」のため創業 子育て女性の離職防止が原点に
-柔軟な働き方の導入や、地域活動のサポートに取り組む理由を教えてください。
そもそも会社そのものが、地域への恩返しのために作られたという経緯があります。創業者は日本人ですが現在の韓国で生まれ育ち、第二次世界大戦後、福岡への引き揚げを余儀なくされました。そのとき、地域の人たちが温かく受け入れてくれたおかげで生活できたことから、地域の役に立ちたいと考えて1948年に当社を創業したのです。
こうした地域貢献の理念は、福岡県で生まれたお子さんに明太子をプレゼントする施策や、博多祇園山笠や博多どんたく港まつり等地域のまつりや文化への参加・支援につながっています。また会社だけでなく従業員にも地域に貢献してもらいたいとの思いから、町内会やPTA、子供たちのスポーツ指導といった活動に取り組む社員に、地域役員手当も支給しています。
-残業なしや週3日勤務など、選べる働き方を導入したのは、どのような経緯からでしょうか。
「やらざるをえなかった」というのが本音です。バブル時代、当社は多店舗展開のために人手を必要としていましたが、男子学生は東京や大阪に就職してしまい、なかなか採用できませんでした。そんななかで入社してくれたのが「地元で働きたい」と考える女子学生でした。
彼女たちは、接客などの場で男性以上に力を発揮しましたが、入社8~10年目でまさに職場の中核に育った頃、結婚・出産のため相次いで退職し始めたのです。戦力ダウンを防ぐには、出産後も働き続けてもらう必要がありました。
当社は中小企業で社長と社員との距離感が近いので、社長が女性たちから困り事を聞き、保育園のお迎え時間に間に合わせるため、残業なしや短時間勤務の制度を設けました。保育園が閉まってしまう土日祝日に、休みを固定できる制度も作りました。
2022年度には従来の制度を発展的に見直し、休みの曜日を固定する働き方以外の働き方については、育児・介護に限らず副業や趣味などの理由でも選べるようにしています。
-理由を問わず働き方を選べるようにするのは、思い切った判断だと思います。なぜそこまで踏み込めたのでしょうか。
近年は若手の離職率が高まり、週3日でも働いて会社に残ってもらった方が、退職してしまうよりもいいという判断がありました。世の中が変わって副業などに取り組む人が増え、働き方を選びたいというニーズが出てきたことも要因です。
また当社の社長は演劇との関わりが深く、劇団員が公演や稽古のため、正社員として働けない姿も見てきました。制約がある人でも働きやすい環境を整えれば、優秀な人材に集まってもらえるのではないか、やってみて行き詰まったらやめればいいという社長の考えが、取り組みの起点となっています。
現在のところ制度利用者の大半は子育て中の社員で、介護や自営業を理由に柔軟な働き方を選択している人は少数です。
正社員のまま週3日勤務も可能に 責任と意欲を維持
-週3日勤務や残業なしを希望する社員については、雇用形態をパートに転換するという考え方もあります。なぜ正社員のままで働き方を選べるようにしたのでしょう。
出産や介護でフルタイム勤務が難しくなっても、仕事の質や責任の重さを変えずに働き続けたい、と考える人はいます。こうした人に、正社員の形態を変えずに働き方の選択肢を提供することで、それまでと同じ責任感や意欲を持って働いてもらえると考えたのです。ただ正社員である以上、雇用保険の適用対象である週20時間以上は働いてもらうべきだとして、週3日勤務を下限に設定しました。一方で、子育てに軸足を置くので責任や業務負担を軽くしたいとパートに転じる人もいます。
当社は社員との対話を重視しており、私自身も入社後、ヒアリングの多さに驚かされた経験があります。柔軟な働き方を選んだ人、育休を取得した人などは丁寧に悩みや困り事を聞くことに力を入れています。毎年度ごとに今の働き方を続けるかどうか意思確認しているので、状況の変化に応じてフルタイムに戻るなど、働き方を変えることも可能です。
-自分は土日も出勤するのに、一部の社員は休める、という状況があることで職場に不公平感は生まれませんか。
かつて女性社員が出産ラッシュを迎え、社員200人のうち24人が時短や残業なしを選んでいた時期がありました。このときはさすがに周囲からかなり不満が出ましたが、特に手当などで報いるのではなく、生活の基盤である家庭が安定してこそ仕事でも力を発揮することができる、と理解を求めました。休んだ人をカバーする立場の人たちにも「誰もが働き方を制約される可能性はあるので、困ったときはお互い様と思って協力してほしい」とお願いしました。
繁忙期の土日祝日に、ベビーシッターに来てもらい、会議室で子供を預かり、母親たちに出勤してもらったこともあります。母親が頑張る姿を見せることで、周囲も協力的になってもらえれば、という思いもありました。
また当時は子育ての大半を母親が担っていましたが、子育ては当社と母親だけでするものではありません。そこで面談の際に父親の同席を呼びかけ、当社の制度を説明した上で「会社ができるのはここまでなので、ここから先はご協力をお願いします」とお話しすることもありました。
中小はフルタイム人材確保が困難に 多様な働き手を集めて生き残る
-働き方に制約のある人が、肩身の狭い思いをするようなこともありましたか。
子供の発熱などで早退や休みが増え、周囲に迷惑をかけることを気に病む社員はいましたし、同僚との関係がぎくしゃくしたケースもありました。こうしたとき、本人には「育児の担い手は親以外にいないのだから、休むのは仕方がない。ただし職場のみんなには感謝の気持ちを言葉に出してしっかりとお伝えし、出勤したとき、一生懸命働いて恩返しをしてください」と伝えました。
その後、出産ラッシュが終わったこともあり、子育てにまつわる悩みは以前ほど聞かれなくなりました。地域活動を推奨していることや、希望者全員が働き方を選択できるようにしたことも「お互い様」の意識を醸成するのに役立ったかもしれません。ただそれ以上に、世間一般で男性の育休取得が増えるなど、父親の育児参加が進んだという社会的な変化の方が、職場の理解を促す力としては大きかったと思います。
-働き方を選ぶ人やご家族、職場の人それぞれに働きかけるとともに、会社ができることも行ってきたのですね。社員の仕事以外の活動に対して否定的、無関心な企業もあれば、意思を尊重し応援する企業もあり、さらに社員が仕事以外で得た学びを取り込んで、成長しようとする企業もあります。自分の職場には、どのスタイルが当てはまると思いますか。
応援はしていますが、自社の成長に取り込むにはまだ至っていない、というところです。副業も当社の業務に活かしてもらいたい、という思いはありますが、まずは本人の生き方を尊重することを目的としています。
ただ子育てや介護を経験すると、当事者の苦労が分かるようになって視野が広がりますし、限られた時間で成果を出す意識も高まります。また、地域活動では職場の肩書や上下関係は全く通用せず、本当の意味で人を動かすリーダーシップが培われます。例えばスポーツの指導で、移り気な子供たちを練習に集中させたり、PTAや町内会で価値観の違うメンバーをまとめたりすることは、部下をマネジメントする上でも役立つはずです。将来的にはこうした社員の成長を、計画的に事業に取り込みたいと考えています。
労働人口減少のなか、地方の中小企業が優秀なフルタイム人材を確保することは、どんどん難しくなっています。これからは多様な働き手を集め、活躍してもらわなければ会社の存続すら危うくなってしまうでしょう。他の企業も「うちは中小だから無理だ」と諦めず、少しずつできるところから、取り組みを始めた方がいいと思います。
-企業の成果に明確には表れていなくても、生活や社外活動を応援することは、貴社にとってプラスに働いているのだということが伝わりました。本日はありがとうございました。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

