
第1回 複雑で見えにくい「家族」×「働く」の形
日本で、「家族」と「働く」の選択はどのように変化してきたのだろうか。
その変化は何をもたらしているのだろうか。
多様化・複雑化する「家族」と「働く」の選択
「家族」「働く」はそれぞれ、個人が充実したライフキャリアを実現する上で大切なものといえる。働くことには、経済的な基盤を得たり、社会の持続や発展への貢献や自己実現の機会を提供したりする価値がある。家族とは何かについての定義は必ずしも定まっていないが、それでも多くの人にとって家族が、親密圏や経済共同体としての価値を提供していること、あるいは提供を期待する対象であることは確かだろう(※1) 。
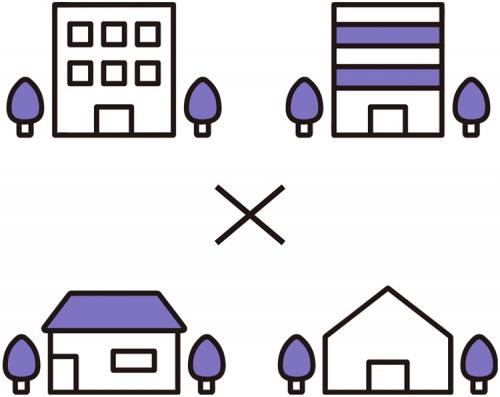
日本では戦後から1970年代にかけて、成人のほとんどが結婚の経験があるか現在結婚している「皆婚社会」が成立したとされる(※2)。大家族で暮らし、職住接近の自営業を営む形が主流であった戦前と比べ、この時期には男性が企業に雇用されて、家族の生活を支えられる賃金を得る一方(※3)、女性が主に家事・育児等のケア労働を担う核家族が急速に増加していった。企業は解雇を極力避ける慣行や社宅・家賃補助、家族手当などの福利厚生の充実、従業員の妻への家族運営に関する教育支援等を通じて、このような家族を支えた。政策も、住宅金融公庫における融資対象からの単身者の除外(1980年度まで)や社宅建設を行う企業への支援、企業における雇用維持に資する様々な政策を通じて、このような形の家族をサポートした。この時期の日本では、「家族」と「働く」の選択にはメインストリームとでもいうべき形があり、良くも悪くも個人、企業、政策それぞれがこの組み合わせを念頭に置くことができたといえる。
しかしその後、状況は大きく変化してきた。家族類型の変化だけみても、男女ともに単身世帯が増加しており、総務省「国勢調査」によれば、全世帯に占める割合は1980年の19.8%から2020年に38.0%まで上昇している。一方、夫婦と子供からなる核家族世帯は42.1%から25.0%まで急減する一方、夫婦のみの世帯は12.5%から20.0%へと上昇した。加えて3世代世帯も減少しているため、世帯あたり人員は1980年の3.22人から2020年の2.21人へと縮小を続けている。
さらに、それぞれの家族類型において世帯員のうち何人が働いているのか、それぞれの働き方はフルタイムかパートタイムか、雇用者か自営業者か、雇用者であれば正社員かそれ以外か、どのような労働条件かといった、働き方の違いも生じている。今日では、「家族」と「働く」のメインストリームは消失し、画一的な議論を行うことは難しくなっているのである。
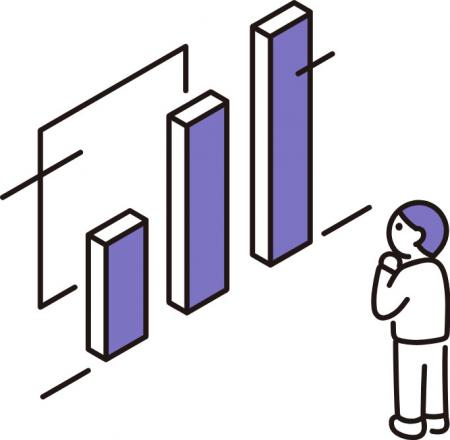
それぞれの抱える問題が見えにくい社会
このような「家族」と「働く」の選択をめぐって、今、日本の社会には大きな問題が生じている。家族であれ、仕事であれ、個人が自身の希望や社会の変化に沿ってこれからのライフキャリアを実現していくためには、経済的な安定や、時間、つながり、学びの機会のように、次の選択を支える資源が必要だ。しかし今、「家族」と「働く」の選択がきわめて多様になるなかで、どのような組み合わせが増えているのか、それぞれの形でいかなる資源が不足しがちなのか、その不足により個人の次の選択にいかなる影響が生じうるのか(生じえないのか)について、社会全体という視点で捉えることが難しくなっている。
もちろん、非正規雇用で働く一人親世帯のように、さまざまな資源の不足に直面しやすい「家族」と「働く」の形があることは、これまでの研究で繰り返し指摘されてきた。一方で、その不足が他の類型と比較してどのような内容なのか、都市部と地方でどのように差があるのかに関する議論は必ずしも十分ではない。また、1980年代頃まで「家族」と「働く」の主流であった正社員の夫と専業主婦やパートの妻の世帯は減少傾向にあるが、その傾向はどのような資源の不足と関わりを持ちうるのか、あるいは正社員同士の夫婦など恵まれていると思われがちな類型で抱えやすい問題はないのか、などの議論も不足している。
個人の価値観が取りうる選択も広がりを見せるなか、新たに画一的なメインストリームを作ることは現実的ではない。一方で、「家族」と「働く」の選択が多様化するなかで、お互いの状況や負担が見えにくいままでは、他者の恵まれた部分を批判しあうだけで、それぞれの最適解を選択することが難しい社会に陥りかねない。今一度、「家族」と「働く」の現状を解き明かす必要があるのではないだろうか。
<参考文献>
居神浩(2004)「家計構造からみた性別役割分業」玉井金五・久本憲夫編『高度成長のなかの社会政策-日本における労働家族システムの誕生』ミネルヴァ書房
釜野さおり (2011)「既婚女性の定義する『家族』」『人口問題研究』67(1), 59-87
正岡寛司(1994)「結婚のかたちと意味」『家族社会学研究』 6(6), 45-52
松木洋人 (2013) 家族定義問題の終焉?日常的な家族概念の含意の再検討」『家族社会学研究』 25(1), 52-63
(※1)学術的な研究においては長く、家族の定義をめぐる議論が行われてきたが、合意には至っていない(釜野、2011)。古典的な議論では、家族が果たす普遍的な機能や特定の成員かどうかによる客観的定義づけが試みられたものの、このような客観的定義に対してはその機能を持たない集団や特定の成員に収まらない人の位置づけが難しいことなどから、1990年代以降は「人は何を家族と捉えるのか」という主観的な家族に着目した議論が浮上している。本研究プロジェクトでは、家族が提供するもの(あるいは提供が期待されるもの)としての親密圏や経済的共同体としての価値に着目しつつ、その把握の難しさを踏まえ、世帯に着目しデータの収集や分析を行っていく予定である。
(※2)正岡(1994)によれば、1950年には40-44歳男性の有配偶率は95%である一方、戦争の影響により同年の30~34歳女性の有配偶率、40~44歳女性の有配偶率は83%であったが、1970年代以降、これらの年齢階層 の女性の有配偶率が9割に近づいたと指摘されている。
(※3)居神(2004)によれば、平均的に見て夫の収入が家族全体の支出を上回るようになったのは、1967年以降である。この状態を安定して確保できたのは夫が事務系雇用者や従業員規模1000人以上の企業の雇用者の場合であり、夫が工場労働者や100人未満の企業の雇用者の場合は、夫の収入は家族の支出に対し若干不足する状態にあったとされている。
執筆:大嶋寧子

大嶋 寧子
東京大学大学院農学生命科学研究科修了後、民間シンクタンク(雇用政策・家族政策等の調査研究)、外務省経済局等(OECDに関わる政策調整等)を経て現職。専門は経営学(人的資源管理論、組織行動論)、関心領域は多様な制約のある人材のマネジメント、デジタル時代のスキル形成、働く人の創造性を引き出すリーダーシップ等。東京大学大学院経済学研究科博士後期課程在学中。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

