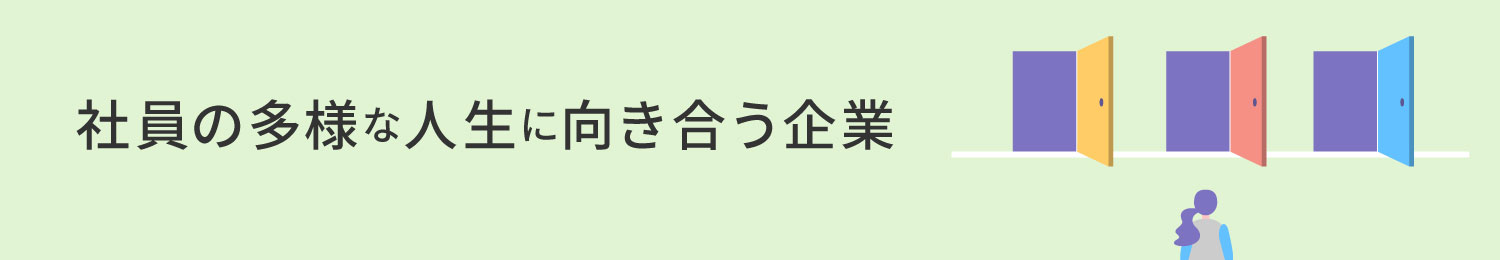
徹底した人材育成と働きやすさが、制約から社員の可能性を解き放つ
 塗装職人の育成会社としてスタートし、現在は建設現場で発生する事務作業のBPOサービスなどを手掛けるKMユナイテッドは、顧客満足度を高める「手段」として、徹底した従業員満足度の向上と人材育成に取り組む。仕事での成長と価値創造に加え、仕事以外の人生をも充実させられる働き方を提供することが、どのように顧客満足につながるのか。竹延幸雄社長に聞いた。
塗装職人の育成会社としてスタートし、現在は建設現場で発生する事務作業のBPOサービスなどを手掛けるKMユナイテッドは、顧客満足度を高める「手段」として、徹底した従業員満足度の向上と人材育成に取り組む。仕事での成長と価値創造に加え、仕事以外の人生をも充実させられる働き方を提供することが、どのように顧客満足につながるのか。竹延幸雄社長に聞いた。
従業員満足度を高めることが、顧客の課題解決につながる
-これまでの取り組みの経緯を教えてください。
2013年に塗装会社竹延の子会社として創業した当初は、塗装職人の早期育成や業務効率化に取り組みました。塗装業は従来、先輩が忙しいなかで新人を教育しても、その多くがすぐに離職してしまい何も残らない、ということの繰り返しでした。古参の職人には「背中を見て学べ」という気風も強く、一人前になるのに10年単位の時間がかかることもしばしばでした。
このため新人に教えるべきことが10あるうち、比較的短い期間で学べる3つの領域を集中的に習得させ、3年で人に教えられるレベルに引き上げる仕組みを作りました。この結果、未経験者も短期間でスキルを獲得できるため応募のハードルが下がって職人が倍増し、夜間・休日出勤が減るなど働き方も改善しました。当初は顧客や同業者から「土日が休みなんて甘い」と言われましたが、こうした変化を見て、周囲も応援してくれるようになりました。
-建設業界の事務作業のBPOサービスなどに乗り出したのはなぜでしょうか。
建設現場の現場監督は、実は膨大な事務作業に追われています。事務をアウトソースすれば、現場監督はコア業務に集中できて過重労働の抑制につながります。一方で当社も、子育て中の女性らにサテライトオフィスで作業してもらうことなどを通じて、さらに人材を多様化できると考えました。今はBPOサービスが事業の主力ですが、ホワイトカラーにも塗装業で培った早期育成のノウハウを応用しています。
ただ当社にとって従業員満足度の向上は、あくまで顧客の課題を解決しCS(カスタマーサクセス)を達成する手段にすぎません。また多様な人が働きやすく生産性も高いという二律背反の実現は、まだ道半ばだとも考えています。
生産性を高めるリスキリングがあるから、社員が意欲を持って学ぶ
-人材を育成するに当たって、どのようなプロセスを踏んでいるのでしょうか。
一つは、社内の知識基盤を作ることです。従業員は機密保持のため、顧客ごとに分かれた部屋で業務を行っており、各職場で生まれた知識やノウハウが横展開されづらくなっています。そこでProposal Briefing for Clientsという、顧客提案の勉強会を月1~2回開催し、社内で誰が何に取り組んでいるのかを見えるようにしています。これによって誰もが、社内に蓄積された知識や技能を引き出して仕事に応用できますし、必要であれば担当者に尋ねることもできます。
このほかにも、大手建設会社などで定年後の再雇用が終了したOBを採用し、BPOサービスなどを担う若手に知識やスキルを伝授してもらっています。OBには教えることに特化してもらい、「教え方」を学べるトレーニングも行います。
-社員が何を学ぶか、誰がどのようにして決めるのでしょうか。
まず徹底的な業務分析を通じて、職場に必要なスキルを明確にします。さらに従業員一人ひとりのできること、できないことを示すスキルマップを作ります。職場のリーダーは各従業員のスキルマップと職場のニーズをすり合わせ、部下と3カ月に1度、次は何を習得するべきかを相談して決めます。従業員は学ぶべきことが明確になり意欲が向上しますし、職場に必要なスキルが蓄積されれば、顧客価値を高めることにもつながります。
日本企業の多くは、個人のスキル習得と事業がうまくかみ合っていないと感じます。従業員に職場の生産性を高めるスキルを学んでもらうことで初めて、組織が前に進むのです。
評価基準を設けることも大事です。当社では「納期を守る・守らない」など30ほどの項目を作って顧客に示して調査を行い、顧客満足と相関関係にある項目を割り出して評価基準に取り入れています。
-御社にとって人材育成はどのような意味を持つのでしょうか。
当社では人材育成は、生産性向上と顧客価値の創出を実現するための投資であると明確に位置づけています。顧客の業務の標準化・自動化をサポートすることで、顧客の生産性が40%上がったとします。その場合、20%分で顧客のために新しい仕事を引き受け、残り20%の一部を、当社の社員のスキル習得に充当しています。学ぶ内容は業務に紐づく知識やスキルであり、成果は顧客に還元されます。
仕事外の人生を大切にしながら、仕事で戦える環境を作る
-このような人材育成は、人材確保とどのように関わっていますか。
この半年間で、100人の求人に対し1800人の応募がありました。若い世代は手に職をつけたいと考える傾向が強く、甘やかさずにきちんと成長させる、という方針に好感を抱くようです。
従業員のなかには、かつて非正規雇用で数年おきに雇い止めされる「ループ」から抜け出せずにいた人たちもいます。「ループ」にはまる人の多くが、女性や外国人なのも理不尽です。日本人男性が採れないからと、次々に弱者を作って「ループ」に落とし込んでいては、海外からも人が来てくれなくなってしまう。当社は女性だけでなく外国人も積極的に採用し、「ループ」にはまっていた人たちに、入社1年で「こんなことができる」という自信を取り戻してもらおうとしています。
また従業員は全て正規雇用ですし、賃金も3年間で16%引き上げました。雇用を保障し、キャリア形成に必要な技術力と自信、収入を得てもらう分、着実に育って組織に貢献してもらいたいと考えています。
-女性管理職の登用も進んでいます。育児などで働き方やスキル形成に制約が生じる人もいると思いますが、どのように女性を戦力化しているのでしょうか。
まず組織全体として「長時間働かない」という意識を持ち、8時間のなかで成果を出すことを徹底しています。そのため短時間勤務の人と通常の勤務時間の人の差が、過剰に開くことはありません。
時短勤務の制度もありますが、女性がそれを取得することでキャリアを形成できず、給与も減ってしまうのは不平等です。このため例えば、午後4時に退社して子供を迎えに行った後、リモートで仕事ができる場合はフルタイム扱いにしています。リモートではセキュリティ上、顧客情報を扱えないので、動画を通じたスキル習得などに参加してもらいます。もちろん習得するのは「職場で必要なスキル」です。これによって、時間に制約があっても職場で「戦える」力をつけてもらいます。
当社は社員とリーダーの女性比率がともに7割で、ジェンダー格差は完全に解消しています。育休からの復帰率も100%です。また定期的に、社員の家族を招いてパーティーを開き、女性社員のパートナーや子供に、自分の妻、母がいかに職場で活躍しているかを理解してもらおうとしています。
なお短時間勤務の取得条件はなく、習い事などでも構いません。仕事以外の人生が仕事にいい影響を及ぼすなら、そちらを優先してもいいと考えています。また女性だけでなく男性にもメリットは大きく、育児と建設業での仕事、どちらも諦めたくないという優秀な人材が、大手建設会社から転職した例もありました。
-多様な人材が活躍できる環境を作ることが、会社にもたらす価値とは何でしょうか。
外国人の未経験者が急成長するのを見て、ミドル層が「そのうち追い抜かれるのではないか」と危機感を抱くようになりました。成長が鈍化した層を活性化し、学びへの意欲を掻き立てることが、ダイバーシティのメリットの一つだと感じています。
業界で「当たり前」の仕事に、外から来た人材が疑問の声を上げるケースも多々あります。女性社員が「なぜこれは手作業なのか」と言い出したのをきっかけに、外国人社員が専門のITスキルを活かして自動化し、それを特許申請するといった事例も生まれています。多様な人材が融合することで、当社のような中小企業も知財という新たな「財」を生み出せるようになったのです。
-一連の取り組みを通じて、どのような世界を目指しているのでしょうか。
人手不足と技能伝承の難しさという社会課題を解決することで「努力し続ける人を取りこぼさない社会」を作ろうとしています。日本は、シニアや女性や障害者が暮らす多様な社会でありながら、偏差値などの画一的な評価基準によって成長の機会を奪われ、活躍の場を得られない人がいます。その半面、一部の人は学歴や肩書にあぐらをかいて、努力を怠っているのに過分な処遇を得ているという不平等な状態もある。努力や学びが正当に評価される環境を作ることで、本人と当社、当社に関わる企業にWin‐Winの関係を築きたいのです。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

