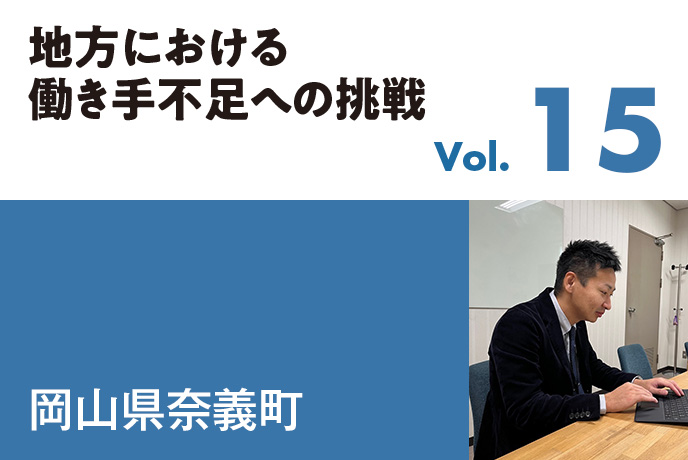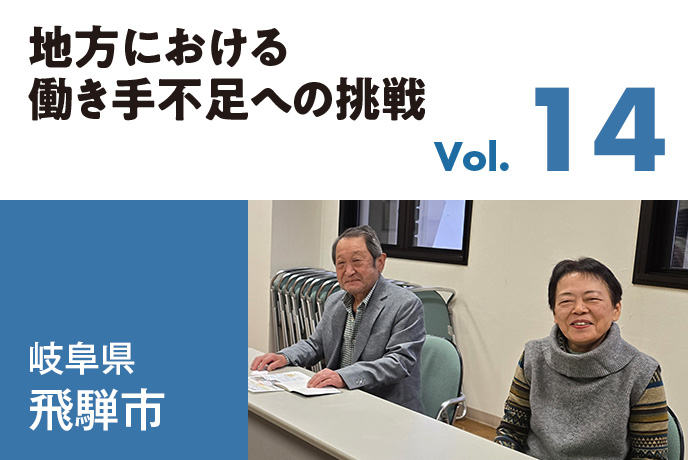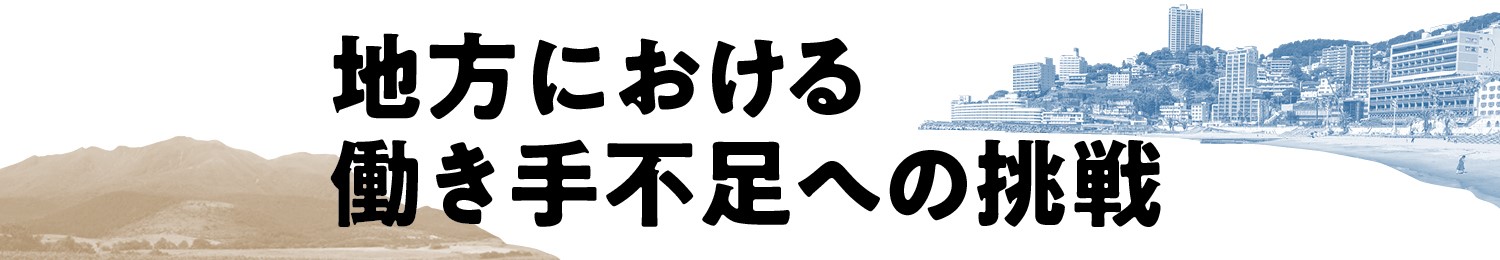
高齢者に働きがいと暮らしの楽しみを。村のための法人が「福祉」と「事業」の両立に挑む――奈良県川上村・かわかみらいふ
奈良県の奥地・川上村では、村民にとってこの地が「ついの住処」であり続けるよう、非営利の一般社団法人かわかみらいふを立ち上げて、さまざまな住民サービス事業を展開している。設立から8年が経った現在、かわかみらいふの事業はどう進化し、また今後の持続可能な運営に向けてどのような課題を抱えているのか。今回、リクルートワークス研究所では現地の実態をより詳細に把握するため、奈良県・川上村に足を運び、川上村役場の辰巳氏と、同法人事務局長の三宅氏にかわかみらいふの現地オフィスにて話を聞いた。
一番の魅力は職員とのコミュニケーション。買物支援には村民の見守り機能も
――かわかみらいふでは村民の買物支援を行っていますが、その仕組みを教えてください。
 一般社団法人 かわかみらいふ 事務局長
一般社団法人 かわかみらいふ 事務局長
三宅正記(みやけ・まさき)氏
三宅:川上村の住民の6割近くは高齢者で、車の運転ができない、あるいは買物に出るのが億劫になった村民のために、移動スーパーと生協の宅配作業を代行しています。移動スーパーは隣町にある唯一のスーパーマーケットから販売業務を受託し、かわかみらいふの職員が商品の積み込み、移動販売、売れ残りの返却を行うという仕組みです。生協の宅配では、ならコープ物流センターから出荷された商品を村内でかわかみらいふの宅配車に積み替え、各家庭に配達しています。両事業は法人の設立登記と同じ2016年に始まりました。当時、村でならコープを利用する方、すなわち組合員加入率は3割程度でしたが、かわかみらいふが代行して以降は伸び続け、おかげさまで今年度は72%を記録し、奈良県でトップの加入率になりました。移動スーパーの売上も受託前より大きく増加しています。
――かわかみらいふが代行して、なぜ利用する方が増えたのでしょうか。
三宅:川上村には26の小さな集落が点在しています。村の人口が減るにしたがい、お年寄りが暮らす数世帯だけの集落も増えてきました。さらにその方々も年々、車を運転して買物に出かけることが難しくなっています。しかし従来の移動スーパーや生協の宅配は、やはり企業ですので売上が見込めないところには行きません。代行サービスはそうした村民たちの利便性を高める目的でスタートしました。
ただ、私たちもやっていくうちに気付いたのですが、利用者増の一番の要因はかわかみらいふの職員たちとのコミュニケーションです。最初は必要性を感じてもらえなかったせいか、無関心の方もおられましたが、「いつも同じドライバーが配達に来てくれる」ということが周知されるにつれ、彼らとのお喋りを楽しみにする村民の輪が広がっていきました。なお、かわかみらいふの職員は総じて人とのコミュニケーションが好きな方を採用していて、今のドライバーもお年寄りに好かれる社交的な若者です。そうすると会話を通して、「この缶詰は先週頼んでいるから、今回は要らないよね」などと、よりきめ細かいサービスができるようになります。なかにはご家族に頼まれ、買い込み過ぎて賞味期限切れにならないよう、こちらで注文をコントロールするケースもあります。
また、移動スーパーも来る前から集落の人々が集まり、ちょっとしたコミュニティを形成しています。人気商品の大放出といったイベントを行ったら、それこそ皆さん顔を出してくれますので、誰かの姿がないと「どうしたの」と訊ねるなど、宅配同様ここでも安否確認ができます。単に商品を届けるのではなく、「お付き合い」のレベルにまで関わりを持てたのが大きいと思います。今では買物支援に関しては、商売ではなく、村民とのコミュニケーションや見守りのために行くという認識です。
――移動スーパーには看護師や歯科衛生士も同乗されていますね。
三宅:移動スーパーを利用する方は高齢者が中心なので、見守られている安心感の提供と、何かあったときのケアのために同行いただいています。看護師さんは役場に所属する保健師で、かわかみらいふが移動スーパーを開始した当初から、川上村の職員として派遣されています。奈良県では地域で生活する人を対象に活動する「コミュニティナース」に力を入れていますが、役場から出て移動スーパーと一緒に地域を回るという、川上村が構築したスタイルはそのはしりと言えるでしょう。好評につき歯科衛生士さんも加え、役場の福祉活動の一つに位置付けています。
若手以上に元気なシニアをできる限り雇いたい
――買物支援事業は売上が順調な一方で、民間企業では手が回らない細やかな取り組みをされているということですが、採算性はどうなっていますか。
三宅:率直に言って厳しいです。移動スーパーも宅配も、売上金額の何%かを販売手数料としてもらうという収益構造になっています。手数料制にしたのは、かわかみらいふが仕入れる必要がなく、かつ雇用を創出できるとともに、事業者側は販売・宅配作業を委ねられるという、ウィンウィンの関係性により事業連携を成立させるためです。しかし経常費が当初の予想以上にかかりました。経常費は人件費に加え、法人が2台所有する宅配車の維持費が主ですが、冷蔵・冷凍庫を搭載した特殊車両のためかなりの金額になります。これらを手数料収入だけで賄うのはなかなか難しく、賄えない部分は今のところ、福祉事業として役場に補助していただくという建て付けです。
――具体的にどのような形で補助されていますか。
 辰巳:現在はほぼ人件費で、他にはかわかみらいふがカフェ事業を運営するふれあいセンターという公共施設の管理費を指定管理団体として助成しています。昨年度の補助金総額は数千万円規模ですが、すべて村が出しているわけではなく、国の特別交付税措置などもうまく活用しながら捻出しています。人件費に関していうと、宅配車のドライバーの1人は、国の地域おこし協力隊の隊員として移住してきた若者なので、協力隊の活動費から給料が支払われています。
辰巳:現在はほぼ人件費で、他にはかわかみらいふがカフェ事業を運営するふれあいセンターという公共施設の管理費を指定管理団体として助成しています。昨年度の補助金総額は数千万円規模ですが、すべて村が出しているわけではなく、国の特別交付税措置などもうまく活用しながら捻出しています。人件費に関していうと、宅配車のドライバーの1人は、国の地域おこし協力隊の隊員として移住してきた若者なので、協力隊の活動費から給料が支払われています。
――人件費が主ということですが、かわかみらいふの職員は何人いらっしゃいますか。
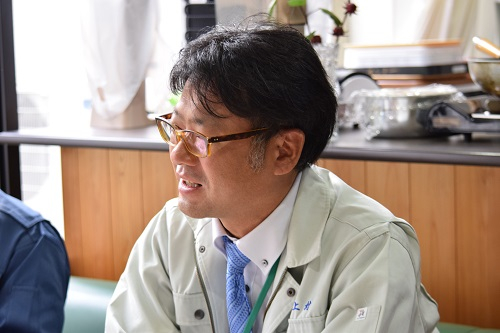 川上村役場 くらし定住課 課長
川上村役場 くらし定住課 課長
辰巳龍三(たつみ・りゅうぞう)氏
辰巳:パート、アルバイトを含めて26人で、そのうち6名が正職員です。また2020年に、国の特定地域づくり事業協同組合制度が施行され、川上村でも「事業協同組合かわかみワーク」を立ち上げました。組合が正規雇用した人材を、林業や製造業など働き手を求めている登録事業所に派遣する制度で、かわかみらいふにも3名派遣しています。この3名も移住者で、職員に占める村民と移住者の割合は半々です。
三宅:事業規模からすると26人は多いかもしれませんが、子育て世代の主婦から高齢者までさまざまな職員がいて、週に1~3回程度働く方も多いです。子育て世代の職員がお子さんの授業参観などでごそっと抜ける日は、高齢者が代わりにサポートするなど柔軟に対応できるほか、勤務のローテーションがうまく組めるのもこの規模感だからです。8年かけてようやく安定してきました。
――職員の皆さんの業務はどのように分担されていますか。
三宅:週に数回勤務するパート、アルバイトは、移動スーパーやカフェ運営などの各事業に専従します。正職員およびフルタイム勤務の職員は、どの事業もできるよう教育しています。また、職員の負荷を考えると、ドライバー業務をはじめスーパーでの積み込みや、重い荷物を遠くまで運ぶといった作業は、やはり体力のある若い世代の方が向いています。一方で、今は充足しているものの、人口減少が止まらない限り、今後、職員が不足するのは明らかです。そうしたことを総合的に勘案すると、若手の職員数は最低限確保したうえで、地域の元気な高齢者をできる限りたくさん雇用したい。それがこれからの重要な課題です。
自走に向けて名産の開発に着手。独立採算事業を増やすことで高齢者福祉も充実
――人口減少を前提にすると村の財源には限りがありますし、国の補助金制度もたびたび変わります。福祉事業との連携は別にして、今後、かわかみらいふが自走するためにどのように取り組まれていますか。
三宅:今のところ村からの補助金に頼らず、黒字で独立経営できているのはガソリンスタンド事業です。これは村に唯一あったガソリンスタンドが後継者不在で廃業するところを引き継いだもので、元々赤字ではありませんでした。一般社団法人は、このように役場とは切り離したビジネスができることも強みですので、そうした事業をもっと増やしていければいいと考えています。ただ、かわかみらいふは成り立ちもそうですし、村民の皆さんから見ても「役場の一部門」という認識が強く、だからこそ信頼を得ている面も大きいです。なかば公的な法人として地域への貢献も求められるなか、どんな事業に取り組み、かつ利益を出せるのかは非常に難しい課題です。
一つ期待しているのは農業の売上です。かわかみらいふでは今、農業を新事業にと職員が野菜づくりを学んでいて、少しずつ収穫もできるようになりました。今年度はならコープにハヤトウリを20kg提供し、それで漬物を共同開発、試食販売してもらいました。うまくいけば川上村が新商品の供給元になれます。ハヤトウリは全国どこでも採れる野菜で、焼いても炒めても美味しいのですが、あまり知られていません。一方、川上村にはこれといった名産野菜がないので、漬物をきっかけにぜひ大きく事業展開していければと思っています。そのほか、商品力の強いイチゴの栽培も本格的に始めました。
――地域貢献度が高く収益を見込める事業を多くつくることにより、福祉的な位置付けの買物支援事業を継続する方向性ですか。
三宅:そのとおりです。ただ、将来的な職員不足や、村民の皆さんのQOL維持を想定して、買物支援もいろいろと見直しを図っています。最近では「お買物バス」の実証実験を行いました。隣町のスーパーまでバスを出すだけでなく、乗客の村民を各家まで送迎し、冷蔵・冷凍容器も積んで、自分では持ちきれない荷物もすべてお届けしました。もちろん看護師も同行しており、福祉の位置付けだからこそできる試みです。目的の一つは、宅配車の維持やドライバーの確保が難しくなったときに備えて、「こちらから行くことができるか」という実験ですが、利用者にも大好評で、あっという間に村中にうわさが広がりました。「次はいつやるんだ」という問い合わせが殺到し、まもなく第2弾を行う予定です。
――事業としての継続と福祉サービスの両立。難しい挑戦ですね。
三宅:どんな事業を手掛けるにしろ、かわかみらいふが第一義とするのは、村民の皆さんにできるだけ長く元気でいてもらうことです。「最期まで住み続けたい村づくり」をまず叶えないと、転出者の増加を食い止めることも、移住者を増やすこともできません。また私はコロナ禍の時期に、家にこもりがちになったお年寄りがすさまじい速さで弱っていかれる恐ろしさを実感しました。人と会う、話すといった生活の張り、つまりコミュニティこそが高齢者にとって最も大切なライフラインなのです。
農業事業に着手したのも、「農業を続けている方はいつまでも元気だな」とつくづく感じたことが動機の一つです。独力の営農が難しくなっても、かわかみらいふが種や苗を用意したり、栽培指導を仰いだりして働き甲斐を感じてもらうことができます。村にとっては、働き手の確保にもつながります。
また、お買物バスにも「暮らしの楽しみを増やす」という狙いがあり、往復の車中では職員たちがレクリエーションで盛り上げてくれました。乗客の皆さんも張り切って普段よりお洒落して、一日中楽しそうでした。コミュニティを通して元気でいられるエネルギーを継続的に提供する。川上村に貢献する法人として、その目的に資する施策を、無理なく実現できる体制を考え続けていきます。
聞き手:坂本貴志
執筆:稲田真木子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ