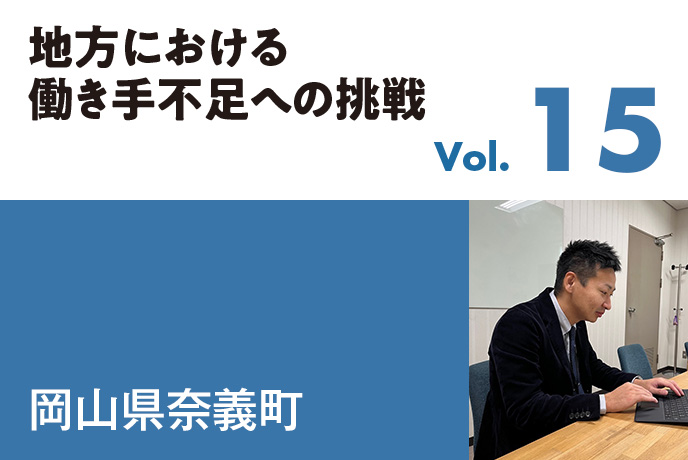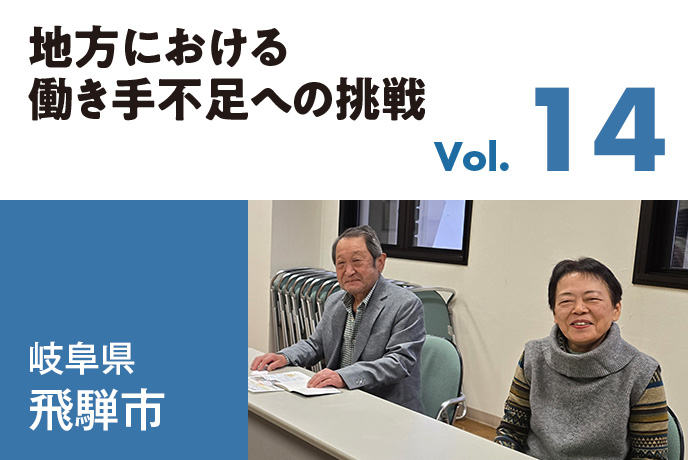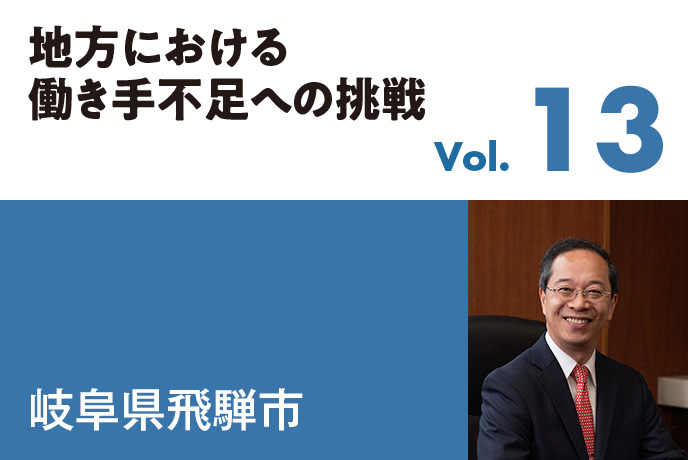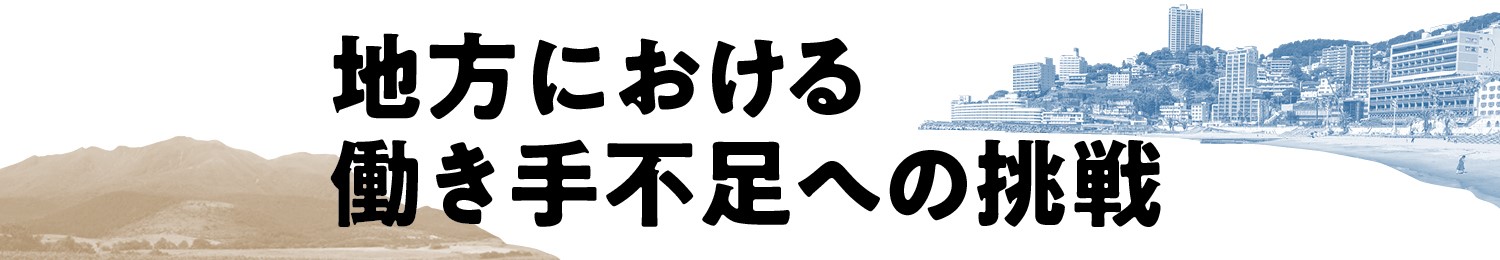
水源地の山村として林業振興に注力。発信力を高め、雇用を復活させたい――奈良県川上村 村長・泉谷隆夫氏
奈良県・川上村は、過疎化と高齢化により「消滅可能性自治体」に指定されている。しかし、この10年で人口減少率は89%から60%と緩やかになった。移住者の呼び込みや福祉サービスが効を奏したとみられる一方で、役場職員の負担増も懸念されるなか、首長は今後の川上村が目指す方向や力を入れる施策をどう考えているのか。新しく村長に就任した泉谷氏に話を聞いた。

川上村村長 泉谷隆夫(いずたに・たかお)氏
末端まで行き届く行政サービスを。移住者は定着に向け支援
――過疎化が進む川上村では、さまざまな課題を抱えているかと思います。特に過疎化に関しては「消滅可能性自治体」に指定されたこともあり、まず人口減少対策をお伺いします。実際、限界集落は増えているのですか。
住む人の半数が65歳以上という限界集落の定義で申し上げるなら、26ある集落のかなりが限界集落です。問題はもっと深刻で、今、一番人が少ない集落はわずか4人です。全員が高齢者で、かわかみらいふやデイサービスを通して安否確認はできるのですが、なにせ奥地ですから、自然災害などで孤立する恐れもあります。実際、この前も道路が陥没して3日ほど通行止めになりました。
――少ない集落の人々を一つに集める、あるいは合併するという方向は考えられないのですか。
平成の大合併では、吉野郡の村が一緒になろうという動きもあったのですが、当時の村長が「川上村は独自路線で行く」と決断しました。それはやっぱり考え方ですね。大滝ダムが完成するときに、近隣の市や村では人を集める施策をとったところもあり、そこは人口が増えていますが、一方で不満の声も聞くようになりました。市街地など人口が集積する場所は手厚いけれど、末端には行政サービスが行き届かなくなったというものです。合併の話が流れたときも、村民の皆さんから「しなくてよかった」という声が多く上がりました。
また、限界集落の村民に打診しても、ほとんどの方は「絶対に移らない」と、頑として拒否されます。川上村の人口流出の一因は、都市部に暮らす子による親の呼び寄せだったのですが、そのときに残った、あるいは「やっぱり都会には住めない」と戻ってきた人たちですから気骨が違います。「ここで暮らして、ここで死ぬ」と、気力を振り絞って畑仕事を頑張っています。
そうしたことを考え併せると、集落の人口がいくら減ろうと、1人でもいる以上は村として手当しなければなりません。その点においてもかわかみらいふの価値は大きく、移動スーパーなどにより買物難民が救われたのはもちろん、村民の健康状態や、落石など村の環境を見守る役目も果たしてくれています。また、らいふの職員とのコミュニケーションも、村人に気持ちの張りをもたらしているようです。
――かわかみらいふは、雇用の面でも村に貢献していると聞いています。
仰るとおりです。特に、移住者の仕事先として受け皿の一つになっているのがありがたいですね。村の存続にも関わる話ですが、近年、川上村には若い人たちが移住してくれるようになりました。お子さんがいる方や、村で出産する方もいて、子どもたちとの触れ合いがお年寄りの活力になっています。また、地域おこし協力隊の子が、村に「HANARE」という、農家を一棟貸しする自炊型の民宿を経営していて、外国人のお客さんもたくさん来てくれます。外国の方は川上村の鄙びた風情がとてもお気に召すようで、長期滞在する方も珍しくありません。今後は、観光にも力を入れる予定です。
――移住者の支援にはどのようなものがありますか。
若い移住者が多いため、特に子育て関係の助成は手厚く行っています。国の制度に加え、出生時や1・2歳の誕生日のお祝い金、高校卒業までの医療費無料など、さまざまな独自の制度を設けていることに加え、中学校の英語研修などにも力を入れています。
職員の負担軽減に向け村のイベントを見直す。任用職員も一般職で雇用
――行政サービスの充実に伴い、村の職員の方の負担も増していると思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。
間違いなく増えていて、1人あたりの仕事量は半端ではありません。霞ヶ関にも負けないんじゃないかと思うほどです。今着手しているのは村のイベントの縮小です。川上村はお祭り事など地域の行事は廃れてしまいましたが、品評会などの村のイベントは近隣町村に比べてかなり盛大です。一番大きいのは、農林産物の即売会をメインとする「山幸彦まつり」。農林業の振興にもつながるイベントなので、何をどう残すかという取捨選択の精査が難しく、また職員も、必ずしも(縮小に)積極的ではありませんが、何とか整理したいと思っています。
――新しい職員の採用も難しくなっていますか。
ここ何年かは、応募者が少し減っていますが、若者の数自体が少ないから、どの自治体も同じような状況だと思います。うちの役場は、今は年功序列でもないし、若手でも村の振興に主体的に関わるなど、働き甲斐があるから割と人気が高いのですよ。県の賞をもらうなど優秀な若手がたくさんいます。ただその分、仕事の熱意が行き過ぎて、結果的にキャパオーバーになったせいか、一時はちょっと退職者が続いたこともあります。今年は内定後に辞退する人もいて、「役場の仕事はきつい」という噂が流れたせいかもと気になっています。
――そのためにも職員の負担軽減を重視しておられるのですね。
そうですね。それと今は任用職員(臨時職員、非常勤職員など)が多いのですが、任用職員にも優秀な方が多くいますので、そのなかから一般職として採用することで人員の強化を図っていきます。さらに新人の育成についても、職員たちの認識を改める必要があります。今の子は、私たちの世代とは育ってきた過程も価値観も異なりますし、頭ごなしに𠮟責してはいけません。コミュニケーションのとり方も、今後皆で変えていこうと思います。もちろん長く働いてもらえるよう、給与水準もそれなりに上げていくつもりですが、最も大事なのはモチベーションです。
林業の振興が最大の使命。山の大切さを発信し理解を深める
――職員のモチベーションについて、もう少し詳しく聞かせてください。優秀な職員が多いのは、実力主義だから頑張れるということでしたが、そうした文化はどうして生まれたのですか。
やはり人口減少に対する危機感だと思います。とりわけ「消滅可能性自治体」とされたことで、逆になにくそ、という反骨精神がかき立てられました。前の村長が非常に熱い人で、職員の皆さんも刺激されて「絶対に消滅させるものか」という思いを共有し、本当に一生懸命になってくれました。私もかつて職員として、また村議会議員として村の振興に関わるなかで、行政の職員にはこのような内から湧き上がるモチベーションが絶対に必要だと痛感しています。ですから新しい職員も、「この山をなんとかしたい」「この村をどうにかしたい」という気概のある人を迎えたい。そういう思いにさせる術(すべ)はないか、教えを乞いたいくらいです。
――川上村の価値を広く知ってもらうことも有効かもしれません。
川上村の最大の価値は山林ですが、人の問題があります。吉野林業の発祥の地である川上村は、昔から林業が盛んで、最盛期には千人を超える優れた技術者が働いていました。技術者と呼ぶのは、V字型の急峻な山の斜面に植林し、70年から100年ほどの木を伐採、集材する知識と技能を備えているからです。ところが、国の方針により海外から輸入した安い木材が広まるにつれ、国内林業は衰退し、技術者たちも高齢化するとともに後継者が育たないという、深刻な問題を抱えています。
一方で、山の手入れがなされていないから、営林の仕事はいくらでもあります。移住のネックとなるのは、仕事があるかどうかです。川上村では移住者の受け皿として、かわかみらいふもありますし、今後はリモートで仕事ができる環境も整えていく予定ですが、ボリューム的には到底足りません。しかし山の持ち主、五大林業家と呼ばれる大手事業者は、雇用に積極的ではないため、村として若者や移住者に林業に興味を持ってもらい、かつ技術者を育成できる仕組みが必要だと考えています。
――市場原理だけでいうと衰退産業から手を引き、新事業を創出するという選択もあるのでは。
いえ、山は絶対に守っていかなければなりません。既に切って植えるという持続的なサイクルが狂ったため、獣が食べる下草が生えず、畑の獣害などさまざまな問題が起きていますが、最大の問題は「水」です。森林は、大雨のときに洪水を防ぎ、水源涵養機能により水を蓄えます。いわゆる水源林です。東京では、多摩川の森林を水道水源林として管理しています。水は私たちの命に関わる大切な資源ですが、地球の水資源のうち、真水(淡水)は2.5%しか存在しません。日本には割と潤沢にあるのですが、その真水を守り、私たちに供給しているのは他ならぬ日本の山々なのです。
――山林の維持は、私たちの身近な生活にもつながる問題なのですね。
大雨被害や渇水などの危機感から水源の山を守ろうとする町村の団体も増え、川上村では水源地に源流館という施設をつくって教育・啓発活動に取り組んでいます。しかし山の大切さを広め、雇用までつなげるには、やはりもっと大きな声で訴えていかねばなりません。ある種の政治力も必要ですので、水源地に位置する私たちがそうした活動を率先してやっていきたいと考えています。また、先ほど触れた農家民宿は、SNSの拡散により国内外の客が増加しました。今後は山の重要性についてSNSの活用なども視野に入れ、職員や村民の皆さんと協力して発信力を高めていきたいと思っています。
――活動費などの原資はどうされているのですか。
地方創生関係の助成金や、2024年から始まった森林環境税などにも期待していますが、川上村にはダムの建設時に国からいただいた賠償金があり、それを基金にして運用しています。これまでにだいぶ使ってしまいましたが、振興には代えられませんので行けるところまで行くつもりです。林業の振興はもとより、長く暮らす住民が「ついの住処」として、また移住者がいきいきと働けるよう、削減できるところは徹底的に削減しながら、最後の砦として有効に活用していきます。
――村の存続に向けて高齢者支援、移住者支援など、さまざまな行政サービスを実施される一方で、決して譲れない山林の維持について村長の想いを聞かせていただきました。特に山林は日本全体の環境に関わる問題であると改めて理解しました。これからの川上村の取り組みにさらに期待しています。
聞き手:坂本貴志
執筆:稲田真木子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ