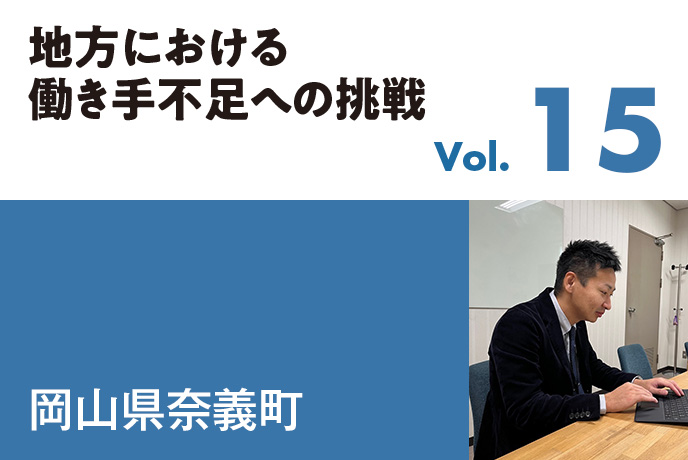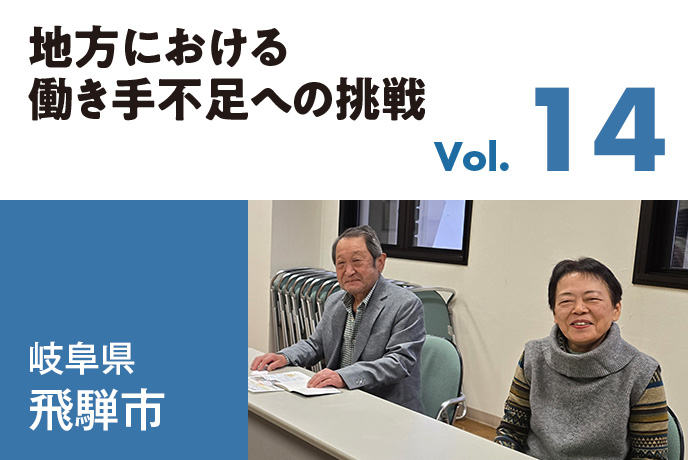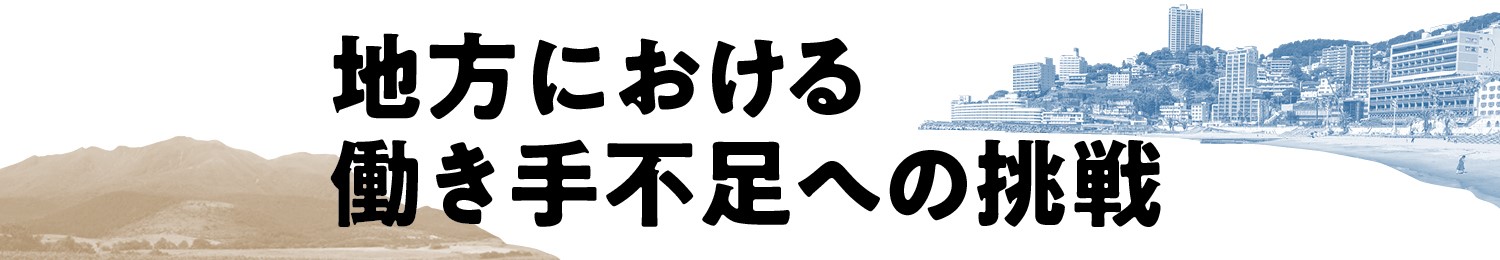
人とつながり、頭と身体を動かすことが元気の源。村にはその仕掛けを期待――奈良県川上村・住民インタビュー
奈良県・川上村では、「村民がいつまでも暮らし続けたい村づくり」に向け、一般社団法人かわかみらいふを設立して、買物支援事業などを通した福祉サービスの提供に力を入れている。サービスを利用する村民は、その恩恵や課題をどのように感じているのか。長く彼の地で暮らす3名の村民に、半世紀にわたる川上村の変化を伺うとともに、地域交流のあり方や、今後かわかみらいふに望むことなどさまざまに語ってもらった。
「行商」の代わりに移動スーパーが定着。なくてはならない存在に
――皆さんは川上村で暮らしてどのくらいになりますか。
Aさん:私は川上村で生まれ育ちました。若い頃は一度村を出て、都会で仕事をしていたけれど、30歳を過ぎた頃に戻り、今73歳です。帰郷して40年以上、合計でゆうに50年は超えているかな。
Bさん:私は他県の出身ですが、両親と一緒に子どもの頃、川上村に移り住みました。人生のほとんどは川上村で過ごしたようなものです。
Cさん:私は結婚がきっかけです。夫が川上村の出身で、一緒に戻ってからやはり50年近く経っています。
――半世紀にわたり川上村に暮らす皆さんから見て、村はどんなふうに変わりましたか。まず日々の買物に関してはいかがでしょうか。
Aさん:10年くらい前まで、生モノの食品は軽トラックに積んで売りに来ていたかな。今の移動スーパーのような感じやけど、魚とか肉とか、個人で仕入れて販売していたと思います。野菜類は自分たちでつくっているから買うのは肉か魚で、売りに来られるのは肉はめったになく魚がほとんど。私が子どもの頃は、天秤棒を担いだサバ売りの行商がよく来ていたものです。その頃は冷蔵庫もなく、行商の人も歩くほかないから、売りに来るサバは舌が痺れるほど塩漬けにされていたのを憶えています。
Bさん:食品はほぼ売りに来ていたから、お店に買いに行くことはなかったね。果物も和歌山のミカンとか、県外の産地から直送で運んできてくれました。お正月が近くなると2トントラック一杯に箱を積んで。あの頃は、一つの家庭で2箱も3箱も買うのが当たり前やったから稼げたんでしょう。
Aさん:魚や肉の行商もそうですが、段々と来なくなったのは、お年寄りばかりの家庭になって量がはけないから採算が合わなくなったんだろうね。ガソリン代もかかるしね。だから今、福祉の一環として赤字覚悟でやっとる移動スーパーが、私たちの命綱です。なくしたらあかん、といつも村長に伝えています。
Bさん:ほんまにそう。この先、事故を起こしたらいけないから車の免許もいずれは返納しなきゃならないし、まだまだ元気な私たちにとっても日常に欠かせないサービスです。
――生鮮食品以外の日用品などはどうされていたのですか。
Aさん:昔は、名前だけやけど「百貨店」と称するお店が川上村に3つあり、衣類や電気製品はそこで買っていました。ただ、一番近くにある百貨店でも8km先、今なら車で15分くらいだけど、当時は道も悪いし、もっと時間がかかっていた。遠くの百貨店だと、大阪に出かけるような感覚かな。
Bさん:だから年に2回、お盆と正月の前に行って、ロウソクとか線香とかお正月用の晴れ着とか、まとめて半年分の日用品を買うのが、村民の慣習のようになっていました。私が二十歳くらいまではそんな感じでした。
Cさん:百貨店がなくなった今は、お店に行くというとホームセンターか、電気製品なら家電量販店。どこも車で1時間以上かかるから、車に乗れない人は近所の人や子どもに頼んだりしているけど不便ですね。ネット通販を利用する人もいるけど、若い人はともかく、うちの地区でネットから買うお年寄りは少数です。スマホは皆持っているけど、電話でしか使いません。
Aさん:私もネット通販をしていたけど、段々面倒くさくなって、最近はもっぱらテレビショッピング。保存が利く水などの日用品は生協で、生モノは移動スーパーで買えるけれど、この2つですべて事足りるわけじゃない。だからかわかみらいふさんには、もっと頑張ってほしいと期待しています。また、移動スーパーにしても、仕入れ先との兼ね合いで、買いたい食品がすぐに品切れになることも割と多いので、まだまだ改善の余地がありそうです。もっとも、かわかみらいふさんの方でも色々と考えてくれていて、この前も、買物ツアーみたいなことをやっていたね。隣町のスーパーに往復する間に、薬が欲しかったら薬局に寄るし、コンビニも回ってくれる。好きなモノが買える良い試みなので、うちの地区でもぜひやってほしいと伝えました。
地域の行事が失われてもコミュニティは健在。移住者も温かく迎える
――お祭りなどの行事を通した地域の皆さんの交流や、地域の助け合いみたいなものは、この50年で変わりましたか。
Aさん:昔は、川上村にも講(※祭りを盛り上げるために結成された団体)があって、盆踊りをはじめいろんなお祭りを盛大に開いていました。「富くじ」という、今でいう宝くじのようなこともやって、大いに楽しんだものです。しかし段々縮小してきたところに、コロナ禍で人が集まることが難しくなったのを機に、一遍に行事がなくなりました。
Cさん:かつては伝統的な行事もたくさんあり、なかでも有名だったのが、江戸時代から続く「千本杵搗(せんぼんきねつ)き」です。これも恒例だった「吉野川・紀の川源流まつり」のなかで行われる子どもたちの餅付きなのですが、8年前に途絶えました。ただ最近、京都の大学生からフィールドワークとして体験させてほしいという話があって、久しぶりに再開し、私たちも見させてもらいました。お爺ちゃんお婆ちゃんが特に感慨深げで、涙される方もいて、外から来た私には窺い知れない想いの深さを感じました。
Aさん:そうやったね。ただ、行事がなくなったのは悪いことばかりでなく、移住してきた人が溶け込みやすくなったという利点もあるかな。都会から来た人のなかには、宗教めいた行事や風習に馴染めない人もおるし、また、絶対に押しつけてはいけません。移住者には年2回ほど、清掃などの奉仕活動に参加してくれるだけでいいと伝えています。
Bさん:祭り事がなくなっても、助け合い精神みたいなものは失われていませんしね。私は民生委員をしていますが、この地区の住民はまるで本当の親戚のように自然と助け合っています。決してベタベタと付き合うわけではありませんが、「あの人、何日か顔を見ていないな」「カーテンが閉めっぱなしだけど」などと誰かが言い出すと、近くの人が様子を見に行ったり、別の誰かが心配している皆さんに状況を伝えたり。そんな絆の強さが一番すごいなと感じています。
Cさん:私もヘルパーとしていろんな地域のお宅に行くのですが、なかには気軽にお隣さんに頼みごとができなかったり、声すらかけづらかったりするところもありますね。でもこの地区では、助け合い精神が根づいています。
Aさん:この地区は31世帯で、住民は30数名。ほとんどが単身か二人暮らしの高齢世帯だから、お互い助け合っていかなきゃという仲間意識が強いのかな。若い世代では、中学生のお子さんがいる50代の夫婦と、40歳過ぎの単身者がいて、彼らは移住者です。40過ぎの彼は、地域おこし協力隊として入ったのをきっかけに移住してくれました。昔は村民の結束が強いあまり、排他的な部分もあったと聞きますが、今は何の分け隔てもありませんから、移住者も暮らしやすいと思います。
自宅でいきいきと暮らすのが健康の秘訣。役場には救急搬送のケア体制を期待
――高齢の方が多いので、介護や医療も身近な関心事だと思います。高齢者福祉や医療サービスに求めたいことはありますか。
Bさん:私は若い頃、川上村に高齢者用の施設があったらいいと思ってたんですよ。でもこの年になり、また民生委員 になって他の地域もいろいろと見て、健康の秘訣は自分の家に住み続けること、とつくづく実感するようになりました。だから施設は要らない、とまでは言いませんが、少なくともぎりぎりまで自宅で暮らすべきと思っています。
Aさん :我が家で暮らし、それに加えて人と会うことやな。この地区では健康づくりのちょっとした集まりがあって、私も今日、体操に参加してきました。先生の言うとおり身体を動かしながら、成功したら笑い、失敗しても笑うというユニークな体操で、「笑い」があるのがいいですな。皆でワイワイ騒ぐとストレスも発散されるし、認知症防止にもつながるようです。うちのお婆さん(母)も、体調を崩して家にこもる日が続くと、自分から外に出たがります。
Cさん:「顔色が悪い」とか、必ず誰かが気付くし、移動スーパーでも看護師さんが一緒に来てくださるから気軽に相談できます。診療所の先生も「外に出ろ、出ろ」と勧めるせいか、川上村には寝たきりの方が少なく、元気なお年寄りが多いですね。
Bさん:私たちは畑仕事を続けていることも大きいかな。畑仕事は種蒔きから収穫まで、天候や作物の特性などさまざまなことを考えなければなりません。「いつ間引こうか」とか、結構、頭を使う仕事です。
Aさん:まあでも年が年だから、骨折したり、脳梗塞や心筋梗塞になって救急車で運ばれることはあるわな。村長にも話したけど、そのときにはやはり、看護師さんなど事情のわかる専門家に、搬送先の病院との橋渡しをしてほしい。私らが付いて行っても何もできないし、親族が駆け付けるまで1人でいるのは本人も心細いでしょう。高齢者は皆、そうした「いざというときの不安」を抱えていると思います。私たちも元気で働くから、安心のために役場にはぜひ刷新的な仕組みを考えてほしいですね。
――時代が変化するなかでも、皆さんが毎日いきいきと暮らされていることがわかりました。ありがとうございます。
聞き手:坂本貴志
執筆:稲田真木子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ