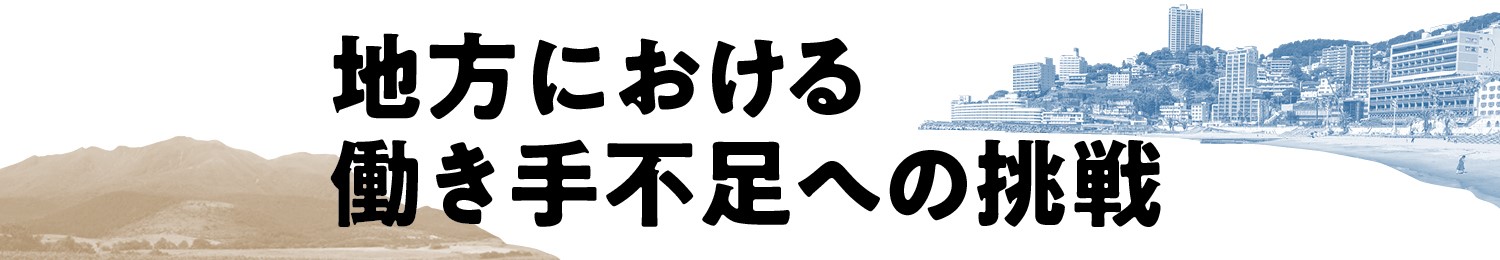
「労働供給制約社会」を前提に、官民協働の新たなシステムによる解決を目指す――福岡県大牟田市【前編】
2015年から2045年にかけて生産年齢人口が6割まで減少することが予測される福岡県大牟田市。「人手不足でケアプランの作成ができなくなりつつある」など、介護や移動、行政などの分野で既にその影響が顕在化しつつある。この「労働供給制約」を一人ひとりの可能性で乗り越えることを目指すのが「大牟田未来共創センター」である。同センターの原口悠氏と協働する地域創生Coデザイン研究所の梅本政隆氏に、問題意識や具体的な取り組みを聞いた。 一般社団法人 大牟田未来共創センター(ポニポニ)
一般社団法人 大牟田未来共創センター(ポニポニ)
代表理事 原口 悠(はらぐち・ひさし)氏(写真右)
株式会社地域創生Coデザイン研究所 未来の社会システム探索チーム
ポリフォニックパートナー 梅本 政隆(うめもと・まさたか)氏(写真左)
1960年代に比べ人口が半減。典型的な労働供給制約地域へ
福岡県南西部、有明海に面した大牟田市は人口10万5,158人(2024年9月1日現在)、高齢化率38.2%(同)の地方都市である。昭和30年代まで石炭産業とともに発展してきた同市の人口は、1959(昭和34)年の20万8,887人をピークに、石炭から石油へのエネルギー転換や産業構造の変化によって生産年齢人口を中心に半減した。今後、出生率などの変動がなく現状を投影した場合、2060年には5万5,287人へとさらに半減すると予測されている。生産年齢人口に着目すると、2015年を基準として30年後の2045年には6割まで減少することが見込まれる。直近の予測では2020年からの5年間で約2,000人(最も年齢の高い現役世代である60~64歳人口とこれから現役世代となる15~19歳の参入組との差分約3,000人に就業率6割をかけた人数)の働き手不足が発生する恐れがある。
既に働き手不足が顕在化している領域としては介護、移動サービス、そして行政などがある、と原口氏と梅本氏は語る。
「介護分野では地域のケアマネジャーがどんどん減っているのでケアプランの作成が遅れ、介護サービスが受けられるまでに従来よりもタイムラグが生じる事態になっています」(梅本氏)。同時に行政サイドでは介護認定のために自宅や病院に行って申請者の聞き取りを行う「訪問調査員」が不足しており、本来30日で認定結果を出すべきものが、これも遅延する事態になっている。加えて、介護の現場の人手不足は大牟田市も例外ではなく、ヘルパー不足のために入浴が週2回だったのが1回になり、体を拭く形式で済ませたりするケースがみられる。在宅の訪問介護の現場では、ヘルパーの高齢化が進み、85歳の要介護の高齢者を75歳のヘルパーが介護する「老老介護」化が珍しくない。
一方、地域公共交通の領域ではバスの運転手不足が深刻だ、と梅本氏。
「バス会社は『補助金を出してくれれば走らせます』というスタンスだったのが、最近は『補助金をもらっても運転手がいないのでこの時間しか運行できない』という状況に変わりつつあります」
代替手段として期待されるタクシーも同様にドライバーが高齢化しており、採用もおぼつかない状態況。今後もドライバー不足によるさらなる減便、路線廃止などが起こる可能性があり、市民の「移動の自由」が損なわれる状況が現実味を帯びている。
公務員の人手不足についても、インフラ維持に不可欠な土木や施工、設備系の専門職の不足が深刻で、通年で募集をかけても応募は限られており、せっかく入職しても忙しさに耐えられず早期に退職する例もみられる。このまま事態が改善されなければ、インフラ維持や防災対策などに影響を与える可能性が高まるだろう。 大牟田未来共創センターのオフィスの様子
大牟田未来共創センターのオフィスの様子
そして、大牟田未来共創センターが梅本氏ら地域創生Coデザイン研究所とともに運営するのが「大牟田リビングラボ」である。近年耳にすることが増えている「リビングラボ」は、社会課題に取り組む際、サービスの利用者である生活者と、サービスの提供者である企業・行政などが共にサービスを創る(共創する)方法論である。「大牟田リビングラボ」では地域課題、行政課題、そして企業や研究機関の課題を組み合わせる形でプロジェクトを組成し、それぞれが今までに気付かなかったような価値や示唆を得ることに取り組んでいる。地域における課題を企業や研究機関にとっての価値に転換することで税金とは異なる資金の流れを生み出している点も特徴といえる。 2021年には大牟田市と大牟田未来共創センターの間で「地域共生社会の実現に向けた連携協定」を締結
2021年には大牟田市と大牟田未来共創センターの間で「地域共生社会の実現に向けた連携協定」を締結
他の自治体に比べ要支援状態の高齢者の「改善」が進まない
大牟田未来共創センターがこれまでに取り組んできたプロジェクトとしては、介護予防分野の「短期集中予防サービス」、障害者をはじめとした働きづらさがある人たちの「超短時間雇用」、「中小企業支援」などがある。
「短期集中予防サービス」はデンマークやイギリスなど海外で実践されている「リエイブルメント(※2)」というプログラムを応用したもので、高齢者が自立して生活を送れるよう支援するとともに、継続的な支援の必要性を適切に減らし、長期的なサービスのコストを削減することを目的としている。要支援状態の高齢者がリハビリテーション専門職と面談しながら3~6カ月の短期間に集中して運動などを行うのが特徴で、先行して導入している山口県の自治体では利用者の60%以上が要支援状態から自立した元の生活に戻っている。
「大牟田の場合、介護予防ケアマネジメントの対象者を抽出して調査した結果、2015年からの4年間で『改善した』のはわずか4.3%にとどまっています。住んでいる地域によって元気になれたりなれなかったりというのは、ある意味住民の権利問題ともいえることから、大牟田でも行政と一緒に短期集中予防サービスのモデル事業を実施してきました。現場レベルでは作業療法士、理学療法士からの一定の評価がありましたが、行政側の人員体制が組めないという問題でいまだ実装には至っていません」(梅本氏)とここでも行政サイドの労働供給制約の影響が露呈する事態になっている。
最短1日15分でも就労を可能にする「超短時間雇用」にトライ
障害者をはじめとした働きづらさがある人たちの「超短時間雇用」は東京大学の先端科学技術研究センターの近藤武夫教授が提唱している、最短1日15分の労働でも報酬を得られる就業モデルである。週40時間、年間12カ月働くキャリアモデルが中心の日本の雇用モデルは、健康な成人男子を暗黙のうちに想定したものであり、それ以外の人々を排除しがちだ。障害者雇用促進法においても障害者が最低週に20時間働くことが前提になっており、働く力があっても短時間しか働けない人たちには対応することが難しい。同モデルはこうした状況を打破するためにタスクを明確化することで超短時間での就労を可能にすること、さらには障害のある人とない人が同じ職場で働くことを目指している。既に大手IT企業や自治体などでモデル事業が開始されているが、大牟田未来共創センターでもこの理念に共感し、先端科学技術研究センターの協力を得てトライアルを始めている。
「ただ、こちらも他の自治体が先端科学技術研究センターと直接協定を結んで実施する体制を組んでいるのに対し、大牟田市はまだ大牟田未来共創センターの自主事業にとどまっています。働きたいという人からの相談は10件以上ありましたが、働く場所や職務内容のマッチングが難しく、まだ稼働は数えるほどです」と梅本氏。軌道に乗せるにはもう少し時間が必要だ。 医療機関での超短時間雇用のケース
医療機関での超短時間雇用のケース
「大牟田として人を雇用し・育てる」仕組みの実現を目指す
高齢者や障害者の可能性を引き出すこととともに、大牟田市の産業の7~8割を占める介護、交通、小売り、飲食などの生活維持サービスの多くを提供する市内の中小企業への経営支援も重要なテーマの一つと原口氏は語る。
「大牟田市における産業活性化策については、これまで協議会方式で議論が重ねられてきましたが、目的や責任が明確化されず、新たな事業の創出やDXを推進する人材の採用・育成、経営者・経営層同士が情報共有できるコミュニティなどが実現できていませんでした。そこで、ワンストップ経営相談窓口である『大牟田市ビジネスサポートセンター』の立ち上げに参画し、スタッフを派遣しています。加えて、行政とともに『隠れた意欲ある経営者・経営層』と出会うためのアウトリーチ策を進め、経営者が安心して弱音や本音を語り合うことができ、人材育成や人材の交流を協働して進めることができる『次世代経営層コミュニティ』を生み出すことに取り組んでいます」(原口氏)
今後、これらの取り組みを発展させることで、「大牟田として人を雇用し・育てる」仕組みを実現し、大牟田市の産業が社会環境に適した形で変容し続けられるようになることにコミットしていくという。 大牟田未来共創センターのスタッフで、企業の経営層へのアウトリーチを行う内田遼平(うちだ・りょうへい)さん
大牟田未来共創センターのスタッフで、企業の経営層へのアウトリーチを行う内田遼平(うちだ・りょうへい)さん
「量」や「規模」の拡大から、「質」や「価値」を高める方向へ転換
大牟田未来共創センターは2024年2月に「労働供給制約社会 大牟田レポートver1.1」で大牟田市の労働供給制約に関連する状況(データ)をまとめ、同年10月には「大牟田への提案2024 『労働供給制約を一人ひとりの可能性で乗り越える』」で過去5年間の取り組みを踏まえた新たな解決策を提示した。その主旨は、労働供給制約によってこれまでの「量」や「規模」の拡大による地域発展の道が閉ざされるなか、「質」や「価値」を高める方向に方向転換することであり、その源泉となるのは「大牟田で暮らし、働く一人ひとりの人間」であるというものである。労働供給制約社会においては、一人ひとりの可能性や意欲が発揮される環境を整えることこそが、大牟田の新たな持続的発展の道を拓くと原口氏らは主張する。上記の提案において原口氏は一人ひとりの可能性を最大限引き出す地域社会の実現には、①新たな官民協働の仕組みの構築、②政策の優先順位付け、行政機能の再構築、③生産性と多様性の向上が不可欠としており、そのうえで④教育・介護予防・移動などの仕組みのアップデートを図ることが必要だとしている。
「従来の行政のあり方として人手不足というとどうしても外から人を連れてくるとか、駅前をにぎやかにすればいいとか、施策をどんどん追加していく傾向があります。しかし、役所の職員の供給すら危うい状況ではなかなか実効は望めません。まずは労働供給制約社会というリアルを共有し、その共通認識に立ったうえで新しい意思決定の方法や仕組みそのものを変えないといけないと考えています」と原口氏。後編ではその新しい意思決定の方法や新たな官民協働の仕組みの方向性などについて見ていきたい。
(※1) 大牟田未来共創センターでは、パーソンセンタードを「人間の豊かさに価値を置き、誰もが持つ潜在能力の発揮にナラティブ(物語性)やつながりが欠かせないとする人間観」と捉えている。
(※2) 日常生活で機能するために必要なスキルを学習または再学習することにより、身体的または心理的障害のある高齢者が自分の状態に適応するのを支援するサービス
聞き手:古屋星斗
執筆:高山淳


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

