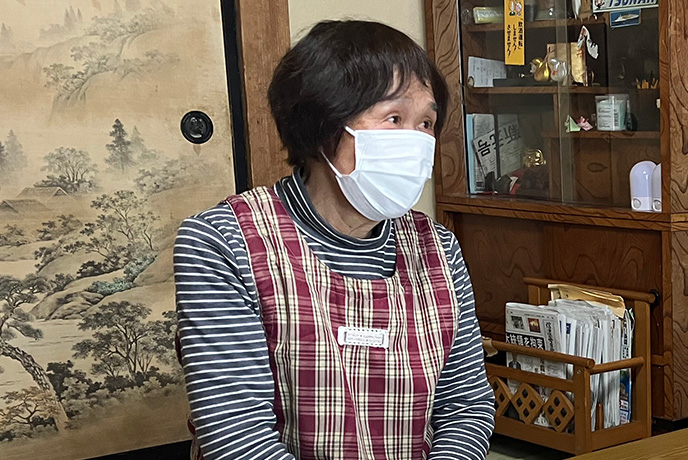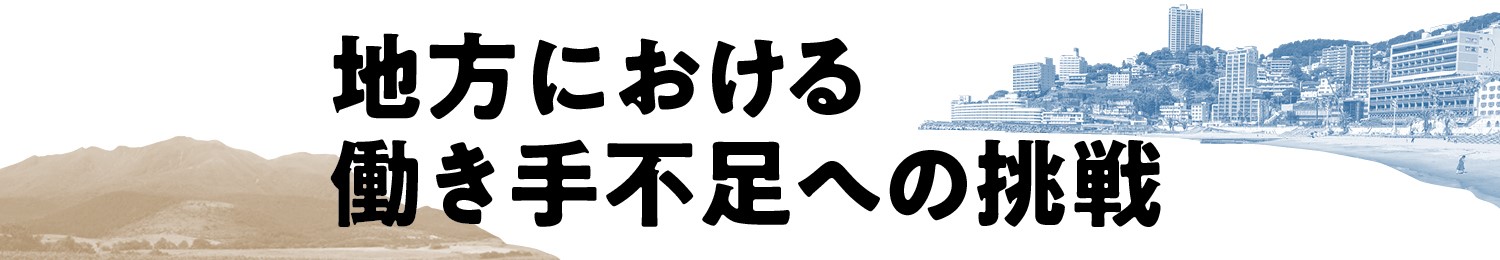
高齢化率45%の中山間地域に持続可能な交通のカタチを提示した「共助交通」――鳥取県智頭町
地方の中山間地域においては、人口減少による採算の悪化やドライバーの確保が困難なことから路線バスなど交通インフラの持続が困難になりつつある。「日本1/0村おこし運動」で全国的にも住民自治が進んだ町として知られる鳥取県の智頭町もその例外ではない。同町が町営バスに替わる新たな交通手段として導入し、利用が広がる「共助交通」について同町企画課の長谷龍太郎氏に導入の背景や運営方法など具体的な取り組みを聞いた。 智頭町役場 企画課
智頭町役場 企画課
長谷龍太郎(ながたに・りゅうたろう)氏
運行収入減少とドライバー不足で町営バスの運行を断念
鳥取県の東南部に位置する智頭町は、総面積の93%を山林が占め、1000m級の山々に囲まれた中山間地域である。多くの地方都市と同様、都市部への流出による人口減少と高齢化という深刻な課題に直面しており、2000年に約1万人だった町の人口は約6100人(2025年2月)まで減少、高齢化率は45%を超える。これに伴い町の生産年齢人口も相対的に減少し、地域経済や社会サービスの維持にも大きな影響を与えている。 総面積の93%を山林が占める智頭町
総面積の93%を山林が占める智頭町
「地方の中山間地域共通の課題ですが、ドライバー不足・高齢化や利用者減に伴う運行収入の減少により5年ほど前から町営バスなど公共交通の経営が困難な状況になっていました」と企画課の長谷氏は語る。町内の主な移動手段としては2007年運行開始の町営バス「すぎっ子バス」が町の中心部から山間部へ4路線、平日8往復で運行されてきた。しかし、通園・通学利用者の交通費無償化やマイカー依存等により利用者が年々減少する一方で、町の財政を圧迫してきたことから、2023年3月末をもって方針転換が決まった。これに先立って町では代替手段として2019年に策定した「智頭町地域公共交通計画」により地域住民参加型の「共助交通」の導入準備を進めてきた。
「共助交通」とは地域住民が主体となって自家用車等を活用し、自身がドライバーとなり有償で運送を行う仕組みのことで、導入しているのは全国でも智頭町の他に愛知県豊田市など数えるほどしかない。ドライバーは専用ステッカーを貼った自家用車等で送迎し、利用者は事前利用登録のうえ、予約、乗車、決済などを行う。
地域公共交通計画では実現に向けて2020~21年に導入計画の検討、国の「地方創生推進交付金」を活用した実証実験を開始し、IP告知端末等による公共交通検索・予約システムの導入や各地区でのドライバーの求人活動を進めてきた。2022~23年には、全地区で行政、住民、事業者が一体となった「共助交通運営協議会」を組織し、23年の運行開始へと歩みを進めた。
役場の職員も副業で走行する共助交通・AI乗合タクシー「のりりん」
新たに導入した共助交通のサービス名はAI乗合タクシー「のりりん」で、配車やルート設定にAIを活用し効率性を追求した運行管理システムを採用している。住民は全戸に配布されているIP告知端末の予約アプリもしくは電話で乗車予約が可能。バスの停留所に当たる乗降ポイントは町内に270カ所設置されており、利用者は予約時にポイントを指定する。配車については自前のコールセンターを整備し、従事するオペレーターが専用システムで配車を行い、利用者に通知する。住民の要望により定期的にポイントの数も拡大されてきている。運賃は単独利用で移動距離にかかわらず一律一乗車500円で、2人以上の乗り合いの場合は400円に割引される。定期券は1カ月乗り放題で5000円。また、18歳以下の人、75歳以上の高齢者や障害者、要介護・要支援認定を受けている人は割引運賃が適用される。
 AI乗合タクシー「のりりん」のドライバーは町内で約30人が稼働
AI乗合タクシー「のりりん」のドライバーは町内で約30人が稼働
ドライバーは運営協議会事務局が呼びかけし、2025年2月現在、町内で約30人が稼働、常時5台が1日4シフトで6時から19時まで走行する。本来、有償運送は2種免許が必要だが公助交通は特例として、国の認定講習を受講すれば普通免許所持者でも運行が可能である。報酬は1シフト4時間で3500円、通しで7時間走ると7000円(交替1時間はシフトの被り)で燃料費は自己負担となる。報酬は乗車回数や距離にかかわらず時間拘束に対して支払われる。予約が入らなくても、運行実績がなくても、報酬は同額である。
「不公平感を解消するため、運行回数に応じて5回で500円などインセンティブも支払います。ドライバーの年齢層としては40代~70代の方で、職場の現役を退いた方や農家の方、警備の仕事とのダブルワークの方などが中心です。中にはバスやタクシーの経験者の方もいて即戦力で活躍いただいています。実は企画課が主管担当課のため私と同僚職員も講習を受けて、補完的にドライバーとして走ることもあります。副業規定の見直しにより、既定の報酬を得ることが可能になりました」
サービス開始から約2年で町民の生活に浸透し、1日平均150件、多い日には180件もの運行を記録、月間では3000件を超える運行件数をコンスタントに記録している。
「共助交通導入により従来の交通施策と比較して財政負担の軽減につながり、利用者の利便性向上に寄与しています。また、副次的な効果で、高齢者の外出機会の創出や地域経済の活性化、生きがいづくりなど、幅広い分野にも貢献していると思います」
「日本1/0(ゼロ分のイチ)村おこし運動」など住民参加による持続可能な地域づくり
智頭町では、「共助交通」以外にも、持続可能な地域づくりを目指した住民参加型の共助による取り組みが行われてきた。その代表例が、「日本1/0(ゼロ分のイチ)村おこし運動」と「百人委員会」である。
「日本1/0村おこし運動」は1997年、「町づくりに答えはない」という理念のもと、住民が主体的に地域課題に取り組み、無(ゼロ)から有(イチ)への一歩を踏み出すことを目指してスタート。各集落が「集落振興協議会」を主体として活動し、それぞれの計画に基づき、伝統行事の維持や地域資源の活用など多彩な活動を展開している(現在は旧小学校区をベースにした「地区振興協議会」へ発展的に移行)。例えば五月田集落の「かんがえ地蔵祭り」は、13世帯という小規模集落でありながら、毎年1000人以上の来場者を集める大規模なイベントとして定着、住民の地域への愛着につながっている。取り組みのテーマは主に地域の特産品の開発や伝統行事の維持・活性化などが中心だが、遊歩道や城跡の整備や紅梅林の管理、高齢者給食サービスなど公助を補完する活動などにも広がっている。 例年多くの来場者を集める五月田集落の「かんがえ地蔵祭り」
例年多くの来場者を集める五月田集落の「かんがえ地蔵祭り」
一方、「百人委員会」は地域課題の解決を目指し、住民が主体的に政策提言を行う組織として2008年に設置された。商工・観光、教育・文化、獣害対策、林業、特産農業などの部会があり、それぞれに役場の担当部署が連携、多岐にわたる分野で活動を展開する。例えば林業部会では2022~23年に町内で管理の行き届いていない桜土手の180本の並木に着目し、堆肥散布による樹勢回復や枯れ枝除去などに公・共で取り組んだ。学生の部もあり、中学生による公園建設の提案や、高校生による商店街活性化のアイデア提案など、ユニークな取り組みが数多く生まれている。

町ぐるみで林業の次代の担い手を育成
冒頭で述べたように智頭町は面積の93%を山林が占め、林業が産業の核を成している。ここでも担い手不足が深刻な状況だが、特定地域づくり事業協同組合制度(※)を利用して2021年に設立された「智頭町複業協同組合」は「半林半X」という新しい働き方の提案により林業の人材不足解消と移住促進を目指す。組合は正社員として雇用している職員を派遣し、職員は林業を軸としながら飲食業など他の仕事を組み合わせて働くことができる。「林業を志して修業し、いずれは生計を立てていきたいがまだ経験がない」という多様なスキルを持つ人材を地域に呼び込み、定着させることを狙う。
「実は企画課で広報や編集デザインの業務をお手伝いいただいているスタッフも同組合に所属しています。役場も林業事業者も正職員の雇用は難しいが、スポットであれば働き手が欲しいというときに非常に有効なシステムです」と長谷氏は語る。町内の林業事業者は毎月定例の「ドラフト会議」を開催し、所属している正社員の育成状況を報告し合い、スキルアップの方向について共有、町ぐるみで林業の次代の担い手を育成している。
智頭町は、これらの取り組みを通じて、人口減少という課題に立ち向かいながらも、住民一人ひとりが誇りと生きがいを感じられる持続可能な地域社会を目指す。また、地域住民の主体的な活動を支援し、多様な人材が活躍できる環境を整備することで、地域全体の活力を高めていこうとしている。
(※)人口急減地域において、人手不足に悩む複数の事業者が組合を設立し、組合で採用した職員を、需要に応じて複数の仕事に従事するマルチワーカーとして各事業所へ派遣する仕組み。島根県海士町など全国に100以上の組合がある。
聞き手:坂本貴志
執筆:高山淳


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ