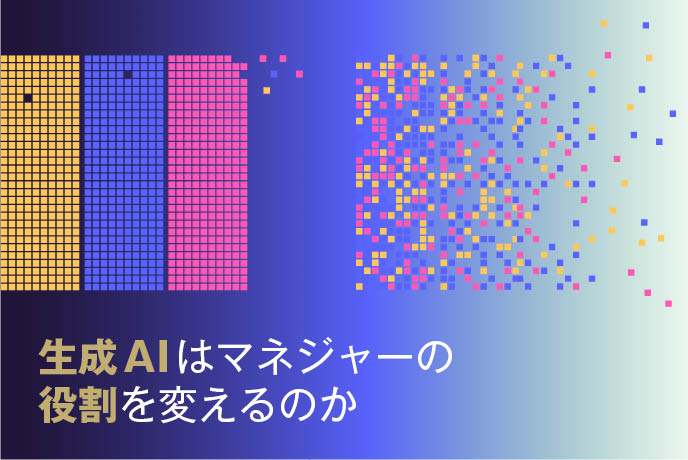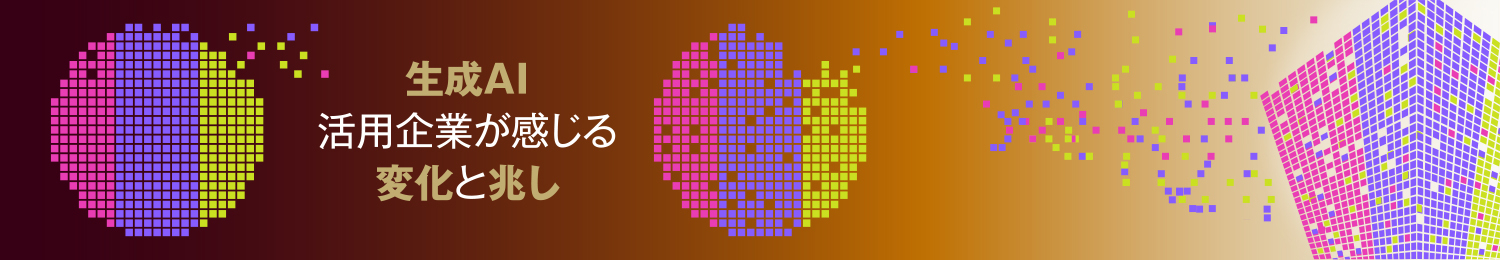
データ活用に専門組織「DIC」を設置 内製化で導入をスピードアップ
流通大手イオンは、データ活用の専門組織である「データイノベーションセンター(DIC)」や社員が生成AIのベーシックなスキルを学べる「デジタルアカデミー」を設け、組織として生成AIを活用しようとしている。DIC統括マネジャーの八木研一郎氏に、生成AIが従業員の働き方や、日々の業務にもたらす変化などを聞いた。
現場の課題がツール開発の起点 大量データの集計・分析に強みを発揮
―DICから生まれた、生成AIの活用事例を教えてください。
DICは2021年に設立され、AIの専門知識やスキルを持つメンバーで構成されています。ただ部署のミッションは生成AIありきというより、バックオフィスや現場から課題を聞きとり、解決策を提案することがメインです。こちらから現場にヒアリングに出向くこともありますし、現場から「この課題を解決できないか」と持ち込まれることもあります。
これまでに生成AIを使って、グループ各社のコールセンターや店舗に寄せられるお客様の声をまとめてトピックを洗い出したり、商品部と連携してECサイトの商品説明文を自動生成するツールを開発したりしました。さらに全国のイオングループの店長を対象とした景気動向アンケートについて、自由記入欄の文章を生成AIでまとめて分析しています。
何千件にも上る大量のデータを、人の力で作成したり集約したりするには時間がかかりますし、人はすべてのデータを精査できるわけではないので、分析の際の正確さにも限界がありました。生成AIを使うことで作業時間を削減できたうえに、すべてのデータを網羅した分析も可能になりました。
―現場から上がってくる数多くのニーズの中から、プロジェクト化するものを選ぶ際の基準はありますか。
グループ内への横展開がしやすく、大きな効果を見込めることが一つの基準です。また既に世の中にツールがあるなら、それを調達すればいいので、世の中に存在せず、イオンが必要としているものを内製することを重視しています。現場のニーズをもとに、プロトタイプを作って試験運用する「PoC(概念実証)」を通じて効果を計測し、活用のめどが立った段階で恒常的なオペレーションに搭載します。事業部門との打ち合わせ中に、DICのメンバーがその場でプロトタイプを作り、それを使ってもらって1週間後にフィードバックをもらい、すぐに修正するといった内製ならではのスピード感がDICの強みです。
開発時間とコストを大幅に削減 手軽さ活かし数をこなす
―業務効率化やデータ分析だけでなく、生成AIを利益拡大に活用する可能性はあるでしょうか。
困り事の解決だけにフォーカスして生成AIを使うと、部分最適に陥るリスクもありますし、トップラインを引き上げることが意識されづらくなります。DICとしても、PoCを実施する際は一つの業務だけでなく、オペレーション全体の流れを見るようにしていますし、効率化で生まれた時間を、トップラインの引き上げに使うための提案も、併せて行うようにしています。ただ職場に実装された事例は、今のところ効率化にフォーカスしたものが多いです。
社会で次世代型といわれる「AIエージェント」の普及が進めば、顧客との対話の中でさまざまな提案が可能になり、売り上げ拡大に貢献する可能性が広がると思います。また今のところ、利益拡大に関しては、生成AIより既存のAIの方が有効に機能する面もあります。たとえば、AIで店から離れてしまいそうなお客様を洗い出して離脱防止の策を打ったり、AIモデルを使って価格を最適化したり、といったことにも取り組んでいます。
―生成AIという技術の強みについて、どのように考えますか。
従来のシステム開発の手法は、何十億円単位のコストがかかり、開発期間も数年に及ぶことが珍しくありません。しかし生成AIを使えば、一人のエンジニアが1~2週間で試作品を作り出せて、コストも100万円程度に抑えられるなど、時間とコストのレベルが大幅に変わります。これは大きなインパクトだと思います。
会計システムのような基幹的な製品については、従来通り時間と費用をかけて、品質を担保する必要があります。ただデータ活用に関しては、手軽なプロジェクトを数多くこなすことも大事だと考えています。DICでは生成AIに限らず、常に20ほどのプロジェクトが動いており、小さめの業務改善からトップラインを一定程度押し上げるものまで創造的なソリューションを、コンスタントに生み出そうとしています。
「アカデミー」を社員の学ぶ場に 空いた時間で顧客との接点を増やす
―DICの生み出したツールを現場で使ってもらうことについて、課題感はありますか。
店舗では通常業務が非常に忙しいこともあり、生成AIを学び使ってみようというマインドを持つ人と、そうでない人が混在しています。このためDICとは別部署にはなりますが、従業員の学びの場として「イオンデジタルアカデミー」が運営されており、DICと連携して、生成AI活用のすそ野を広げようとしています。アカデミーでは、オンラインイベントや勉強会などを開催し、受講者に生成AIのベーシックな知識やスキルを身につけてもらいます。
設立当初こそ指名制での従業員参加もありましたが、生成AIが業務改善に役立つという認識が職場に広がるにつれ、自発的な参加者で枠が埋まるようになりました。中にはITスキルを持たない現場の従業員が、ノーコードアプリの作成トレーニングを受けて、売り場のルーティンワークを可視化するアプリを作り、新入社員などに重宝されるようになった、といった事例も生まれています。参加者が、学んだ内容を職場に持ち帰って業務に活用することで、職場に化学反応を促すことも期待しています。
―生成AIによる業務の効率化は、小売業にどのような変化をもたらすと考えますか。
従来、先端的なデジタル技術は、取り扱いに専門知識が不可欠で、小売業の従業員にとって縁遠い領域でした。このため現場では無駄な仕事の削減など、技術を使わない効率化を主に推し進めてきました。しかし生成AIの登場によって、誰でも気軽に技術が使えるようになり、現場と技術が融合しつつあります。
しかもお客様とのコミュニケーションが不可欠な小売業は、他産業と比べてもフレキシブルな対応が求められ、生成AIが入り込む余地はむしろ大きいと考えられます。これからは上から仕組みを押し付けるのではなく、従業員にベースとなるスキルやツールといった「武器」を提供し、自分たちで業務に活かしてもらうことが、組織の成長にとっても重要になってくるでしょう。既存のツールでできることには現場主導で取り組んでもらい、新たなツールが必要な場合や、大容量のデータ処理などについてはDICが担うことになると考えています。
―生成AIの活用は、必要な人員を減らすことにつながるでしょうか。
業務を効率化した分、人を減らす発想は当社にはないと思います。吉田昭夫社長が社内外で語っているように、効率化で生まれた時間を使って、売り上げにつながる仕事をすることが大事だというのが基本的な考え方です。現場のメンバーを見ていても、AIの活用によって生まれた時間で接客をより充実させ、売り上げ拡大に貢献するという意識は非常に強いと感じます。売り場でお客様の様子を見て「あの商品は個包装の方が売れそうだ」などと判断するのは、AIには難しいですから。
マネジャーの役割は「生成AIウェルカム」な気運の醸成
―これからのマネジャーには、どのようなあり方が求められますか。
これからのマネジャーには、部下が生成AIを使ってみようとしたときに「目の前の仕事に集中しなさい」と言うばかりでなく、挑戦を後押しすることが求められるでしょう。部下が作ったアプリなども積極的に職場に導入し、テクノロジーの活用に前向きな空気を、職場に醸成するのです。特にデジタルネイティブの若い世代は、アプリや生成AIを使うことに慣れています。彼らのやる気を引き出すことで、たとえば魅力的なポップの文章を生成するAIツールを作り出す、といったクリエイティビティを発揮してもらえる可能性もあります。
生成AI活用に前向きなマネジャーと、昔ながらのやり方を続けるマネジャーに二極化していく可能性もあります。職場の好事例をグループ内で共有する、生成AIの活用度合いを人事評価に盛り込む、といった組織的な取り組みによって、マネジャーのマインドを変革する必要もあると思います。
職場内での生成AIの活用は、マネジャーの負担を増やすのではなく、むしろ部署内の業務効率を高め創造性を広げる効果をもたらします。ですからマネジャーも「部下が自分のわからないことをやっている」といったアレルギーを起こさず、取り組みを認める寛容さを持ってもらいたいです。
 八木 研一郎 氏
八木 研一郎 氏イオン株式会社
データイノベーションセンター 統括マネージャー
2019年8月にイオン株式会社へ入社し、データ共有のための基盤構築、データイノベーションセンターの立ち上げ、データ活用プロジェクトの立ち上げと推進などに取り組む。
聞き手:武藤久美子
執筆:有馬知子

武藤 久美子
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ エグゼクティブコンサルタント(現職)。2005年同社に入社し、組織・人事のコンサルタントとしてこれまで150社以上を担当。「個と組織を生かす」風土・しくみづくりを手掛ける。専門領域は、働き方改革、ダイバーシティ&インクルージョン、評価・報酬制度、組織開発、小売・サービス業の人材の活躍など。働き方改革やリモートワークなどのコンサルティングにおいて、クライアントの業界の先進事例をつくりだしている。2022年よりリクルートワークス研究所に参画。早稲田大学大学院修了(経営学)。社会保険労務士。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ