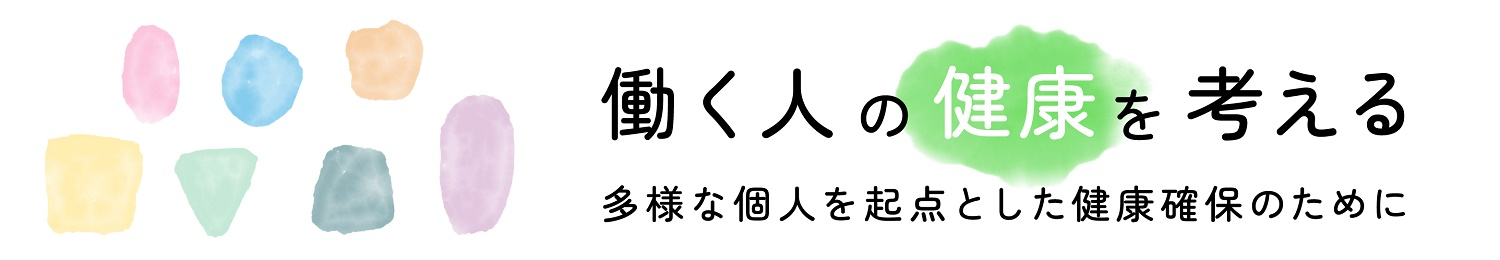
デジタル技術が産業保健の在り方を変える リスクとの「さじ加減」が重要に
センシング技術やAIといったデジタル技術を搭載したツールの普及は、健康診断をはじめとする産業保健の仕組みそのものを大きく変える可能性があると、産業医科大の榎原毅教授は予測する。榎原氏にデジタルツールが産業保健にもたらす可能性とリスクについて聞いた。 産業医科大学 産業生態科学研究所 人間工学研究室 教授 榎原 毅氏
産業医科大学 産業生態科学研究所 人間工学研究室 教授 榎原 毅氏
2005年3月名古屋市立大学大学院医学研究科満期退学、博士(医学)・認定人間工学専門家。2005年同学労働生活・環境保健学分野助手、2007年助教、2009年講師、2019年より環境労働衛生学分野准教授を経て、2022年9月より現職。
IEA(国際人間工学連合)理事(2021-2024)、日本人間工学会副理事長(2016-2018)・理事(2012-2024)、人間工学専門家認定機構・機構長(2024-)、国際標準化機構ISO/TC159(人間工学)国内対策委員会SC3分科会委員長(2012-2024)、人間工学誌編集委員長(2020-2024)、Environmental and Occupational Health Practice誌編集委員長(2020-)、Journal of Occupational Health副編集委員長(2020-)ほか。専門分野は、産業保健人間工学(筋骨格系疾患予防策)、ビッグデータを利用したライフログ解析の産業保健応用など。
普及始まるデジタルツール 活用指針の策定も始まる
榎原教授によると、メンタルヘルスに不安を感じながら生活している人は世界に約3.1億人、うつ症状がある人は2.8億人に上り、予防と介入は世界的な課題となっている。
デジタル技術の進展に伴い、脳波や顔映像、心拍からストレスの状態を推定できるデバイスや、認知行動療法(CBT)を提供するアプリなどが現れ、個人でも自分のメンタルを把握できるようになりつつある。海外にはアバターを作って画面上で会話すると、やり取りの中から認知の歪みを検出して行動変容につなげたり、緊急時に救急医療や警察への緊急通報ダイヤルに連絡できたりするCBTアプリも存在する。榎原氏は「近い将来、ヘルスケアの領域では、デジタルツールの活用がさらに進むと考えられます」と話す。
日本は、デジタルヘルスケアの体制整備の面で欧米諸国に後れを取っており、科学的な効果が本当にあるか否かを示す信頼できる情報も、ユーザーには提供されていない。このため8つの学会が連携して、デジタルツールをメンタルヘルスに活用するためのガイドライン(指針)の策定が始まっており、榎原氏は研究チームの代表者を務めている。CBTのアプリや睡眠管理のアプリなどについて、研究論文のエビデンスをもとに効果を推定し、ツールの普及の度合いなどの社会的な要因も考慮した上で、活用を「推奨」するかしないかなどを5段階のレベルで評価するという。
しかし「睡眠管理アプリ」とひとくくりに言っても、製品の機能は一つひとつ異なる上、論文で効果が認められた製品はほとんどが外国製で、日本で普及している製品が必ずしも同じ効果を持つとは限らない。また研究の被験者は製品を使い続けてくれるが、実際のユーザーは使い始めて約1週間で9割が利用をやめてしまうという調査結果もあり、「研究で得られる知見と社会実装のギャップもあるため、より慎重な議論が必要です」。
社会実装にはメリットとリスクがある さじ加減が大事
指針には、将来的にどのようなデジタルヘルスケアのサービスが産業保健に応用され得るか、という予測も盛り込まれる予定だ。「新たな健康課題が顕在化してから対策を考えるという、従来の産業保健のアプローチでは、技術革新のスピードについていけません。新しい技術が実装された時、働き方や産業構造がどう変わり、どんな課題が生じ得るのかを先取りして検討する必要があるのです」と、榎原氏は理由を説明する。
策定チームは、今進められている技術開発の動向をもとに、将来のツールには睡眠解析や音声による感情解析など11の技術領域が使われる可能性が高いと予測した。特に研究が活発な領域の一つが音声感情解析で、オンライン会議で相手の精神状態をモニタリングしたり、音声の波形をもとに、ストレスの状態や感情をリアルタイムで推定したりする技術が生まれている。この技術が実装されれば、例えばコールセンターの働き手の声をモニタリングし、ストレスが高まったら産業保健のスタッフがアプローチする、といった用途での活用が期待できるという。
「デジタルツールを活用する利点は、状態が悪化して休職したり通院したりする前の、早い段階で予防介入できる可能性があることです。さらに従来の問診票は主観に基づくものでしたが、客観的にメンタルの状態が見える化されるメリットもあります」
一方で、ツールが実装された場合のリスクも考える必要がある。音声情報で健康状態が分かるようになった場合、音声には機微に触れる健康情報が含まれることになり、それに見合った取り扱いを考える必要が出てくる。解析技術が進み、仮に治療法のない病気を検知できるようになった時、本人に病気を告知すべきかどうか、といった「知る権利」および「知らない権利」の問題も生じる。
人が相手にどんな感情を抱いているか、といった情報はプライバシーにも関わる。例えば謝罪会見の音声を第三者が勝手に解析し「内心では反省していない」との結果をSNSに拡散した場合、たとえそれがAIの誤判定でも、謝罪した人が社会的な批判を受けかねない。
「心の状態を全て可視化することが、社会課題の解決につながるとも限りませんし、全ての技術を実装すればいいわけでもない。さじ加減は考える必要があります」
情報管理の取り扱いを変える場合は、法制度の見直しも視野に入ってくる。「情報管理の規制をあまりにも厳しくすると、スタートアップの新規参入などを阻害し産業保健サービスが発展しなくなる恐れもあります。法制度を考える時は、個人情報保護だけでなく社会に役立つ産業の振興など、幅広い視点を持つことが求められます」
技術が産業保健の姿を変える あるべき未来像の設定が大事
榎原氏は「技術革新に伴い、産業保健の在り方も劇的に変わる可能性がある」とも考えている。
例えば非接触センシング技術の進化に伴い、産業保健の柱である健診の姿も変わるかもしれない。既に現在、ウェアラブルデバイスなどを通じて心拍や歩数が計測され、記録がスマホに送られて蓄積される環境が整いつつある。「2040年にはウェアラブルデバイスを通じて、日常生活を送りながら常に健診ができる社会が当たり前になっているかもしれません。ユーザーは異常値が出たらChatbotで自己診断をして、必要なら病院を受診するのです」
実際に英国では、生成AIを使って自己診断できるアプリのダウンロード数が、20万回にも上っているという。
また日本の過重労働対策は、複数月で80時間以内、単月で100時間以内という労働時間を基準としている。これは睡眠時間が1日6時間を下回ると脳疾患や心血管疾患のリスクが2倍になるという1980年代の疫学研究を根拠としている。
「睡眠の量や質が測れなかった時代、労働時間は効果的な代理メルクマールでした。しかしセンシング技術で毎日の睡眠時間を把握できるようになれば、月の労働時間を集計するよりはるかに早く、その日のうちに身体の異常を検知し悪化を防ぐ道も拓けます」
従業員の睡眠データを部門単位で解析し、職場の労働負荷を評価してマネジメントに活用するなど、個人だけでなく組織的なアプローチにも役立つという。
「誰が警鐘を鳴らそうと技術革新は止まらず、新たなツールはどんどん世の中に出てきます。こうした状況で重要なのは、目指すべき産業保健の未来像を設定し、その実現のためにはいつ、どのような環境整備が必要か、バックキャスティング(逆算)で考えることです」
重要性増す産業保健職 健康管理責任は企業から個人へ
日本では、ヘルスケア関連のデジタルツールの7割が、企業や健保組合が労働者へ提供するBtoBtoC型で普及している。榎原氏はこのことも「ツールが将来、どのように普及するかを考える上で、大事なポイントの一つです」と話す。
ほぼ個人ベースでツールを利用する諸外国と違って、日本ではツールと労働者の間を、産業保健スタッフが取り持つ形になっている。これによって、ツールに何らかのトラブルが生じた時、産業保健スタッフを介してユーザーに適切な対処が届きやすいというメリットもある。
「産業保健スタッフは、従業員に適切にツールを届けて有効に使ってもらう役割を果たすことになり、これから重要性が高まるのではないでしょうか」
一方で、テレワークなどが普及して「核労働化」が進み、同時に個人がメンタルヘルスを含めた自分の健康情報を把握できるようにもなった。こうした中では、「従業員の健康管理責任を企業に課すという従来の在り方から、個人が健康管理をマネジメントし、企業がそれを支援する枠組みに変えることを検討する必要もあります」とも榎原氏は指摘する。
産業保健が集団ではなく個人ベースに変わることで、企業規模が大きいほど産業保健にアクセスしやすく、中小零細企業には届きづらいという課題も解消に向かうことが期待できる。
「デジタルツールの導入を前提に、企業と個人が健康管理に対してそれぞれどのような立ち位置で臨むべきかを規定し、それに基づいて産業保健職の役割を含む産業保健制度全体も設計し直す必要があるでしょう」
執筆:有馬知子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

