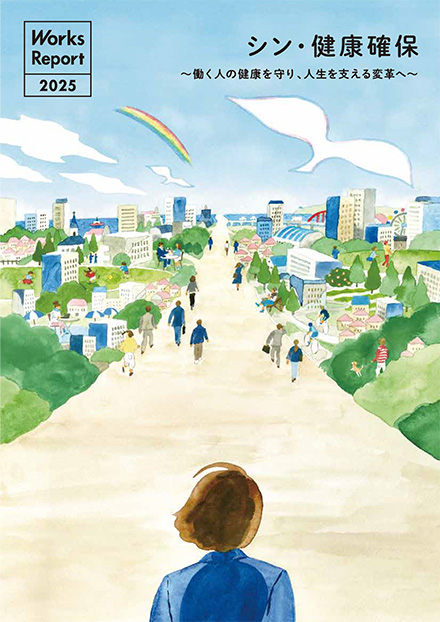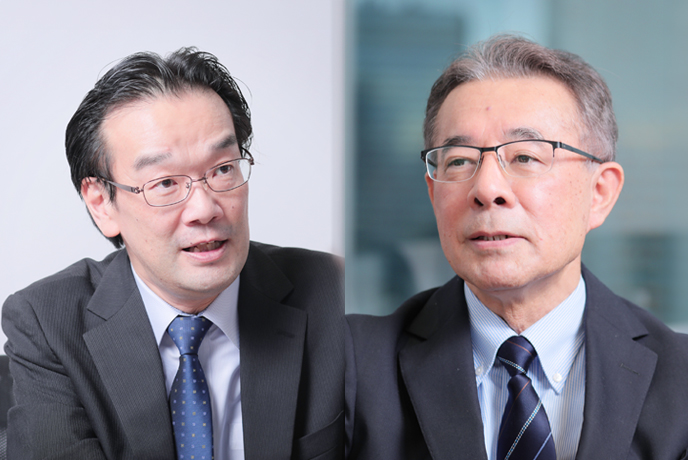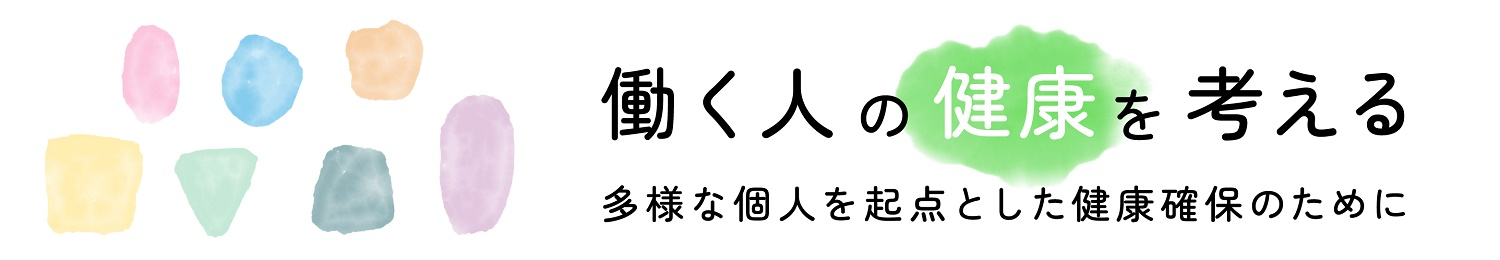
【座談会】働く人の健康の未来――シン・健康研究会報告から見えてくるもの(前編)
リクルートワークス研究所は、社会が急激に変化する中、働く人の健康確保はどうあるべきかというテーマで報告書を取りまとめた。これを受けて学習院大学名誉教授の今野浩一郎氏、組織の心理的安全性構築を支援するコンサルティング会社、株式会社ZENTech取締役の武田雅子氏、健康経営に力を入れる測定機器メーカー、株式会社ミツトヨ上席執行役員の中里典夫氏と、リクルートワークス研究所客員研究員の松原哲也が、報告書の意義や今後求められる取り組みなどについて話し合った。 【出席者】
【出席者】
学習院大学名誉教授 今野浩一郎氏(写真左上)
株式会社ZENTech取締役 武田雅子氏(写真右上)
株式会社ミツトヨ上席執行役員 中里典夫氏(写真左下)
リクルートワークス研究所客員研究員 松原哲也(写真右下)
個人起点で仕組みを作り直す 健康は身体と心の領域から、やりがいなどの社会的領域へ拡張
松原:当研究所は働き方の多様化や労働市場の流動化、さらに生成AIをはじめとするデジタルヘルステクノロジーの進化などに伴い、働く人の健康確保はどのように変わるべきかを考える研究会を設けて議論し、報告書をまとめました。その中で、働き手が自ら健康を守る意識を持つことこそ最も重要だ、というメッセージを発信しています。まずは報告書に対するご感想やご意見を、お聞かせいただければと思います。
今野:まず「健康とは何か」という概念について、身体と心の領域だけでなく、やりがいなど社会的な領域へと拡張している点が印象的でした。なぜ健康が必要なのか、という問いに対しても、個人の望む働き方やキャリアの実現に不可欠であり、企業にとっても成長につながるからだ、と明確に説明しています。こうして「What」「Why」の問いに答えた上で、ならばどのように健康を守るかという「How」について、個人を出発点に仕組みを作り直し、企業や産業保健の専門家は個人を支援する発想へ転換すべきだと主張している点が、大きなポイントだと思います。企業経営をレベルアップするには健康管理の在り方も変え、従業員の健康に対する意識のレベルを引き上げなければいけない、というロジックとも捉えられます。
武田:個人と企業と産業保健スタッフの3者が、対等な関係を築く時代が始まることを感じさせる内容でした。つまり企業の担当部署が、従業員の健康管理を丸抱えにするという「お母さん人事」から脱却し、働き手がスキルや知識と同様、健康も自分でマネージするようになる。そして企業は、従業員が惜しみなく手持ちのリソースを注げるよう、環境を整える役に回るというメッセージだと受け取っています。今野先生のご指摘の通り、ある程度セルフマネジメントができる人に管理のレベルを合わせるという、高位平準化に近い面もあるでしょう。
また、働き手の圧倒的多数が、健康に働き続けるため職場の人間関係、つまりメンタルヘルスが最も重要だと考えていることに衝撃を受けました。こうした従業員のニーズに応えられる産業医、保健師は不足していますし、メンタルケアに長けた産業保健職の育成が大きな課題だと感じました。
中里:当社は海外売上比率が80%を占めますが、海外顧客は取引先、ステークホルダーのサステナビリティ、人権尊重を重要視しており、その延長線上で従業員の健康や安心・安全も確保しなければ事業が成り立ちません。企業が従業員の健康を意識して経営に当たるべきだという報告書の内容は、まさにその通りだと思います。
ただ従業員に、自ら健康を管理する意識を持ってもらうことは容易ではなく、中には「構わないでほしい」という人も存在します。実態としては人事や総務の担当者が受診を説得するなど、後押ししながら少しずつ意識を変える必要もあると思います。例えば職場で禁煙しても、反動で帰宅後に大量に喫煙していたら意味がないですし、何をすれば健康を守れるのか、日々自問自答しています。
受け身の働き手をどう変える? アプローチに「奇策」なし
松原:今お話があったように、従業員の大多数は健康確保に対して受け身で、流れのまま健康診断を受けているだけ、という印象も受けます。一方、企業も働く人の健康確保に責任を持つという中で、働き手に意識変革を促す必要があります。この際、企業は個人に対して、どのようにアプローチするのが効果的だと考えますか。
中里:若者は総じて健康についてあまり気にしませんが、40代半ばを過ぎて慢性的な体の不調が出てきた頃から、健康を意識し始める人が多いのではないでしょうか。親など近しい人が亡くなる場面が増え、「命」を意識する感覚が芽生えるのも一因でしょう。
このため、ミドル以上の層への働き掛けが重要だと考えています。とはいえやり方に奇策はなく、ウォーキングイベントや節煙キャンペーンのような意識啓発の機会を増やしつつ、不調を抱える人は個別に専門家につなぐことに尽きます。また年齢のリスクばかりを強調すると、本人たちが「自分はもう年だ」 などと意気消沈しかねず、雇用を長期化していく中でモチベーションの維持にも、併せて取り組む必要があります。
武田:私も30代後半以降の社員を主なターゲットに、人事や産業保健職が必要な情報を伝えるのが効果的だと考えています。健康診断で要受診になった人は、膝詰めで受診を促すといった地味な取り組みも、しつこく続けなければいけません。社内の好事例を横展開することや、イベントなどを開いたら必ず振り返りを行い、PDCAを回して産業保健スタッフの育成に結び付けることも重要です。さらに他社や健康保険組合とうまく連携し、年間を通じてコンスタントに情報を出し続けることができれば望ましいと思います。また、中里さんからご指摘のあったシニアについても、役割と居場所とミッションを提供し、奮起を促す必要があるでしょう。
全ての働き手が健康に向け行動 企業は後方支援の発想へ転換
松原:今野先生は人事マネジメントがご専門ですが、個人に、自分の健康を自分で守るという意識・責任を持たせるという発想そのものについては、どうお考えでしょうか。
今野:多くの人が「健康は会社が担保する」ものだと思っていますが、個人が企業に「労働」というサービスを提供する以上、サービスの「質」を決める健康は自分で担保しなければいけないという視点が必要です。またキャリア同様に健康も自立を目指すなら、能力やスキルと同じように健康も「見える化」し、それをベースに何が足りないか、どう行動すべきかを考えることになるでしょう。
お話を聞いていると、企業は要受診者など健康状態が一定の「レンジ」を外れた人には介入するが、レンジの中に収まっている人には、特に行動を求めないようにも受け取れます。企業側がレンジの中か外かという基準で、行動すべき働き手を規定するなら、それは「個人起点」とは言えなくなってしまいます。「個人が希望する働き方やキャリアを実現し、企業も成長する」という健康確保の目的を達成するためにも、全ての働き手が自ら行動し、企業が行動を後方支援するという思考回路が必要だと思います。
中里:確かに多くの企業は、健康に関して求めるレンジの中にいる人はひとまず「良し」として、スキルや経験など別の足りない部分を伸ばしてもらおうとします。ただ年齢と共にレンジをはみ出すリスクは高くなるので、はみ出さない時間を延ばしましょうという働き掛けはしています。
松原:研究会に際して行ったアンケートで、働く人に心身の健康のため何を重視するか聞いたところ、「職場の人間関係」が最も多く全体の4割に上りました。報告書でも、会社には同僚などとの日常的な会話と、組織と従業員とのやり取りという2つのコミュニケーションが存在し、そのいずれもが健康確保において重要だとしています。コミュニケーションが心身の健康を左右すると感じているということは、裏を返せば今はコミュニケーションができていないことの表れとも考えられます。現場にいる中里さん、武田さんはどのように見ていますか。
中里:当社の意識調査を見ると、従業員は半径3メートル以内といった職場内の近しいコミュニケーションについては、問題を感じていないことがうかがえます。しかし業務の問い合わせのような組織間レベルのコミュニケーションに対する従業員の評価は、低下してしまう。個人レベルのやり取りには満足していても、その範囲を超えたやり取りが生じると、やりづらさを感じることもあるようです。
武田:半径3メートルのコミュニケーションが円滑なら、本人は問題を感じないと思います。しかし人事から見ると、コミュニケーションは常に不足しています。在宅勤務の普及などで働く場所が多様化した上、省人化が進んで1人で管理している工場もあります。さらに若手の中には、デジタル上のやり取りで十分だと考え職場でほとんど会話しない人もいます。こうした中で、コミュニケーションが健康、特にメンタルヘルスを左右するリスクは大いにあり、人事としてきちんと目配りしなければいけないと考えています。
■今野浩一郎氏 学習院大学名誉教授
1973年東京工業大学大学院理工学研究科(経営工学専攻)修士修了。神奈川大学、東京学芸大学を経て学習院大学教授。現在は学習院大学名誉教授、学習院さくらアカデミー長。著書には『マネジメントテキスト―人事管理入門』(日本経済新聞出版)『正社員消滅時代の人事改革』(日本経済新聞出版)、『高齢社員の人事管理』(中央経済社)、『同一労働同一賃金を活かす人事管理』(日本経済新聞出版)等がある。
■武田雅子氏 株式会社ZENTech 取締役
クレディセゾン、カルビー、メンバーズと業種の異なる上場企業で人事担当取締役、CHROなど人事の責任者を務めながら、組織風土改革やリーダー育成をはじめ、経営と現場をつなぐ戦略人事を各社にて展開。現在は組織の心理的安全性をベースに組織開発を行うZENTechでの活動をメインに、さまざまな企業の人事部門のサポートやCHROはじめ人事メンバーの育成などを行っている。株式会社コロプラ、株式会社SmartHR、静岡鉄道株式会社の社外取締役。
■中里典夫氏 株式会社ミツトヨ 上席執行役員
1989年に複写機メーカーに入社。営業、システムエンジニアを経て人事を担当。2020年に株式会社ミツトヨに入社し、執行役員兼人事部長、2025年1月に上席執行役員兼総務部担当兼人事部長に着任。
執筆:有馬知子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ