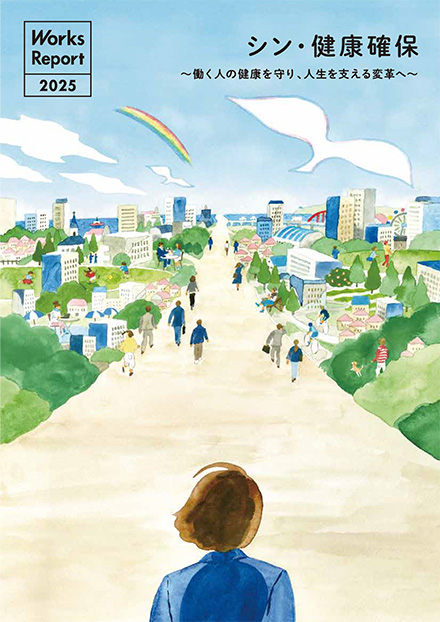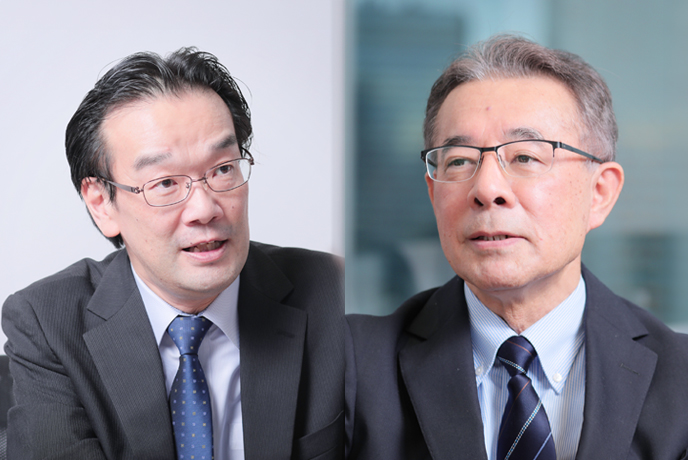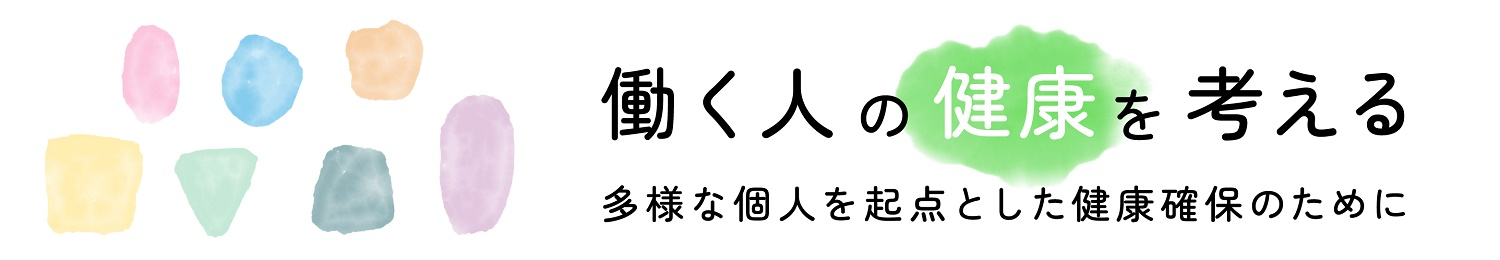
【座談会】働く人の健康の未来――シン・健康研究会報告から見えてくるもの(後編)
新しい時代における働き手の健康確保の在り方について、リクルートワークス研究所の報告書を基に話し合う座談会の後編。4名の出席者が企業に課される健康診断や安全配慮義務の在り方、今後の健康管理に当たって働き手や企業、専門職に求められる姿勢などをテーマに議論した。 【出席者】
【出席者】
学習院大学名誉教授 今野浩一郎氏(写真左上)
株式会社ZENTech取締役 武田雅子氏(写真右下)
株式会社ミツトヨ上席執行役員 中里典夫氏(写真右上)
リクルートワークス研究所客員研究員 松原哲也(写真左下)
業務上のけがからメンタルヘルスまで 安全配慮、企業に重い負担
松原:日本では法律上、健診などで得られた健康情報を事業主が把握する建付けになっており、事業主に幅広く安全配慮を求めるような裁判例もあります。従業員を雇用する以上、健康管理に一定の責任が生じるのは当然ですが、働く人を取り巻く環境の生々流転のスピードが上がっている現状においては、事業主にとって重い負担となっているとも感じられます。研究会では、健康診断だけに頼る形では、メンタル疾患の増加など時代の変化に対応できないのではないかとの指摘もありました。会社と個人の責任の在り方について、どのように考えていますか。
武田:健診は今も、がんなどの早期発見や病気予防に一定の役割を果たしています。ただ健診項目などが時代に追いついていないのは事実で、メンタルヘルスの部分だけでなく社員の高齢化といった変化も踏まえ、進化させるべきだと思います。
また企業における産業保健の領域は、業務上のけがなど明確に企業が責任を負うべき部分と、人材に活躍してもらうためにプラスアルファで行う部分に分かれていると考えられます。しかし今は両者の境界があいまいで、プラスアルファ部分についても法定事項の延長のように扱われていることも、問題だと考えます。安全配慮義務がこうした在り方のままでは、確かに企業負担が大きすぎるので、今後見直しの議論を進める必要もあるでしょう。
中里:健診に関しては、データを把握したら安全配慮義務がついてくる、ならばそのデータは取らない、という方向に企業が向かうのは望ましくないのではないかと思います。もう少し広い意味で、健康という財産を増やす方向で議論し、何が真に必要な情報となるのか考えることが、企業と個人双方にプラスの影響をもたらすのではないでしょうか。
今野:中里さんのご指摘の通り、何のために健康に関するデータを取るか、という構えは大事です。あくまで従業員に元気で活躍してもらうために行うべきであって、例えばメンタルを損ねた部下を職場から排除することを目的に健康状態を把握しようとしたら、社員のエンゲージメントは低下してしまう。人に企業の「財産」であり続けてもらうために健康を管理するのだ、という前向きな姿勢で臨むべきでしょう。
中小へノウハウ伝える仕組みが必要 地域資源と連携を
松原:研究会では大企業と中小企業で、働き手の受けられるサポートに格差があることも課題として挙げられました。特にメンタルヘルスに関しては、国が一律に措置義務を課す形になっていますが、管理職のサポートなどへは全く手が回っていない中小企業も多いのではないでしょうか。規模間格差を解消するには、職域だけでの取り組みでは限界があり、拠点病院や専門職など、地域の医療資源との連携も求められてくるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
中里:メンタル不調に陥る従業員が年間1人、2人程度なら、組織マネジメント内で上司が対応できるかもしれません。私自身も管理職として、部下のメンタルを管理するのは非常に難しい仕事だと実感しています。産業医の意見により、メンタル不調の原因や背景を理解することはできます。しかし重要なのは、その上で会社や職場でどのように対応すればよいかです。職場での対応のケースをまとめて、事例として提供されるような仕組みがあれば、ノウハウも蓄積でき有用ではないかと思うのです。
武田:地域包括支援の産業医版のようなイメージで、経営者が駆け込み寺のように相談できる地域共通プラットフォームがあればいいと思います。ただ産業医は連携すべき相手ではありますが、最終的な判断を下すのはあくまで企業です。メンタルに関する相談に応じられる力量を持った産業医は少ないですし、保健師もレベルにばらつきがあり、両者の育成も課題です。
職場のメンタル疾患をゼロにするのは、実質的には不可能です。ですから企業は、休職しても戻れるという事例を従業員に示すことで、早期に発見・治療し復帰するというサイクルを作ることを重視すべきです。従業員も経験談を知っていれば、自分が不調を感じた時に相談しやすいでしょう。また中里さんがおっしゃるように、メンタルの管理は職場の管理職の関与も不可欠ですが、面倒見のいい管理職ほど、部下の不調を抱え込みがちです。手に負えない時は産業保健のスタッフらへリファーするといったノウハウを、管理職に伝えることも重要です。
活用進むデジタル技術 健康情報の取り扱いに課題も
松原:デジタルヘルステクノロジーについてもお伺いしたいと思います。近年、オンライン相談・診療と医師・看護師らリアルの人材を組み合わせて働く人の健康確保をサポートするサービスが現れるなど、デジタル技術が健康確保の在り方を少しずつ変えようとする動きがあります。一方で、健診などの重要情報がデジタル化されることで、流出などのリスクも生じます。デジタルヘルステクノロジーの有用性と危険性について、どのように考えますか。
中里:多くの企業はまだ、テクノロジーを活用する手前の、デジタル化を進めている段階だと思います。今後も、どこまでデジタルで対応するかというレベルは企業によって違ってくるでしょう。当社としては、デジタルヘルステクノロジーによるダイレクトな健康改善への取り組みの前に、健康管理業務の効率や生産性を高めるためにデジタル技術を使いたいと考えています。
武田:テクノロジーについては、有用性7、危険性3くらいだと考えています。有用性の方が圧倒的に大きいと思いますが、例えばがんの当事者で、健診で病気だと分かると昇進に影響するのではないか、という不安を抱く人はいますし、影響を恐れて既往歴を伏せて入社する人もいます。データの取り扱いについては、難しい部分がかなり残されているとは思います。
「どうやって生きていくのかを考える」ことが、健康確保の意識も促す
松原:デジタル化の進展などで、これまで想像もしなかったような変化が起こり得る大きな「転換点」の一つに立っている、という感覚は多くの人が持っていると思います。これに伴い、AIに仕事を奪われる不安が高まったり、経済的・心理的な格差が拡大したりする懸念もあります。働き手が心身ともに健康で働き続けられるよう、社会と企業、個人が次の一歩を踏み出すために、どのようなメッセージを伝えたいとお考えでしょうか。
今野:働く人に対するメッセージは「自分がどうやって生きていくか、食べていくか、自分で考えましょう」という言葉に尽きます。そうすれば自ずと、健康をどう確保するかも考えるようになるはずですし、企業や専門職の役割も、働き手に自ら考えるよう促し、彼ら彼女らが行動を起こした時に後方で支援することへと変わってくるでしょう。
かつてのように年功序列で、仕事が半ば自動的に降ってくる時代は終わり、業務とそれに必要なスキルも多様化しています。健康に限らずキャリアやスキルなど全てにおいて、自分の資本をどう作りどう守るのか、自分で考えなければいけない時代が来ているのです。
武田:定年延長やコロナ禍で、働く人の健康に対する意識は一段、バージョンアップしたと思います。しかし多くの人は喉元を過ぎると忘れてしまうので、繰り返しセルフマネジメントの重要性を訴え、意識を定着させていくことが重要です。
人事の究極の役割は、働く人の市場価値を高めることであり、その土台の一つが健康です。時代と共にスキルは入れ替わっていきますがし年齢を重ねると健康も当然リスクをはらむようになっていきます。企業も、教育を通じて少しでも健康を長く維持できるよう社員へ働き掛けていく。それによって結果的に、活躍し続ける期間が延びたり、いいコンディションでパフォーマンスを出せる人材の輩出につながったりして、働く人にも企業にも大きなメリットをもたらすと思います。
中里:製造現場では自動化、省力化が進む中、労働者の役割も従来の手を動かす作業から、製造ラインの効率化や進化といった、エンジニア的な内容へと変わりつつあります。従業員に対しては、環境変化に合わせた個人の資産とスキルが向上できる場を提供する必要があり、その資産の中でも重要な一つに健康があるのだと考えています。
地方にある工場の従業員の多くは、地元で生まれ育った人です。少子高齢化による地方の人口問題がある中、地元の人々の健康と雇用を守り、地域経済を支えることは今後ますます企業に求められるでしょう。人材をはじめとした地域のリソースを、十分に活かせる企業が成長するのだと考えています。
■今野浩一郎氏 学習院大学名誉教授
1973年東京工業大学大学院理工学研究科(経営工学専攻)修士修了。神奈川大学、東京学芸大学を経て学習院大学教授。現在は学習院大学名誉教授、学習院さくらアカデミー長。著書には『マネジメントテキスト―人事管理入門』(日本経済新聞出版)『正社員消滅時代の人事改革』(日本経済新聞出版)、『高齢社員の人事管理』(中央経済社)、『同一労働同一賃金を活かす人事管理』(日本経済新聞出版)等がある。
■武田雅子氏 株式会社ZENTech 取締役
クレディセゾン、カルビー、メンバーズと業種の異なる上場企業で人事担当取締役、CHROなど人事の責任者を務めながら、組織風土改革やリーダー育成をはじめ、経営と現場をつなぐ戦略人事を各社にて展開。現在は組織の心理的安全性をベースに組織開発を行うZENTechでの活動をメインに、さまざまな企業の人事部門のサポートやCHROはじめ人事メンバーの育成などを行っている。株式会社コロプラ、株式会社SmartHR、静岡鉄道株式会社の社外取締役。
■中里典夫氏 株式会社ミツトヨ 上席執行役員
1989年に複写機メーカーに入社。営業、システムエンジニアを経て人事を担当。2020年に株式会社ミツトヨに入社し、執行役員兼人事部長、2025年1月に上席執行役員兼総務部担当兼人事部長に着任。
執筆:有馬知子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ