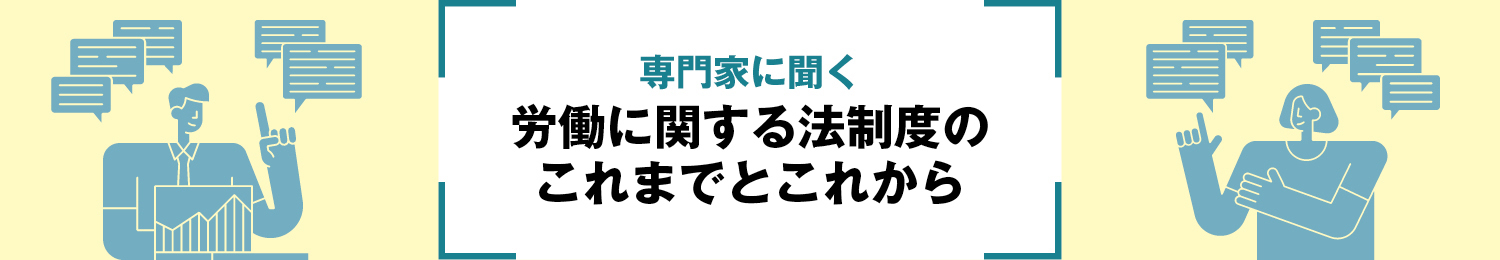
労働市場の需給逼迫時代に求められる法制度とは
過去、非正規労働者に関しては労働契約法の無期転換ルール(※1)が設けられて雇用の安定化が図られ、高齢者については高齢者雇用安定法の改正で労働参入が加速した。今後は労働需給のさらなる逼迫が予想される中、法制度はどのように変わるべきだろうか。東京大学副学長で社会科学研究所教授の玄田有史氏(労働経済学)に聞いた。
非正規の待遇改善は時代を超えた課題 無期雇用へのこだわりは薄れる
―非正規労働は、労働市場の中でどのように位置づけられてきたのでしょうか。
非正規労働は高度成長期の「日雇い」から2010年代の「非正規」、最近の「エッセンシャルワーカー」などと呼び方は変わりましたが、企業環境の先行きが不透明な中、雇用調整の余地を残すための「緩衝地帯」として常に存在してきました。非正規労働者の割合は過去10年ほど30%台後半で推移していますが、雇用が不安定で賃金も低く、将来の見通しも持てないといった深刻な状況に陥っている層は、このうち概ね16%程度ではないか、と分析しています。将来的に非正規の仕事は機械にシフトする、という幻想も常にありますが、ロボットやAIが進化しても、非正規労働者が担う周辺的なワークを完全に代替するには至っていません。
―非正規労働者を取り巻く課題を政策や立法で解決するに当たって、何が障壁となっているのでしょうか。
非正規労働者にまつわる問題は、いわゆる正規労働とはリスクの種類や程度が大きく異なるため同じ政策ではカバーしきれず、別建ての政策や法律が必要です。さらに「正規労働」と「非正規労働」の明確な定義が存在しないことが、法整備や政策立案の難しさにつながっています。臨時雇いやパートタイマーなどを「非正規」と規定しても、必ずこぼれ落ちる人が出てしまいますし、働き方の多様化に伴い、定義はますます難しくなっています。
また非正規の中でもとりわけ待遇改善が必要なのは、正規の仕事に就けず非正規を選ばざるを得なかった「不本意非正規」の人たちです。しかし「不本意」という概念もあいまいで、すべての選択は労働者本人が自分で下した結果というロジックが通れば、不本意非正規は存在すらしなくなってしまいます。
―非正規労働は1990年代後半以降、労働者派遣法などの改正によって規制が緩和されましたが、その後、雇用の不安定さが社会問題となり再び規制強化に転じました。これからの有期労働法制はどうあるべきだとお考えでしょうか。
2013年に施行された労働契約法の「無期転換ルール」は、不況とデフレが長期化して労働需給も緩み、企業が無期雇用の採用に慎重な時期に導入されました。雇い止めなどが問題視されていたこともあってこのルールは社会的に支持され、無期雇用に転じた当事者の満足感や、仕事へのやりがいを高めることにもつながりました。
しかし現在は、労働者のキャリア観も大きく変化しています。特に若い世代にはより良い職場があれば移るという意識が強まり「無期」であることへのこだわりも薄れました。法律は時代にフィットした時に機能するので、需給が緩んでいる時期にフィットしたルールは、需給がタイトになればフィット感も変わります。
ただリーマン・ショックの時のように、今後も日本国内や米中、インドなどの経済危機や金融危機で労働需給が突然大きく緩むリスクは常にあります。法律は恒久的な意義があって成り立っているので、その時の需給に応じて作ったりなくしたりすべきではないでしょう。
高齢法改正、70代の就業機会確保の義務化を焦点に
―現在は需給の逼迫に伴って若年非正規の割合は低下し、時給ベースの賃金も上昇しています。こうした時期に求められる政策はあるのでしょうか。
労働者にとって望ましいのは、有効求人倍率1.08~1.1倍程度の緩やかな人手不足が長く続く状態ではないでしょうか。このくらいの需給バランスだと、企業側は人を集めるため、待遇改善に着手せざるを得なくなります。これに照らすと2024年8月時点の有効求人倍率は1.23倍で、やや強めの人手不足と言えます。
ただ人手不足は需給バランスによってだけでなく、労働移動が円滑に進まないために起きることもあります。例えば高度成長期の末期も人手不足でしたが、当時は若者の数も多く、政府は出稼ぎや集団就職などを制度的にサポートすることで、対応が可能でした。しかし今の人手不足は、労働者それぞれが健康や育児、介護など多様で複雑な問題を抱えて身動きがとりづらくなったために起きています。こうした「重い人手不足」は、単に賃金を上げたり法制度を整えたりするだけでは解決しにくく、法律よりも行政レベルで、個人が抱える問題に対応する手法が適しているかもしれません。
―非正規の問題以外に、日本の労働市場にはどのような課題があるとお考えですか。
上位管理職を除く中間管理職については、労働組合から離れてしまうのに管理職として必要なサポートも不十分で、ハラスメントに関しても加害・被害両方のリスクを抱えています。社会的な処遇改善を進めなければ女性の管理職比率も高まりませんし、男女ともに管理職になろうというモチベーションも高まらず、リーダーが育たなくなってしまいます。中~下位の管理職を組織化するなど、企業が労働組合を上手に使うことも、一つの解決策として考えるべきだと思います。
また、高齢化に伴い、高齢者雇用安定法(高齢法)を再改正して、70歳までの就業機会確保を「努力義務」からより拘束力の強い「義務」に変えることも、今後の大きな課題です。
高齢法で65歳までの雇用確保が義務化されたのは、不況真っただ中の2012年でした。同じ時期に公的年金の支給開始年齢が引き上げられたこともあり、雇用確保の必要性については社会的な共通認識もありました。しかし若者の雇用にしわ寄せが及ぶという反対意見も根強く、2025年度までという長い経過措置も設けられました。あの時高齢法が改正されていなければ高齢者の労働参入は今ほど進まず、人手不足はもっと深刻化していたはずで、政府に先見の明があったと思います。
70歳までは同じ職場で働き続けるようにコンセンサスを
―高齢法の再改正に当たっては、何がポイントになりますか。
現在は人手不足で高齢者が必要とされており、2012年に比べれば就業機会の確保を企業に求めやすくなっていますが、それでも調査研究や議論には一定の時間がかかるでしょうし、経過措置なども決める必要があります。重要なのは、現在50歳前後の「就職氷河期世代」が65歳に達する時期に間に合うよう、再改正に必要なプロセスを進めることです。
氷河期世代は賃金水準が低く、保有資産も少ない。スキルを習得した経験も乏しいため、中高年期にリスキリングして定年後に別の仕事に転じるのも限界があります。ですから、どんなに遅くともこの世代が65歳に達する2040年ごろまでには、非正規やフリーランスなどへ雇用形態は変わっても、少なくとも70歳までは同じ職場で働ける環境を整える必要があると思います。そのためには2020年代後半には法改正の議論を始め、2030年代には「働くことを望む高齢者は、70歳まで働くのが当たり前」という社会的なコンセンサスを作っておかなければなりません。
―希望する人は70歳まで働ける社会として、どのような在り方をイメージしていますか。
現役で働く70代には、実は自営業者が多いのです。高度成長期に上京して、勤め先の社長の「のれん分け」のような形で独立し、子どもを大学進学させるため必死で働いたような人が、今も頑張っています。
パート女性の中にも、70代まで生き生きと働いている人がたくさんいます。彼女たちの多くは子育てが一段落した40代ごろから働き始めて店長、副店長などの基幹業務を任されるようになり、今も若い社員から頼られています。70代も現役で働く人たちの姿が、新しいジャパニーズドリームになればいいと思います。
現在、70歳以上の労働人口は536万人に上りますが、労働力としてはあまり顧みられることがなかったため従来は研究されてきませんでした。しかしこの世代の就業は今後、人手不足や社会保障を救う救世主となり得ますし、いずれ80代が重視される時代も来るでしょう。
氷河期世代の人が70代に入れば、労働市場や社会環境はさらに別の姿に変わります。私たちは時代に合わせて必要な研究を進め、法制度を整えていく必要があると思います。
(※1)労働者が同じ雇用主と有期雇用契約の更新を繰り返し、通算の就労期間が5年を超えた時、労働者本人の申し込みによって無期雇用に転換されるルール。

玄田有史氏


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ