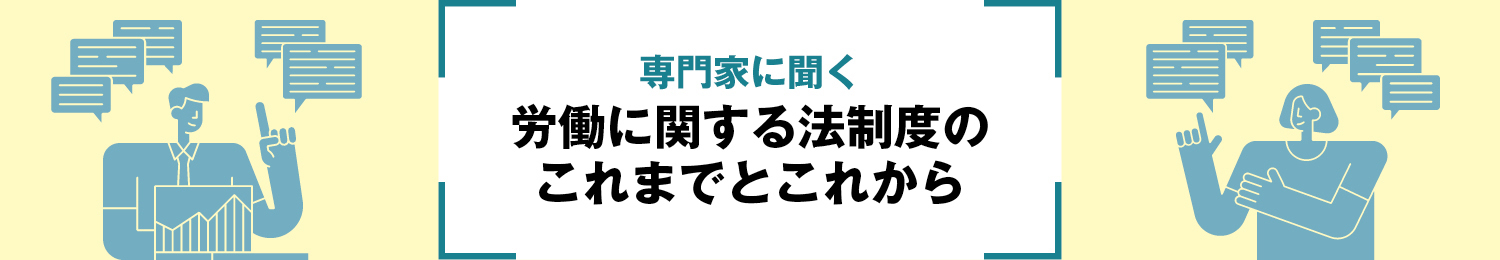
労働移動を前提に法制度をデザイン 解雇規制は既存のルールで対応可能
これまでの日本の法制度は、「定年まで1社で働く」ことを前提に枠組みが構築されてきた。成蹊大学教授の原 昌登氏(労働法)は、人手不足への対応には雇用の流動化が不可欠であり、労働移動を前提とした法制度をデザインすることが重要だと訴える。原氏に新しい時代の法制度に対する考え方や、流動化の議論で必ず話題となる解雇規制のあり方について聞いた。
流動化で出会いのチャンスを広げる 濫用的な解雇は引き続き規制を
―近年の労働市場の変化とそれに対する法的な対応について、どのような点に注目していますか。
近年、雇用の流動化を進めて、企業と労働者双方の選択肢を広げていこうという動きが見られます。労働者と企業の出会いのチャンスが増えれば、アンマッチが解消され人手不足が解消されることが期待されます。
労働者が、より高い賃金や労働環境を求めて移動しやすくなれば、企業も人材の獲得や定着のため、賃上げや職場改善に取り組まざるを得ず、労働環境の改善が見込まれます。企業が内部留保を賃金に回せば、優秀な人材が集まり企業成長にもつながります。もちろん一つの職場で長く働くことが否定されるわけではありませんが、これからは労働者が移動することが前提になるのだとマインドを転換し、それに沿った法制度を整備することが求められます。
近年は20~30代を中心に、転職を通じたキャリアアップの動きも広がり、もともと転職の多かった中小企業に加えて、大企業も中途採用を拡大しています。実態はすでに変化しているのに、日本型雇用の昭和的なイメージが先行し、硬直性が強調されすぎている面もあると思います。
―雇用の流動性を高めるためには、解雇規制の緩和が必要だという主張もあります。
流動化を目的に、解雇規制の緩和を進めることには大きな疑問を感じます。たとえ流動化が進んでも、転職先で容易に解雇されるリスクがあれば、労働者側の移動のインセンティブは低下し、人手不足の問題も解決しません。
また世間には、現在の規制では解雇が全くできないかのような誤解もありますが、法的な要件を満たせば、解雇も認められることになります。企業側も労働者側も、解雇ルールを正確に理解することが重要です。
整理解雇も、ルールである「4要件」をすべて満たせば容認されます。4要件をクリアするための企業側の負担は小さくはありませんが、人を雇用する以上、必要な責任はきちんと果たすべきです。一般的な解雇における解雇権濫用法理(労働契約法16条)にも同じことが言え、合理的でなく、社会通念上相当とも認められない「濫用的な解雇」についての規制はあるべきだと考えています。
一方で、労働者や労働組合の側も、解雇にはさまざまなケースがあり、必ずしも絶対的に否定されるものではないということを理解する必要があります。議論の際も「絶対ダメ」という条件反射的な反応をするのではなく、濫用的な解雇は許さないという前提を守りつつ、制度の内容を理解して対応を検討する必要があるでしょう。
金銭解決、まずは既存の枠組みで対応 求人メディアの環境整備も
―解雇の金銭解決については、どのように考えますか。
解雇の金銭解決といった時、「お金を払えば解雇できる」というイメージが強いですが、実際は解雇に伴う救済の選択肢の一つであることを、まず理解すべきです。
不当解雇に遭った時、現在の法制度だと、労働者にできるのは解雇無効を主張して職場復帰を要求することです。解雇の金銭解決とは、不当解雇について、労働者が企業から金銭を受け取り、雇用関係は終了するという形での解決を「制度的に」可能にするものなのです。
ただし実際には、労働審判やあっせんなどのADR(裁判外紛争解決手続)を通じて、事実上の金銭解決は現在においてもかなり行われています。現場で行われていることを制度化するには、具体的な解決金の金額設定など、多くの壁があります。仮に無理やり金額を設定して制度を作っても、労使の理解は得られないでしょうし、金額が一人歩きして、労働審判など既存の枠組みでかえって柔軟性が失われるなど、マイナスの影響も出かねません。解雇の金銭解決についてはこうしたデメリットとメリットを勘案しながら、どういった制度設計があり得るのかを考えていく必要があります。
解雇の金銭解決に関して要件の明確化をするのであれば、まずは実際に行われている和解の内容などを分析し、解決金の水準も含めた実態を明らかにする必要があります。その上で、制度を作り、ガイドラインなどで水準を提示するといったプロセスが求められます。また、企業側からの金銭解決の申し立てを認めると、一方的な解雇を誘発しかねないので、あくまで労働者の救済手段の一つとして、労働者側だけが申し立てられる制度にすべきでしょう。
―流動化を進めるにあたっては、どのような政策が必要だと考えますか。
求人メディアや職業紹介事業者が、より良い求人情報を安全な形で提供できるよう、行政がルール整備をさらに進め、求職者が転職活動しやすい環境を整えることです。
ただ法律を改正して情報の開示範囲を拡大するというより、法律では最低限クリアすべきハードルを示す方が、実態になじむかもしれません。行政は、法で定められた必要事項がきちんと開示されているかどうかをチェックすると同時に、ガイドラインなどを通じて、法律のさらに上をいくような、求職者の判断に役立つ項目を提案することも考えられます。
また転職者は、若手で育成がまだ完了していない人と、即戦力として活躍できる人に大きく分けられます。ですから求人企業も求人内容を通じて、求める人材が即戦力なのか、育成前提の人材なのかを明確に伝えてほしいと考えています。行政は求職者のニーズを広く求人企業に発信していくほか、採用力の弱い中小企業が、中小ならではの強みを求人情報に反映できるよう、ひな形などを作ってサポートすることも求められます。
―流動化の障壁となっている制度や法律はありますか。
あくまで印象かもしれませんが、年金をはじめとする社会保障制度は、1社に長く務めることを前提に作られている部分が大きいと感じます。転職した場合、年金や健康保険が円滑に新しい職場に引き継がれるかというと、そうではない実態もあるようです。また、企業年金の一種である確定給付型年金のように、勤続年数が長いほど有利になる制度もあります。社会保障制度を、転職の足を引っ張らない仕組みへと変える必要があります。
退職金制度も勤続年数が長いほど金額が増えますし、税制上も優遇される仕組みで、移動をためらわせる原因になっているおそれがあります。企業年金も退職金制度の設計と関連が深いので、連動して考える必要があります。
同一労働同一賃金は「説明」がカギに 高齢者雇用との整合性も課題
―流動化に関するトピック以外で、注目している法制度はありますか。
人生100年時代を迎える中で、高齢者雇用と同一労働同一賃金の原則との整合性が問われるようになりました。定年退職後の再雇用であっても、賃金に現役社員と不合理な違いがあることは許されず、賃金水準を下げるなら、なぜ下がるのかについて説明できるようにする必要があります。40~50代の賃金を抑える代わりに定年後も大きくは賃金水準が下がらないようにして、なだらかな形で70代まで働ける方が、労働者側も働きがいを失わずに済む可能性もあります。いわゆる賃金カーブを、働き続けることを前提とした形に変えざるを得なくなるでしょう。
同一労働同一賃金の原則のもとで、賃金の違いが不合理かどうかを判断するには、「説明可能かどうか」が大きなポイントになります。賃金制度を構築する際も、従業員に説明し、対話しながら設計することで、納得性の高い仕組みを作ることが重要です。
―労働組合の組織率が低下する中で、労使の対話の難しさも増しています。労使コミュニケーションをどのように考えればいいでしょうか。
労働組合は労働組合法で手厚く保護されるなど、労働者側にとって非常に「使える」仕組みであることを、もっともっと周知していく必要があります。非正規労働者も、労働組合を組織すれば、企業側と待遇改善について交渉できますし、必要ならストライキを行うこともできます。まずは、今ある制度を活用していくことが重要です。その上で、将来的には、例えば従業員代表制の創設なども含め、協議や交渉など労使コミュニケーションの実現、推進を目指して議論していく必要があるでしょう。
―原先生のご専門である、ハラスメント対策についてはどのように評価しますか。
ハラスメントは被害者本人を傷つけ、時には死につながるおそれがあるだけでなく、職場環境を悪化させ離職を招くなど、多くの労働者に影響を及ぼします。ハラスメント対策は人事・労務部門だけでなく、経営全体に関わる問題だと捉えることが非常に重要です。
2020年からいわゆるパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行され、企業も着実に取り組みを進めています。顧客によるカスタマー・ハラスメントについても、2025年4月から東京都で防止条例が施行される予定で、政府としても法制化が検討されています。こうしたルール化は、被害者を守り加害者を処分するという機能だけでなく、ハラスメントは「アウト」だという意識づけにも重要な役割を果たしています。昔は上司が部下を怒鳴って何が悪いという人もいたかもしれませんが、今やパワハラ気質やセクハラ気質の人は業務でも評価されないというように、社会の意識も変わってきました。法律や条例が周知・啓発にもたらす意味は非常に大きいと思います。
聞き手:坂本貴志
執筆:有馬知子

原 昌登氏


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ