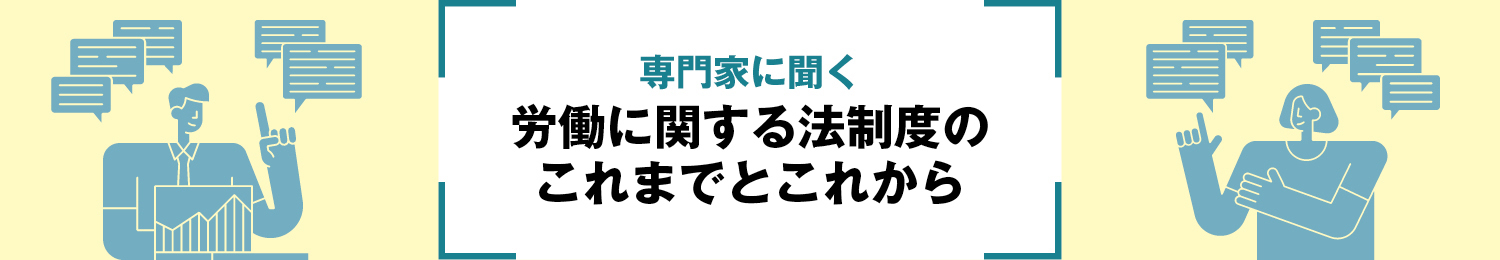
メンバーシップからジョブ型へ システムの修正は日本社会のあり方も変える
大手企業に、職務に基づいて従業員を管理する「ジョブ型」的な人事制度を導入する動きが広がり、政府も2024年8月、ジョブ型人事指針を発表した。勤務地や職務を限定しない「メンバーシップ型」からジョブ型への移行は今後、加速していくのだろうか。労働政策研究・研修機構(JILPT)所長の濱口桂一郎氏に聞いた。
社員の自律性を取り戻す 試行錯誤の中でジョブ型に注目
―日本企業に「ジョブ型」的な人事制度を導入する動きが広がっていることについて、どのようにお考えですか。
欧米では「デフォルト」であり硬直的な働き方ですらあるジョブ型が、日本で「新時代の働き方」として持ち上げられることには不思議さを感じます。また日本のジョブ型の多くは、入社後の扱いを職務給的にする内容で、採用段階から職務を限定する本来のジョブ型とは同列には語れない面もあります。
ただ日本の大企業が、メンバーシップ型で人材を採用し会社主導で動かしてきた結果、自律的に行動できない社員が増えてしまったという問題意識を持つようになったのは確かで、この問題に対処するために「ジョブ型」という言葉が注目されたのだと考えています。
またメンバーシップ型の賃金制度は、生計費がかさむ40~50代とそうでない時期との間で賃金配分にメリハリをつけ、職業人生を終えた時点でバランスがと取れていればいい、という考え方で構築されてきました。しかし次第に、若年層に応分な賃金がを分配されないというデメリットの方が強く意識されるようになり、また企業も、退職年齢が上がり続ける中で、高齢者の賃金水準をどうすべきかという課題に直面するようになりました。ジョブ型の導入には、生活保障を目的とした年功的な賃金制度を変える、という面も大きいと思います。
―ジョブ型の導入によって、シニア層の報酬制度の問題は解決に向かうのでしょうか。
現在の賃金制度では、定年前の社員の多くは職場への貢献よりも高い報酬を得ています。企業側にとって、再雇用の際に給与水準を下げるのは、不当に高い報酬水準を是正するという意味合いがあります。ただ、同じ仕事を続けさせて報酬だけ引き下げるのは、同一労働同一賃金の原則に反しますし、かといって全く別の仕事をさせると生産性が低下してしまう。結果的に、仕事内容は大きく変えず責任だけ外すことになります。一方で働き手は、定年前の報酬を「能力に見合う水準」だと考えているため、不当に報酬を下げられたと感じ、貢献への意欲が大きく低下する場合もあります。
また、ある程度年功的に昇格させる仕組みが残る企業も多く、40~50代社員の大半は、管理職に昇格します。役職定年と退職再雇用による処遇の引き下げは、「自分は勤め先で一定の役割を果たしている」という労働者のアイデンティティを揺るがしかねません。これが案外、ミドルシニアの問題の本質だという気もします。
ジョブ型の導入によって、シニアの報酬を適正性水準に設定できる企業も出てくるでしょう。ただ働き手のモチベーションを保ちながら処遇を引き下げるのは容易ではなく、成功のハードルはかなり高いとも感じます。
中間管理職の残業は野放し 残業代と労働時間、切り離して議論を
―改正労働基準法で、長時間労働の上限規制が設けられましたが、経済団体などからは適用除外(デロゲーション)の導入を求める声も上がっています。労働時間規制には、どのような課題が残されているでしょうか。
どの国の労働時間規制も、対象として一般労働者を念頭に置いており、管理的・専門的な仕事に就く人に対してはデロゲーションを設ける方向へ向かいます。しかし日本の労働時間規制における最大の問題は、一般労働者に限りなく近い中間管理職も、管理監督者と見なされて事実上、規制からデロゲート(除外)されてしまい、深夜の割増賃金を除けばほとんど何の規制もないことです。さらに一般労働者の残業に上限規制が入ったことで、中間管理職が部下の仕事まで背負って残業するという事態に陥っています。
一方で高度プロフェッショナル制度(高プロ)など、職務内容に着目したデロゲーションの導入には厳格な要件がを課され、導入後も企業に多くの責任が課されるためほとんど普及していないといういびつな状況もあります。少なくとも中間管理職については、高プロと同程度には規制の網を掛けるべきです。
ただ、管理職の労働時間規制がすべ全て外れることは、残業代が付かなくなることとイコールで捉えられているため、規制を掛けるのが非常に難しい。残業代と労働時間を切り離して議論する必要があります。
―働き方が柔軟化するのに伴い、深夜労働の割増賃金規定を見直し、労働者が自己裁量で働けるようにすべきではないかという議論もあります。
コロナ禍で多くの人がテレワークをするようになった時、法規制を厳格に適用しすぎると、仕事を中抜けするのに時間単位の年休取得が必要になるなど、働き手の使い勝手が悪くなることが明らかになりました。働く時間と場所を柔軟化するなら、自由な働き方を阻害しないよう規制を緩めることも検討する必要があります。
ただ一方で、規制があるからこそ無軌道な深夜労働が抑制され、仕事と家庭の両立が可能になってもいます。欧州は深夜労働に回数制限を設けるというEU指令のもと元、各国で具体的な回数を規定しています。深夜労働も含めた労働時間規制は、柔軟な働き方というメリットと健康被害などのリスクを、両にらみで制度設計しなければいけません。
ジョブ型が突き付ける「階級格差」の是非 社会のあり方にも関わる
―職務限定の採用や、本人同意を前提とした転勤の仕組みが導入され、企業の人事権がある程度制約されるようになりました。司法判断も含め、解雇に対する考え方も変わる可能性はあるでしょうか。
平時に転勤を拒否した労働者が、拠点閉鎖などの際に「配転によって雇用を維持しないのは不当だ」と主張するのは無理があり、人事権が制約されれば司法判断も変わるはずです。また職務に紐づいて人を採用するという、欧米本来のジョブ型が広まれば、該当する職務がなくなるなどした場合の解雇の障壁も、下がる可能性があります。
ただ欧米企業にはトップマネジメント、ミドルマネジメント、一般労働者という、歴然とした階級格差があり、転勤があるのは多くの場合、トップマネジメントだけです。一方、メンバーシップの最大の特徴は階級格差が存在しないことで、一般労働者にも理論上は、転勤の可能性が平等に存在します。このためたとえ実態として転勤がなくとも、企業は解雇回避義務を課されているのです。
解雇の議論を突き詰めると、階級格差を認めるのかという問題に帰結します。日本の一般労働者は、平等であるがゆえにマネジャー的な視点も持ちながら職場で臨機応変に対応し、それが「現場力」につながってきました。階級格差を認めると、社員がこうしたふるまいをしなくなり、現場力が失われる可能性があります。デジタル技術が進展する中、むしろ海外の企業が一般労働者にマネジャー的行動を求め始めるという、皮肉な現実すらあるのです。
―働き方のあるべき姿について、どのようなイメージを持っていますか。
昇進に職業人生の目標を置くあり方から、一人ひとりが多様なキャリアを描きその実現を目指すといった姿へ変わることになるでしょう。そのためには企業が一般労働者に、現場の「マイスター」など多様なキャリアのモデルを示すことが求められます。職務を軸にしたキャリアを示すことは、階級的なジョブ型の働き方が広がる中で、一般労働者のモチベーションを維持することにもつながります。職務にこだわる若い世代の志向とも合致すると思います。
また戦後の日本社会は、メンバーシップ型の企業が労働者の健康確保や生計維持といった、生活の相当部分を引き受けることで成り立ってきました。メンバーシップ型が修正されるなら、企業が引き受けてきたこれらの「ライフ」の一部は、働き手に返還されることになります。返されただけでは生活が成り立たないので、労働者の生活を支えられるよう、社会システムそのものも変わる必要があります。私たちは労働問題にとどまらず、日本社会をどうしていくかを考えていく必要があるのです。
聞き手:坂本貴志
執筆:有馬知子

濱口桂一郎氏


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ