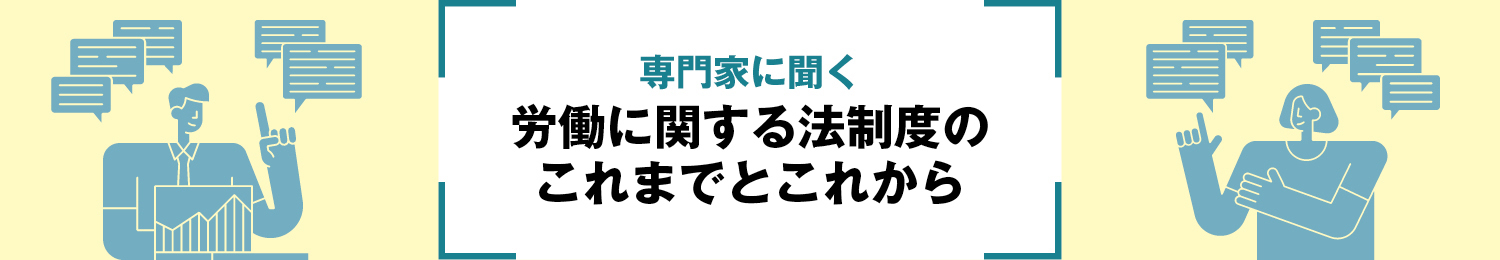
労働者概念を拡大し、フリーランスを保護 司法の果たすべき役割は大きい
欧州を中心に、プラットフォーム上で仕事を請け負うフリーランスの保護について争われることが多くなっている。日本では2024年11月、フリーランス保護を目的としたいわゆる「フリーランス新法」が施行された。雇用と自営の狭間にある働き手を守るため、今後どのような法律や政策が求められるだろうか。学習院大学法学部教授の橋本陽子氏(労働法)に聞いた。
フリーランスは労働者性の本質的テーマ
―なぜフリーランスという論点に注目されたのでしょうか。
私はこれまで労働者性についての研究を行ってきました。この労働者性を考える上で、フリーランスは本質的なテーマなのです。労働法という学問が確立して以来、世界中で労働法の対象となる人は誰なのかが長いあいだ議論されてきました。労働法上の法律(日本には単一の「労働法」はなく、労働基準法、労働契約法など数多くの法律から労働法が構成されています)は「労働者」に適用され、自営業者には適用されません。労働者と自営業者の区別の問題が労働者性または労働者概念と呼ばれています。フリーランス(自営業)とされていた人が、本当は労働者なのではないかということは、労働法が誕生してから常に問題となってきました。法律の適用とは、「適用」か「適用されない」かの二分法なのですが、現実の社会は法律の想定した境界線ではっきりと区別できるものではなく、境界線上にはどちらとも言えない場合(グレーゾーン)が常に存在するからです。グレーゾーンに線を引く作業が裁判であると思います。「(裁判で)白黒はっきりさせる」という表現がこのことを示しています。
私はずっと労働者性を研究してきたのですが、2024年11月にフリーランス新法が施行されたのを機に、改めてこの問題が注目されるようになったのです。
―欧州では、労働者性を拡張し保護する動きがある一方、日本では法的保護が不十分ではないかと、ご著書(※)の中で指摘されています。フリーランス新法をどのように評価していますか。
※『労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える』
発注者が業務受託者に対して一方的に取引条件を押しつけることや、著しく低い報酬を提示する「買いたたき」などが禁じられ、フリーランス本人が最低限の保護を受けられるようになったことは進歩です。またフリーランスの中には従来、法的保護を受けられることを認識していない人も多かったのですが、フリーランス新法ができたことで自分も保護を受けられるのだと気づくようになった点も評価すべきです。
しかしフリーランス新法は、フリーランスとして働く人を労働者として保護するための法律ではありません。このためフリーランスが契約を途中で解除される、つまり事実上、解雇されることに対する規制や、契約を解除された人への救済策は実質上、盛り込まれませんでした。最低賃金も適用されません。このため労働者性を広く認め、フリーランスを保護することが課題として残された形です。
―新法は、なぜ労働者概念を広げてフリーランスを保護する、という方向性をとらなかったのでしょう。
労働者概念の判断基準を明確化することは、非常に難しいからです。労働者の定義は、世界中でほぼ普遍的な定義が用いられており、「指揮命令拘束性」または「指示と監督」(direction and control)と総称されていますが(日本では、労働基準法9条の「使用される」の文言がこれを示しています)、その具体的な判断基準(判断要素)はさまざまです。例えば、日本では、業務諾否の自由の有無、時間的・場所的拘束性、具体的な指揮監督の程度、労務提供の代替性(他人に代わってもらうことができるか)、専属性、事業者性(機械・器具の負担、収入額、補助労働力の利用の有無)などの総合判断によって、「使用される」と言えるか(使用従属性)の有無が判断されることになります。
どのような事実から、これらの具体的な判断要素を満たしていると捉えるかの判断にも幅があります(例えば、タイムカードで始業・終業時刻を管理されていないと時間的拘束性は認められないのか、タイムカードで管理はされていなくても、一定の出社義務を負っていれば時間的拘束性は認められるのかなど、個々の事案の特徴や裁判官によっても評価が変わってきます)。このように、有償で役務を提供する個人に労働者性があるかどうかはケース・バイ・ケースで、最終的な判断は裁判所に委ねられることになるため、予測が困難です。
これは、労働者概念だけの特殊な問題ではなく、法律学における定義について一般に当てはまることです。重要な概念であればあるほど、最終的に裁判官の判断に委ねざるを得ない面もあるのです。もちろん、立法者としては、最近のEUのプラットフォーム労働指令が義務づけたように、推定規定を導入するという方法があり、私も、これは日本でも検討すべきであると考えています。しかし、立法化するということは、立法のプロセスにおいて関係者の利益調整が必要なので、重要な問題こそ立法化できない場合が多いと言えます。フリーランス新法の制定にあたっても、難しい労働者性の問題をあえて扱わず、契約条件の適正化などの部分でフリーランスを保護するという、手を付けやすい部分から取り組んだのだと考えられます。
プラットフォームで働く人は「労働者」 EUで相次ぐ判決、立法も促す
―立法以外の方法で労働者性のあるフリーランスを保護するためには、どのような選択肢が考えられるでしょうか。
一つは労働基準監督署が、労働の現場で当事者をサポートすることです。例えばフリーランス自身が、自分は実態として労働者なのか、それとも独立性が高いのかを判断するのはかなり困難です。この点、厚生労働省が作成した労働者を自己診断できるチェックリストは、労働者性の把握を簡単にしたという意味ではよくできています。ただ、当事者が自分は労働者なのかフリーランスなのかを判断できるかというとやはりまだまだ難しいと思います。ですから、体制としての難しさも想定されるものの、監督署が、適切な指導を行い労働者性の判断を支援するといったことがカギになると考えています。当事者も最寄りの監督署を把握しておき、困りごとがあったら、相談に行くのがいいでしょう。
最終的に、労働者概念の拡大に関して、重要な役割を果たし得るのが司法です。欧州諸国では裁判所が画期的判決を出し、各国の司法機関も追随する形で判例が積み重なった結果、EU全体でギグワーカーの労働者性を広く認め保護するという動きにつながりました。監督署と司法が重要な役割を担っていると思います。
―EUの裁判所はどのようにして、労働者概念を広げていったのでしょう。
まずフランスで2018年、アプリを通じて仕事を請け負うフードデリバリーの配達員を、自営業者ではなく労働者であると認定する判決が出されました。その後、スペインやドイツ、イタリアなどの裁判所でもプラットフォームを通じて働く人の労働者性を認める判決が相次ぎました。特にスペインの最高裁は、労働者と自営業者の中間に当たる「第3カテゴリー」の契約を結んでいたフードデリバリー配達員を労働者と認定し、同国はこれを受けて、アルゴリズムによって管理されるプラットフォーム上で働く人を労働者と推定するという「ライダー法」を制定しました。「第3カテゴリー」とは、労働者と自営業者のグレーゾーンにある人に対して、一部の労働法の規制を適用するという制度です。欧州では、ドイツとスペインにこの制度があります(英国にもこれに相当する制度があると理解されています)。イタリアにもあったのですが、企業側が第3カテゴリーを悪用して若年層を労働者として雇用せずに、このカテゴリーに吸収していることが問題視され、カテゴリーそのものが廃止されました。
英国でも2021年、ライドシェアのタクシー運転手の労働者性を認め、労働時間規制(年休)の適用を命じる判決が出されました。こうした流れを受けて、EUでも2024年4月にプラットフォームワーカーを従業員と認める指令案の採択が決まり、同年10月に同指令が発効しました。このように、司法と連携する形で立法も進んでいるのです。
日本の司法も時代の変化に対応を
―なぜ欧州の司法機関は、画期的な判決を出せたのでしょうか。
欧州では多くの国が憲法裁判所を設け、積極的に違憲審査を行う仕組みがあります。これによって司法全体に、憲法で保障された人権を尊重し、法律の是非に踏み込んだ判決を出す積極性が生まれています。日本でいうと、最高裁の上に憲法裁判所があるというイメージになるので、最高裁判決が憲法裁判所によって覆される可能性が出てくることになります。最高裁は、こうなってしまうと面子を失うので、そうならないように国民に開かれた積極的な司法を目指すようになるのです。もちろん、憲法裁判所の裁判官の人選も鍵となります。
各国の憲法裁判所だけではなく、欧州では、EUレベルではEU司法裁判所(ルクセンブルクに所在)があり、またEUよりもさらに多くの国が加盟する欧州人権裁判所(フランスのストラスブールに所在)もあります。裁判所が複数あることで(日本の一元的司法に対して、欧州は多元的司法と言えるかもしれません)、お互いに良い緊張関係が生まれて画期的な判決を下しやすいという側面もあります。
しかし、日本には憲法裁判所のような仕組みはなく、裁判所は違憲性がよほど明白でない限り、違憲判決を下さない傾向があります。労働分野に限らずすべての領域に関して、司法の消極性が、時代に即した画期的な判断を妨げている側面があるのではないかと私は考えています。
裁判官の考え方も無関係ではありません。裁判官の社会問題に対する認識が結局は判断の根底にあると思うのです。ですからフリーランスの置かれた状況や本人たちの心情に対する理解も欠かせないと考えています。
―司法を変えるには、どのような策が考えられますか。
司法全体を改革するには、憲法裁判所の設置などが望ましいですが、今すぐに実現できるという改革ではないでしょう。しかし、目指すべきだと思っています。韓国では、1987年の民主化宣言後に復活した憲法裁判所は、当初は予算もなく、国民に受容されるまで苦労したようですが、積極的司法の実現に大きな役割を果たしました。
現状では、例えば、厚労省は2024年10月、労働者性判断に関する裁判例を整理した参考資料集をまとめました。こうした資料を通じて、裁判官にも新しい認識を持ってもらうなど、地道な取り組みを積み重ねるしかないと思います。
東京高裁は2020年、劇団員の労働者性を認めて最低賃金を適用するという判決を出しました。一審の東京地裁は、劇団員が裏方として働いた分の労働者性は認めたものの、けいこや舞台への出演は自営と認定しました。しかし高裁では舞台出演も含めすべて劇団側に指揮命令権があったとして、最低賃金の適用を認めました。日本の司法では一審で労働者の訴えが認められても、二審ではなかなか認められない傾向があります。これを踏まえれば、希望の持てる判決だと思います。
この訴訟の原告は、私が聞いた限りでは、劇団の理不尽なやり方に対する怒りが強く、労働審判などでの和解も拒否して3年にわたる裁判を戦い抜いたそうです。当事者の情熱が新しい判例を生み、社会の認識を、少しずつ変えていくことにつながった事例っでもあります。しかし、この方法は、個人に多大な負担をかけるものです。日本では、もっと制度的な整備が必要だと思います。憲法裁判所は大きな話になってしまいますが、例えばフリーランスの保護については、厚労省が数年来、第二東京弁護士会に委託しているフリーランス・トラブル110番が重要な役割を果たしています。これを委託事業ではなく、裁判所の調停制度に組み込むなどの改革が考えられると思います。
聞き手:坂本貴志
執筆:有馬知子

橋本陽子氏


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ