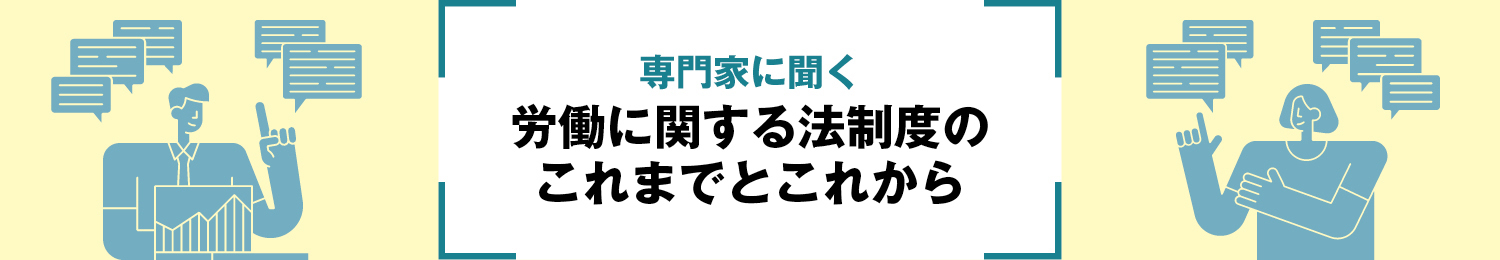
管理職比率の「数合わせ」から、組織改革を通じた「本当の女性登用」へ
女性のキャリア形成などを研究する関西学院大学教授の大内章子氏は、同大で女性のキャリアアップやリーダー育成を目的とした「ハッピーキャリアプログラム」も運営し、女性たちの生の声を日々受け止めている。大内氏に、男女に「昇進格差」が生じる要因や、格差是正には何が必要かを聞いた。
見かけだけの女性登用 仕事配分の差が昇進格差を生む
―ここ10年ほどの間で、仕事と家庭を両立する環境整備が進み、2016年には女性活躍推進法が施行されて、企業に女性管理職の目標数値や行動計画の策定が求められるようになりました。女性のキャリア形成に対する企業の認識に、どのような変化が起きていますか。
2010年代前半ごろまでは、余裕のある企業だけがワークライフバランスを通じた女性活用に取り組んでいた面もありましたが、2016年に女性活躍推進法が施行され、企業の認識はかなり変化しました。同法を通じて政府から「企業は変わらなければいけない」というメッセージが打ち出されたことは、意義があったと思います。しかしそれでも「うちの会社では難しい」と考える人も残っており、本気で取り組むには至っていない企業も多いのが現状です。
また同法では、女性活躍の具体的な進め方に関しては企業に委ねており、強制力もありません。このため「課長代理」や「担当課長」など意思決定ラインに乗らないポストに女性をアサインしたり、社外取締役に女性を迎えたりして、見かけの比率を増やす企業も見られます。政府は2030年までに女性役員の比率を30%にする目標を打ち出していますが、現在女性役員の約9割は社外登用です。社内登用の役員だけで政府目標を達成することに踏み込めば、効果が表れてくると思います。
―なぜ本当の意味で、女性登用が進まないのでしょうか。
企業の社員は、仕事の配分と配置転換によるさまざまな仕事経験を通じてスキルを高めるという、長い育成プロセスを経て管理職に昇進します。日本は欧米に比べて昇進スピードが遅いので、10~20年かけて、やっと課長になれるという企業も少なくありません。しかし企業の多くは、女性を本当の意味で育成プロセスに組み込めていないために、登用が進まないのだと考えています。
例えば入社後の配属で、男性にコアな業務を、女性に補助的な業務をアサインする企業が見られますが、これは男性をキャリアの「特急」に、女性を「各駅停車」に乗せるようなものです。男性は難しい仕事をやり遂げたら次も重要な仕事を任されますが、女性はこのサイクルに乗れず、出産などのライフイベントを経験すると、さらにスキルの蓄積が遅れてしまうこともあります。こうした日々の積み重ねが大きな差を生み、男性は部長になれるが女性は係長に昇進するのが精いっぱい、という構図が生まれるのです。
こうした中では、仮に役員や管理職の女性比率をあらかじめ決めておく「クオータ制」を導入しても、十分に育成されていない女性を形だけ管理職に据えることで事業運営に悪影響が生じ、結果的にダイバーシティの逆行を招くおそれがあります。女性を登用するには育成のプロセス全体を見直す必要がありますし、その中で係長やその手前のリーダー職にクオータ制を導入し、早期育成につなげるといった手立てが有効だと思います。
―女性活躍の取り組みを本格的に進めている企業と、そうでない企業の違いはどういった指標に表れますか。
「登用比」を見ると、取り組みの本気度がわかります。登用比とは、管理職の男女比を従業員の男女比で除したもので、今女性管理職がどの程度存在するかではなく、女性が男性と比べてどれくらい登用されているかを示します。例えば男女の社員がそれぞれ100人いて管理職も男女10人ずつなら、登用比は1で平等な状態です。しかし実際には、登用比が0.1~0.2といった企業が大半で、競争率は女性の方がはるかに激しい。まずは女性の登用比を1にすることを目指すべきだと思います。
登用比からは、その企業がどのように女性を活用しているかもわかります。例えば金融機関のように女性一般職が多い職場では、総じて係長までの女性の登用比は高めですが、課長以上で大きく落ち込みます。総合職・一般職という形で男女のキャリアパスが実質的に分かれており、一般職ルートは係長級で頭打ちになるためです。本気で取り組む企業は、課長以上の登用比も1に近くなります。離職を考慮しながら登用比を算出するのは難しいのですが、数値を把握することで企業側も、社内のどの職位、どの部署で女性のキャリアに「目詰まり」が生じているかがわかり、改善策も立てやすいはずです。また、個々の管理職で登用比を見ると、女性部下を育てている管理職とそうでない管理職というのが露わになると思います。育てていない管理職にその数値を見せて、改善を求めることもできます。
本当の女性登用には、組織全体の改革が必要
―政府の打ち出す女性活躍推進を、企業側はどのように受け止めているのでしょうか。
経団連や日本生産性本部は、女性の活躍を業績拡大に結びつけたいという意向があり、概ねポジティブに捉えていると感じます。ただ、私たちが厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」を用いて企業約1300社を対象にした共同研究では、女性管理職を増やした企業の業績は、上がったとは言えないという結果が出ました。理由の一つは、先ほどご説明したように企業が見かけ上の比率を高めただけで、女性たちは意思決定に関わっておらず、業績に影響を及ぼしていないためだと考察しています。
女性を本格的に管理職、役員へと昇進させるには、採用から人材育成、人事評価などを含めた組織全体の改革が必要です。業績へのインパクトが見えないのは「女性登用にメリットがない」のではなく、組織が変わらないから業績に結びつかないのだと考えています。また現段階では2016年からのデータの蓄積しかなく、熱心な企業でも女性の多くが育成途上で業績への影響が表れていない可能性もあります。
―日本の管理職は、負担ばかり増えて賃金はさほど上がらないといったデメリットも、女性たちの昇進に対する意欲を削いでいるように思います。
女性に限らず若い世代は総じて、管理職は忙しすぎて割に合わないと考えています。企業が管理職にプレイングマネジャーを担わせているのが大きな問題です。働き方改革で一般社員の残業時間を抑え、積み残した仕事を管理職にさせるといったやり方を続けていたら、企業はいずれ立ち行かなくなるでしょう。
管理職の役割は、男性や女性、外国人など多様な人材を育成して仕事を配分することであり、忙しすぎるとこうしたことを考える余裕もなくなってしまいます。管理職を本来の業務に専念させれば、組織がうまく回るようになるだけでなく、管理職が自己裁量で仕事の進め方を決められるようになり、男女にかかわらず働きやすいポストになると思います。
取り組み遅れた中小には好事例を示す 欧米企業は育成に課題も
―中小企業の管理職登用を進めるには、何が必要でしょうか。
中小は大企業以上にシビアな競争にさらされているため、生き残りをかけて男女関係なく管理職に登用し、機会を与える企業が現れています。一方、経営者の考え方が硬直的で、女性登用に後ろ向きな企業もあり、二極化しています。例えばKMユナイテッドという塗装会社は、何十年もかけて職人を一人前に育てるやり方から、職務を分析して3年で一流の職人になれるよう育成のやり方を変えました。さらに女性や外国人も活躍できる組織にしたことで、若手が定着し業績も急拡大しています。女性活躍が遅れている企業には、こうした好事例を示し「中小企業でもこうすればできる」という姿を見せることが大事です。
―欧米の女性登用の現状はどうなっていますか。
米国の企業はD&Iが浸透し、女性が経営トップを務める企業も増えています。トランプ政権の発足に伴い、D&Iが後退するとの懸念もありますが、企業業績によってドライに評価する面も大きいので、方向性が大きく変わることはないでしょう。たとえバックラッシュがあったとしても、それに反対する社会的な運動が起きると思います。
欧州、特に北欧は男性の育児参加などを政策的に進めた結果、女性が意思決定に関わらなければ、組織が成り立たないところまで来ています。総じて昇進が早く、短期間で結果が見えやすいことも、組織改革を進めやすくしたと思います。
ただ欧米企業は流動性が高いため、離職する可能性の高い人材に投資することのインセンティブが薄れ、育成をあまりしなくなっています。特に米国ではそれによって格差拡大も招いており、日本企業がむやみに倣うべきだとは思いません。
日本でも雇用の流動化は進んでおり、育成へのインセンティブが薄れていく可能性はあります。こうした中で、企業がいかに女性をはじめとした人材の能力を引き出し、事業成長に生かしていくかが課題となるでしょう。
聞き手:大嶋寧子
執筆:有馬知子

大内章子氏


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ