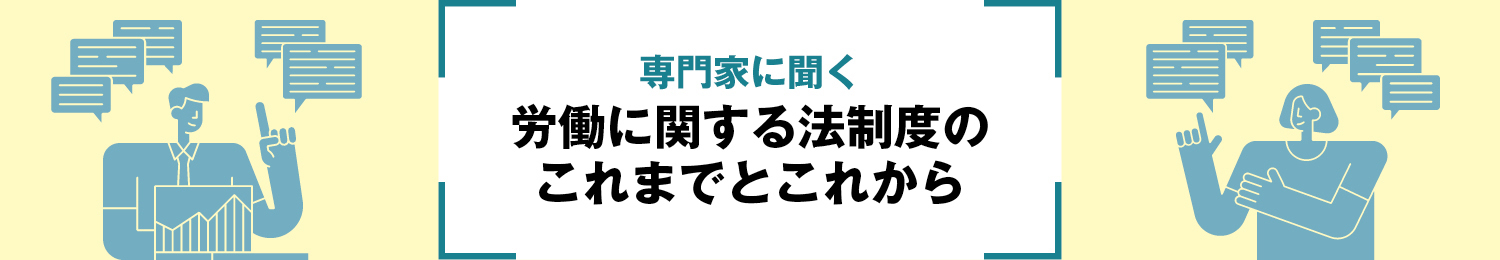
「正社員中心主義」の弊害を排除するため、障壁となる法制度を変える
働き方改革で兼業・副業やフリーランスの働き方が広がり、ジョブ型的な人事制度が導入されるなど、労働の現場ではさまざまな変化が起きている。こうした中で、法制度はどのような役割を果たすべきだろうか。早稲田大学教授の水町勇一郎氏に聞いた。
ジョブ型導入、副業・兼業促進で、働き方の多様化を進める
―労働市場と労働者にまつわる法制度を時代にフィットさせるため、現時点で最も重要な取り組みは何だと考えますか。
政府はこれまで、時間外労働に上限規制を設けたり、副業・兼業の解禁を通じて多様な働き方を促したりすることで、日本型雇用システムに内在する「正社員中心主義」の弊害を排除しようとしてきました。今後も、この取り組みを続けることが重要だと考えています。
日本企業は無期・直接雇用のフルタイム正社員を中心に据え、それ以外の人を非正規という、周縁的な存在として位置づけてきました。これによって正社員は、企業側の命令で受動的に働くようになり、キャリアオーナーシップを奪われています。賃金水準や雇用の安定性の面で、正規と非正規の間に格差も生まれました。
こうした弊害を取り除くための策の一つがジョブ型的な働き方の推進で、2024年にはジョブ型人事指針も公表しました。企業が社員をがんじがらめにするのではなく、「職務」を客観化することで、ジョブを軸とした労働者の主体的な移動を促したのです。同時にフリーランスや副業・兼業といった多様な働き方を普及させることで、働き手にキャリアオーナーシップを発揮してもらおうとしています。
一方で、勤続年数が長い人ほど退職金への課税が優遇される制度や、本業と副業・兼業の労働時間を通算して割増賃金を支払う仕組みなど、変化を妨げる法律もまだ残っています。今後は法的な障壁を取り除くと同時に、インセンティブによる政策誘導という「アメ」と規制という「ムチ」の両方を使い、働き方に中立的な制度を実現させていく必要があるでしょう。
―人事制度や報酬体系を決定するのは基本的には企業です。これまで政府はどのように、働き方の変化を促してきたのでしょうか。
1990年代以降、日本型雇用の弊害は次第に明らかになりましたが、対応を労使に任せていてもなかなか事態が変わらなかった。そこで経済産業省は人的資本開示を打ち出し、投資家が人的投資を評価するという、いわば「外圧」で企業を動かそうとしました。その後、企業側もグローバル化と人手不足の中、人的投資の必要性を認識するようになり、両者の方向性が一致して変化が起こり始めたのです。
ただ大企業では取り組みが進み始めたものの、中小企業は具体策をなかなか打ち出せずにいます。これからは中小企業に対して、モデルとなる好事例を示した上で、ノウハウや資金をサポートすることも求められます。また、なかなか進まない正規・非正規の格差解消についても、是正すべき「不合理な待遇」の具体例を示すなどして進展を促すべきです。
「ノーマル」を定めるのが法の役割 ルールの実効性担保が課題に
―労働市場において、法制度はどこまで踏み込んだ規制を行うべきでしょうか。
大多数の国民が「ノーマル」だと考える働き方を守ることが法律の役割であり、法律の枠内で具体的な運用を決めるのは、労使であるべきです。例えば時間外労働はかつて、三六協定を結べばほぼ青天井でした。スキルもない新入社員を月に100時間以上も残業させることが可能な状態は、明らかにノーマルではないため、時間外労働に上限規制が設けられました。高収入で自律的に働ける専門職などについては、労使の合意に基づき適用除外を設けて対応すればいいですし、例外的に深夜労働の規制を外すという選択肢もあり得るかもしれません。ただ深夜労働については、絶対に健康被害は生じないという明確なエビデンスを得るのが難しく、規制緩和のハードルは高いでしょう。
最低賃金も、生活が成り立たない水準は「アブノーマル」だと言えます。ただ「ノーマル」な水準をどこに定めるかが重要なポイントで、選挙などを通じて国民の選択に委ねるべき部分とも言えます。
―労働時間や賃金について、諸外国の法制度はどうなっていますか。
欧州ではEU指令によって、労働時間は残業も含めて週48時間、勤務終了後は始業まで11時間のインターバルを設けるというルールが設けられています。他方、米国には労働時間規制が実質的に存在しません。日本は、国民性やマーケットの構造などはどちらかと言えば欧州に似ているので、欧州型をモデルにするのがいいでしょう。
欧州では、労働時間などのルールが守られているかどうかを労働組合がチェックしますし、労働者個人が裁判所を利用して解決することも定着しています。かたや日本の中小企業の多くは労働組合がなく、労働審判の利用率も、欧州の数十分の一に留まります。労働基準監督官も欧州が労働者1万人あたり1人なのに対し、日本は2万人に1人しかいません。こうした状況では、規制が強化されても実効性が担保されない懸念があります。厚生労働省と法務省が連携して労働審判制度を見直し、使い勝手を向上させるといった取り組みが必要です。
求職者への情報開示で、労働移動を促す デジタル化の遅れも大きな課題
―日本でなかなか労働移動が進まない理由はどこにあると考えますか。
近年は40~50代でも、転職によって収入が上がる人が増えてはいますが、まだ十分ではありません。企業年金をポータブルにするなど、転職しても損にならない制度に変える必要があります。
また上場企業には人的資本情報の開示が義務付けられる一方、非上場企業や中小企業に開示義務はなく、求職者に提供する情報に格差が生じています。賃金についても、欧州は産業別に賃金表がありますが、日本は企業横断的な基準がなく、転職先で得られる賃金が不明確なことが移動を阻害する要因になっています。
これからは、企業側にウェブサイトなどを通じて中途採用比率や賃金水準、労働時間など生活に関わる情報を積極的に開示していくよう促していく必要があります。民間の職業紹介事業も豊富な情報を提供するよう健全な発展が期待されると同時に、「闇バイト」や口コミサイト上の偽情報などをチェックすることも求められます。
―労働力不足に対処するという観点において、課題はどこにありますか。
深刻化する人手不足に対応するには、従業員に長時間労働を強いるのではなく、より少ない人数で仕事を回せるよう業務を改善しなければいけません。業務改善にはデジタル技術の導入が不可欠ですが、日本は諸外国に比べてデジタル化が圧倒的に遅れています。特に、本来なら中小企業のDXをサポートすべき地方自治体が、デジタル診断の提供といった簡単な支援すら十分にできておらず、大きな課題となっています。
また今後は、デジタル技術の活用に伴って発生する全体的な問題にも、政策的に対応する必要があります。例えば、社員がいったん個人情報の提供に同意すると、経営側に健康状態など仕事以外の情報もすべて把握され、野放図に使われかねないという問題があります。EUでは、企業側の個人情報の利用状況を、労働組合などがチェックする仕組みの導入が議論され始めており、日本でも今後、同様の取り組みが求められるようになるでしょう。
―労働組合の組織率が低下する中、労使自治を実現できない職場も増えています。労使コミュニケーションには、どういう方向性が考えられますか。
働き手の多様化に伴い、現場の柔軟な対応が求められるようになる中、労使コミュニケーションの重要性は以前より高まっています。しかし労働組合などが存在しない企業では、経営側が制度を一方的に決め、結果的に労働者の搾取につながってしまっているケースも見られます。例えば、組合が存在しなくても、労働問題について詳しい専門家が相談に乗ってくれるよう情報ネットワークを充実させるなど、政策的な対応もあり得ると思います。国が決めた法律と個々の労働契約の中で自由に決めてよいという考え方が両極にある中で、その中間の現場の労使関係や情報ネットワークをいかに整備していくかというのは今後も重要なテーマです。
欧州でも組合組織率は低下していますが、そういう状況だからこそ労使の基盤をどう作っていくかという取り組みに非常に腐心しています。組合のない職場では、デジタル技術を導入する際に、労使が会議体を作ってともに進めなければいけないというルールを設けるなど、各国政府が労使協議の舞台を作ろうとしています。日本も労働組合だけでなく、労働者同士が課題や悩みを共有し相談できるプラットフォームなど、さまざまな形のネットワークを構築するべきだと考えています。
聞き手:坂本貴志
執筆:有馬知子

水町勇一郎氏


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ