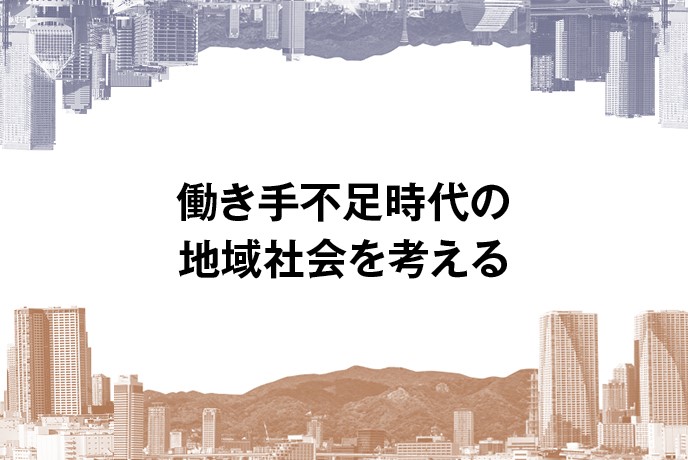地方自治体に迫る「静かなる危機」と集約化へのハードル――佐藤主光氏×坂本貴志

佐藤主光(一橋大学教授)×坂本貴志(リクルートワークス研究所研究員)
生活維持サービスの担い手不足に起因する様々な課題が、多くの地方自治体で顕在化しつつある。地方財政に詳しい一橋大学の佐藤主光教授と労働供給制約社会を見据えた地方分権の在り方や備えについて議論した。
地方で不足しているのは財源ではなくマンパワー
坂本:高齢化や人口減少は地方でより深刻です。公共事業も入札不調が相次ぐなど従来にはなかった事態も散見されます。働き手不足と地方自治体の財政課題について、どのような所見を持っておられますか。
佐藤:「ヒト・モノ・カネ」の資源のうち、地方自治体に不足しているのは「カネ」や「モノ」ではなく、圧倒的に「ヒト」です。「カネ」については主に地方交付税による国からの財政移転のほか、基金の積み立てもあって案外充足しています。「モノ」も公共施設の老朽化に伴う更新投資の議論が活発な状況ですから不足しているわけではない。一方で、決定的に足りないのは「ヒト」、つまりマンパワーです。人口減少は単に住民がいなくなるだけでなく、あらゆる分野の行政サービスの担い手が減っていくことを意味します。近い将来の内政課題をまとめた総務省の「自治体戦略2040」でも、地方公務員が半減することを前提に合理化を促すなど国も危機感を共有しています。
坂本:地方自治体に足りないのは財源ではなく、マンパワーだという認識は近年浮上したのか、それとも徐々に積み重ねられてきたものなのでしょうか。
 佐藤:人口減少は日本全体で以前から徐々に進行していたものの、これまで十分認知されてこなかった、というのが実情でしょう。長時間労働も過重労働も当たり前という働き方の風土が、人手不足を見えにくくしてきた面もあります。しかし、あらゆる職場の無理が限界に達し、教職員の大量離職や地方公務員の採用難といった形で顕在化したのが近年の状況です。終身雇用は実質的に終わり、処遇の悪い職場から働き手がどんどん流出しています。地方行政の現場はその典型と言えます。
佐藤:人口減少は日本全体で以前から徐々に進行していたものの、これまで十分認知されてこなかった、というのが実情でしょう。長時間労働も過重労働も当たり前という働き方の風土が、人手不足を見えにくくしてきた面もあります。しかし、あらゆる職場の無理が限界に達し、教職員の大量離職や地方公務員の採用難といった形で顕在化したのが近年の状況です。終身雇用は実質的に終わり、処遇の悪い職場から働き手がどんどん流出しています。地方行政の現場はその典型と言えます。
坂本:地方自治体に足りないのは財源ではなく、マンパワーだという認識は近年浮上したのか、それとも徐々に積み重ねられてきたものなのでしょうか。
 佐藤:人口減少は日本全体で以前から徐々に進行していたものの、これまで十分認知されてこなかった、というのが実情でしょう。長時間労働も過重労働も当たり前という働き方の風土が、人手不足を見えにくくしてきた面もあります。しかし、あらゆる職場の無理が限界に達し、教職員の大量離職や地方公務員の採用難といった形で顕在化したのが近年の状況です。終身雇用は実質的に終わり、処遇の悪い職場から働き手がどんどん流出しています。地方行政の現場はその典型と言えます。
佐藤:人口減少は日本全体で以前から徐々に進行していたものの、これまで十分認知されてこなかった、というのが実情でしょう。長時間労働も過重労働も当たり前という働き方の風土が、人手不足を見えにくくしてきた面もあります。しかし、あらゆる職場の無理が限界に達し、教職員の大量離職や地方公務員の採用難といった形で顕在化したのが近年の状況です。終身雇用は実質的に終わり、処遇の悪い職場から働き手がどんどん流出しています。地方行政の現場はその典型と言えます。坂本:地方公務員はひと昔前まで人気の職種でしたが、いまは3次、4次募集をかけても採用予定者を確保できないという声も聞きます。なぜこうなったのでしょう。
佐藤:それには2つの要因があります。一つは移動や職業選択の自由度が広がったこと。首都圏などの都市部には公務員以外に様々な職種の選択肢があり、都内でも郊外の自治体は職員の確保に苦労しています。もう一つ、地方の場合、若者の絶対数が減るなか、大学進学で地元を離れた若者が就職を機に戻るケースがかなり減ったことが挙げられます。地方は若い世代の絶対数の減少と流出が相まって、人手不足が加速している可能性があります。
坂本:総務省が発表した2024年の人口移動報告によると、足元でも東京への流入数が拡大する一方、25道府県で人口流出が加速しています。首都圏など都市部のほうがより高い賃金を得られることなどが影響しているのでしょうか。
佐藤:いまの若い人は所得だけでなく、自分のライフスタイルを大事にしている点も考慮する必要があります。都市部は賃金が高いのに加え、様々な消費の選択肢があることが流入に作用しているのでしょう。人が集まることによって様々なサービスが拡充し、需要が増えると賃金も上がる。こうした「集積の経済」による相乗効果で都市の魅力は増していきます。逆に、人口流出地域では商店の廃業が相次いで「シャッター通り」が広がり、ますます生活が不便になる。これが地方の若者流出を促す悪循環の構図です。
「撤退と集中」の戦略をどう描くか
坂本:国も地方交付税などで自治体に財政移転を図り、地方の不利性解消に努めてきました。こうした政策についてはどう見ておられますか。
佐藤:東京への一極集中は震災や安全保障上の観点からも望ましくありません。東京だけではなく地方の中核都市や政令指定都市に経済活動を集約させていく取り組みは不可欠です。しかし地方交付税は、その流れに逆行してしまっています。規模の小さな過疎地域の行政サービスも都市部と同水準の維持を図る前提のため、補正係数を駆使して基準財政需要額を上積みし、交付額の調整を行ってきたのが地方交付税の実態です。これは正しい財政措置と言えるのか。むしろ相応額を近隣の中核都市などに配分して公共交通の整備に充て、過疎地とのアクセスをよくする、といった方向に切り替えていくほうがサステナビリティの観点からは良いはずです。
佐藤:東京への一極集中は震災や安全保障上の観点からも望ましくありません。東京だけではなく地方の中核都市や政令指定都市に経済活動を集約させていく取り組みは不可欠です。しかし地方交付税は、その流れに逆行してしまっています。規模の小さな過疎地域の行政サービスも都市部と同水準の維持を図る前提のため、補正係数を駆使して基準財政需要額を上積みし、交付額の調整を行ってきたのが地方交付税の実態です。これは正しい財政措置と言えるのか。むしろ相応額を近隣の中核都市などに配分して公共交通の整備に充て、過疎地とのアクセスをよくする、といった方向に切り替えていくほうがサステナビリティの観点からは良いはずです。
坂本:地方交付税や国庫支出金が充実しているため、かえって地方の集約化を妨げている面もある、というわけですね。
佐藤:地方創生は本来、集約化を加速する役割を担うはずだったのではと思っています。各自治体の活性化のアイデアの中から実効性の高い事業に国が助成し、地域の自律的なシステム構築につなげていく。逆に言うと、活性化を実現できそうにない自治体はおのずと地方創生の枠から外れていく、というのが一つの考え方だったのではないでしょうか。ところがふたを開けると、1700余の自治体すべてを活性化していく議論になっています。
今後の人口減少社会を見据えれば、将来的に存続させていく地域と、そうでない地域を区分けせざるを得ません。それができるのは(区分けの必要が薄い東京都を除く)道府県だと思います。道府県がイニシアチブを取らない限り、市町村の側から「撤退します」とは言い出せないでしょう。道府県が行うべきは区分けとタイムラインの提示です。例えば、「向こう20年間は今いる人たちに行政サービスを続けるが、その後は橋や道路の更新投資はせず、公共交通も都市部に集約させていく」といった具合に短・中・長期の工程を示す。つまり、撤退戦略と集中戦略の両方の構築が必要です。その役割を担うのは国もあり得ますが、道府県がカギを握ると考えています。
坂本:将来に向けての工程表を提示しながら、住民が選択するのが本来あるべき姿だと。ただ問題は、どの市町村も存続をかけて奮闘しているなか、「撤退」は実行可能なのかという点です。
佐藤:「存続したい」という自治体内部の思いと、実際に存続できるかは別の話です。いまは地方創生のアイデアを出さないと国からお金をもらえないシステムですが、「将来の存続は諦めますが、今いる人たちのための行政サービスは継続してください」という自治体に対する支援もあっていいと私は思います。
坂本:退出する地方自治体にはどういうインセンティブを付与できますか。
佐藤:高齢化が進む自治体では、自主財源で介護や福祉関連の事業を賄うのが困難になっています。こうしたコア業務に人や財の資源を集中できる支援があれば、自治体にもメリットを感じられるはずです。コア業務は手厚い地方交付税で支える一方、自治体としての自立はあえて求めず、「上手な撤退」を促す。すべての自治体に「自走」を求める時代ではなくなりつつあります。
求められる「地方分権のパラダイムシフト」
 坂本:撤退と集中の戦略が比較的うまく機能している県などはありますか。
坂本:撤退と集中の戦略が比較的うまく機能している県などはありますか。佐藤:参考になりそうなのが、「奈良モデル」です。奈良県は山間部が多い地理的条件もあり、市町村合併が進みませんでした。大きな都市が存在しないことから地域医療や徴税、人材育成などの業務を県がイニシアチブを握って推進してきた実績があります。
とはいえ、「県主導で」といっても、今はその県自体が人口減少に直面しています。将来的に日本国内に47の拠点を維持していけるかと問われれば、厳しいと言わざるを得ない。とすれば、幾つかの府県を合併した道州制も視野に入ってくるでしょう。医療や介護といった行政サービスだけでなく、観光や農業、企業誘致などの経済政策を担う地方の拠点エリアの規模は大きいほうがいい。
地方創生には、地方への財源のばらまきにつながっているという批判もあれば、やりようによっては機能を上手に集約化させていくこともできるという二つの顔があります。うまくやれば、既存の県などの枠組みを超えて地域の再編成を促す可能性もある。そのために政府は「均衡ある国土の発展」というフレーズから脱却し、1700余のすべての自治体の活性化を志向する非現実的な政策目標を捨てるべきです。
坂本:今後の地方創生はどういった展開が望ましいとお考えですか。
佐藤:前述の道州制の導入なども必要だと思いますが、まずは地方分権の受け皿を市町村から道府県単位にしていくことが必要です。政令指定都市は別でもいいと思いますが、それ以外の地域は「奈良モデル」のように、地方分権のイニシアチブを道府県に移行していくべきです。具体的には、土木系やソーシャルワーカーといった専門人材を県が一元管理して市町村に派遣する仕組みの導入など経済活動を集約化するのと同時に、ライドシェアの導入なども含めて周辺地域との公共交通ネットワークの充実を図る。
これからは、小さな自治体はサービスの「提供主体」ではなく、サービスの「購入主体」でよいと思います。市町村は住民代表として事業者と交渉して公共交通やインフラ維持を民間委託したり、近隣の中核都市に委託したりする。そうすれば小さな自治体も存続できます。大事なのは様々な選択肢の中からよりよい形を「選べる」ことです。
こうした仕組みを構築するためには、地方分権のパラダイムシフトが求められます。2000年に施行された地方分権一括法は都道府県と市町村を対等なパートナーと位置付け、市町村が受け皿の主体と位置付けられています。しかし、これからの時代はそうはいかないでしょう。これまでの地方分権の在り方そのものをまず問い直す。その先にあるのが、地方交付税の配分先の議論です。その過程で配分基準を見直し、県などに集約化しやすい仕組みをつくっていくべきです。
日本を覆う「静かなる危機」
坂本:ここまで佐藤先生が指摘されたような議論は、現状、どの程度行われているのでしょうか。
佐藤:2000年代初頭には、小さな自治体は業務の一部を県などに委譲することを義務付ける案もありました。ところが、「自治体間で差別的な扱いをしてはいけない」という声が広がり、自治体の規模にかかわらず等しくフルスペックの行政サービスを提供すべきだという結論になりました。あるべき地方分権とは、地方自治体の規模や財政力とは無関係に同じ権限と責任を負うことだという理念を「集権的分権改革」と私は呼んでいますが、それへの賛同が近年揺らぎだしたのはやはりこのやり方では行き詰まっているからだと思います。
国の財政状況も非常に厳しく、国と地方の基礎的財政収支(プライマリーバランス)の黒字化も未達のままになっています。国からの財政移転に大きく依存している現状では一旦、国が財政危機になれば、東京を除く全自治体が財政危機に陥りかねません。企業の連鎖倒産と同じです。自治体は国に頼れなくなっても自活できる仕組みをつくらなければいけない。そのためには資金や人材を集約し、自治体の税収をどう増やすか、という方向に思考を転換する必要があります。
坂本:地方で人手不足がさらに深刻化していったとき、最終的にどのような形での調整が起きるのでしょう。
佐藤:国の財政破綻によってある日突然、危機が顕在化するのとは対照的に、マンパワー不足によるリスクは「静かなる危機」だと思います。地域経済の基盤が徐々に沈んでいくのに伴い、自治体運営も徐々に行き詰まっていくでしょう。
今後の調整は物価もそうですが、モノやサービスで調整されていくのかもしれません。つまり、自宅で寝たきりだけども介護をしてくれる人も医者も病院もない、そんな「介護難民」が巷にあふれるイメージです。道路に穴が開いても水道管が破裂しても誰も補修してくれない、といったことも想定されます。おそらくそういう形でサービスの絶対量が失われていく方向で調整が進むと思います。その結果、他地域に移動できない人たちはそこに取り残されてしまいます。これが最も危惧する点です。
おそらく地域によってそこのバランスは大きく違ってくるはずです。担い手がいてお金もある都市部はサービス価格が高騰していく一方、担い手のいないところはお金をいくら積んでもやってくれる人がいないためサービス量そのものが低下していく。
デフレからの脱却に伴い、私たちは遠からず物価調整に初めて直面することになると思います。それは行政に限らず、人手が足りないあらゆる分野のサービス価格がはね上がっていく、そんな社会への移行です。そうならないようにするためには、今必要な対策を早急に取り組んでいくべきです。
佐藤 主光 氏 (さとう・もとひろ)
一橋大学経済学研究科教授
専門は税制・財政学。主な著書に「地方税改革の経済学」(毎日エコノミスト賞受賞)、「ポストコロナの政策構想」(共著)、「日本の財政」など。政府税制調査会特別委員、内閣府規制改革推進会議委員、財務省財政制度等審議会委員、東京都税制調査会委員などを歴任。2019年日本経済学会石川賞受賞、2024年春の紫綬褒章授賞。
執筆:渡辺豪


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ