
複雑化するマネジャーの役割を再考する
第1回のコラムでは、本プロジェクト「マネジメントを編みなおす」の問題意識について発信した。繰り返しになるが、本プロジェクトの起点は、個人や組織が直面する状況がますます複雑化し、多様化している現在、従来の枠組みをそのまま維持しながらマネジメントを行うことには限界が生じているのではないか、という認識に基づいている。
これらに解決策を提起していくためには、実際に企業でマネジメントを担うファーストラインマネジャー(以下、マネジャー)に関するどのようなことが、マネジメントに取り組むことを困難にさせているのかについて実態を押さえる必要がある。
本プロジェクトでは、こうした問題意識のもと、これからのマネジメントの機能がどのようにあるべきなのか、という問いに対し集まった11名の部長職相当以上による「マネジメントの機能再考」研究会を開催した。そこで本コラムでは、なぜここまで企業の中で、マネジャーをめぐる課題が注目されているのか、その理由に焦点を合わせて、研究会から聞かれたリアルな声を紹介する。
何がマネジャーを複雑にさせているのか
ここ最近、管理職は罰ゲームと揶揄されている。実際、その一役を担うマネジャーを経験した人からはその大変さを聞くこともある。マネジャーの役割について、研究会の中でも、ビジネス目標の達成と人材育成という両者の重要性が指摘されていた。一見するとシンプルなようだが、今日、なぜこんなにも人事課題としてマネジャーが注目されているのか、マネジャーを取り巻く環境が複雑化してきた理由について整理する。以下、主に3点を挙げる。
第1に、外部環境の変化やそのスピードへの対応である。これまでのように経営トップが意思決定し、それを現場に落としていくやり方では、市場や社会の変化に適応することができなくなってきた。したがって、これまで以上に、個々の持つ能力を最大限、最速で活かせるよう、個が活きるマネジメントが求められるようになってきた。
第2に、業務やリスクへの過剰な管理負荷である。本当に必要かどうか疑問が浮かぶような余計な業務が増えてきたことである。例えば、過剰なコンプライアンスへの対応や、業界特有の規制、監査の増加(特に日本の現場での負担感が増しているという)などといったことが、現場の労働量を増加させているという。さらに、必要以上の監査やルールが現場の士気の低下に拍車をかけている。
第3に、現場で働く人のモチベーション低下の抑制である。モチベーションが低下している個人への対応には多くの時間とリソースがかかる。モチベーションが低下する理由はさまざまだが、例えば、キャリアのミスマッチのほか、健康やプライベートな問題など枚挙にいとまがない。ワーク・ライフ・バランスが業績を後押しするという研究もあり、マネジャーには仕事以外にも配慮したマネジメントが求められている。
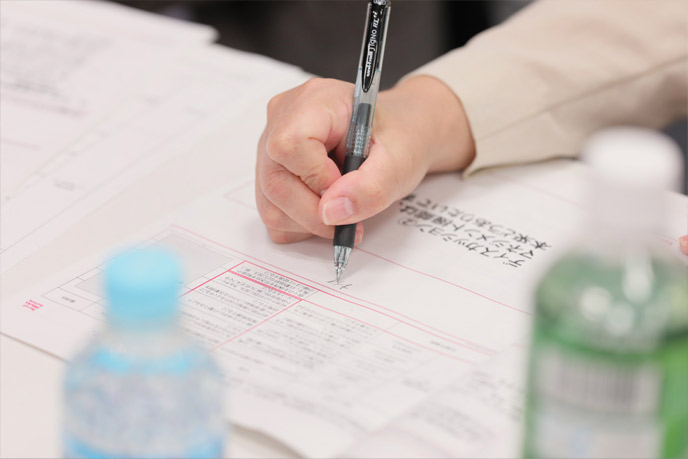
企業は、これまで多くの業務をマネジャーに割り振り、その結果として彼らに過剰な負荷をかけてきた反省がある。こうした状況が長く続いた結果、現在ではマネジャーを取り巻く環境において、さまざまな矛盾や課題が顕在化していると言える。
こうしたマネジャーへの負担増大の背景には、業務や環境の複雑化や組織運営の効率化などを、マネジャーに押しつけてきた構造的な問題がある。現状はその姿が表出化されているとも受け取れる。
マネジャーの役割見直しは一時的な解決策にとどまる
研究会に参加した企業の部長からは、そもそも「マネジャーの役割が定義されていない」という意見も挙がった。こうした企業においては、マネジャーの仕事やその役割を見直すことは、一定の意味を成す。ひいては、マネジャーの役割定義が、マネジャーへの期待を定め、マネジャーの行動を変容させていく基本となる。
しかし、マネジャーの役割定義やその見直しは一時的かつ表面的な解決策でしかない。なぜなら、第1に、マネジャーの役割は、組織全体の事業戦略および機能設計と密接にかかわっているからである。つまり、組織の目的や機能そのものを見直さなければ、マネジャーの役割の変更が事業戦略と整合しない可能性がある。第2に、マネジャーの役割を見直しても、それが現場の実情と乖離がある場合、運用上の課題が残ってしまうことが懸念される。最悪の場合、役割の見直しが形骸化し、実際の業務負荷や期待役割のズレを解消できない可能性がある。
つまり、マネジャーの役割見直しは局所的な対策にすぎず、本質的な意味で組織課題を解決することは難しいと言える。したがって、組織全体の事業戦略そのものから見直す必要がある。このため、本プロジェクトの問題意識として、マネジメントの機能に着目する必要がでてくるのである。
マネジメントの機能の再構築が未来のカギ

マネジャーになることは、本当に罰ゲームなのだろうか。筆者は適当な表現とは言えないと考えている。マネジャーは、組織の最前線で現場のメンバーを直接的に管理・指導する役割を担っており、企業の成功にとって極めて重要なポジションである。例えば、メンバーの能力を最大限に引き出すための支援やフィードバックなどを通じて成長を促し、チームの生産性の向上を担う。当然、メンバーにおける適切な目標設定を行い、企業の目標達成に寄与することは大前提だ。
さらに、マネジャーの役割は事業目標とメンバーの成長支援にとどまらず、現場で発生するイレギュラーな事態への対応や事業部間の調整役など、多岐にわたる。このような役割は、組織全体の円滑な事業運営や持続的な成長を目指していく上で組織にとって欠かせない存在と言える。事業環境が急速に変化する上で、ファーストラインにいるマネジャーにこそ、外部環境への変化に対応する力を発揮する役割が求められる。
これから企業が注力すべきは、マネジメントの機能そのものを再構築することだろう。研究会で意見が交わされたように、マネジャーの業務の負担を分散させる事例も出てきた。例えば、人事部門がヒトの課題を支援し、マネジャーが業務に集中できるような役割分担を進める企業事例も見られる。また、マネジャーは課題を抱え孤立に陥りやすい状況を踏まえて、その部長や人事部門が相談役となってフォローする体制を構築することも有効だろう。さらに、マネジャーだけが頑張るのではなく、チームで業績を上げるために一人ひとりが組織の雰囲気を変え、チームに貢献した人に対してしっかりと報いる仕組みを整えることが企業には求められる。しかし、こうしたマネジャーの役割について議論する際には、一足飛びに進めるのではなく、事業戦略からマネジメントの機能を再設計していくこととセットで検討していかなければならない。こうしたマネジメントの編みなおしが持続可能な組織運営の実現につながる。
PHOTO=平山諭

千野 翔平
大手情報通信会社を経て、2012年4月株式会社リクルートエージェント(現 株式会社リクルート)入社。中途斡旋事業のキャリアアドバイザー、アセスメント事業の開発・研究に従事。その後、株式会社リクルートマネジメントソリューションズに出向し、人事領域のコンサルタントを経て、2019年4月より現職。
2018年3月中央大学大学院 戦略経営研究科戦略経営専攻(経営修士)修了。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

