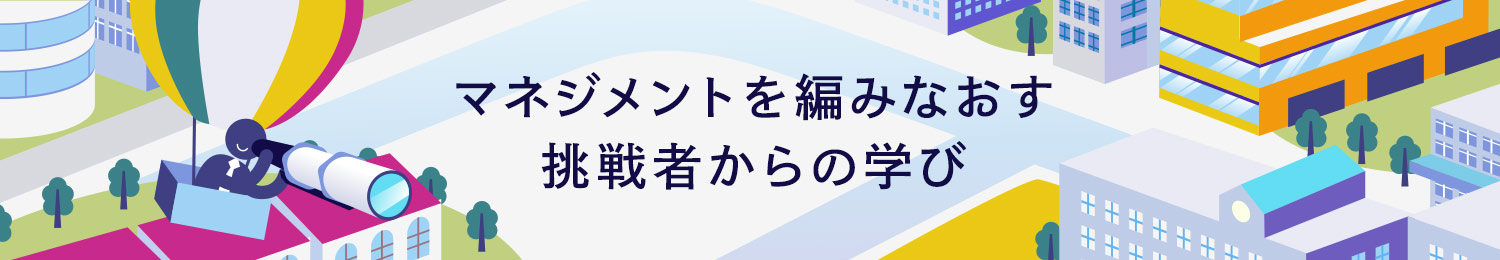
能力ある人材を見いだし活躍の舞台を与えることで、新たな展示手法の拡大を図った
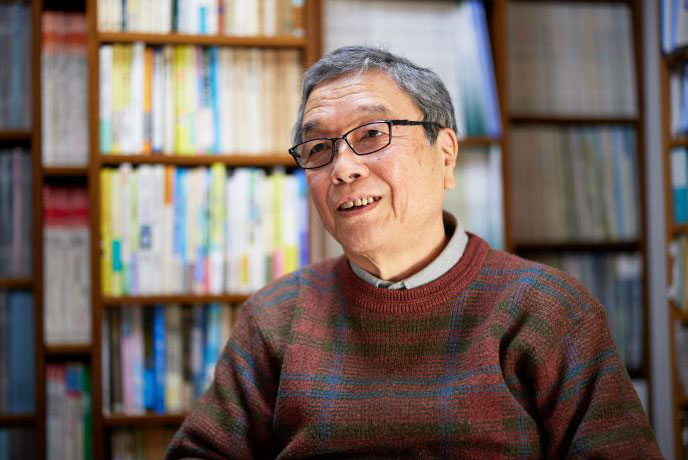
元上野動物園園長・小宮輝之氏
小宮輝之氏は大学卒業後に東京都職員となり、多摩動物公園で飼育係を担当。その後、恩賜上野動物園(以下「上野動物園」)東園飼育係長、飼育課長などを経て、2004年から2011年まで上野動物園園長を務めた。現在、公益財団法人 日本鳥類保護連盟 会長。上野動物園では、斬新な展示方法を打ち出したり、それまで繁殖が不可能とされていた動物の繁殖を成功させたりしてきた小宮氏。どのようなやり方で部下をマネジメントしていたのだろうか。
周囲を巻き込みながら実績を上げ「やりたいこと」を実現
――まずは、小宮さんがいらっしゃった頃の上野動物園について簡単に教えてください。
当時の上野動物園には、動物園全般を管理する「庶務課」、設備を作る「工事課」、園の施設を管理・整備する「管理課」、そして動物の飼育を行う「飼育課」などの部門が置かれていました。そして飼育課は「東園」「西園」「は虫類館」などに分かれ、さらにその下に6人程度の班がいくつか設置されている、といった仕組みでした。当時は、飼育課だけで60~70人くらいのメンバーがいたと思います。
――小宮さんは、動物園の役割をどのように捉えていらっしゃいますか。
教育、研究、レクリエーション、そして自然保護が、動物園が果たすべき役割だと思っています。
――その中で管理職の一つである課長には、どんな役割が期待されているのでしょうか。
大きく分けて3つあります。1つ目は、動物がきちんと飼育されるように組織を管理すること。2つ目は、お客様へのご対応を考えること。そして3つ目は、仲間をきちんとまとめることですね。もちろん、こうした役割は係長にも求められるのですが、課長の方が管理の幅が広いのです。
なお、課長の中には現場の飼育員として育っていった人もいれば、動物園以外の都職員としてキャリアを積んだ人もいます。前者からは、「こういう新しい動物を飼おう」とか「こういう展示をしたらお客様が喜ぶのでは」などの提案がよく出てきました。一方、後者からはそうした提案が少なく、現場をよく知る係長などに任せる傾向が強かったと思います。
――小宮さんは飼育員の経験が豊富でしたが、係長や課長時代に新提案をする機会は多かったのでしょうか。
ええ、いろいろ挑戦をさせてもらいました。例えば、2001年に初来園したアイアイ(マダガスカルに生息する小型の霊長類。絶滅の危機に瀕しており、日本では上野動物園でのみ飼育されている)は印象深かったです。私が飼育係長だったとき、マダガスカルにある動物園の係長さんが上野動物園に実習に来て、そこで私たちと仲良くなりました。良い人間関係を築けていたので、マダガスカルがアイアイの海外飼育を認めたとき、上野動物園がすぐに受け入れられたのです。
アイアイが来園した当時の園長は、動物園以外でキャリアを積んだ人でした。そのため、動物のことは現場の私たちに任せてくれました。そこで飼育課長だった私はアイアイのために既存の動物舎を改修した仮設ケージで、約6年にわたってアイアイの生態を研究したのです。その知見を生かし、夜行性であるアイアイが暮らしやすい環境を整えながら、お客様にも見やすい施設を作ることに成功しました。
――園長さんが、小宮さんの提案をそのまま受け入れてくれたのですね。
そうです。園長が「好きなように飼っていいよ」と言ってくれたのがありがたかったですね。そういえば新人の頃、上司にガン(雁)の繁殖の件でも自由にさせてもらいました。
当時、国内でガンの繁殖に成功した動物園は一つもありませんでした。でも私は学生時代から、「ガンが繁殖する北極圏と近い環境を用意すれば繁殖させられるのでは?」と考えていたのです。それで蛍光灯を使った施設の建設を申請したのですが、いきなり新設するのは予算の関係で不可能でした。それで工事課の同僚に相談したらものすごく面白がってくれて、既存施設に100メートルくらいのコードを伸ばして蛍光灯を設置してくれたのです。そうしたら繁殖に成功して、それで園としてガンの新しい繁殖施設づくりを認めてくれたという流れでした。
――いきなり大きな予算をかけられない場合は、周囲を巻き込みながら可能な範囲のことをやる。そして成果を上げて上司に受け入れてもらうというスタイルで、小宮さんはやりたいことを実現していったのですね。
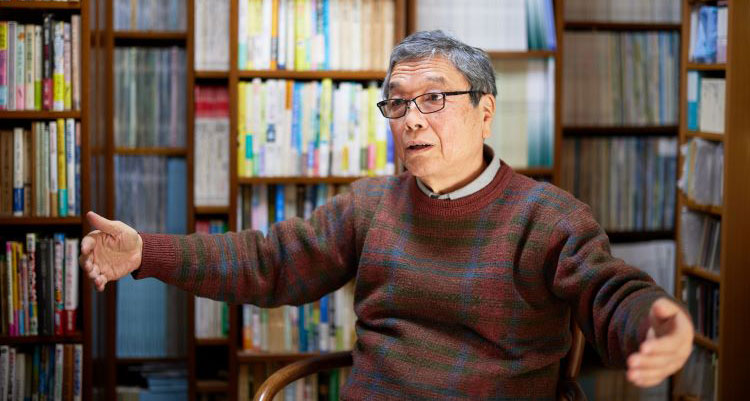
優れた部下に仕事を任せ、新たに生まれた手法を周囲に広げる
――動物を新たに飼ったり、斬新な飼育・展示法を試したりしたとき、現場のスタッフの中には負担増を嫌って反発するケースがあったのではないかと思います。そうしたとき、小宮さんはどうやってメンバーを引っ張っていったのでしょうか。
当時は、メンバーにリアルな野生動物を見せようと心がけていました。野生の動物はイキイキしていて、実に素晴らしいものです。その姿を知っていれば、現状の動物園における飼育法を「当たり前」と思わなくなり、もっと環境を良くしたいという意識が生まれてくると考えました。
――動物園のメンバーの自律性ややる気を引き出すため、小宮さんはどのようなマネジメントをされましたか。
動物好きで観察眼が鋭い人を見いだし、その人に新たな取り組みを任せるようにしました。
私が園長だった頃の上野動物園では、ホフマンナマケモノを屋外展示していました。最初は決められたエリアの中でのみ動けるようにしていたのですが、あるとき、1人の部下が「園内の通路にあるイチョウの木まで丸太でつなぎ、そこを伝って移動する姿をお客様に見せましょう」と提案してきました。私は、イチョウの木の周りにも柵を設置するのだろうと思ったのですが、部下は柵などいらないと言うのです。ナマケモノは細い枝をつかんで器用に動けるが、太い幹は抱けない。だからイチョウの木を降りることはないというのが彼の説明でした。納得して彼の言うとおりに施設を改造したところ、本当に柵など不要だったのです。このやり方はお客様にとって見やすく、その後はいろいろな動物園でも取り入れられました。
――なるほど、やる気と観察眼を兼ね備えた部下に任せたことで、新たな発想ややり方が生まれたわけですね。
そのとおりです。そして、そういう人が新たなやり方を編み出したら、他の人が広めていけばいい。
――多くの飼育員は「柵を作らなきゃ動物は逃げるだろう」という発想から逃れられないでしょうね。
でも、観察眼が鋭くて動物を愛している人には、斬新な発想ができるのです。そういう人がどんどん育っていくと、組織は面白くなると思いますね。
「やってみなはれ」の精神で部下のチャレンジを促そう
――小宮さんの著書を読んだのですが、動物園同士で研究成果を持ち寄るなどの交流が活発なのが意外でした。
動物園同士の交流は盛んになっています。また昔に比べると、動物の行き来も増えました。例えば私が飼育係長だった1996年、上野動物園が「ゴリラ・トラのすむ森」を作りました。当初はゴリラが1頭しかいなかったのですが、これでは絶対に繁殖などしません。そこで、周辺の動物園にいたゴリラを上野動物園に集めたのです。その結果、国内のゴリラはかなり増えました。千葉市動物公園から借りた「モモコ」などは、これまでに6頭もの子どもを産んでいるほどです。
一つ指摘しておきたいのは、動物の身体と心に配慮し、快適な環境で飼育する「アニマルウェルフェア」の存在です。昔の上野動物園では、ゴリラ、チンパンジー、オランウータンという3種類の類人猿を飼っていました。それぞれを別のエリアに分けていたため、1種類あたりの領域はかなり狭かったのです。ところが今は、ゴリラは上野動物園、チンパンジーは多摩動物公園のアフリカ園、オランウータンは多摩動物公園のアジア園に集約されていて、その結果、広くて快適な環境が実現できています。これも、動物の行き来が増えた背景の一つで、その先駆けとなったのが上野動物園でした。
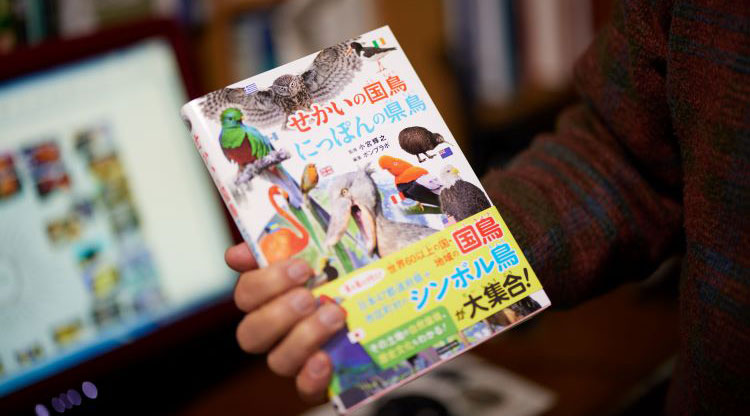
――やはり上野動物園は、いろいろな意味で注目されている存在なのですね。そして、そういう上野動物園が新たなやり方を発信したり他園と交流したりすることで、日本の動物園全体のレベルが上がっているのかもしれません。
さて、最後の質問です。係長、課長時代にはやりたいことに挑んで次々と実現し、園長時代にはメンバーの面白い提案を受け入れてきた小宮さんは、部下の良さを引き出すために何が大事だと考えていますか。
サントリーの創業者である鳥井信治郎さんは、「やってみなはれ」の精神で部下を伸ばしたそうですね。失敗を恐れず、部下のチャレンジを受け入れる。そういう態度が、マネジャーには必要だと私は考えています。
そういう意味で、私はマニュアルが嫌いです。マニュアルを渡すと多くの人は、マニュアルに書かれていること以外やらなくなってしまう。その結果、「やってみなはれ」の精神からは大きく外れてしまうのです。もちろん、マニュアルが必要なケースもあるんですよ。レッサーパンダやタンチョウのような希少種は飼育のノウハウが乏しいですから、私が中心となってマニュアルを作り、あちこちの動物園に配布したことがありました。でも、それが絶対というわけではありません。あるとき、マニュアルに「100平方メートル以上で育てること」とあるのを読んで、広い敷地があるのにきっかり100平方メートルのエリアで動物を育てているところがありました。敷地に余裕があるのだから、もっと広いエリアで育てる方が動物にとってはいいはずなのに、そういう発想が出てこないんですね。
――だから「やってみなはれ」が大事なのですね。まずは、部下が自分で工夫しながら動くよう促すという。
そうです。創意工夫できる部下を見いだし、その人にまずは任せてみる。そうして新たな発想を導き出すことが、管理職の大切な仕事なのではないでしょうか。
〈企業組織への示唆〉
小宮氏のマネジメント手法は、企業の管理職にとって重要な示唆を与える。小宮氏は「やってみなはれ」の精神で部下の自主性を尊重し、新たな挑戦を促した。企業においても、マネジャーは単なる指示役ではなく、個々が持つ能力を引き出し、創意工夫を支援する役割を担うべきである。優れた人材を見いだし、適切な権限を与えることで、組織全体の革新が促される。さらに、アニマルウェルフェアという視点を取り入れることで、動物の飼育方法だけでなく、動物園全体の運営を変革する先駆的な取り組みは、自社・顧客に限らず、業界の価値を最大化していくための参考となるだろう。
聞き手:千野翔平
執筆:白谷輝英
写真:梅原渉


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ