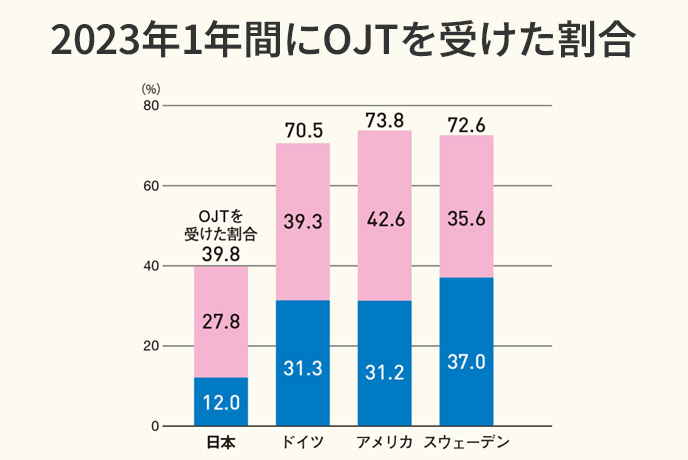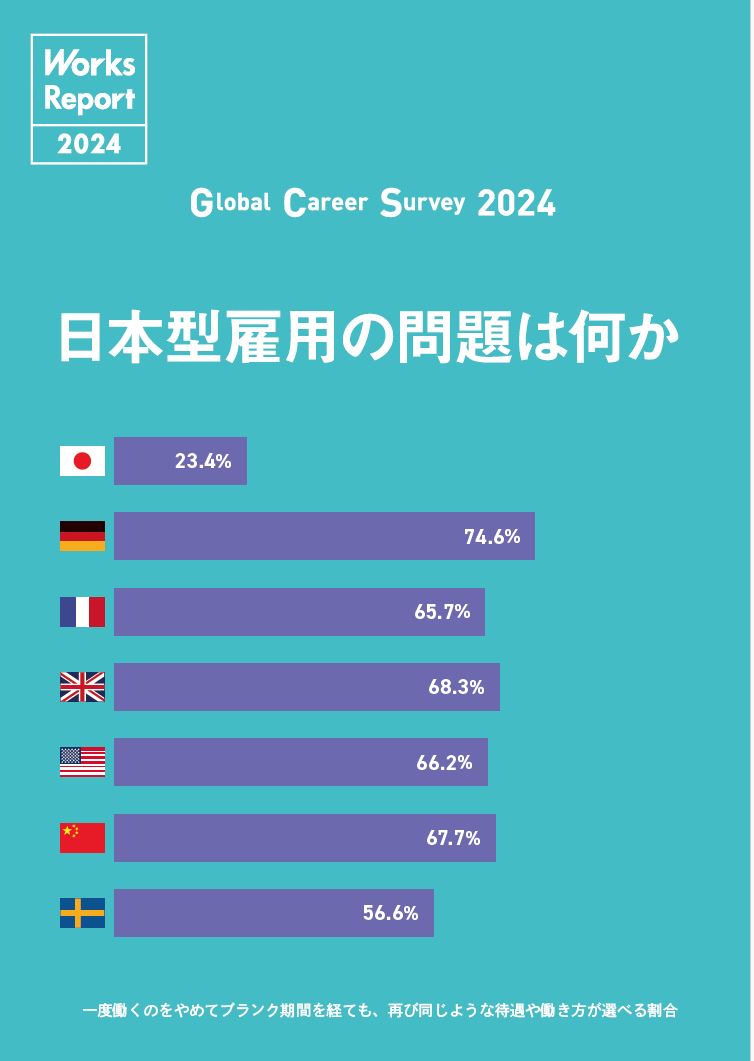異動・昇進を通じた人材育成は、新卒採用と定年制に対して合理的。だから簡単には変わらない
人的資源管理の専門家であり、日本の、特に大企業ホワイトカラーの雇用システムや、異動と昇進などの人事管理、また管理職に着目して研究されている八代充史氏に、異動・昇進を通じた人材育成の実態と、日本の雇用システムの変化の可能性について伺った。
日本的雇用の定義は、新卒採用と定年制
——これまでの日本型雇用、ないしは日本的雇用と呼ばれる雇用システムが存在したとされる時代の特徴について、どのようにお考えですか。また、それらは現在、変化しているのでしょうか。
私は、日本的雇用の定義を、新卒採用と定年制だと考えています。あとは長期雇用ですね。この3つを指標とするなら、日本的雇用は今もあまり大きく変化していないと思っています。
そもそも日本的雇用というものが存在したのかどうかについては、いろいろな考え方があると思います。実在したのは一部の大企業が中心でしたから。しかし、即戦力重視の中小企業、ベンチャー企業でも、いずれは生え抜きを育てたいという強い欲求が存在していたという意味で、一種の規範、いわば理念型のようなものとして、日本的雇用は存在してきたと思っています。
そもそも日本的雇用というものが存在したのかどうかについては、いろいろな考え方があると思います。実在したのは一部の大企業が中心でしたから。しかし、即戦力重視の中小企業、ベンチャー企業でも、いずれは生え抜きを育てたいという強い欲求が存在していたという意味で、一種の規範、いわば理念型のようなものとして、日本的雇用は存在してきたと思っています。
転職市場が活性化しているといってもやはり今も企業は、新卒採用に対して非常に強い志向性をもっているし、定年制とそれに伴う長期雇用も変わっていないし、法律ではなく判例法理に基づく解雇規制があるという性質上、今後も簡単には変わらないでしょう。
実は、この解雇規制が日本の雇用システムの最大背景だと私は思っています。解雇によって雇用調整を行うことができない日本企業は、社内の配置転換によって人員需給の調整を行わざるを得ない。そのためには、その会社固有の幅広さをもった、しかも他社と差別化できる自社コンピタンスを身に付けた人材を育成しておく必要があるわけです。そうした背景から、異動や昇進(縦の異動)、配置転換を通じたキャリア形成を行う。私は、これこそが日本のホワイトカラー雇用の本質なのではないかと思っています。
異動による雇用調整が可能なのは、人件費の管理を人事部門が行うから
——そのような仕組みは、期待する部門に人材を投下できるという意味ではとても合理的に見えますが、なぜ他国ではそうした需給調整システムがとられてこなかったのでしょうか。
この人員需給が可能になる背景には、日本の場合、人件費を管理しているのが、個々の部門ではなく人事部門だということがあります。日本はもともと、人事部と労働組合が団体交渉して総額人件費を決め、各部門に配分する慣行があります。しかし海外のように部門の予算で管理する形だと、部門を超えた異動は、日本のようには行いづらくなります。ただ逆にいえば、日本で職種別採用が根付かない原因もここにあるといえます。入り口の段階で職種別採用を行っても、やがてそれらの職種で余剰人材が生じたときに、部門内では対処できないんですね。そのため、一度、職種別採用を導入しても、部門間異動を行いやすい従来の職能資格制度に戻ってしまう企業が多いように思います。
——昨今日本でも増加傾向にある、専門職についてはどうお考えですか。
——昨今日本でも増加傾向にある、専門職についてはどうお考えですか。
理系の場合は学会活動や学位があるので専門職として成り立ちやすいですが、文系の場合、大学の教育との接合性、あるいは企業横断的な職業資格のどちらかがないと成り立たないでしょう。たとえばアメリカには、人事ならSHRM(Society for Human Resource Management)という団体の人事管理1級、2級などの資格があって、どのぐらいのレベルの実務ができるのかを見る指標として企業横断的に使われています。日本でもかつて似たようなものを作ろうとしたのですが、パテントの問題などがあってうまくいきませんでした。大学の教育との接合性にしても、企業横断的な職業資格にしても、日本ではまだしばらくは難しいのではないかと思います。
でもだからといって、日本に専門職が本当にないのかというと、そうではない。日本の場合、非常に属人的な形で存在するんです。よく、「あの人に聞けばわかるよ」と言われるような人がいますよね。日本の企業はメンバーシップ型なのでそういう属人性が重んじられる。その部門になんとなく長くいるうちにいつの間にかその部門のキーパーソンになっていく。日本の場合、そういう形で事実上の専門職化が行われてきたように思います。
遅い昇進、小幅なラダーで格差を最小化し、モチベーション管理
——日本の雇用システムの特徴として、昇進が遅いことが指摘されます。アメリカのようにスターをどんどん昇進させる早期選抜が日本では行われないのも、異動を通じた育成システムと関係するのでしょうか。
異動を通じた育成は、一部の人だけでなく全員を潜在的エリートとみなす育成なんです。長期雇用が前提なので、早くから、どうせノンエリートなんだと開き直られてしまうと会社も困るんですよ。だから決定的な差をつける時期をなるべく遅くしようと、昇進を遅くし、小幅のラダーを上がっていく仕組みをとってきたのです。できるだけ格差の少ないインセンティブでモチベーションを維持していこうということですね。早期退職優遇制度の適用年齢の下限は、45歳ぐらいだと思いますが、この辺までは皆に可能性があるような絵を見せながら引っ張っていくわけです。これについては、今後、役職定年制が廃止されたり、定年が延長されたりしていった場合にどうなるのか、会社としても今、頭が痛いでしょうね。
一方で、このやり方だと、2:6:2でいう上の2の人のモチベーションを下げかねません。そこに対しては、日本の企業は、誰が見てもエリートだと思うようなコースやポジションを経験させて、「君は将来のエリートだよ」と匂わせるという、金銭や昇進スピードとは全く異なる形の報酬を作り出し、離職を阻止してきた。今後このやり方が、通用していくのかはわかりませんが、これまではそれが日本企業のやり方だったのだと思います。
職能資格制度は建前。
日本の昇進制度の実態は学歴別年次管理
——そうした遅い昇進、小幅のラダーでの昇進では、職能資格ないしは職務能力の定義もかなり細かな管理が必要になりそうです。どう行われていたのでしょうか。
職務能力は、多分、あまり数量的に細かく定義されていない。どこまで客観的に定義することが可能で、どこからが評価者の判断なのかという問題は常にありますし。職能資格要件とは、そういうものがないといい加減に評価していることになってしまうから用意した、アリバイ的な意味での存在なのだと思います。
要するに、昇進を遅くし、ラダーを小幅にする昇進制度は、学歴別年次管理の仕組みなんです。それを、いや年功序列じゃないんだよ、と正当化するために、建前として掲げられてきたのが職能資格制度なんですね。従業員も、年功で上がっているんじゃなくて、上司が査定してちゃんと能力が認められて上がっているんだと思えた方がハッピーです。誰も不利益を被らない。だからいまだに続いている。そういう、人の心の中に根付いたものはなかなか崩れませんね。ですが、職能資格制度は能力の評価でありながら降格がないという大きな欠陥を抱えています。これは非常に問題だと思います。
異動と昇進による企業主導の育成は、結局のところずっと変わっていない
——日本でも、成果主義の風潮が強まるとともに、昨今ではキャリア自律にも関心が集まっていますが、日本の異動と昇進を通じた企業主導の育成は、今後も継続していくのでしょうか。
成果主義の議論は、これまでも経済危機のたびに盛り上がるのですが、日本ではなかなかうまくいかないですね。成果を重視するのであれば、自分で選択した職種や業務で能力を発揮することが必要になりますが、今、議論されている職種別採用とか社内公募も、どちらかというと、新卒の離職リスクを低減させるための意味合いが強いように思います。
キャリア自律についても、もともと自分のもののはずのキャリアが、会社に預けているうちにいつの間にか会社のものになってしまった面もあるので、いきなり自律しろというのは酷な話だと思います。これは時間をかけて少しずつ変わっていくしかないと思います。
恐らく、企業主導型の異動やそれを通じて人材育成を目指す仕組みは今後も維持されるでしょう。新卒採用と定年制のもとでは、一定の合理性がある以上、必ずしも変わっていく必要がないからです。
しかし、従来のやり方が何も変わらないということではないと思います。これからは労働力不足の影響が非常に強くなるはずです。労働力が不足してくれば、会社は従業員に歩み寄らざるを得ないので、転勤、能力開発、人事異動についても、従来よりは時間をかけて、個人に納得してもらう仕組みを作るとか、あるいは転勤そのものを減らしていくとか、転勤しないことをペナルティにするのではなく、転勤する人にインセンティブを与えるなど、企業がイニシアチブをとり続けつつも、制度を変えていく必要は生じるでしょう。
同様に、新卒採用や定年制、長期雇用の大きな枠組みが変わらないからといって、日本の雇用が変わらず旧態依然のままだということではない。その大きな枠は変わらずとも、これまでも中身はいろいろ変わってきていると思いますし、そうした企業というものの変化、適応能力を、我々は決して過小評価してはいけないというふうに思います。
聞き手 山口泰史、萩原牧子、孫亜文、石川ルチア
執筆 荻原美佳(ウィズ・インク)
執筆 荻原美佳(ウィズ・インク)
プロフィール

八代充史氏
慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。日本労働研究機構研究員、慶應義塾大学商学部助教授を経て、2003年より現職。専門は人的資源管理論,労働経済学。主な著書に『大企業ホワイトカラーのキャリア─異動と昇進の実証分析』(日本労働研究機構、1995年)、『人的資源管理論ー理論と制度(第3版)』(中央経済社、2019年)、『日本的雇用制度はどこへ向かうのか一金融・自動車業界の資本国籍を越えた人材獲得競争』(中央経済社、2017年)、『問いから考える人材マネジメントQ&A』(共編著、中央経済社、2024年)など


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ