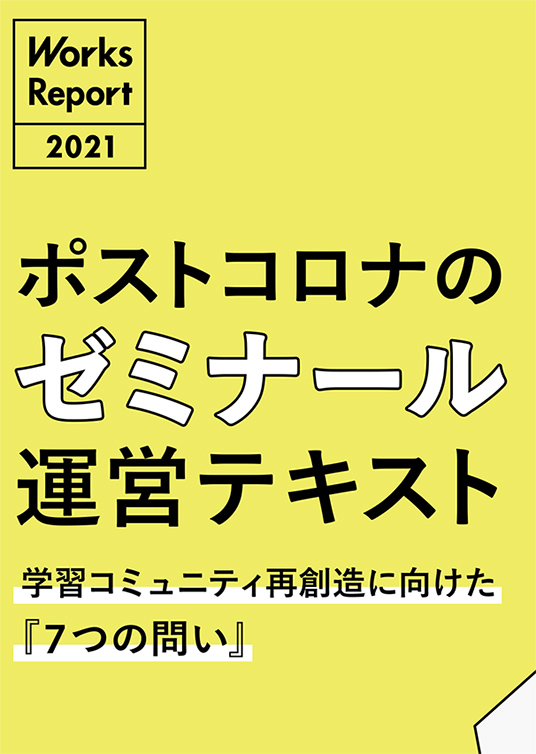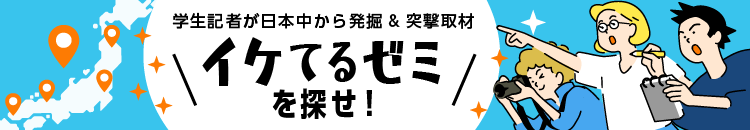
アートと人を「愛」でつなぐ【Vol.7 多摩美術大学芸術学科フィールドワーク設計ゼミ】
イケてるゼミ第7弾は、芸術系のゼミ。専門分野は美術ジャーナリズム。ゼミで独自のアート誌を発刊する、という実践的な活動をしている。何かテーマを決めて、取材し、記事にする、という活動は、ゼミナール研究会・学生記者の活動とも大きく重なるところがある。そんなアート誌作りのプロセスから見えてきたものとは? 学生記者はどこに心惹かれたのか?
取材・文 中村春菜(淑徳大学3年)

写真:小川教授と取材に参加してくださった学生の方々、取材陣で一枚(左から齊藤さん、岩田さん、岩﨑さん、岡村さん、小川教授、足立さん、中村〔学生記者〕、髙久さん、中野さん、豊田〔ゼミナール研究会メンバー〕)
【Seminar Data】
教員:小川敦生 教授
多摩美術大学 芸術学科
専門分野:美術ジャーナリズム
開設年:2012 年
構成員:3、4 年生 6~10 名程度
位置づけ:選択必修科目
単位数:通年科目で 4 単位
卒業研究:有
大学の中にある出版社
「単なる文章講座ではなくて、実際に雑誌を発行するのが一番の経験になるんじゃないかと思ったんです。本学に就任してまず自分の中で決めたのは、このゼミを小さな出版社の編集部にしようということでした。実際に市販誌を作っている出版社の編集部と同じことをできるだけやっていこうと、最初から意識したんです」
小川教授の語りはおだやかに、しかしこのゼミの特異性をはっきりと示していた。
写真:フィールドワーク設計ゼミが刊行しているアート誌「Whooops!」。「東京でキリスト教美術を見る」「平成リバイバル」など様々な記事が掲載されている
訪ねたのは多摩美術大学芸術学科 八王子キャンパス。八王子に広がる緑豊かなキャンパスで、小川敦生教授が担当するフィールドワーク設計ゼミは活動している。所属学生は 10名ほど。少人数でありながらWeb記事の制作や SNS の運営を行い、年に3回刊行するオリジナルのアート誌「Whooops!」は多摩美術大学のキャンパスのみならず、青山ブックセンター本店や、東京・千葉・大阪・京都・福岡のアートギャラリーなど多くの場所に設置されている。研究発表を主な活動とする一般的なゼミとは一線を画したこのゼミは、なぜこういった活動内容になったのだろうか。小川教授の冒頭の言葉は、その理由を語ったものだ。
市販誌の編集部を再現したというゼミ。一見、大学の学びと結びつかないその活動は「学生自身が経験すること」を主眼にしている。そこには小川教授が大学教員になる以前、雑誌編集部で働いていた経験が影響しているようだ。
「『日経エンタテインメント!』という雑誌の編集部に配属になったのですが、最初はまったく記事の書き方を教えられなかったんです。いきなり取材してこいって言われて、とにかく原稿にして提出しました。それを、編集長が 一から百 まで書き直した。すると、稚拙な文章としか言えなかったものが、普通の雑誌に載っているような記事になったんです」
その経験に大いに感動した小川教授は、学生にも同じ経験をしてほしいと思い、指導方法としてゼミの中に雑誌制作を取り入れているという。さらに、商品として通用する一般誌レベルのアート誌を発行することを目標にした。出版社の編集部での経験は活動の随所に生かされており、それがこのゼミの特異性として表れていた。
「ゼミ自体を出版社にしてしまおうというのが、目指すところです。ですから、学生の皆さんもアクティブでないと成り立たないし、実際、とてもアクティブです。半年かけて俳優の竹中直人さんのアポイントを取ったり、カメラマンとして巣立ったゼミ生がいたりしますが、すべて学生の自主的な活動なんです」
ゼミ生が記者として自分で記事のテーマを決めて、自分で取材を進めること。それは非常に大きな経験になる。企画立案に始まって取材・執筆・誌面デザインや印刷会社とのやり取りまで、様々な場面で学生の自主性が重んじられる。実際、授業で行われる企画会議の中で、学生の企画案はよく通るようだ。「漫画家の取材やアート双六の付録化など、私には思いもよらないような面白い企画案がよく出てくるんですよ」と小川教授。教授が考える理想と実際のゼミの活動が完全に一致しており、学びの場としての完成度の高さがうかがえた。
そのような活動を経た学生たちは、4年次の卒論を教授からのサポートも受けながら完成させ、就職先を自分の手で見つけていく。取材時には就職先が決まっていたある4年生は、「最終面接に自ら撮影した写真が表紙に使用された『Whooops!』を持参したら、ゼミの活動によって育まれたデザインスキルや文章能力が評価されました」と語ってくれた。スキル面はもちろん、自らの学びの成果として雑誌を持ち込んだ行動力も、このゼミの活動で育まれたのかもしれない。
愛を言葉に アートに向き合う人生

写真:取材中の小川教授
小川教授は、アートと共に人生を歩んできた。
小川教授の両親はアートへの理解があり、幼少期から家には音楽全集や美術全集がそろっていたという。テレビCMを見たのがきっかけで親にせがんで出かけたオーケストラのコンサートに触発されて10歳の頃始めたヴァイオリンは生涯の趣味となり、大学生の頃は学業よりものめり込んでいたという。社会に出た後も、美術雑誌「日経アート」の編集に 10 年、日本経済新聞の文化部の美術担当記者として7年間在籍するなど、世の中にアートの魅力を発信し続けてきた。
「環境に恵まれていたと思います」と幼い頃のことを思い返す小川教授は、幼い頃から知らず知らずのうちに音楽やアートの世界の虜になっていたのだろう。では、小川教授をとらえて放さないアートの魅力とは、いったい何なのか。それは、「非日常」にあるという。
「日常生活って、歯磨きだとか掃除だとか入浴だとか、ルーチンワークをしないといけないじゃないですか。そういうところから離れた世界に連れて行ってくれるのがアートの魅力なんです。たとえば、ピカソの絵なんて、見ようによっては落書きとしか思えないのに、世の中にはこんなものの見方や絵の描き方もあるんだということを教えてくれる。面白いですよね」
常人には至ることのできないアーティストの発想が形となった作品の数々。それらに接することによって、気づきや感動をもらえるのだ。小川教授がアートジャーナリズムの道に進んだのは、その気づきや感動を広めたい、というアートへの愛の発露だった。小川教授のアートへの愛は、作品に接する際のスタンスにも強く表れている。
「美術品にはアーティストの魂が宿っているので、人間だと思って向き合っています。そう意識して取材すると、返ってくるものもちょっと違うんです」
「愛をもって作品と接し、いい関係を保つとハッピーになれる」とも小川教授は言う。人と人が愛をもって接するとお互いが幸福な気持ちで満たされるように、芸術作品と向き合う時にも愛をもって臨むことによって、愛が返ってくる。「美術品や展覧会を取材する際に、取材者が作品を愛せるかどうか。それによって理解が変わり、記事で表現できることの次元も変わってくると思うんです」という小川教授の言葉には、あふれんばかりのアートへの愛と、アーティストを尊重する姿勢が感じられた。
20 年以上雑誌や新聞で美術担当記者としての活動を経た小川教授が 2012 年に教員として着任した多摩美術大学芸術学科では、30年ほど前に美術批評家が設立に関わった経緯もあり、「言葉」を重要視しているという。
「美術にしても音楽にしても、それを 100%言葉で表現することは不可能です。ただ、人間は言葉の動物なので、アート作品を制作するにしても、音楽作品を制作するにしても、必ずどこかに言葉が関わっている。この美しい風景をスケッチブックに描きとめようとか、恋人への愛を歌で伝えたいとかは言葉で考えるわけです。さらに、言葉を介在することによって、アートの表現の可能性も広がっていく。戦争をやめさせたいけど、絵でアピールするにはどんな風に描けばうまくたくさんの人に伝わるかとかを徹底的に言葉で考える。そのうち、思いもよらないような表現が突如として生まれたりする。なので、言葉ってアートにとって、すごく大切なんです」
アートという正解のない曖昧な存在と、ジャーナリズムという客観性や正確性が求められる概念。一見、水と油とも思えるが、できるだけ努力をしてアートをまず論理的な言葉で表現してみることには大きな意味がある、と小川教授は言葉を一つひとつ、選びながら語った。フィールドワーク設計ゼミの指導には、当然のようにこの考え方が反映されているという。作品写真が掲載されている記事においても、まずそれがどのようなものかを、あえて言葉で説明する。それによって、それまで見ていなかった作品の特徴が見えてくることがある。「学生の皆さんにも、ぜひそういう経験をしてほしい」と紡いだ小川教授の言葉には、記者活動の経験に裏打ちされた、力強い説得力があった。
現地の言葉を届ける取材
アート誌「Wooops!』の制作は、ゼミ生と小川教授による企画会議からスタートする。普段は自由に各ゼミ生が企画案を提案するが、昨年10月に発行したVol.35では小川教授からの提案で「SDGs×アート」などいくつかの特集になりそうなテーマに沿った企画案も提出することになり、ゼミ生はそれぞれ2案を準備した。企画会議では、学生がそれぞれの案を短くプレゼンし、教授だけでなくゼミ生の意見やアドバイスも交えて、企画が決まる。そして、ゼミ生が自分でアポイントを取り、実際に取材活動を進めていくことになるそうだ。
「でも、うまくいかないことも多いんですよね」
そう言いながら、ゼミ生たちは互いの苦労を分かち合うように顔を見合わせた。提案する企画案は多くの場合、ゼミ生が前々から好きだったり、気になっていたりした有名なアーティストを取材対象とすることが多い。しかし、有名であればあるほど多忙なので、かなりの確率で取材を断わられるという。それでも当たり前と思ってめげずに、企画会議で提案した別の案を成立させるべく努力し、それでもダメならさらに新しい案を提案するなどして、取材を受けてもらえるまで挑戦し続ける。「うまくいかなくても、次がある」。取材中、笑って語られたこの言葉は、これまで積み上げてきた苦労を感じさせるとともに、取材をやり遂げてきたことによる確かな自信にあふれていた。
アポイントが取れ、取材を無事終えると、ゼミ生は原稿の執筆に取り掛かる。初稿完成後、小川教授からの添削があり、何度か修正をして完成原稿ができる。次に、Adobe InDesign CCというパソコン用のソフトウェアを使って文章と写真や図を配置する誌面レイアウトの作業に移る。どの写真を大きくするか、見出しをどう置くかなど、考えなければならないことは多い。レイアウトを小川教授に提出し、アドバイスを受けて整えたら、今度はプリントアウトしてゼミ生全員で校正作業に移る。他のゼミ生の記事がどのように出来上がっているかについては、お互いにこの段階で初めて知ることが多いという。逆に言えばそれまでの取材・原稿執筆・レイアウトなどの作業は、自分自身との闘いだ。読むのと書くのとでは大違いで、実際に記事を制作して人に普通に読んでもらえるようにするのは想像以上に難しく、ともすれば心が折れてしまいそうになることもある。しかし、小川教授の的確な指導があるので、迷えるゼミ生たちは安心して誌面の制作に臨むことができているという。「校正の時には、私が見逃している間違いを発見するなど、ゼミ生たちは、なかなかしっかりしていると思いますよ。文章もだんだん上手になっていく」と小川教授。良好な信頼関係が形成されているようだ。
記事を書いてみて、「あ、こんなことも聞いておけばよかった」と思うこともよくあるという。あるゼミ生は次のように話す。
「取材の時に、原稿で使える客観的な言葉を現場で引き出そう、と意識するようになりました」
言葉を引き出すのは意外と難しい。ジャーナリズムには客観性が求められるが、アートには曖昧だったり多義的だったりする側面がある。そのため、両者を一つの記事の中で成り立たせるには的確な言葉が必要になるのだ。しかし、アーティストがそんなに都合よくしゃべってくれるわけでもない。ある3年生のゼミ生は、最初の頃は記事が感想文のようになってしまっていた。しかし、小川教授からアドバイスをもらうことで「大多数の人に文章を見られる意識」を持つようになったという。客観性や事実を重視した、人に読んでもらうための文章づくを日々教えられる中で、記事の完成形を意識して取材することを心掛けるようになったのだ。
「できるだけその人の見え方やその人だからこそ聞ける情報、記事に書ける言葉を、引き出そうと思っています。作品には形があってもアーティストの思想に形はないので、作品の見た目通りに伝えても、肝心な意図を間違って書いてしまうことがあるんです。だから僕は、アーティストの言葉を大切にして、記事でも忠実に使うようにしています」
3年生のゼミ生は小川教授から教わったことについて、そう語った。
取材の現場で聞いた言葉を、曲げることなく読者に伝えること。記事制作という経験に裏打ちされた、ジャーナリズム、ひいては言葉を使って表現することの本質が垣間見えた瞬間だった。

写真:インタビューに答えてくださった学生の方々。ありがとうございました
うまくいかないことも多いうえに、個人作業のため責任も個人で負うことになる。そんな中でも精力的に活動するゼミ生のモチベーションは、何なのだろうか。
「やっぱり、雑誌の発行が一番のモチベーションだと思います。取材も、大学生だからこそ受けてもらえるということもかなりあるんです。自分が興味のあることを聞くことができる、記者だからこその特権も、モチベーションの一つです」
「写真を撮りたい、と思ってこのゼミに入ったので、雑誌の表紙に自分の撮った写真を使ってもらえた時には、やりがいを感じました」
大変な活動だからこそ、得られる達成感は大きい。自分の手がけた記事が実際に手にして読める雑誌の形になる嬉しさは、計り知れない。号を重ねるごとに洗練されていく記事は、確かな学びのしるしとして、残り続けるのだろう。
学生と教授 伝わる愛の輪
「教授を一言で表すと…、やっぱり親しみやすいから…、『愛され』でしょうか」
横に座る小川教授の顔をうかがいながら、ゼミ生が言う。普段は親しみを込めて学生からは下の名前である「あつお」と呼ばれているという小川教授。取材の場が小川教授の話題になったとたんに俄に沸き立つほど、学生からの人望は厚い。ゼミの卒業生が小川教授の白黒顔写真シールを製作したり、ゼミの公式 X (旧Twitter)では、教授の本日の様子を投稿するためのハッシュタグ『#今日のあつお』が使われたりする。前年度の活動では、そのタグをつけて毎週のゼミのたびに投稿されていたというのだから、人気は推して知るべしだ。もちろん、人気は卒業生のみのものではない。小川教授が大好きでフィールドワーク設計ゼミへの所属を決めたゼミ生もおり、その親しみやすさと学生からの信頼は、言葉にせずともはっきりと伝わってきた。

【小川ゼミ X(旧Twitter)アカウント】 https://twitter.com/aogawageige77

写真:ゼミのXアカウントで「#今日のあつお」のハッシュタグをつけて投稿された写真。卒業生が作成した小川教授の白黒顔写真シールは現ゼミ生に受け継がれている
その信頼関係は、小川教授の学生への接し方によって構築されている。学生と接する時に特に気を付けていることとして、小川教授は「多様な視点」を意識している、と話した。
「自分としては、知識を教えるということはあまり重視していない。どうやって視点を多方向から持つか、どういう視点で見るとどういう考えが増えるのか、ということをかなり意識しています」
知識は当然有用だが、本を読むだけで習得できるものも多い。それ以上に大切なのは、「知識とどう向き合えばいいか、ということだ」と小川教授は言う。多様な視点を持つことで、一つの作品やできごとに対する考え方が変わってくる。自分が今まで思ってきたことばかりが正しいわけではないことに気づくこともある。小川教授は「美術作品は、多様な視点を提供してくれる格好の素材でもあるのです」とも。学生の自由で柔軟な考えが伸びている理由が見えてきた。この指導方針はおそらくゼミ生が持つ積極性のさらなる飛躍につながっているのではないだろうか。
「学生から影響を受けることも、結構あります。たとえば雑誌のどこかに空白ページができた際に、積極的に『この企画を追加しましょう』『この企画のページを増やすともっとたくさんいい作品を紹介できます』と提案し、すぐに実行に移してくれる。学生との付き合いは、なかなか刺激的です」
自分もアクティブでいようと考えてはいるが億劫なことも多いから身を引き締められる、とにこやかに話し続ける小川教授は、心なしか楽しそうに見えた。
フィールドワーク設計ゼミは、2012年の 1期生から活動的な学生が多かったという。開設からわずか約3か月で雑誌の刊行を実現した裏では、教授の関与しない、学科を超えた学生のネットワークが大きな役割を果たしていた。今も使われている「Whooops!」のロゴデザインと猫のマークは、当時グラフィックデザイン学科に所属していた、ゼミ生の知人の学生が作ったものだという。小川教授は語る。
「こういう媒体をゼロから作るのは、やってみて初めて大変さがわかる。にもかかわらず、学生の力で実現できたことにはびっくりしました」
個々の学生に合わせた丁寧な指導、長い時間をかけて学生の原稿を見てくれる面倒見のよさは、小川教授がアートそのものはもちろん、学生やアートに関わる人たちに愛をもって接しているからこそのことだ。学生たちもそれに応え、伸びやかに活動する。それが、雑誌の形となって、この世に現れる。アートに魅了された小川教授から、アートジャーナリズムを通して学生へ、そして読者へ。アートへの愛の輪はつながっていくのだろう。
「先生、愛されてますね」
「愛があってよかった」
記者の言葉に小川教授が返すと、場は笑い声に包まれた。「また一つ愛が伝わった」のかもしれない。
【Student’s Eyes】
■小川教授もゼミ生の皆さんも、 取材に快く応じてくださって非常にありがたかったです。 経験あるのみ、と言うと旧時代的な場所を思い描いてしまいがちですが、 実際に感じる雰囲気はまったく違います。 取材前のアンケートで優しいお言葉をくださったり、 原稿執筆中に出来上がった「Whooops! Vol.35」をデータで送ってくださったり、本当にありがとうございました。現地の言葉を曲げることなく届ける、という取材の姿勢をはじめ、 私自身、大学や学生記者活動で記事を書くことが多いため「なるほど」と勉強になりました。(中村)
■学生たちの意欲が小川教授にも影響を与え、互いに刺激を受ける信頼関係が築かれています。この環境は、学生たちの個性を伸ばすための重要な要素だと感じました。学生が記事を執筆するうえで欠かせない「アイデア」については、小川教授が学生のアイデアの引き出しを開けるための手助けをしている印象を受けました。ゼミで得た経験が、学生たちの大学生活全体における個々の成長や学びの幅を広げてくれるのだと思いました。 (上野真凛/淑徳大学3年)
【ゼミナール研究会 学生記者EXPO】のお知らせ
連載記事「イケてるゼミを探せ!」を企画・制作している学生記者が、自分たちのこれまでの活動を報告するEXPOを2/26にハイフレックスで開催します。
新たな仲間の募集も兼ねた場です。ぜひご来場ください。
概要、お申し込みは、下記をご参照ください。
詳細はこちら


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ