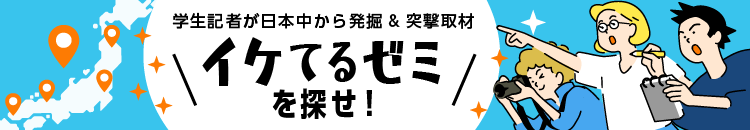
企業からの「よくできました」で終わらない。成長剤は厳しい批評【Vol.11京都産業大学 国際関係学部 植原ゼミ】
イケてるゼミ第11弾、植原ゼミの専門分野は「国際ビジネス」。ゼミ生たちは複数のグループに分かれて一つの企業を徹底的に分析。ディスカッションを重ねて仕上げた「海外展開の提案」を、直接その企業に赴いて行うという。今回学生記者は京都まで足を運び、その「企業訪問」の現場に潜入。ゼミ生たちの学びの大きさ、それを生み出す植原教授のこだわりに迫った。
取材・文 東島 琉奈(明治学院大学3年)
【Seminar Data】
教員:植原 行洋(うえはら ゆきひろ)教授/京都産業大学 国際関係学部
専門分野:国際ビジネス、中小企業の海外展開
ゼミ開設年:2019年
構成員:3・4回生(各学年13~15名)
位置づけ:必修のゼミ
単位数:8単位(3・4回生合計)
卒業研究:有

イントロダクション
大学の講義や講演の質疑応答で、静まり返る教室を見たことがあるだろうか。学生にとって、専門家である教員や講師に、直接質問を投げかけたり、まして意見を伝えたりすることは容易ではない。しかしながら、学生が専門家に積極的に質問し、意見を述べ、さらには「提案」までしてしまうゼミがある。
それが、京都産業大学 国際関係学部「植原ゼミ」だ。植原ゼミは「国際ビジネス」を主軸に置き、学生たちが果敢に「外」へ飛び出していくという学内でも有名なゼミナール。そんな場所で、ゼミ生たちは一体どのような挑戦を続けているのだろうか。今回、筆者は植原ゼミにお招きいただき、期待に胸を膨らませながら、秋めく京都へと降り立った。
ゼミ生VS国際ビジネスの第一線
植原ゼミで最も特徴的な活動の一つは「企業訪問」だ。ゼミの学生たちは、京都が誇る大企業から面白いビジネスを展開する中小企業まで、多様な企業を訪れる。しかしながら、ただの「訪問」では終わらないのが植原ゼミ流。学生たちは、時間をかけて企業を分析し、訪問先の担当者に「その企業の商品をどのように海外展開できるか」を提案する。この「海外展開の提案」こそ、企業訪問の一大イベントなのである。
植原ゼミの企業訪問で行う「提案」は、マーケティングをイメージしてもらうと分かりやすいだろう。まず、植原先生によって、「どこの国に商品を展開するのか」といったテーマが設定される。それから学生たちは複数のグループに分かれ、活動をスタート。3週間という準備期間の中で、ゼミ生たちは扱う商品の強みや弱み、海外市場の動向、現地のライフスタイルや消費の嗜好などを研究する。もちろん、商品を海外に広めるために、効果的な宣伝方法や販売の仕組みを提案することも忘れてはならない。
学生たちは、質の高い提案を作り出すためにディスカッションを重ね、授業外でも集まって準備を進める。「それくらいしないと無理、終わらないってパターンが多いんです」と3回生の玉川さんは話す。しかし、いざ準備に取り掛かった時の、彼女の心境はこうだ。「あー、来たな。よし、やったるか!」。筆者は思いがけない前向きな言葉に耳を疑った。彼女だけではない。取材を受けたゼミ生全員が「必ず成功させてやろう」という前向きな気持ちを持って取り組んでいる。彼ら彼女らは、企業への提案が簡単な活動ではないからこそ、自分が成長するための大きなチャンスと捉えているのだ。
一方植原先生は、企業訪問での「提案」は、学生たちが企業のビジネスを「自分事」として捉えるきっかけになると話す。さらに、担当者の前で、緊張しながらも意見や提案を述べる経験は、学生たちの自信にもつながるという。植原先生はこれまでの職歴を活かして過去に繋がりのあった企業やビジネスパーソンに声をかけ、訪問の場をセッティングしている。「企業側から活動への参加を断られることもあって、正直アレンジをするのはしんどい時もある。だけど、今後もできる限りは(企業訪問を)やっていきたいと思っています」。少しでも多く学生たちに学びを届けようとする植原先生の思いが伝わってくる。
植原ゼミのコミュニティとしての雰囲気について尋ねると、4回生の佐賀山さんは、ゼミ内のモチベーションが特別高いとは思っていないと話す。全員で張り切るというよりは、互いの得手不得手を理解し、地道に準備を進めていくだけだという。「だけど他のゼミに行ったら多分浮くとは思います」と彼女は付け加えた。

取材にご協力いただいた植原ゼミの4名
左から佐賀山奈央さん(4回生)・玉川愛菜さん(3回生)
俵隆之亮さん(4回生)・古家一輝さん(3回生)
「私は苗床の管理人」と植原先生
「学生主体」の活動が徹底された植原ゼミ。それは、教員である植原先生の関わり方によく表れている。海外展開の提案では、植原先生は途中経過を確認するのみで、最終成果の提案時に初めて聞く部分もある。教員が手を加え過ぎてしまえば、成果物から学生たちのオリジナリティが失われてしまうからだ。
植原先生は言う。「教員は『苗床の管理人』。苗が育つように土壌を整備するのが私の役割なんです」。もちろん、ガーデニングの話をしているのではない。「苗床の管理人」とは植原先生のゼミでのスタンスを表している。先生のこだわりは「大学内で完結しない学び」。植原ゼミでは、企業訪問だけでなく、ビジネスパーソンとの意見交換、駐日外国大使との交流など、外部の人と積極的に対話をする機会が豊富だ。しかし、先生はあくまでそれらの機会(苗床)を提供するだけ。どのような準備をして臨み、そこでどのような学びを得るのかは、全て学生に委ねている。ゼミ生を積極的に外へ連れ出す活動は、苗を生長させるための「肥料」ともいえるだろう。植原先生は自分が提供した苗床で、ゼミ生たちがどんな種を蒔くのか、それが花開くのか、または枯れ果ててしまうのかを、毎年見守っている。
植原ゼミでは学生がゼミの「舵取り」を任される。ゼミ長などの役割はないため、全員で意見を出し合いながら役割分担し、活動を進めていくことになる。教員が先導しないからこそ、学生一人一人がゼミ活動の命運を握る。「だから、学生は頑張んないといけない、ということはありますね」と植原先生は話す。ゼミ生たちが先生の期待に応えるのは一筋縄ではいかなそうだ。
先生との「距離の近さ」が学生の原動力になる
学生たちにとって、企業やビジネスパーソンと関わる機会は貴重だ。だからこそ、毎回の活動で、時間をかけ、質の高い成果物をつくりあげていく。しかし、いつでも100%の力を出すことは簡単ではないはず。彼ら彼女らが頑張れる理由は一体どこにあるのだろう。
取材前に実施したアンケートでは、ゼミ生全員が「第一志望」で植原ゼミを選んでいた。志望理由を伺うと、3回生の古家さんは開口一番、「植原先生だからです」と答えた。ゼミ活動で帰宅が遅れた古家さんが、植原先生に車で送ってもらった時のこと。その車内で、彼は植原先生から「今日の学びは何だった?」と問いかけられた。古家さんが自分なりにまとめた言葉を話したところ、先生は「確かに、そこ学びだったね。俺は気付かなかった」と素直な感想を伝えてくれた。「(植原先生は)すごく謙虚な方。何歳になっても、誰からでも学びを得ようっていう姿勢、僕はすごく尊敬していて」。彼の言葉に、他のゼミ生も同意するように頷く。植原ゼミを志望する理由は様々挙げられたが、一貫していたのは「植原先生の人柄」だった。
4回生の俵さんは、ゼミ生が頑張れる理由として、植原先生との「距離の近さ」を取り上げる。「経歴からしたら、(植原先生は)本当にめちゃくちゃ凄い人なんですよ。なのに謙虚で僕たちをめっちゃ褒めてくれる。そういうところが、ゼミ生が頑張れる理由なのかなと思いますね」。
学生たちにゼミの舵取りを任せるという植原先生。しかし、決して放任するのではなく、彼ら彼女らの雄姿をしっかりと見届け、時にエールを送っている。だからこそ、ゼミ生たちは荒波にもまれながらも、自分たちの思うままに進むことができるのかもしれない。学生たちに「より良く、面白い学び」を提供したいという植原先生の思いは、ゼミ生たちにしっかりと伝わっている。
悔しさを飲み込んで、次の挑戦へ
「良くできていましたね」「凄かったです」海外展開の提案を終え、フィードバックとして企業の方からこんな言葉を貰った時、佐賀山さんは、「ああ、足りなかったか」と肩を落としたという。一般的には、褒められることは喜ばしいことだと考えるだろう。これは一体、どういうことだろうか。
「海外展開の提案」は企業訪問のメインイベントだ。ゼミ生たちが研究・分析の成果を企業の担当者へ直接ぶつけられる絶好の機会でもある。彼ら彼女らが目指すのは「学生の単なる成果発表」ではない。国際ビジネスの視座を持つ者として、担当者に海外展開を「提案」することだ。
しかしながら、企業からただ褒められるだけで終わってしまった時、学生たちは悔しさを噛み締める。「多分、学生フィルターが入っていたんだろうな…」。俵さんは当時の思いをこんな言葉で表した。企業の担当者から反論や訂正さえも引き出せなかった時、学生たちは同じ土俵に立てなかったことを痛感したのだ。逆に、フィードバックで鋭い指摘を受けた時は「自分たちの課題をより明確にすることができた」。知見があると思っていた分野で全く歯が立たなかった時は「もっと学ばなければ!」、そんな自己内省につながった。
筆者が驚いたのは、悔しさを受け止め、「挑戦」を続ける姿勢がゼミ全体に広がっていることだ。植原ゼミの学生たちは企業へ提案を行うことを「貴重な経験」と捉えている。プロである相手に海外展開の提案をすることは、いわば「釈迦に説法」。だからこそ、ゼミ生たちは質の高い提案をつくり、企業から忌憚ない意見を貰うことで、自身の成長へ結びつけようと足掻くのだろう。
取材に協力してくれたゼミ生に、自身の成長について尋ねると、「臨機応変な対応力」「精神力」「プレゼン力」「ビジネスやマーケティングの知識」と様々な返答があった。まだ入って日の浅い3回生の二人も、ゼミに参加したことで、すでに自身の変化を感じているという。ゼミ生たちは「Always Be Challengers/常に挑戦者たれ」という信条のもと、時に悔しさも飲み込んで、これからも「挑戦」を続けていく。植原ゼミについて生き生きと語る学生たちの姿は、力強く芽吹く「苗」を彷彿とさせた。
いざ、「企業訪問」に潜入!
さて、今期のゼミ生たちは一体どのような「海外展開の提案」を行うのだろうか。筆者は3回生の企業訪問を現地で見学させていただいた。
ゼミ生たちが訪れたのは、京都が誇る酒造メーカー・黄桜株式会社の運営する「黄桜 伏水蔵」。この施設では、「黄桜」のこだわり満載の酒造の展示や日本酒・地ビールの製造工場を見学することができる。筆者も施設を見学させていただき、黄桜の変遷や地域に根差した多種多様な商品を学ぶことができ、日本酒・ビール製造の奥深さを知った。
 写真:「黄桜 伏水蔵」の内部
写真:「黄桜 伏水蔵」の内部
今回、植原ゼミが黄桜株式会社に提案するのは「日本酒・ビールのオランダ展開」の実現プラン。ゼミ生たちは3つのグループに分かれ、それぞれ20分程度の発表を行った。驚くべきことに、この提案プロジェクトはオランダからの留学生とともに実施されたため、発表や質疑応答、企業担当者のフィードバックは全て英語である。
プレゼンは聞き手を引き込むような話題提供から始まり、黄桜の商品がオランダでどのように広められるのか展望を話していく。例えば、あるグループでは、商品の展開を「パンデミック」と表現し、オランダで「日本酒パンデミック」を起こすための施策を紹介していた。1人でも日本酒にハマれば、2人、4人、8人…と伝染するようにブームを広められるという企画だ。続けて学生たちは、オランダ人留学生と共に練り上げた「日本酒とオランダの食文化を融合させるプラン」を説明していく。その他にも、輸出方法や宣伝方法、売り上げの算出など、プレゼンに盛り込まれた内容は多岐にわたった。
 写真左:オープニングの挨拶をする植原先生、すでに英語
写真左:オープニングの挨拶をする植原先生、すでに英語
写真右:ゼミ生たちは緊張の中プレゼンを進めていく
最も印象に残ったのは、空気が張り詰める中、ゼミ生全員が原稿を見ることなく、聞き手の反応を伺いながら、プレゼンを進めていたことだ。例えば、聞き手から、「OH!」と声が上がった時は発表者もそれに反応し、さらに説明を加えていた。英語を流暢に話すことではなく、提案を相手に「伝える」ことを強く意識していると感じられた。
フィードバックには、企業の担当者だけでなく植原先生からも容赦ない指摘が英語で飛ぶ。学生たちは、質問者に納得してもらえるよう、協力して言葉を紡いでいく。1人の学生が言葉に詰まってしまっても、すぐに別の学生が説明を付け足すというグループもあった。「より良い提案をつくりあげていこう」という、ゼミ生たちの真摯に向き合う姿勢が伝わってくる。全てのグループが提案を終えた後には、今度は学生から企業へ多くの質問が寄せられた。海外駐在経験のある担当者が話したオランダでの実体験に、学生たちは興味津々。最後まで学びを吸収しようとする貪欲な姿勢はここにも表れていた。
 写真左:学生たちは企業の担当者からのフィードバックに真剣に耳を傾ける
写真左:学生たちは企業の担当者からのフィードバックに真剣に耳を傾ける
写真右:植原先生からも鋭い指摘が
企業訪問を終えた学生たちは、「うまくいったな」「ああ、終わった」と言葉を交わしながら、笑顔を見せた。心境を尋ねると、ある学生は「達成感というよりも、いつものルーティーンを終えた後の気分」と話した。「次の企業向けのプレゼンもすぐにありますから」。植原ゼミの学生たちは、次の「挑戦」に向けてすでに歩き出していた。「海外展開の提案」は、学びの集大成を見せる一大イベント。しかし、学生たちは、いつものタスクを片付けるように、淡々とこなしていく。帰路につく彼ら彼女らの姿は、まるで一仕事終えた後の熟練の職人のように映った。
 プレゼンを終え、黄桜株式会社のお二人の担当者とともに全員でパシャリ。
プレゼンを終え、黄桜株式会社のお二人の担当者とともに全員でパシャリ。
三回生からは思わず笑みがこぼれる。
植原ゼミでは、学生たちが大学から飛び出し、国際ビジネスを軸としてビジネスパーソンや専門家と密接に関わっている。ゼミ運営のInstagramにはワンスクロールでは収まりきらない多様な活動の数々が掲載されている。
彼ら彼女らの学びの軌跡を、ぜひ覗いてみてほしい。
植原国際ビジネスゼミKSU/Int.Business
【Student’s Eye】
「誰もが主役って感じです」。これは、取材の最後にゼミ生の1人が伝えてくれた言葉です。学生たちが互いに協力し合いながら、一歩先の挑戦へ踏み出していく。そんな植原ゼミを表すのにふさわしい言葉だと感じます。企業への海外展開提案の現場まで見学させていただき、「こんなにも学びを深められるのか!」と、驚くことばかりでした。国際学部生の1人として、焚きつけられたような心地です。私も卒業まで、国際学部だからこそ得られる学びを大切に、挑戦を続けていきたいです。
最後になりますが、植原先生、ゼミ生の皆さま、取材を快く受け入れて下さり、そして温かく迎え入れてくださって、本当にありがとうございました。(東島)


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ