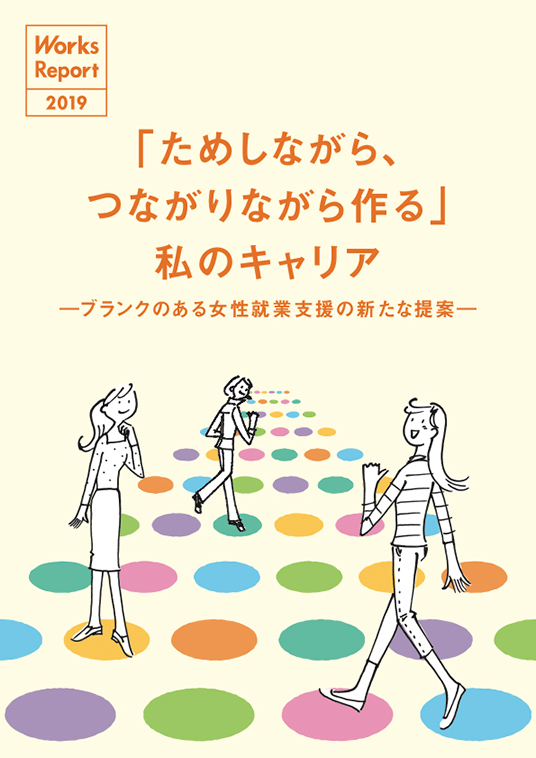都市部の女性に見える景色と、地方の女性が見ている景色は違う 「心の蓋」を開く支援の重要性――株式会社MOKA. 森崎三記子氏
北海道で子育て中の女性たちのエンパワーメントや就労のサポートを行ってきた森崎三記子氏は「都市部の女性に見えている世界と、地方都市に住む女性たちの目に映る世界には乖離がある」と話す。地方に暮らす女性と、その受け皿となる地元企業に見えている景色と、それぞれが抱える課題について聞いた。 株式会社MOKA. 代表取締役 森崎三記子氏
株式会社MOKA. 代表取締役 森崎三記子氏
「出産したら子ども中心」 再就労が難しく
――これまでの活動と、今力を入れている取り組みについて教えてください。
私はハローワークでキャリアコンサルタントを務めるなかで、女性たちが「自分らしく働く」ことをサポートしたいと考えるようになり、2011年に市民団体「釧路モカ女性プロジェクト」を立ち上げました。毎年約2カ月間、女性たちの就労や起業、生活設計などを支援する「MOKA’s SCHOOL」を開講しています。最近はシニアや障害者にも対象を広げ、北海道の委託を受けるなどして、働きたい人を掘り起こして就労に結び付けるため、各地で合同企業説明会やマッチングイベントなどを開いています。2017年には、事業範囲を広げるため株式会社MOKA.も設立しました。
――働く女性は増えましたが、家事育児に響かない範囲で家計補助的に働く形がまだまだ多く、キャリアを狭い範囲に限定してしまっていると感じます。森崎さんは地方で子育てする女性たちについて、どのような認識を持っていますか。
都市部の女性と、釧路のような地方都市に住む女性の目に映る世界には、乖離があると感じています。地方でも女性の価値観は少しずつ多様化してはいますが、依然として出産後は、子ども中心でものを考える女性が多数を占めます。それまでバリバリ働いていた女性も、妊娠すると「今までのように働けないなら、戻っても仕方ない」と考え、キャリアを中断する人も少なくありません。産休・育休制度を有効活用し職場復帰しているのは、公務員や看護師など一部の職種に限られるように思います。また育休を取った人も、多くは早期復帰より子どもと長く過ごしたいと考えており、育休中に2人目を出産して育休期間を延ばすケースも見られます。
一度家庭に入った女性は、家庭と育児が生活のほぼ100%を占め、社会からの疎外感やキャリアに対する不安はあっても「子どもがいればいい」という思いの方が強くなります。そうした生き方を否定はしませんが、長いブランクを経て育児が一段落してから働き始めようとすると、行動を起こすまで非常に大きなエネルギーが必要になってしまいます。
意識は変わっても環境は未整備
――女性活用に関する中小企業の意識に変化は起きていますか。
意識改革は進んだとは思いますが、女性を受け入れる環境は整っていません。最初から「うちの会社は無理」と環境整備をあきらめている企業も見られます。女性は子どもを持ったら辞めるという固定観念が残っていますし、働き方に制約のある社員が増えても、既存の人員では穴埋めできないのでむしろ困る、という思いもあるのでしょう。女性を採用する前に、企業として人材活用の方向性を定める必要があると感じます。
ただ30~40代の2代目、3代目経営者には、性別にこだわらず人材を採用し、全員が働きやすいよう組織の方を変えよう、という気構えがあります。10年後、20年後に彼らが地域経済の柱になれば、柔軟な職場が実現すると期待しています。
――大企業はいかがでしょうか。
道内には製紙や製鉄など、大手メーカーの製造拠点があり、そこで事業を展開するグループ会社には、親会社の方針に従い女性活躍を推進したいという意向があります。ただ製造現場にある女性の受け皿は事務員くらいで、女性技術職の育成などにも取り組む必要があります。こうした企業に求める人材を聞くと「技術職」といった大まかな答えが返ってくることも多く、もう少しペルソナを明確にしてほしいとも思います。ミスマッチを防ぐため、スクールの受講生にも、就職活動の際は企業に「自分はこれができる」「これをやってみたい」といった「自己紹介」をしてあげてください、という話はしています。
学びの場に母親が来ない 子ども向けイベントは盛況
――退職した女性たちが、学びを通じて再びキャリアアップを目指すといった動きは広がっているでしょうか。
コロナ禍以降、学びの場に参加する母親が少なくなったと強く感じます。子ども向けのイベントについては人気が復活し、参加費が数千円かかる会などにも多くの親子連れが参加しているのですが、母親のリスキリングを目的としたスクールやセミナーには、なかなか人が集まらないのです。
当社はコロナ禍以降、夜間にオンラインでスクールを開いており、こちらは子どもの世話などをしながらでも受けられることから人気があります。ただリアルのスクールには、対面で意思を伝える話し方など、リアルだからこそ学べる内容もあります。一方で私たちとしても、母親たちのニーズの変化を見定めて、内容を工夫する必要もあると考えています。
――女性側の意識に変化はありますか。
「子育て中心」という意識が変化したという肌感覚はあまりありません。ただ、出産前にフルタイムで働いていたような女性のなかから、子育てをしながらでも社会のなかで役割を果たしたいと、託児所や子どもの遊び場、親子の居場所づくりなどを始める人がちらほら出始めました。近年は、こうした勢いのあるママがスクールに毎回1~2人はいて、周囲のメンバーを巻き込んで活動を始めるといったケースもあります。スクールにはアクティブでキャリアに対する意識の高い転勤族やUターン、Iターン女性の参加者も多く、こうした女性たちと一緒に学ぶことを通じて、地元の女性が刺激を受けている面もあります。
また母親だけでなく女性全体を見ると、10年前に比べて様々な理由から結婚・出産が叶わなかった人が増えたように思います。彼女たちは働き方に制約はありませんが、「自分の力で生きていかなければ」といった危機意識が強く、私たちのもとへ今後のキャリア形成についての相談も寄せられるようになっています。
就労前に仲間と「リハビリ」 意思表明の力を取り戻す
――「おうち起業」のような動きはあっても、企業のなかで再びキャリアを形成する動きは鈍い。それはなぜでしょうか。
出産前に事務職をしていた人が、10年後に同じ仕事でキャリアを再開しようとしても、デジタル技術や業務プロセスは当時とは大幅に変わっているので、キャッチアップするのは容易ではありません。結局「無理はしないでおこう」と、単純作業のパートなどを選択してしまうのです。
ただ入り口がどうあれ、職場で力を発揮し活躍することは十分可能です。特に中小企業は、経営者が職場全体に目配りできるので「あのパートさんが入ってから仕事がはかどる」といった様子も把握しやすい。スクール受講生のなかにも、単純作業のパートからスタートして仕事ぶりが経営者や上司から認められ、中核業務を任される人が出ています。
「すき間バイト」のような仕事も働き始めるハードルが低いため、就労の入り口として有効です。当社もバイトアプリとの連携などを模索しているところです。
――どのように女性の背中を押し、気づきを促しているのでしょうか。
就労にブランクのある女性の多くは、意見を言わず周囲に右ならえして働こう、と考えがちです。育児や家事に専念しているうちに、家族の声を優先して、自分の気持ちにふたをしてしまっている人も多い。「ガラスの天井」の下に、意見表明を押しとどめる厚いふたがあるのです。
しかし言われるままに働くよりも、職場を良くする意見や提案をどんどん出した方が、能力も伸びるし仕事も楽しくなります。それによって上司や同僚から「助かったよ」と評価されるという成功体験を積み重ねれば、自信もやりがいも高まります。
このためスクールでは、就職活動前に「リハビリ」として、信頼できる仲間たちを相手にふたを少しずつ開ける練習をしています。ディスカッションなどで恐る恐る意見を口にしたら、仲間から「すごいね」と褒められた、といった経験を積み重ねることで次第に「私も若いときは、職場で遠慮なく意見を言っていたかも」といった気づきも生まれます。
意思の表明は、自己中心的なふるまいではなく人生を人任せにしないことであり、それこそが「自立」なのだと、女性たちに伝えようとしています。
聞き手:大嶋寧子
執筆:有馬知子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ