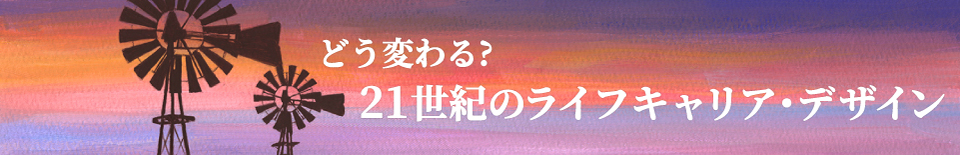
第7章【未来提言】ポスト・アイデンティティ時代の生き方・働き方
第1章で、そのさわりに触れたエリクソンの漸成説モデル。このモデルの背後には、「ひとは、生まれ持った遺伝的(genetic)な資質、能力によって人生のあり方が決まっているのではなく、生涯にわたって発達していく漸成的(epigenetic)な面を持っている」という生涯発達心理学の根源的な考え方がある。
図表1:エリクソンの漸成説
 Erik Homburger Erikson
Erik Homburger Erikson
そして、そのベースにあるのは、ひとは、生涯をかけて、人間としての完成の域に到達する、という思想だ。エリクソンモデルの第8段階の発達課題が、「統合」と銘打たれていることが、その表れだろう。つまり、生涯をかけて、ひとつのサイクルを回す、ワンサイクル人生モデルだ。加齢とともに、成熟していく、という考え方だ。
アイデンティティは、今も重要なのか?
そうした思想をさらに顕著に表しているのが、第5段階の発達課題である同一性=アイデンティティ。自分の中にある多様な経験、行動、思考の底流にある首尾一貫した自己という存在を発見するという段階だ。自分とは何者なのか、自分は何がしたいのか、自分はどのように生きていくのか。「自分探し」という日本語は、その核心を適切に表している。
ひとは、働きはじめる20歳前後の時期に、緩やかに自己を認識し、さらに他者と交わり、後進を生み、育てることを通じて、唯一無二の個性を持った存在へと統合されていく。
これが、20世紀中盤に、エリクソンが生み出したモデルだ。そして、私たちは、この理念モデルを、さして強く意識することなく、ごくごく当たり前の考え方として受け入れている。そのように首尾一貫した人生を過ごして生涯を閉じることが幸せな人生である、という発想だといえばいいだろうか。
このモデルは、人生100年時代にも、有効なものだろうか。ひょっとすると、既にモデルの賞味期限は過ぎてしまい、新たなモデルが待ち望まれているのではなかろうか。
第4章で紹介したサイクルシフトを果たしている事例を再掲してみたい。
学生時代にバックパッカーとして海外を3年間放浪し、日系の証券会社、外資系銀行で働いていたHさん。バブル崩壊を目の当たりにし、この業界からの転身を図るにあたっての選択は、ロシアへの留学だった。ある人から「特殊語を取得すれば、人生何かしら生きていけるよ」と言われたのがきっかけだ。それも、短期の語学留学ではない。大学院まで進み、修士論文を書き上げたのだ。その後、語学力を生かし、教育機関などで働き、現在は合弁企業を立ち上げている。
エレベーターガール、アパレルの販売員、スキーのインストラクターなどを経験し、結婚、二人の子供を出産し、専業主婦となったKさん。しかし、夫の身勝手に耐えられず離婚。事務職経験がなく、職探しは難航。単発のアルバイトをしながら職安でパソコンを習い、派遣社員としてデータ入力の仕事などもするようになった。あるとき、小学校の図書館の学校司書の仕事を紹介される。Kさんは、以前は子どもが嫌いだった。しかし、出産とともに、価値観が一変。自身の子どもだけではなく、子ども全体がいとおしく思えてきていた。その仕事は、最初はパートでの採用だったが、自身の仕事にしたいと思い聞いてみると、教員免許がなければ就けないという。そこで、Kさんは通信教育で、教員免許と司書教諭の資格を取得。今は、小学校の教員として、一番手がかかるといわれる低学年を主に担当している。
この2人がインタビューで答えてくれた内容を、エリクソンモデル、生涯発達心理学の通念に準じて読み解くならば、こうなる。
「初期キャリアは自己を同定できていなかった。つまり同一化できておらず、アイデンティティ拡散の状態にあった。その段階で発達が止まっていた。しかし、転機の到来とともに、やっと自己を確立し、人生の発達段階をやや遅れながらも進み始めた」
だが、話を聞いた私には、そのような解釈は受け入れられない。Hさん、Kさんは、キャリア初期にも、自分らしい自分を生き、そして、転機ののちに、また別の自分らしい人生を生きている。転機は不連続であり、その前と後では、よって立つ価値規範は違っている。違う人生を生きている。
ある一貫した価値規範のうえで、ステージシフトを繰り返していく、というのが、生涯発達心理学の考え方に根差したライフキャリアのありようだ。しかし、不連続なサイクルシフトを遂げた人は、そうではない。新たなライフテーマが生まれるというのは、過去に大切にしていた価値規範とは別の価値規範が生まれるということだ。それは、発達ではない。変容だ。
転機を境に、別の人生=サイクルが始まる。生まれ変わるわけではないので、その前後に、何もつながりがないとはいえないが、それまでとは違う人生が始まる。転機以前を否定するのではなく、しかして、その延長上にはない人生を歩み始める。セカンドライフということもできる。
「セカンドライフ」が意味していたもの
閑話休題。読者の皆さまの中には、「セカンドライフ」を楽しんだ方がきっといると思う。米国リンデンラボ社が2003年に開始したインターネットサービスだ。3Dの仮想世界の中で、好みの分身=アバターを作り上げ、現実とは異なる「セカンドライフ」を楽しむものだ。サービスは現在も続いている。
このサービスのブレイクの要因は、現実世界からの逃避ができるから、なのだろうか? もちろんそういうユーザーも一部にはいるだろうが、多くは違うだろう。人間は、現実の自分とは異なる自分を持つ、言い換えれば、ある異なる人格の人間を演じることを楽しみたいのだ。
若者研究の第一人者・浅野智彦氏(東京学芸大学教授)は、著作『「若者」とは誰か―アイデンティティの30年』の中で、若者の中に生まれた多重人格ブーム、キャラの使い分けなどの実態を紹介し、彼らが「多元的自己を生きている」と語る。このありようを、アイデンティティ拡散の極み、発達の遅滞と捉える向きもあるようだが、おそらくそれは誤りだ。人生をワンサイクルで回す時代が終わっただけではなく、異なるサイクルを同時にいくつも回していく、ということを、時代は要請しているのだ。そうした社会環境変化に、いつの時代もいち早く反応する若者が、そうした行動をとり始めていることを、20世紀的な文脈で切り捨てることは適切ではない。
そして、それは、若者だけに限らない。第6章でご紹介した「100年ライフ調査」の結果からも、「役割によって自己を演じ分けている」という個人の存在が浮かび上がる。演じているということと、自分らしく生き生きとしていられるということとが同時成立している人が、実はたくさんいることも見えてきた。仕事、学び、家族などのさまざまなライフロール、そのライフロールに対応したコミュニティへの参加を通じて、ひとは、既に多元的な自己を生きている。そして、多元的であることが、キャリアのマルチサイクル展望につながっているのではないか、という仮説が浮かび上がる。
21世紀のライフキャリアを考えるうえでは、アイデンティティという20世紀に生まれた概念を、時代の変化に合わせて捉えなおす必要があるのだと思う。ペルソナ、アニマ、アニムスというユングが探索した概念の周辺にまで立ち返ることも必要なように思う。
次なるアクションに向けて
今回の特集ページには、「人生100年時代のライフキャリア」という大タイトルがついている。この大きなテーマに切り込んでみたが、答えらしきものはまだまだ見えない。大きな問いがおぼろげながら見えてきたというところだろうか。このように入口に立った程度の報告ではあるが、あえてこのように形にしてみた。仕掛品ではあるが、発信することを通じて対話を生み出していきたいと考えている。一連の内容に、いろいろと思うところのある方のご意見をぜひお聞きしたい。そして、次のアクションにつなげていきたい。この発信が、何かを生み出す起点となることを、心から祈りつつ。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ