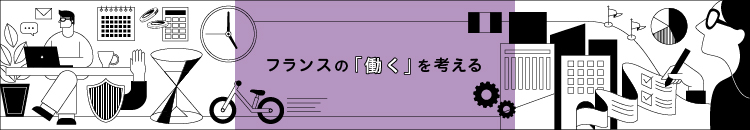
「リゼンティーズム」の拡⼤とウェルビーイング施策の可能性
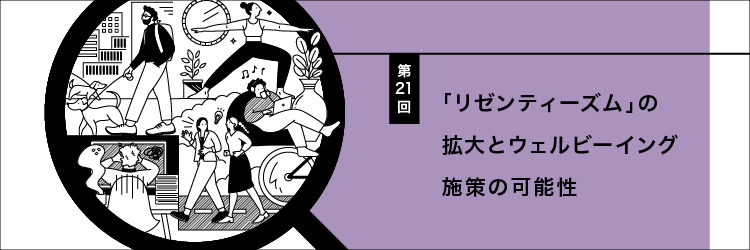
「10⼈中8⼈」が⼼理的苦痛を訴える
2024年にEmpre inte HumaineとOpinionWayが共同で実施した調査(※1)によると、仕事で「ストレスを感じている」など、⼼理的苦痛を抱える労働者が10⼈中8⼈もいることが判明した。この感情は「少なくとも部分的に仕事に関連している」と回答しており、フランスの職場環境は改善されるどころか、むしろ悪化しているといえる。
新型コロナウイルス感染症によるパンデミック以降、⼈々は働き⽅そのものを根本的に⾒直すようになった。リモートワークの柔軟性や⾃主性を経験した労働者にとって、従来の働き⽅に戻ることへの抵抗感は⼤きい。現在、ハイブリッドワークを⾏う従業員の割合は20%で、前年⽐6ポイント減少している(世界平均は34%)(※2)。
かつてはウェルビーイングのパイオニアだったフランス
フランスは歴史的に従業員のウェルビーイングを重視してきた国である。職場環境における雇⽤主の責任が明確にされたのは1893年のことである(※3)。1960年代には、ギャラリー・ラファイエット(百貨店⼤⼿)が勤務時間内にリラクゼーションのための休憩を導⼊したことから、コーヒーマシンを囲んだ休憩⽂化が定着した。柔軟体操などの時間を設けるなど、職場でのウェルビーイング向上が図られ、多くの企業の⼿本となった。
しかし、2019年末より始まったパンデミックは労働市場を根本から覆した。多くの労働者は仕事の意味を改めて問い直し、これまでとは異なる働き⽅を求めるようになった。かつてのようにがむしゃらに働き、企業に貢献しようとする姿勢は薄れ、バーンアウトを経験した⼈々の中には、仕事へのやる気を失い「無気⼒化」するケースも⾒られた。
「リゼンティーズム(不満を持つ従業員)」に頭を悩ます企業

企業はこうした変化を迅速に汲み取ることができなかった。労働者が仕事の意味を問い直した⼀⽅で、企業は従来の労働モデルに回帰しようとした。このズレがフラストレーションを⽣み、不満を抱えながらも働き続ける「リゼンティーズム(※4)」を助⻑する要因となった。
さらに、社会的不安要素がこの状況に拍⾞をかけた。物価上昇の継続、⾼い失業率、ウクライナ情勢、不安定な内政など、先⾏きの不透明さが増すなかで、転職や起業といった新たな⼀歩を踏み出すことに躊躇する⼈も多い。特に、インフレによる物価上昇に対して給与の伸びが追いついていないことが決定的な要因となった(※5)。どれだけ働いても⽣活⽔準が向上しないという現実が、企業への不満をさらに増幅させた。
パンデミック収束後にはフランスでも「⼤量離職」や「静かな退職(※6)」といった傾向が確認されたが、今回は少しわけが違う。それは、リゼンティーズムに陥った従業員は、仕事に対してまったく喜びや満⾜感を感じておらず、⾃分の仕事や職場環境への不満を公然と表明する傾向が⾒られることだ。それは、職場の雰囲気を悪化させる要因となる。⼈事担当は、個別⾯談や、従業員のエンゲージメントや⾝体的・⼼理的状態などをリアルタイムで分析するプラットフォームなどを導⼊して、現状の分析に注⼒している。
QLWCマネジメント
現状を深刻に捉えた企業は、リゼンティーズムの解決を視野に⼊れたQLWC(Quality of Life and Working Conditions)マネジメントに着⼿している。それは、⻑期的かつ抜本的なウェルビーイング改善であり、従業員のメンタルケア、テレワークの再導⼊、時短政策など広域にわたっている。
2025年にQualisocialとIpsosが共同で実施したQLWCに関する調査では(※7)、調査に参加した従業員の91%が「QLWCマネジメントは企業戦略において最優先事項または優先事項であるべきである」と回答している。
同調査では、従業員のメンタルヘルスが職場に与える影響は⾮常に⼤きいとし、「メンタルヘルスが良好な従業員は、そうでない従業員に⽐べて集中⼒が2.4倍⾼く、仕事へのエンゲージメントが40%向上している」という結果が出ている。
実際に、効果的なQLWCマネジメントを導⼊し、職場のウェルビーイングや従業員のメンタルヘルス向上に取り組む企業では、その有効性が具体的に実証されている。施策を導⼊した企業の61%が、「ポジティブな効果があった」と回答している。さらにこの割合は、QLWCの取り組みを優先事項とする企業では71%まで上昇する。
スポーツを通したウェルビーイング
2024年のパリオリンピック・パラリンピック後は、特にスポーツを従業員のウェルビーイング向上の⼀環として取り⼊れる企業が増えている。⾝体的な健康促進だけでなく、メンタルヘルスの向上、チームワークの強化、さらには仕事の⽣産性向上にもつながることが実証されている。

会議室ではなく公園などを歩きながら⾏う「Co-walking(ウォーキング・ミーティング)」が注⽬を集めている。歩きながら会議をすることで、クリエイティブな発想が⽣まれやすくなり、同時に運動不⾜の解消にもつながるという、⼀⽯⼆⿃の取り組みである。家具メーカーのCAMIFでは、従業員の年次⾯談は必ず社屋近くの川沿いを散策しながら⾏う。⾃然の中で歩きながら話すことで、従業員はリラックスし、有益な話し合いができるという。
Spartは、パンデミックによりテレワークが普及し、運動不⾜やモチベーション低下が問題視されるなか、スポーツを通じて従業員同⼠のつながりを強化することを⽬的としたプラットフォームである。創設者のアンドレ・レンケット⽒はスポーツ科学を専攻し、競技者としても活躍した⾃らの経験から「従業員の健康は企業の成功に不可⽋」と考えている。Spartのプラットフォームを通じて、従業員は運動習慣を共有しながら健康を維持し、チームワークを深めることを⽬的としている。現在、SNCF(フランス国鉄)やフランス・テレビジョン(フランス公共放送)などの企業がこのサービスを導⼊している。
⽝と出勤「Dog at Work」

Dog at Workを導⼊するUbisoft(ゲーム開発)では、Dog at Workが開催される⽇は通常よりも従業員の出社率が30%増加し、従業員のエンゲージメント向上にもつながっている。ホスピタリティマネジャーのマリー・シモニアン⽒は、「パンデミック後のさまざまな課題に直⾯するなかで、Dog at Workは職場環境において⼤きな成果をあげている取り組みです」と絶賛している。
Poilu.s Parisは、企業が従業員のペットの⽝を職場に受け⼊れるための環境整備やルール策定を⽀援している。現在Dog at Work導⼊を希望する企業からの依頼が殺到しているという。
パリの9区に2023年にオープンしたWeWorkは、ペット同伴が可能なコワーキングスペースである。フランスではパンデミックをきっかけに⽝を飼う⼈が増えたが、オフィス回帰の流れの中で、⽝を理由にフリーランスへ転向する⼈も少なくない。そこで、⽝と⼀緒に働く時間を⼤切にするフリーランサーを取り込むことを狙ったサービスは好評である。
ウェルビーイング施策の境界線
HR系インキュベーターNIE/Dの共同設⽴者であるマチルド・トレユ⽒によると、雇⽤主は従業員が⼼⾝ともに健康であるための施策を取る義務を負っているものの、「以前は『おまけ』にすぎなかったが、パンデミック後は、『must have』になっている」と強調している。また、離職によるコストが給与の9カ⽉分に相当すると推計されていることに⾔及し、「何も⾏動を起こさないことによるコストは、積極的に対策を講じるコストよりもはるかに⾼い」と述べている。
確かに、QLWCを企業戦略の中⼼に捉える企業は増えている。しかし、「家庭環境などが複雑に影響する精神⾯のケアまで雇⽤主に⼀⽅的に求めることは⾮現実的だ」とする企業側の声もある。さらに、フランスの現状を考えると、職場環境の改善策(たとえばベビーフットやリラクゼーションスペースなど)は⼀定の満⾜度を与えるものの、給与⽔準が⼗分でない場合、従業員の根本的な不満解決には⾄らない。
実際、多くのフランス⼈労働者は現在、こうした「付加価値的な施策」よりも、直接的な経済的報酬(賃上げ)を優先する傾向にある。今後は、労働者⾃⾝の責任範囲はどこまでなのか、労働者の⾝体的・精神的管理を企業がどこまで担うべきなのかという点をクリアにし、現実的な労働条件の改善と給与の⾒直しが、QLWCと並⾏して進められるべきであろう。
ウェルビーイング系スタートアップの活躍
フランスにおける職場のウェルビーイングの取り組みでは、スタートアップが⼤きな役割を担っている。その⼀部であるが、4社の取り組みを紹介する。
Lab RHは、企業のイノベーションを⽀援する組織である。特にウェルビーイングに関するトピックスに強く、組織メンバーには⼤⼿企業、研究機関、⼈事専⾨家など、300のテック企業をはじめとするスタートアップが集結してエコシステムを構築し、職場のウェルビーイングを推進する⾰新的なソリューションを提供している。
Bloomr Impulseは、従業員の⾃⼰啓発とエンゲージメントを促進するためのデジタルプラットフォームを提供している。従業員ごとにパーソナライズされたコーチングを通じて、従業員のスキルアップとキャリア開発を⽀援している。ブイグ・テレコムやマラコフ・メデリックなどの⼤⼿企業をクライアント持つ。Bloomr Impulseの代表のローラン・モレル⽒は、「以前は従業員のウェルビーイングが『おまけ』のような存在であったが、現在は特に⼤⼿企業では、企業の中⼼課題となっている」と語る。
Wittyfit(※8)は、Lab RHのメンバーであり、従業員の満⾜度と⼼理的・⾝体的状態をリアルタイムで分析するプラットフォームを提供している。Wittyfitは、2年間にわたる⼤学病院と労働衛⽣専⾨家およびCNRS(フランス国⽴科学研究センター)の研究者とのパートナーシップのもと誕⽣した。科学の視点で開発されたプロトコルは、WHO(世界保健機関)に認可された公式サイトにも掲載されている。このツールを活⽤することで、企業は従業員のフィードバックを基に職場環境の改善策を迅速に講じることが可能となり、結果として⽣産性と従業員の幸福度の向上につなげている。
Supermoodは、従業員エンゲージメントを測定し、組織⽂化を強化するためのアンケートツールを提供している。企業は定期的なフィードバックを収集し、データドリブンなアプローチで職場のウェルビーイング戦略を策定することを可能にする。ENGIE(エネルギー)、Fnac-Darty(流通)、Natixis(⾦融)などの⼤⼿250社がSupermoodのサービスを利⽤している。
(※1)2024年5⽉23⽇から6⽉4⽇までに2000⼈の会社員を対象に⾏われた調査で、タイトルは「フランス⼈労働者の⼼理状態:企業の予防対策とは」である。本⽂では調査内容を報道した以下、RH Matinより情報を得た:https://www.rhmatin.com/qvt/bien-etre-travail/rps-30-des-salaries-concernes-par-les-risques-de-burn-out.html
(※2)2024年6⽉にADP Research Instituteが発表した調査「People at Work 2024:lʼétude Workforce View」は、18カ国34000⼈以上の労働者を対象に実施した。うちフランスは約2000⼈が調査対象となった:https://www.fr.adp.com/a-propos-adp/communiques-de-presse/teletravail-travail-hybride-quel-etat-des-lieux-4-ans-plus-tard.aspx#:~:text=La%20part%20des%20collaborateurs%20hybrides,12%20%25%20au%20niveau%20monde).
(※3)現在では、労働法典L4121-1条にて、「雇⽤主は従業員の安全を確保し、⾝体的および精神的健康を守るために必要なあらゆる措置を講じる義務がある」としている:https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/developpement-entreprise/droit-social/obligation-de-securite-et-responsabilite-employeur
(※4)リゼンティーズムはフランス語で「résentéeism」と表記されることが多い。定義は英語と同様である
(※5)レゼコーの記事:https://www.lesechos.fr/economie-france/social/comment-les-salaires-ont-evolue-en-france-face-au-choc-inflationniste-2127313
(※6)静かな退職は、フランス語では「démission silencieuse」だが、⽂献では英語表記の「quiet quitting」が使⽤されることが多い
(※7)2025年1⽉公表、QualisocialとIpsosが労働者3000⼈を対象に実施した調査「2025年メンタルヘルス&QLWC(労働⽣活の質と労働条件)バロメーター」:https://www.qualisocial.com/barometre-sante-mentale-qvct-qualisocial-ipsos/
Spart:https://www.spart.life/
Poilu.s Paris:https://poilusparis.com/
Lab RH:https://lab-rh.com/
Bloomr Impulse:https://www.bloomr-impulse.com/
(※8)Wittyfitは2022年にCegid(ソフトウエア)に買収され、現在はCegid Wittyfitとなっている:https://www.cegid.com/ca/produits/cegid-wittyfit/
Supermood:https://www.supermood.com/
TEXT=田中美紀(客員研究員)


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

