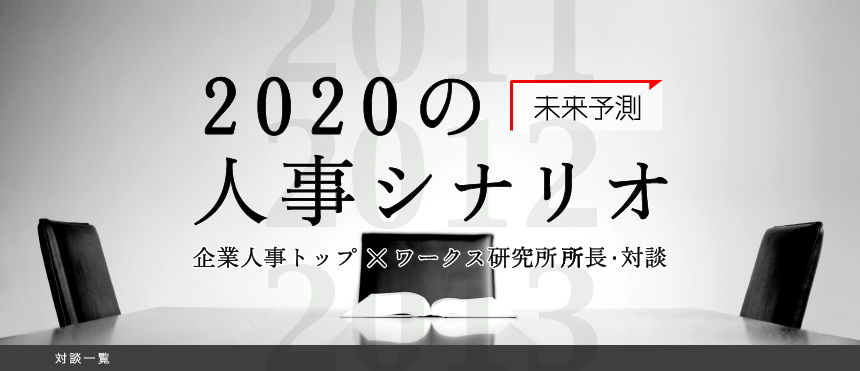
Vol.08 小林 文彦氏 伊藤忠商事

全球規模で人材を把握するIGC
大久保 この対談ではまず各社の人事課題を伺っているのですが、時節柄、グローバル展開に関するものが多くなっています。総合商社というと存在自体がグローバルですが、御社の場合はいかがですか。
小林 おっしゃる通りで、我々の大きなテーマの1つがグローバル化の進展です。当社の場合、グローバル化には2つの意味があります。1つは海外客先との貿易(トレード)や顧客の海外進出支援などで、これは従来から力を入れてきた伝統的な分野です。もう1つは主に現地の企業をパートナーとすることも含めて、地場事業拡大を図ることです。両者は同じ海外基盤のビジネスですが、求められる人材は大きく違います。後者に関しては、当社では150の事業会社を海外にもっており、現地のナショナルスタッフの採用から育成、抜擢まで、非常にハードルの高い課題が横たわっています。
大久保 何かよい方法はあるのでしょうか。
小林 こうしたグローバルレベルの人材戦略を進めるために、ある"物差し"を導入しました。本社の社員およびナショナルスタッフを、職務と職責に応じて8つに分けるIGC(ITOCHU Global Classification)という人材区分です。これによって、どんな職種、職歴、グレードの人材がどこにいるのかが即座にわかるようになりました。たとえば、これを使って、伊藤忠グループの将来の経営者を育てるプログラムも始めました。このプログラムの受講者のなかからすでに複数の役員が生まれ、優秀なナショナルスタッフも育ってきています。時間はかかりますが、こうした施策を地道にやっていくしかありません。
大久保 トップ層のみを対象にしたリストをつくる企業はたくさんありますが、スタッフレベルまで広げたのは珍しいですね。
小林 全体を対象にしないと真の意味のグローバル化は達成できません。一方で、拙速は避けなければなりません。海外管理職ポストが現在300ほどあり、2013年までに半分を現地の人とするという目標を掲げたことがあるのですが、無理に昇進させると弊害も出てくるので、今はそれにはこだわっていません。
大久保 グローバルの人事データベースもつくられている。
小林 はい。課長層以上のナショナルスタッフ全員、数にして約300人の基礎データを把握し、育成や活用に役立てています。さらにそのなかから、優秀な人材100人を抽出し、今後の育成計画をつくりました。こうしたタレントマネジメントができるのもIGCのおかげです。
大久保 かなり綿密な仕組みですね。そもそも地場の企業の経営は現地の人に任せるのがいいのか、日本人がやるべきなのか、いかがでしょう。
小林 基本は現地の人でしょう。いちばん実効性があるのは現地で優良パートナーを見つけ、任せていくことです。お金だけを出す投資銀行と何が違うのか、と言われそうですが、我々は、技術だけでなく、与信や経理の仕組み、物品管理、コンプライアンス対応といった、特に新興国で不足している管理手法を彼らに伝授できる。また実体としての「トレード」を持っていますので、商売、人材に関する情報確度も高いのです。そこが大きな違いです。
あえて外国人にはこだわらない新卒採用
大久保 総合商社では扱う商材によって組織が明確に分かれています。御社もカンパニー制をとっていますが、カンパニーをまたいだ人材異動はよく行われていますか。
小林 今まではあまりなかったのですが、これからはもっとやらなければなりません。特に縮小気味の事業分野から成長途上の事業分野へ人員をシフトする必要があります。
大久保 先ほどのIGCを使い、カンパニー間の異動を考慮した育成計画をつくればよいのではないでしょうか。
小林 役に立つと思います。今はカンパニーごとの育成計画しかありませんが、ナショナルスタッフに関しては異動のための処遇ガイドラインも作成しました。仕組みはもうできているので、あとはどう実行するか、ということでしょう。
大久保 新卒採用に関してはいかがでしょう。2010年は新卒採用を海外でも行ったそうですね。
小林 1人だけではありますが、中国で北京大学の卒業生を総合職として採用しました。日本に来ている外国人留学生は、従前より毎年数名採用してきましたが、現地大学卒業の現地人学生を採用するために現地に行くというのは初めてです。このような取り組みは当社としても今後の多様な人材活用の試金石と考えています。
大久保 留学生も含めた外国人の新卒採用をこれからも強化していきますか。
小林 特にそのような考え方をしておらず、外国人にこだわることもありません。たとえば、将来中国で活躍してもらおうと中国人留学生を採用する例がありますが、こちらが故国に戻って活躍することを期待したとしても、その思惑通りにいくことは多くはありません。仮に帰参したとしても、その国のナショナルスタッフとの関係がぎくしゃくしてしまうこともあります。そういったことも含めて苦い経験もたくさんしてきました。
大久保 日本企業の間で外国人の新卒採用が大きなトレンドになっていますが、そのうち、揺り戻しがあるかもしれませんね。
小林 私は、英語の公用語化の動きも疑問に思っています。当社も一度、試したことがあるのですが、日本人同士が英語で会議をやると、言いたいことも言えなくなり、本末転倒となり、その結果仕事の質も落ちるという弊害が発生し、今は止めています。現在は日本語と英語の2カ国語体制で、今般更に中国語が出来る人材を大きく強化しようとしています。

課長支援による現場力の強化を
大久保 グローバル化以外で、どんな課題がありますか。
小林 人員構成のいびつさの問題があります。いびつさは事業や業界の伸縮に対して組織の伸縮の呼応が難しいという点と、社内の人口ピラミッドの形状がいびつである、という2つの要因からきています。後者は、ポスト団塊ジュニアの問題です。団塊ジュニアは今40歳前後で、課長相当のクラスにいるわけですが、そのあとに続く世代の数が非常に少ない。つまり、今後、課長になる層が大いに枯渇してくることになります。
大久保 そうすると、数少ない課長に大きな負荷がかかることになりますね。
小林 はい。「現場力強化」を中期経営計画で掲げましたが、そのためにも課長の支援・強化が不可欠です。方策の1つとして、これまで2年に1回だった課長対象の多面観察を、2011年から毎年行うようにしました。結果を本人に伝え、行動改善につなげてもらうわけですが、必要な場合は個別にコーチもつけるようにしました。また、当社でもメンタル不全を訴える社員がいて、その負担の多くが課長に回っていきます。そうした負担を軽減するため、キャリアカウンセラーや臨床心理士と社員の面談の機会を増やすなどして、メンタル未然防止と発生した場合の適切な処置に向けたケアをしています。
大久保 そこまできめ細かくやると課長力は大きく伸びるでしょう。育成の研究をしていて最近わかったことがあります。上に立つ人にはリーダーシップが必要だ、とよくいわれますが、そもそもリーダーシップは上に立つ前に磨かれなければならないのです。取引先と良好なパートナーシップを結ぶ力、同僚との協働力、上司に対してうまいフォロワーシップがとれる力、こうしたものがあって初めてリーダーシップが生きる、もしくはその3つの総体がリーダーシップなのです。
小林 その通りだと思います。人事部門はリーダーシップが社内できちんと開発されているかどうかを定量的に測る努力をするべきです。たとえば上司や部下などによる多面観察において、リーダーシップに関連する評価項目を経年で集計していくと、順調に開発されているかどうかを把握することができます。そういう人材開発データを、人事部門は経営に報告する義務があると思います。
大久保 大変興味深いお話です。私も多面観察をうまく使えばリーダーシップを高めるモデルができると思っています。

(TEXT/荻野 進介 PHOTO/刑部 友康)


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ