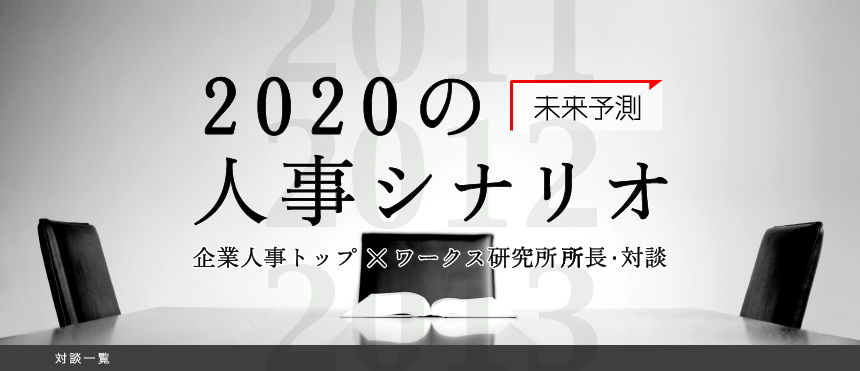
Vol.27 和気 靖氏 朝日新聞社

従来型マスメディアと自前主義からの脱却
大久保 最初に、御社の中長期的な経営課題からお聞かせいただきたいのですが。
和気 昨年、2015年に向けたビジョン策定で会社のミッションを再確認しました。「朝日新聞社は日本の民主主義社会に必要不可欠なメディアとして、社会と読者に価値ある情報を届け続ける」というものです。言わずもがなという社員もいましたが、ネット社会の到来により、メディアを取り巻く環境は激変しています。2009年度には、株式会社化してから初めての最終赤字に陥りました。そうしたなか、これまでの成功体験にあぐらをかき、同じやり方を続けていていいのか、と自らに問いかけ、創業の原点に立ち返る意味から、あえて明示したのです。それは、「組織も社員一人ひとりも『進化』しなければ、生き残れない」というメッセージでもあります。
大久保 「原点回帰」というのは、今回の対談で多くの企業から出てきたポイントです。大きな変化に突入するからこそ変えてはいけないものを確認しておくということなのでしょう。一方の変えるですが具体的にはどのようなことがあげられますか。
和気 キーワードの1つが、「ハイブリッド型メディア」です。紙とデジタルのハイブリッドはもちろんですが、800万人の読者を擁するマスメディアと、個々人の求めに対応するパーソナルメディアとのハイブリッドも意味します。朝日新聞社は、130年を超える歴史を持つ古い企業です。特に戦後はビジネスモデルが盤石で、業績も右肩上がりだったからでしょうか、自前主義を貫いてきました。その歴史が今、変わりつつあります。携帯電話やスマートフォン向けの有料ニュース配信サービスではKDDIと、語彙読解力検定の事業はベネッセコーポレーションとの協業に踏み出しました。自前にこだわらないことで、すばやい事業開拓が可能になりますし、自社の強みと至らぬ点を知ることにもなります。
大久保 中立性を重視する新聞社にとって自前事業からの脱却というのは大きな変化ですね。新聞購読料と広告を収入の二本柱とするシンプルなビジネスモデルが変わるとなれば、新たなビジネスモデルをつくる人材の育成や獲得が課題になります。
和気 ハイブリッド型メディアという考え方は、既存の経営資源を最大限活用して、新たな価値創出につなげようとするものです。ニュースを取材、編集して、価値あるコンテンツをパッケージ化するというスキルと、全国津々浦々にある販売店を通じてお届けしている800万の購読者というネットワーク、この資源をどのように活かして新たな時代に対応するかということです。白紙に新たなビジネスモデルを描いているのではありません。
大久保 ミッションを明確にしつつ、これまで培ってきた強みを生かして、他社が真似できないことをやっていく、ということでしょうね。
和気 はい。一種の差別化戦略です。記者クラブに安住せず、調査報道で新たな事実を掘り起こしていくこともその1つです。以前は、官庁や企業といった発表主体が、記者クラブを通じて限られたメディアに情報を提供していました。しかし、今やネットを通じて、発表主体は情報を直に社会に伝えることが出来ます。われわれはプロのジャーナリストを擁するメディアとして、その原点に立ち返る時が来ました。組織が発表したい情報ではなく、出したくない情報、隠しておきたい背景をいかに探り当て、その事実を示すことができるのかが勝負になります。その取り組みはジャーナリズムの地力を強めるとともに、メディア企業としての基盤を固めることにもつながります。
終身雇用・年功序列の"一枚岩組織"を変える
大久保 そうなると、記者育成のあり方も変わってきますね。
和気 はい。「これが正解だ」という段階まではまだ来ていませんが、従来のように全国の県庁所在地にある総局に新人を配属し、総局長やデスクが一人ひとりを徒弟制のように育てていくというやり方から、新人を何人かまとめてグループで育成したり、本社のジャーナリスト学校での座学を定期的に取り入れたり、といった方法を模索しています。
大久保 中途採用に関してはいかがでしょうか。
和気 同業他社や別の職種で経験を積んだ社会人の採用も積極的に進めています。新卒で入社し、総局勤務を二カ所ほど経験し、本社の専門部に「上る」という、従来の記者キャリア形成に、新しい風が吹きつつあります。また、ここ数年、デジタル部門を中心に年俸制の有期雇用社員を採用しています。デジタル業界での人材の流動性の高さや若い技術者の意識の変化に対応したものです。新しい事業領域で、能力と意欲のある人材をどう確保し、力を発揮してもらえるのか。人事システムに関しては柔軟性、弾力性をさらに強めたいと思っています。歴史を紐解けば、朝日新聞社は、かの夏目漱石を東大から引き抜き、ライバル新聞社からも看板記者を相次いでスカウトしていたのです。明治・大正期のそうした熱気ある組織をもう一度、再現したいと思っています。
大久保 既存の社員に対してはいかがでしょう。
和気 2012年から「プロデューサー制度」を始めました。これまでは編集部門においてのみ、年俸制の編集委員という制度があったのですが、これを事業部門にも広げ、高いスキルと意欲を持った人材を年俸制で処遇する制度を全社に取り入れたのです。若手の登用や外部からのスカウトにも活用し、実力を発揮する人に報いたいと考えています。これまでの安定的、悪く言えば墨守的な人事システムを揺さぶる改革を次々に仕掛けていこうと思っています。

特派員も1つの分野の専門家であってはならない
大久保 今の日本はグローバル化の推進という大きなテーマに直面し、読者の関心も、外へ向かっているように思います。海外の駐在体制には変化があるのでしょうか。
和気 特派員の総数に目立った変化はありませんが、国際報道のあり方は近年、大きく変わってきました。記者クラブ問題とも似ていますが、以前なら新聞を通じて得ていた海外の一次情報をネットで直に得ることができるようになっています。メディアを取り巻く環境がネットによって激変するなかで、新聞の国際報道はどうあるべきかは、編集部門で絶えず検討されています。結局、ネットとは一味も二味も違う独自情報と切り口がないと、読者から評価していただけない。そういう意味では、今の特派員は以前に比べ、より高い仕事のハードルが課せられています。
大久保 特派員のキャリアにも影響が出るでしょうね。
和気 はい。たとえば、かつての中国特派員といえば、大学で中国語や中国文化を学び、その後も中国への関心を持ち続けていた専門家タイプが多かったのですが、最近は変わってきました。現在の中国総局長は、もちろん中国語は堪能ですが、その前はアメリカのワシントン特派員でした。ある地域だけ詳しくてもダメで、複眼的に、地球的な視野で見ることが欠かせません。これは何も国際報道に限ったことではなく、主として国内を取材する政治部や社会部、経済部なども、タテ割りの垣根を低くして、記者の流動性と組織の風通しに気を配っています。朝日新聞社というのは元来、タテ割りの強い組織なのですが、環境変化に対応すべく、編集部門ではゼネラルマネジャーが全体を見渡して人事を行なう制度に改めています。
大久保 人の問題はとかく時間がかかります。変化を志向した場合、経営計画以上の長期視点で物事を考えなければなりません。今後はどうやって変化を推進していくのでしょう。
和気 変化の時代にあって、現状維持はリスクです。かといって、変えればいいというものでもない。培ってきた強みまで失ってしまっては元も子もない。いくつかの改革を同時並行で走らせたうえで、うまくいったものは残し、ダメだったものは取りやめながら、時代の潮目を見極め、波頭に乗って、朝日新聞社という船の舵を絶えず修正し、帆をいっぱいに張り続けたいと思っています。

(TEXT/荻野 進介 PHOTO/刑部 友康)


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ