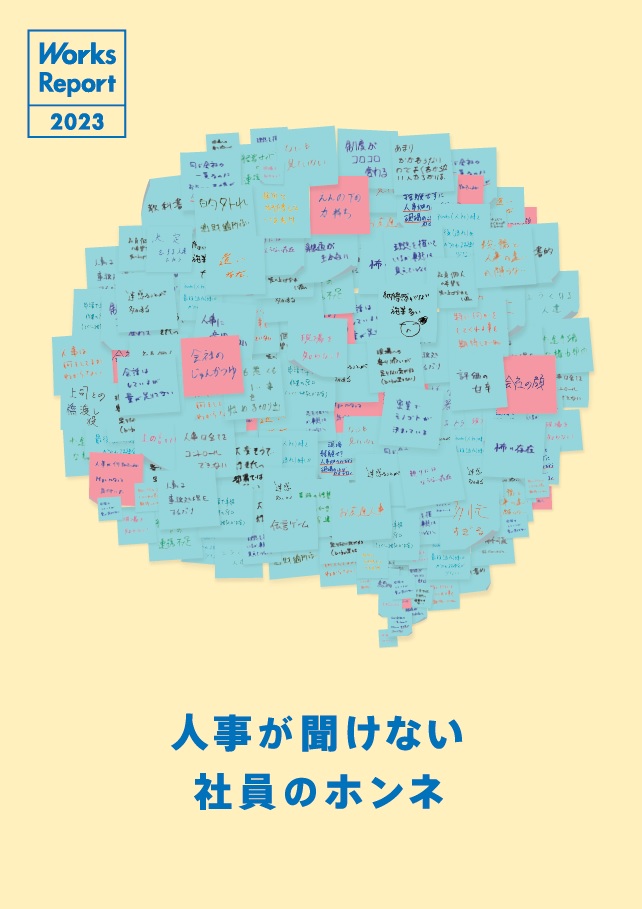社員個人を活かす組織づくりを人事がサポートし、不連続な変化への対応力を高める(馬塲杉夫氏)
 社会の不連続な変化に対応するには、社員個人に主体的に働いてもらうことが重要だという認識が、日本企業に広がりつつある。それに伴い企業と社員の関係も、企業側が強力な人事権を行使してきた従来の形から、より対等に近づくと予想される。そうなった時、人事はどのような役割を果たすことになるだろうか。「個を活かす組織」を研究する専修大学経営学部教授の馬塲杉夫氏に聞いた。
社会の不連続な変化に対応するには、社員個人に主体的に働いてもらうことが重要だという認識が、日本企業に広がりつつある。それに伴い企業と社員の関係も、企業側が強力な人事権を行使してきた従来の形から、より対等に近づくと予想される。そうなった時、人事はどのような役割を果たすことになるだろうか。「個を活かす組織」を研究する専修大学経営学部教授の馬塲杉夫氏に聞いた。
不確実性強まる事業環境 人事の権力行使に限界も
従来の日本企業は、社員の配置や給与、キャリアなどに関して人事部門が直接的・間接的に決定権を行使してきた。
「社会の予見可能性が高く、確立されたビジネスモデルを維持できる時は、人事部門が毅然と人事権を発動して組織の人員配置を調整し、事業部門は事業に集中するという分業体制に、一定の経営合理性がありました」
しかし事業環境の不確実性が強まるなか、ビジネスモデルはかつてのように強固ではなくなり、変更を迫られることも多くなった。「不確実なものは人間の力では調整が難しいため、人事がシステマチックに機能することにも限界が生じるようになりました」
ただ、企業の人事部門が人事権を手放す方向へ向かうのか、維持し続けるのかは、トップの考え方や事業の性質などによってそれぞれ異なるという。またすべての社員が基本的には主体性を備えているものの、発揮の度合いには濃淡があり、企業主導の人事をよしとする人も一定数存在する。
「これからは大量生産・大量販売のような強固なビジネスモデルを維持する企業では、人事が力を持ち続ける、社員の主体性を重視する組織では人事が一歩引いて『見守り』のスタンスを取るなど、人事の在り方も多様化していくでしょう」
全社員に主体性発揮の機会を開く
馬塲氏は、世界のどこでどのような変化が起きるか予測できない以上「一部の選ばれた社員ではなく、すべての社員に主体的に行動する機会を提供し、組織の変化対応力を高める必要があります」とも強調する。
ただ日本企業には従来、欧米企業に比べて主体性を発揮する機会が開かれていたという。トップダウンで業務を進める欧米企業に対し、日本企業は現場でトラブルが起きた時、裁量を越えて解決に取り組む社員が一定数存在し、組織もこうした社員の行動を受け入れてきたからだ。
より多くの社員が主体的に動けるようになれば、こうした「現場力」はさらに高まる。意見やアイデアが出されることで新しい価値が生まれやすくなり、組織が誤った方向へ進み始めた時、暴走を抑える効果も期待できる。
「主体性を発揮する大前提として、社員が企業のビジョンに共感し、『この会社で働けば、自分のやりたいことを実現できる』と認識することも不可欠です」
年功序列・終身雇用モデルが機能していた時代、社員が「なぜこの会社で働くのか」を意識する機会はあまりなかった。入社する時には明確な動機があっても、時が経つにつれ初心を忘れ、会社の意思に反論せず唯々諾々と従うようになる。企業側にも「モノを言わない」社員を管理することで、組織運営をある程度効率化できるという一定の合理性があった。
バブル崩壊以降、こうした日本企業の体質は「ぬるま湯」だと批判され、成長から取り残されたことを「ゆでガエル」とも揶揄された。「しかし年功モデルが過去あまりにも高い効果を発揮し、それ以上に合理的なモデルもなかなか生まれなかったため、画一的な組織の在り方がその後も長く定着してしまうことになりました」
社員の主体性は遠心力を生む 求心力の形成が人事の仕事に
近年ようやく、若手を中心に企業ビジョンを踏まえて職場を選択し、主体的にキャリアを築くという意識を持った層が増え始めている。ただ彼ら彼女らには同時に「会社と自分の目指す方向性が違ったら、組織を離れる」という「遠心力」も働く。
「経営者の望む『主体性』は組織内で発揮されることを想定していますが、主体性を獲得した社員は社外も見るようになります。『やりたいこと』を実現できるかどうかが、人事主導の配置という『運』で決まるようでは、求心力はますます失われてしまいます」
これでは優秀な人材ほど組織を去り、そうでない人が留まるという状態にもなりかねない。このため、いかに求心力を生み出すかが、企業の大きな課題となっている。
「パーパスやミッション、ビジョンの重要性が高まっているのは、求心力を生み出さなければ組織が空中分解してしまうという危機感の表れです。経営層だけでなく人事、そしてマネジャーがそれぞれの仕事のなかで、求心力の形成に取り組むことが求められています」
たとえばグローバル企業のなかには、海外支社の社員をオンラインではなくあえて日本の本社に招き、ビジョンやミッションを再確認する機会を設けている組織もあるという。こうした場合、経営層が打ち出した「社員にビジョンを再確認させる」という方針に対して、それを実現する仕組みをつくるのは人事の役割だと、馬塲氏は指摘する。
「マネジャーは日々の業務を通じて、自ずと部下の短期的な求心力に影響を及ぼしています。彼らにこれ以上の業務負荷をかけるのは難しく、全社的な求心力を支える仕事は、人事の役割になりうると思います」
一方、社員のマネジメントについては「人事部門が力を持ちすぎると、いいことはあまりありません」と語る。
「人事の顔色を見ながら働くのは社員にとって快適ではないですし、評価のために働くようになる懸念もあります。マネジャーが機能している間は任せることで管理職としての責任感ややりがいを喚起し、ルールを逸脱しそうになったら介入する形が望ましいでしょう」
価値の創造と収益確保 最適なバランスを見出す
社員には主体性を発揮し新しい価値を生み出してもらうと同時に、既存の事業で利益を確保してもらう必要もある。この2つはどちらも企業成長に欠かせないが、一方を進めれば他方が停滞するという表裏の関係でもある。
「組織のなかで両者を同時に存在させようとすれば、歪みや矛盾が生じることは避けられません。歪みが最も少ない、可能な限り整合の取れた状態をつくることが、企業のパフォーマンスを高め、従業員にとっても幸福な状態を生み出すと考えています」
そのための具体的な手法として考えられるのは、価値創造は経営企画室や製品開発室、収益の確保は営業・生産部門などと、役割によって部署を分けることだ。企業のなかには、開発の現場に絞って主体性の発揮を求めるメッセージを発信しているケースもある。また、別のやり方として、業務の成果を評価する既存の人事制度に加え、新製品の提案を評価する制度を設けるなど、制度を「二本立て」にすることも考えられる。
業務時間中に新しいことに取り組む部下を、上司が黙認するといったインフォーマルな方法もある。ある企業では、開発担当者が非公式に他部署の社員へヒアリングに行き、聞かれた方も「これも職務に含まれる」と暗黙のうちに認識して答えているという。
「どこまでが職務、という境界を設けずにあいまいさを残し、社員が自己裁量で歪みを調整できる状態にしておくことが大事です。一方で、たとえばお金の使い方や人権問題などに関しては、逸脱がないよう明確な枠組みやルールを設定すべきです」
価値創造と収益確保の最適なバランスは、企業によって異なるだけでなく、1つの組織のなかでも、事業環境や社員の意識の変化に伴い絶えず揺らぎ続ける。揺れ動く最適解を見極め、組織をその方向へ誘導するという環境整備に関しても、人事は一定の役割を果たす必要があるだろう。
聞き手:千野翔平(研究員)
執筆:有馬知子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ