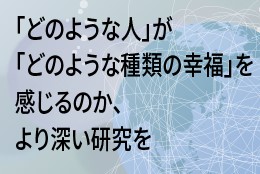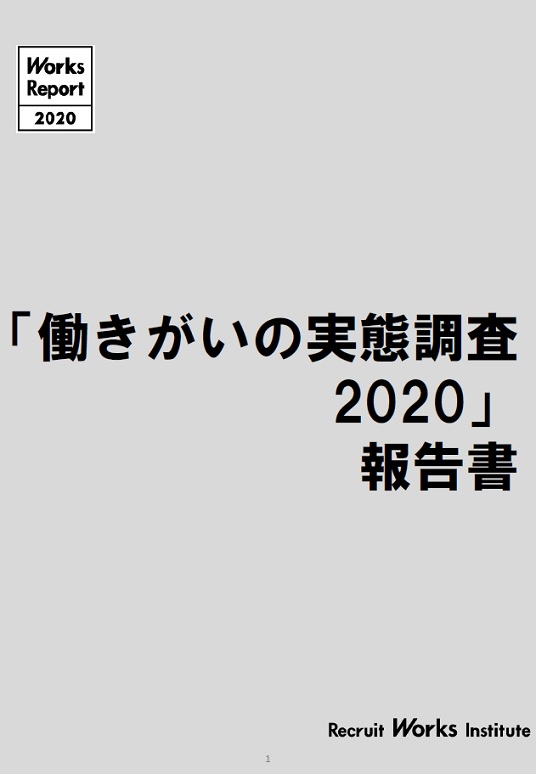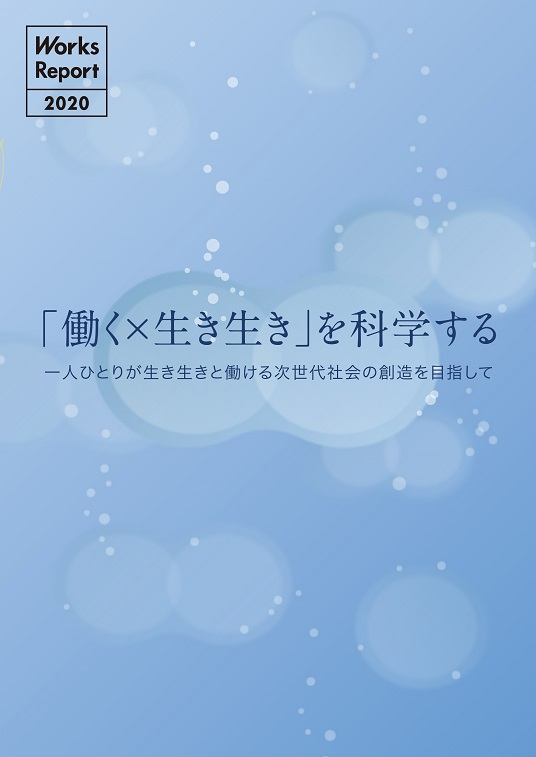第1回 「幸福感研究」の観点から 大石繁宏 氏
「生き生き働いていない」人たちとの比較・検証を
【プロフィール】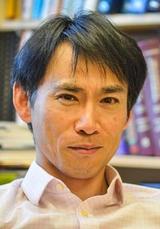 大石繁宏(おおいし・しげひろ) ヴァージニア大学心理学部教授。国際基督教大学を卒業した後に渡米し、2000年、イリノイ大学大学院でPh.D.(心理学)取得。ミネソタ大学心理学部准教授を経て、現職。幸福感と文化に関する研究の第一人者として多くの論文や著書を発表。そのユニークな研究から数々の賞を受賞しており、2017年にはアメリカ実験社会心理学会Career Trajectory Awardを受賞。代表的な著書に『幸せを科学する-心理学からわかったこと』(2009)がある。
大石繁宏(おおいし・しげひろ) ヴァージニア大学心理学部教授。国際基督教大学を卒業した後に渡米し、2000年、イリノイ大学大学院でPh.D.(心理学)取得。ミネソタ大学心理学部准教授を経て、現職。幸福感と文化に関する研究の第一人者として多くの論文や著書を発表。そのユニークな研究から数々の賞を受賞しており、2017年にはアメリカ実験社会心理学会Career Trajectory Awardを受賞。代表的な著書に『幸せを科学する-心理学からわかったこと』(2009)がある。
「働く×生き生き」これまでの研究結果を読み解く
「クリエイティブ・クラス」が日本にも遅れて出てきた
「生き生き働いている」とはどういう状態なのか-自由記述調査で得られた回答例を見ると、「自分の意思、決定で進める」「自分のペースで働く」「自分らしくいられる」などといった“個人主体”のワードが多いことに時代の変化を感じます。
遡ってアメリカの話をすると、終身雇用が崩れて働く環境が大きく変わったのは、1980年代から90年代にかけてです。アウトソーシングやギグ・エコノミーの出現に伴って雇用者の価値観も変わり、いわゆる大企業で一生働くよりも、自分のペース、裁量で仕事をしたいと考える人たちが出てきました。こういう新たな経済的階層を、リチャード・フロリダ(都市経済学者)は「クリエイティブ・クラス」と定義しましたが、アメリカでは20世紀末から急増し、2000年前後の段階で国内労働人口の3割以上になっています。
クリエイティブ・クラスの特徴は、フレキシブルな働き方をしていること。9時-5時の就業時間や、職場では「スーツにネクタイ着用」といった旧来の“当たり前”にとらわれず、自分が働きたいときに一生懸命働き、リラックスしたいときはプライベートの時間を楽しむ。また、長いスパンにおいては、自分のライフステージに合わせて労働時間や場所を調整するなど、主体性に基づいたフレキシブル・ワークを実践しているわけです。今回の調査で多く見られた「自分の」という表現は、まさにクリエイティブ・クラスを示しており、日本にも遅れて出てきたという印象ですね。
ただ、それは働いている人たちの願望というか、一つの価値観として現れている段階なのかもしれません。日本の場合、例えばスタートアップの土壌が弱いとか、能力主義に振り切れない職場が多いとか、個人の思いを実現させる環境がまだ整っていませんから、今はきっと過渡期にあるのでしょう。フレキシブルなマインドセットを持つ企業が生き残り、古い固定観念が淘汰されていけば、環境が整い、より実態的になってくるだろうと思います。
多くの共通点を持つ「幸福感」と「生き生き働く」
幸福感研究においても、「ハピネスのイメージとは?」を問うと、やはり同じような個人主体のワードが出てくるんですよ。先に触れた回答例とかなり似通っています。それが働いている人であれば、職場で生き生きしている人は人生全般においても幸福感を持っているケースが多い。
そして、人生の幸福感や満足度にかかわる一番の要因は対人関係で、家族、友人関係に加えて、職場での人間関係ももちろん重要になってきます。実は、これには「自由に使える時間がどのくらいあるか」が関与しており、時間のある人のほうが対人関係は全般的に良好です。自由な時間を一人だけで過ごしたいというのはマイノリティで、多くの場合、人は対人関係において時間を使うことを大事にしたいと考えるからです。いずれにしても、自主性を介して、自分のやりたいことがどのくらいできているか。これは要因として大きいですから、幸福感と「生き生き働く」との間には、かなりの共通点があると考えられます。
「働く×生き生き」これからの研究課題を紐解く
若い層へ深くアプローチし、未来につなげるヒントを
これだけの調査量があれば、生き生き働いている人たちと、そうでない人たちをプロファイルしてみて、その違いを浮き彫りにすることができると思います。その上で、生き生き働いているのはどういう人たちなのか、あるいはどういう職場にいるのか、より詳しい分析結果を見てみたいです。雇用者と自営業者とには違いもあるでしょうし、また、組織に属していながらも生き生きと働けているならば、そこには日本特有の職場環境があるのかもしれません。そういった点が見えてくると、面白いですよね。
次に、若い人たちへのアプローチ。今回の調査では、年齢や所得の高い人ほど仕事満足度が高い傾向にあるということでしたが、ならば、同じく満足感を持っている若者はどういう人たちなのか、という分析です。例えば、持っているスキルや教育歴が関係しているのか。小さな企業で働いている人なのか、逆に大企業で働いている人なのか。などといった一定のプロファイルが出てくれば、将来へのヒントが得られると思います。つまり、それらに準じた職場環境を増やしていけば、生き生きと働ける人たちも増えていくのでは-という仮説が成り立つわけで、次のステップにいけるのではないでしょうか。
執筆/内田丘子(TANK)
※所属・肩書きは取材当時のものです。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ