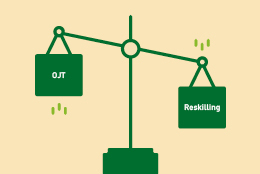収集方法から分析、活用まで「データの読み書きそろばん」を教える「DX寺子屋」
三重県ではコロナ禍をきっかけに、「稼ぎ頭」である製造業の潜在的な課題が浮き彫りになった。有識者会議が新たな製造業の在り方を検討した結果、デジタルトランスフォーメーション(DX)を通じて組織やビジネスモデルへの変革を促す必要がある、という結論に至り、DX支援の施策が打ち出された。
施策のなかで注目されるのは、参加者が自分の職場で得たデータを「教材」にして、その活用方法などを学ぶ「DX寺子屋」と、DX寺子屋の卒業生を「DX伝道師」に育成する取り組みだ。三重県雇用経済部ものづくり産業振興課班長の葛山美香氏、主事の伊東萌氏に寺子屋の内容や、支援の際に重視していることなどについて聞いた。
企業の半数がDXを知らない 人材や情報が不足
―――県がDX支援に取り組むようになった経緯を教えてください。
県では以前から、製造業におけるDXの必要性が議論されていました。コロナ禍を受けて、サプライチェーンが毀損して部品調達に支障が出たり、非対面のビジネスが求められるようになったりと課題が顕在化し、今まで以上に危機意識が強まったと感じています。
まず県内企業の実情を知るため、製造業3264社にアンケート調査を実施しました。すると回答企業の56.5%が、DXという言葉を聞いたことがないとの回答でした。
また企業の78.5%は、事業戦略見直しの必要性を感じていましたが、人材や情報が足りずどこから手を付けていいか分からない、必要な協力相手を見つけられないなどの理由で、そのうち半数以上は見直しに取り組めていない状況でした。
今後、中小企業が生き残るには、データやデジタル技術を使って顧客や社会のニーズを把握し、ニーズにかなった製品やサービスを生み出すことが不可欠です。そのためには、アウトプットを生み出す組織や企業風土から、変革する必要があります。こうした変革を推進していくため県は2021年7月、企業のDX推進を促すための組織「デジタルものづくり推進拠点」を設置しました。
―――拠点の主な活動を教えてください。
相談対応と、「DX寺子屋」「DX伝道師」による人材育成、そして協力企業や団体との交流・マッチングという3本柱で進めています。
マッチングについては、高等教育機関や金融機関、商工団体、デジタル技術を持つ企業などに「サポーティングパートナーズ」として登録してもらい、課題を抱えた中小メーカーへ、デジタル技術を活用したソリューションなどを提供してもらいます。さらに地域の金融機関とITの専門家が連携し、財務諸表や原価計算など中小製造業のバックヤードの見える化なども支援していきたいと考えています。
DXの具体的なイメージを持てない企業も多いと思うので「下請け体質から脱した」「新事業を創出した」といった成功事例を1つでも早く作って、周囲の企業にDXのメリットを知ってもらうことが、当面の目標です。
自社のデータが「教材」に 実践的なスキルを学ぶ
―――DX寺子屋の概要を教えてください。
DX寺子屋は、経営者向けコースと現場改善コースの二つに分かれています。組織全体の変革には、経営者のデジタル技術に対する理解を深めることが不可欠なので、経営者向けのコースを別建てで設けました。いずれのコースも2021年7月から2022年1月まで計12回、オンラインとリアルのハイブリッドで開催します。
東大の産学連携プロジェクト「東大グリーンICTプロジェクト(GUTP)」代表の江崎浩東京大学大学院教授に有識者会議の座長をお願いした縁で、寺子屋にも全面的な協力をいただきました。講師もGUTPステアリング委員の中島高英氏に務めてもらっています。
特に大々的な宣伝はしませんでしたが79人もの参加者が集まり、DXへの関心の高さがうかがえました。参加企業は規模も分野もさまざまで、一つひとつの手作業を大切にする企業からの参加者や、さぁ、これからデジタル技術を学ぼうという意欲をお持ちの方もたくさんみえます。
―――具体的には、どのようなカリキュラムになっているのでしょう。
参加者にはまず、データに基づいて事業戦略や課題を考えるという「データ思考」を伝えます。その上で、データを集めて分析し、次の戦略に活かす方法を、具体的に学んでいただきます。「教材」にするデータは、自社のどの機械にセンサーをつければ現場改善やリードタイムの短縮につなげられるのか、といったことを参加者自身で考え、収集していただきます。データの「読み書きそろばん」を教える塾、という意味合いで、「寺子屋」という名前が付けられました。
さらにDX寺子屋の卒業生を伝道師に認定し、地元の他の企業にも、DXを広めてもらいます。さらに社内でも、従業員のリスキリングを主導してもらえればと思います。
カリキュラムには、参加者の交流を目的とした事例発表なども盛り込んでいます。変革を志す企業のコミュニティを作ることも、DX寺子屋の目的の1つです。
―――DX寺子屋での「コミュニティづくり」はなぜ必要なのでしょうか。
「寺子屋」という言葉には、落ちこぼれを作らず学び合いと交流を深める場、という意味も込められています。企業は、機密事項が壁になって横の連携を取りづらい側面もあり、経営者も相談し合える同士を求めているのだと思います。しかしDXを実践してもらうためには、企業同士が機密に触れない部分で悩みを共有し、切磋琢磨(せっさたくま)する必要があると考えました。
「デジタル化をこんな風に進めたら生産性が上がった」「従業員にこんな提案をしたら受け入れられた」といった仲間の事例を知ることで、「あそこが頑張っているから自分も頑張ろう」と考えるようになると思います。それによって、参加者がともに成長できるのではないかと思います。
デジタル導入を目的にしない DXの本質は働く人の負担軽減
――DX支援で、最も重視していることは何でしょうか。
デジタル技術の導入、そのものを目的にしないことが大切だと思います。AIやIoTを入れれば、社内がすべてバラ色に変わるわけではありません。従業員の働きやすい仕組みを作って生産効率を上げたい、不良率を下げたいなど、企業のニーズや困り事はそれぞれ異なります。自社の課題を踏まえた上で、解決に必要な技術を導入することで初めて、DXの効果が出てくると思います。
私たちも、企業各社のニーズにかなったサポーティングパートナーをマッチングするなどして、それぞれの課題に対応したいと考えています。
―――中小企業のDXを妨げる要因は何だと思いますか。
多くの企業が、デジタル技術を使いたいという漠然とした思いは抱いています。しかし費用がかかる、どこから取り組んでいいか分からない、といった心理的な抵抗感が壁になっています。
また、かつてベンダーなどに勧められるがまま汎用のツールを導入したが、お金ばかりかかって課題解決につながらなかった、という企業も多々あります。こうした事例に対する反省も、DXを目的にせず施策を進める理由の1つです。
―――リスキリングに取り組む企業からしばしば、「現場が変化を受け入れない」という悩みを耳にします。従業員に新しい技術を受け入れてもらうには、どうすればいいでしょう。
トップダウンで「デジタルツールを導入せよ」と命じるのではなく、従業員の困りごと解決にテーマを絞って導入すると、受け入れられやすいようです。例えば従業員の記入する日報について「紙からデータベースに変えれば、記載も簡単で用紙の紛失や置き場の確保に困らなくなって、楽になりますよ」といった持ち掛け方をすると、現場の抵抗感は和らぎます。私たちも、デジタル技術は本質的に、人を助けてくれる、人の活動の幅を広げてくれるということをアピールしていきたいと考えています。
「今、現場は何に困っているか」を分析した上で、その解決に適したデジタル技術を導入し、使いこなす。それによってヒューマンエラーが減って従業員が働きやすくなり、最終的には生産性が高まって企業利益が拡大する、また、新たな価値を生み出していく――というのが、私たちの目指すDXの姿だと思っています。
聞き手:大嶋寧子
執筆:有馬知子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ