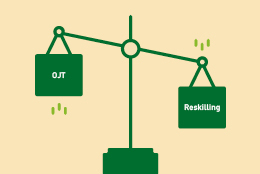隂山建設株式会社:経営者主導で全員の知識を底上げし、スクラムでデジタルを使いこなす企業を目指す
福島県郡山市の建設会社、隂山建設は十数年前、業界に先駆けてITを建設現場に導入する「ICT施工」を取り入れた。現在は、受注から竣工まで建設現場の状況を可視化するアプリ「Building MORE(ビルモア)」を自社開発し、外販も始めている。
ただ、隂山正弘社長は「従業員のITリテラシーは、とびぬけて高いわけではない」と強調する。高齢化が進む取引先の職人に、抵抗なくアプリを使ってもらう必要もあった。このため重視したのが、誰もが使いこなせるアプリを自分たちで作ることだ。
「簡単で壊れない」アプリで、誰もが使えるように
――御社では、多くの従業員がドローン操縦免許を持っているとのことですが、どのような必要性にもとづいているのでしょうか。
 社員へのインパクトが強く、なじみやすそうなドローンからDXを始めることで「面白そうだ、使ってみたい」という気持ちを引き出そうとしました。今は管理職以外の技術者の9割以上がドローンの操縦をマスターしています。そして、せっかくだからドローンによる空撮画像をお客さまに見ていただこうという発想が、建設プロセスをリアルタイムで確認できるアプリ「ビルモア」の開発につながりました。
社員へのインパクトが強く、なじみやすそうなドローンからDXを始めることで「面白そうだ、使ってみたい」という気持ちを引き出そうとしました。今は管理職以外の技術者の9割以上がドローンの操縦をマスターしています。そして、せっかくだからドローンによる空撮画像をお客さまに見ていただこうという発想が、建設プロセスをリアルタイムで確認できるアプリ「ビルモア」の開発につながりました。
ビルモアでは建設現場の写真画像を見てもらうだけでなく、見積書や打ち合わせの議事録なども閲覧できます。施主さまと担当者がチャットで話せる機能や、スケジュールを確認できるカレンダー機能も盛り込み、徹底的に「お客さま目線」を追求しました。
われわれ施工側もデバイス1つで現場を確認できるようになり、業務効率が改善したのです。現場監督の残業が減り、従業員も有休を取りやすくなりました。
――ビルモアの開発にあたって、心がけたことはありますか。
見積もりから竣工まですべての建設プロセスをカバーし、かつ機能はシンプルな、「広く浅い」アプリをスピーディに開発することです。携帯電話でいうと、「らくらくホン」のイメージです。画面が見やすく、操作が簡単で、誰でも使える。ここは外せないポイントでした。
当社だけでなく、多くの建設会社では、ITリテラシーの高い従業員はごく一部です。またビルモアは、社員だけでなく下請けを担う協力業者の職人にも使ってもらうことを前提としています。職人の中には、メールアドレスすら持たない人も多く、無理やり高度なデジタル技術を押しつけても、アレルギーを起こして「ついていけない」と言われてしまう恐れすらありました。経営者から新入社員、社外の職人にいたるまで、現場にいるすべての人が使えて、どんな操作をしても壊れないアプリを目指しました。このため、開発者から機能追加の提案が出ても、私が「そこまでは必要ない」とストップをかけることもありました。
「会社のため」から「お客さまのため」に現場の意識が変わった
――開発に必要なメンバーを、どのようにして集めたのでしょうか。
2018年にグループ内にIT開発会社を立ち上げ、地元のITベンチャーから社長と開発人材を招きました。また社内に「DX推進室」を作り、社員も開発に参加させました。社員が建設現場のニーズを吸い上げ、グループ会社の開発陣がそれを踏まえて、実際の作りこみを行っていくという形です。
グループ内に開発会社を作ってアプリを内製したことが、成功の大きな要因だと考えています。建設業の知識を持たないIT企業に外注するのでは、現場の作業員や職人までもが使えるアプリが出来上がるとは思えないのです。
今は協業を申し出てくれるプロ人材やベンチャー企業も現れ、「餅は餅屋」で外部の開発者の手も借りながら、それぞれの強みを活かすような形で取り組んでいます。
――ビルモアの導入後、社員の意識や働き方に変化はありましたか。
建築業界では、若手が雑用ばかりのような仕事に失望し、離職するケースが後を絶ちません。当社でも若手の主な仕事は、先輩社員の補助と現場の写真撮影です。現場の写真は何千枚にもおよぶことがあるのですが、以前は、竣工後にお客さまにまとめてお渡ししていたのです。お客さまも引き渡し後にこんなものをもらっても困る、と思っていたかもしれません。しかしアプリを導入してからは、リアルタイムでお客さまに、その日の現場の様子をお伝えできるようになりました。お客さまから直接「あの写真を見て、よくわかったよ」などと褒め言葉をいただけることも増え、若い社員がやりがいを感じ、向上心を持って仕事に取り組むようになりました。かつては、お客さまと直接には接しない現場の人々は、営業部門に比べて顧客満足に対する意識が低く、社内に温度差があると感じていました。ビルモアは徹底的に「お客さま目線」にこだわって作ったのです。これによって、現場も自然に「会社のため」から「お客さまのため」に仕事をするように、意識が変わってきました。
全従業員の知識を底上げしスクラムを組む 社長が学びを社員に共有
――従業員のスキルアップについては、どのような方針で取り組んでいますか。
 特定の社員をハイスキルな人材に育てるのではなく、全従業員のITの知識を底上げし、スクラムを組めるようにすることを意識しています。だからこそビルモアも、高いスキルがなくとも使いこなせるよう、アプリの方を現場のITリテラシーに合わせたのです。
特定の社員をハイスキルな人材に育てるのではなく、全従業員のITの知識を底上げし、スクラムを組めるようにすることを意識しています。だからこそビルモアも、高いスキルがなくとも使いこなせるよう、アプリの方を現場のITリテラシーに合わせたのです。
DX推進室も、文字通りDXを「推進する」という位置づけの組織です。推進室のメンバーがプロの開発人材になることが目標なのではなく、必要なデジタル関連の知識を社内に広めるのが部署の役割なのです。推進室の努力の甲斐もあって、今は若手だけでなく70歳を過ぎた人も、デジタルツールを受け入れています。
――従業員の知識を底上げするための、具体的な取り組みを教えてください。
まず、先ほどお話ししたとおり、グループ内に開発会社を立ち上げて会社の「本気度」を示しました。これによって、従業員に「職場にデジタルツールが入る以上、自分も変わらなければ」という覚悟を持ってもらったのです。
そして私自身、表計算や文書作成のソフトを使う程度の知識しかなかったので、私も含めた社員全員で、「プラットフォームって何?」「IoTってインターネットと何をつなぐの?」というレベルから、一つひとつ学んでいきました。
私は開発者をつかまえて質問したり、IT関連の会合で聞いた用語をすべてスマホに入力し、帰りの新幹線で検索したりして勉強しました。そして毎月の社員会議で、学んだ内容を社員にこんこんと話しました。自分たちと同じレベルの人から話を聞けるので、従業員も理解しやすかったと思います。
――建設業界のDXや、人材のスキルチェンジが遅れている理由は何だと思いますか。
DXが直ちに利益につながる、という期待をしすぎることが問題なのではないかと思っているんです。何かをデジタルに切り替えたり、ソフトやアプリを導入したりしようとしても、初期には設備投資がかさんでかえって利益率が低下することもあります。短期的に利益につながらないことには、経営陣は投資に踏み切れないものです。当社は幸いにして、私というオーナー社長が意思決定しさえすれば、会社を動かすことができました。利益が出るかどうかよりも、まずはお客さまのためになるかどうかを重視するんだ、と言い切れたのです。
さらに建設業界は99%が地場の中小企業で、特にビルなど一般建築の分野は、何層もの下請け構造が存在することも、現場のデジタル化を妨げています。先ほどお話ししたように、職人たちにツールを納得して使ってもらうことも容易ではありません。
社長就任直後に経営危機 挑戦し進化できる企業に
――隂山社長はなぜ、業界に先駆けてデジタル化を進められたのでしょう。
社長就任直後にリーマンショックが起き、発注者が破産してしまったという出来事がありました。当然、当社が進めていた仕事もストップし、資金繰りは悪化。毎月の給料の支給も危うくなり、廃業も考えるほどでした。周囲にも、3代目が3カ月で会社をつぶすなどと言われましたが、多くの人に助けられ、東日本大震災後の復興需要などもあり、何とか経営を立て直しました。こうした経験から、社会の変化に合わせて挑戦し進化できる企業にして、次の世代へバトンを渡したいという思いを持つようになりました。
――社員の意識や働き方が変わるなか、採用や人材育成の面で変化はありましたか。
当社は従来、新卒や技術者の採用に苦戦していましたが、この1~2年は5、6人が面接に来てくれるようになりました。企業説明会では学生たちの目の前でドローンを飛ばすなどして、同業他社との差別化を図れることが有利に働いていると思います。
さらに今年は、志望者の半分以上が女性でした。男性職場といわれる建設業でも、当社なら力を発揮できると思ってもらえたのは、嬉しい驚きでした。
労働力不足の解消には、外国人だけでなく女性、高齢者、誰もが活躍できる環境整備が不可欠です。このため女子更衣室などのハード面、子育てと両立しやすい働き方などのソフト面の両輪で環境整備に取り組んでいます。DXのプロジェクトは、結婚・出産を経て、現場に出るのが難しくなった女性技術者らの受け皿としても機能しており、経営陣から女性たちに、「職場環境を整備するので、皆さんも働き続ける覚悟を持ってほしい」と伝えられるようにもなりました。
――今後の取り組みについて教えてください。
建設現場の人手不足は深刻で、2025年までに職人の約3分の1がいなくなるといわれています。今後は、協力会社との情報共有や職人の勤怠管理などをデジタル化し、職人の労働環境の改善や、業界の質の向上、ひいては新たな人材の確保に貢献できればと考えています。
また当社では災害時に当社のドローンを被災地に飛ばして、行政や報道機関に提供することも増えています。このようにテクノロジーの力を活用して社会の課題を解決すること、例えば、平面画像からその地にある廃棄物の量を算出したりするなどの新しい取り組みにもチャレンジしていくつもりです。
聞き手:石原直子・石川ルチア・坂本貴志
執筆:有馬知子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ