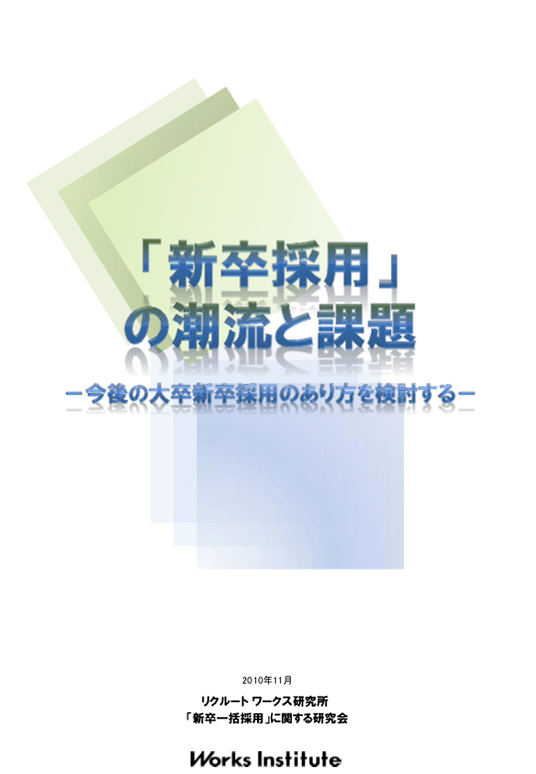インターンシップは再び迷走してしまうのか? ──豊田義博
用すべきではないと考えます。日本のインターンシップに、ターニングポイントが訪れている。様々な問題を抱えながら拡大を遂げてきた大学生対象のインターンシップが変わろうとしている。
産学協議会(※1)が時間をかけて議論してきた改革プランに、筆者は大きな期待を抱いてきた。しかし、その姿が明らかになるにつれて、懸念が湧きあがってきた。このままでは、成果を生み出せないのではないだろうか? インターンシップは、企業の新卒採用の一手段へと矮小化されてしまうのではないだろうか?
起点は1997年の三省合意
インターンシップとは、そもそも何か。短い単語で置き換えれば、就業体験、ということになるだろう。英語圏の意味を調べてみると、Wikipediaには“An internship is a period of work experience offered by an organization for a limited period of time.”と書かれている。出典はオハイオ州立大学の情報なので、本家での一般的な解釈と判断していいだろう。
日本では、1997 年に当時の文部省、通商産業省、労働省によって公表された「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(通称三省合意)の「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」という定義が広く行き渡っている。そして、定義には、経験機会を提供した企業などの組織・団体は、その際に取得した学生情報を広報活動や採用選考活動に使用してはならない、という趣旨の一文が付け加えられていた。この一文が、その後の日本でのインターンシップの展開の起点となっていく。
‘90年代初頭に展開を始めたインターンシップ
今日に至る経緯を簡単に振り返っておきたい。大学生対象のインターンシップ(以下インターンシップ)が日本において展開され始めたのは1990年代。日本の経済状況、産業構造、国際的な位置付けなどが大きく変容していく中で、それまでの高等教育と産業界の関係を見直そうという機運が高まり、そのシンボルのひとつとして注目されるようになった。この時代には、各経済団体から大学改革についての提言がなされているが、その中には、インターンシップをカリキュラムに組み込むという具体的な内容も盛り込まれている(※2)。
こうした機運を大きく後押ししたのが、1991年に施行された「大学設置基準の大綱化」だ。社会のニーズの変化に対応できるように大学制度を弾力化・柔軟化するとともに、各大学の自主的な取り組みを尊重するという趣旨のこの施策は、新たな学部やカリキュラムをたくさん生み出すことにつながっているが、インターンシップはその典型だといえる。
大学が主体となって実施するインターンシップが、このような経緯で日本社会に広がっていくのと並行して、企業主体のインターンシップも’90年代に立ち上がり始める。この時代に日本での新卒採用を強化し始めた外資系金融・コンサルが、採用活動の一環として優秀な人材をスクリーニングする目的で実施したのがその嚆矢だ。当時まだ存在していた就職協定で定められた選考活動解禁日よりはるかに早い時期に特定大学の学生だけを対象として実施されていたもので、その内容は就業体験ではなく、学生がグループになって課題を解決していくケースメソッドが主流であった。このスタイルが、現在多くの企業が実施しているインターンシップの原型のひとつとなっている。
こうした状況を受けて、1997年に上記の三省合意が取り決められたのだが、この年は就職協定が廃止され、大卒新卒採用市場が自由化された年でもあった。産業界としては、より実践につながる教育機会を大学界に期待し、その協力姿勢を示してもいたわけだが、就職協定が廃止されれば、インターンシップが採用活動早期化の温床となってしまいかねない。それが「その際に取得した学生情報を広報活動や採用選考活動に使用してはならない」という一文が付け加えられた背景である。
大学主導型と企業主導型の対照的な展開
この一文は、企業の姿勢に大きく水を差すものとなった。得られた接点や情報の活用を禁止されては、単なる慈善活動になってしまう。就業機会の提供は、現場にも少なからずの負荷がかかる。加えて、90年代後半はバブル崩壊後の景気低迷にあえいでいた時期であり、新卒採用の意欲も大きく減退していた。学生を社会全体で育成していこう、という総論には賛成しつつも、各論では協力を渋るというのが、多くの企業が取る姿勢となった。
かくして、大学のカリキュラムとして定着し、平成期を通じて実施する大学が増え続けた大学主導型のインターンシップは、産業界からの要請を受けて広く浸透していったにもかかわらず、その産業界からの協力が得られず、機会を得られる学生の数は伸び悩み、そして現在に至っている。内容的には、質の高いものも増え、米国のカリキュラムに引けを取らないCO-OPプログラム(※3)も誕生している(※4)のだが、量的な広がりは見られていないのが現状だ。
一方で、企業主体のインターンシップは劇的な広がりを見せた。企業の求人意欲が大きく回復し始めた2000年代中盤から、大学生との早期接触の機会としての活用が進んだのだ。その契機となったのは、就職協定廃止とともに日経連が定めた倫理憲章(※5)の改訂である。
1997年に制定された倫理憲章には、当初、採用活動開始時期などの具体的な日程は表示されていなかった。しかし、一部企業の早期からの採用活動に大学界から批判が集まったことを受け、「採用選考活動は、最終学年になるまでは行ってはならない」という趣旨の文言を付記することになる。2004年のことだ。
この文言によって、大学3年生との接点が持てなくなった企業が目をつけたのがインターンシップという存在である。「取得した学生情報を広報活動や採用選考活動に使用してはならない」という規制はあるものの、学生との接点をオープンに持つことができるこの存在を、企業は有効活用し始めた。しかし、その多くは数日以下の極めて短期のプログラムであり、その内容も、業界研究や課題解決・企画提案などの研修的なものが大半であり、就業体験の機会が織り込まれているものはごく一部に過ぎなかった。
企業の新卒採用意欲は、リーマンショック後に一次的に減退するものの、今日に至るまで堅調に推移し、インターンシップは広く浸透している。その実施率は、新卒採用実施企業の7割にも及ぶというデータもある(『就職白書2022』就職みらい研究所 リクルート(※6))。しかし、その内容は、インターンシップがこうして採用活動の隠れ蓑のような形で使われ始めてから今日に至るまで、大きな変化はない。就職みらい研究所が昨年実施した「2024年卒 インターンシップ・就職活動準備に関する調査」によれば、インターンシップないしはそれに準ずる機会に参加した学生のうち、プログラムが「1日以下」であったのは85.9%を占めている。「2~5日未満」は11.1%、そして「5日以上」はわずか3.0%に過ぎない(※7)。
産学協議会が示した4類型
ここまで見てきたように、インターンシップと名のつくものは、数多く実施されている。だが、学生にとって有益である就業体験を伴うものはごく一部であり、その多くはプレ採用活動として位置付けられている。産学協議会は、こうした実態を問題視し、2021年春に「ポスト・コロナを見据えた新たな大学教育と産学連携の推進」と題する報告書をまとめ、Society5.0を共創していく人材を産学協働で育成していくためのビジョンを描いた。そして、「第Ⅲ章 Society 5.0 の採用・インターンシップの実現に向けて」において、インターンシップを「学生が、その仕事に就く能力が自らに備わっているかどうか(自らがその仕事で通用するかどうか)を見極めることを目的に、自らの専攻を含む関心分野や将来のキャリアに関連した就業体験(企業の実務を体験すること)を行う活動(但し、学生の学修段階に応じて具体的内容は異なる)」と再定義し、産学協働の取り組みを以下の図表のようにまとめた。
図表:学生のキャリア形成支援における産学協働の取組み(全体像)
産学協議会の問題意識、方向性には概ね共感する。そして、この4類型にも、基本的には異論はない。現状では企業主導型インターンシップの90%以上を占める「見せかけのインターンシップ」をタイプ1・2に切り出し、就業体験を伴うタイプ3・4だけがインターンシップという名称を掲げることを許される。そして、タイプ3・4を増やしていくために「取得した学生情報の広報活動や採用選考活動への使用」を認める。理に適ったものだと思う。しかし、この区分によって、これまで大学が実施してきたインターンシップの一部に、「インターンシップ」という名称が使えなくなる、ということが、大きく引っかかるのだ。
有益な取り組みなのに、インターンシップという名称が使えない?
その内容は、昨年末に産学協議会が発行したFAQ集(※8)にも、以下のように明確に記述されている。
Q4)職場体験を伴う学部1・2年生を対象としたプログラムを従来、「インターンシップ」と呼んできましたが、2023年度以降は、当該プログラムでは「インターンシップ」という名称は使用できなくなるということでしょうか。
・はい、使用すべきではないと考えます。
・産学協議会における検討において、特に大学側から、「学生にとって、就業体験活動の主たる目的が、学部1・2年生の場合は『その仕事・業務について知ること』である一方、学部3年生以降は『その仕事・業務・職種に対する学生自らの能力を見極めること』であり、外形的には同じ就業体験活動であっても、その目的は対象年次によって異なる」という指摘が多く出されました。
・ そうした指摘を踏まえ、「タイプ3」のインターンシップは、あくまで学部3年生以降に実施するプログラムに限定することとしました。
新定義に基づけば、この「決定」もまた合理的なものだといえる。しかし、大学サイドから、「主たる目的が違う」という指摘が実際にあったとしても、その指摘を踏まえて、低学年の就業体験プログラムには、インターンシップという言葉を使ってはならない、という決定を、どう理解すればいいのだろうか。これまで苦心しながら低学年からのインターンシップカリキュラムを育んできた大学界が、そのような決定を望まないことは火を見るより明らかだ。文部科学省も、これまでのキャリア教育施策において、低学年からのインターンシップを推奨してきている。そもそもインターンシップは就業体験を意味する一般名詞である。それに該当するものにその言葉を冠してはならない、などという理不尽が許されていいものか。
なぜこのような決定がなされるのか。それは、ひとえに採用活動の早期化を恐れるからなのだろう。インターンシップが採用活動につながることを、グローバルスタンダードに合わせて、認めていこう。しかし、それによって、採用活動の早期化が促進されてはならない。ならば、時期の規制をしよう、という意図によるものなのだろう。インターンシップという言葉を、現在すでに盛んになっている3年生の夏休み時期より前(2年生の春休みなど)に使わせない、つまりはインターンシップを悪者にしないための決定なのだろう。背景にあるポイントは、25年前の三省合意と同じなのだろう。
この決定をもとに、タイプ3のインターンシップは、増えていくであろう。しかし、大学3年生以降に限定するということは、インターンシップが採用の一手法に矮小化されてしまうことをも意味する。日本のインターンシップは、新たなガラパゴス化への道をまた進んでしまうのだろうか。また、この決定自体も、早期化を引き起こすだろう。現に、大学3年生の前期期間中にインターンシップを実施しようとする企業の動きが生まれている。また、インターンシップという名前が使えなくなるからといって、タイプ1・2の形をとった企業主導の情報提供・機会提供が減ることはないだろうし、この新たな枠組みを踏まえた低学年へのアプローチも増えていくであろう。開始時期を規制すると、その規制を最大限に生かした施策や、規制を逆手に取った施策が生まれてくる、というのは、戦後から一貫した日本の新卒採用の見慣れた風景である。歴史はまた繰り返すのか。
多様性を大切にしよう。時期の規制をやめよう。
改めて問いたい。今回の改革は、何を目的としたものなのか? Society5.0人材を数多く生み出すために、産学が協働して様々な機会を生み出していくことではないのか? もしそうであるならば、時期の規制を盛り込むことは見送ってほしい。タイプ3・4の機会提供時期は、学年を問わず、という形にしてほしい。
それでは、採用活動の早期化を助長するのではないか、という危惧があることは十分理解している。そして、そのようにすれば、大学2年次からアプローチを開始する企業が現れるであろうことも承知している。しかし、それはごく限られたものになるはずだ。時期の規制がなければ、右へ倣え、という日本の悪癖は生じることはない。それもまた歴史が証明している。
高度成長以降の日本の新卒採用市場に、開始時期の規制がなかった時期がある。就職協定が廃止されてから、倫理憲章に開始時期の規制が盛り込まれるまでの7年ほどの期間である。この時に新卒採用市場はどうなったか。一部の企業は、やはり早期からのアプローチを開始した。廃止前の就職協定は、4年生の7月から解禁であったが、それ以前から採用活動を開始する企業が、時の日経連加盟企業でも現れた。その時期は徐々に前倒しされ、やがて3年生の春休みに選考活動をする企業も出始めた。
しかし、大半の企業は、7月から採用選考活動をスタートしていた。時期の定めがなくなることで、全体がどんどん前倒しするのではないか、という声は各方面から聞かれていたが、早期化は一部の企業に限られた。この時期に起きていたのは、分散化だったのだ。3年生の春休みにも、4年生の夏休みにも、そして、秋から冬にかけても。春と秋に採用する企業も、通年採用に切り替える企業も出てきた。しかし、その一部企業の早期化を問題視し、倫理憲章に時期の規制を謳ったことで、各社の採用開始時期は4月へと収斂していったのだ。
就職協定が廃止された1997年当時、就職情報誌の編集長であった筆者は、これから起きるであろう変化に大きな期待を寄せていた。そして、その変化を「集団お見合いから自由恋愛へ」という言葉にして発信していた。学生と企業が定められた短い時期に同じような形でお見合いをするような就職活動ではなく、様々な時期に様々な出会い方をし、相思相愛の相手を見つけていくような就職活動へ。その期待は、現実のものとなりつつあった。もちろん混乱もあったが、好ましい方向へと推移していた。
あの時、倫理憲章に時期の規制が謳われることがなければ、もっと自由で選択肢の多い世界が生まれていたに違いない。現在のように、大学生全員が大学に入学した時からシューカツのことを考えて憂鬱になり、働くことに後ろ向きになってしまうような閉塞的な世界ではなかったはずだ。社会では多様性が大切だといわれながらも、みんなが3年生の夏にはインターンシップに行き、春休みにはエントリーシートを書き、同じ色のリクルートスーツを身にまとう、というような画一的な状況を変えていかなくてはならない。
今回のインターンシップの改革は、今も変わらずに集団お見合いを繰り返している日本の就職活動・新卒採用活動を変える契機になり得るものだ。そして、その機会とするためには、時期に関する規制をしないことが肝要である。産学協議会の勇気ある決断を、心より望みたい。
(※1)正式名称は「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」。経団連と国公私立大学の代表者により構成される。
(※2)経済同友会『「選択の教育」を目指して』 1991 年/日本経営者団体連盟『新時代に挑戦する大学教育と企業の対応』1995年
(※3)大学で受ける科目授業とインターンシップが組み合わされたプログラム
(※4)文部科学省が令和3年度に行った「大学等におけるインターンシップ表彰」において最優秀賞を受賞した大阪夕陽丘学園短期大学のカリキュラムは、その一例である
(※5)正式名称は「採用選考に関する企業の倫理憲章」。後に「採用選考に関する指針」と改められ、2021年に廃止に至っている。
(※6)https://shushokumirai.recruit.co.jp/wp-content/uploads/2022/02/hakusho20220221_01-1.pdf
(※7)https://shushokumirai.recruit.co.jp/wp-content/uploads/2022/11/topic_24s_20221115.pdf
(※8)「よくあるご質問(FAQ)-産学協働による学生のキャリア形成支援活動(4類型)の実践-」2022年12月27日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ