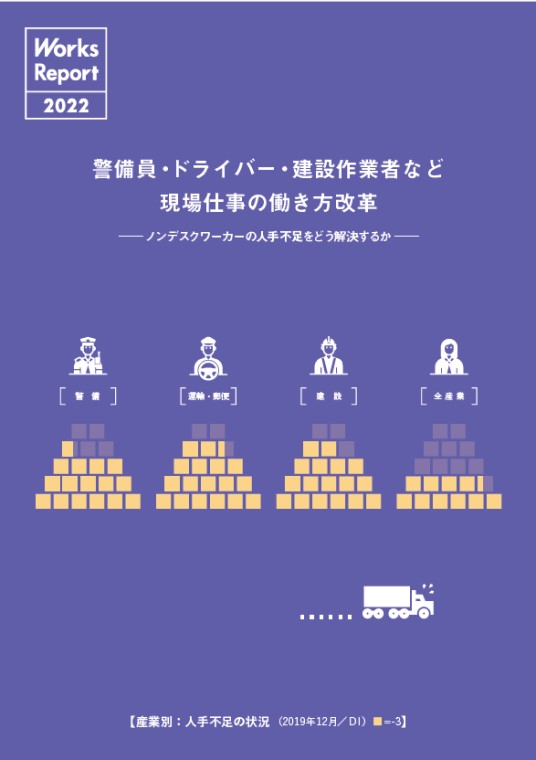なぜ今最低賃金を引き上げるべきなのか― 坂本貴志
短時間労働者の時給が上昇している
近年、最低賃金の引き上げが続いている。最低賃金の全国加重平均は2010年度の730円から足元である2021年度の930円まで断続的に引き上げられている(図表1)。
もちろん最低賃金を引き上げたところで、実際の労働者の賃金が上昇しなければ意味がない。この点、賃金が上がらないという問題が世間を賑わせているように、政策がうまく効果を発揮していないという感覚を持っている人も少なくないのではないだろうか。
しかし、結論を言えば、最低賃金の影響をうけやすい短時間労働者の賃金は実際に大きく上昇している。図表2は厚生労働省「毎月勤労統計調査」からパート労働者の時給を算出し、その推移をとったものである。これを見ると、近年、パート労働者の時給は急速に増加していることがわかる。2021年は新型コロナウイルスの感染拡大(コロナ禍)で最低賃金の引き上げ幅が+0.1%にとどまった影響もあり、前年比+0.9%と小幅な伸びにとどまっているものの、その前年度は+4.5%の上昇と大きく増加している。
なお、最低賃金の決定プロセスとしては、まず最新年度の最低賃金が厚生労働省の中央最低賃金審議会で決まり、それを目安に都道府県が最低賃金を決めることになる。そして、その金額が市場で反映されるのは例年10月頃となるので、最低賃金が実際の賃金に影響を及ぼすまで1年程度のラグがある。このため、コロナ禍で2020年度の最低賃金の引き上げ幅が抑制された結果は主に2021年度に顕在化している。
図表1と図表2を見比べると、最低賃金とパート労働者の時給はよく連動しているように見える。ただ、近年のパート労働者の時給上昇のどの程度が最低賃金引き上げによるものなのかはよくわからない。というのも、近年は多くの業界で人手不足が深刻化しており、市場における賃金の上昇圧力が高まっている。足元の賃金上昇が実際の労働市場の需給逼迫が牽引しているのか、政策効果によるところが大きいのかは判断が難しいところである。
ただ、こうしたなかで近年のパート労働者の時給の増加率を見ると、最低賃金の引き上げ率に決して見劣りしない水準になっている。もし、最低賃金が実勢の賃金を主導しているのであれば、パート労働者の時給は最低賃金に限りなく漸近していくはずである。しかし、最低賃金の推移と実勢の賃金の伸びを比較してみると、必ずしもそのような状況にはなっていない。このため、実際の賃金上昇はおそらく労働市場の逼迫が牽引している部分がたぶんにあるのだろうと考えられるのである。
図表1 最低賃金の推移(全国加重平均) 出典:厚生労働省「地域別最低賃金改定状況」
出典:厚生労働省「地域別最低賃金改定状況」
図表2 パート労働者の時給 出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査」
出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査」
最低賃金の引き上げは雇用の減少を招くか
経済学の理論上、最低賃金引き上げの大きな問題点として指摘されるのは、それが雇用の減少を招く可能性があるということである。最低賃金が引き上げられて、経営者が高い人件費を払うことにためらいを感じれば、低賃金で働いていた人の雇用が失われてしまうと懸念される。
この点、最低賃金の引き上げが経済全体にとって好ましいものになるかどうかは、その時々の経済環境に大きく依存する。つまり、失業率が高く、働きたいのに働けない人が労働市場に多くいる環境下においては、最低賃金の引き上げは好ましくない。最低賃金の引き上げを行うと、企業が採用を抑制してしまい、失業者が市場にあふれてしまうからである。一方で、企業が深刻な人手不足の状態に陥っており市場に働き手が不足している状況下にあれば、最低賃金の引き上げはそのデメリットよりメリットの方が上回ることが予想される。
それを踏まえて、現在の日本の労働市場の状況を振り返ってみれば、最低賃金引き上げのデメリットを憂慮するような状況にないことは明らかである。
総務省「労働力調査」によると、足元の失業率は極めて低い水準で推移を続けている(図表3)。コロナ禍以前には2%台前半まで低下しており、ほぼ完全雇用に近い状況だったと言ってもよいだろう。さかのぼってみると、失業率が最後に2%台前半にまで低下したのは1993年のはじめのことである。この時期はまだバブル景気の余韻が残っていた時期で、日本経済が右肩上がりで拡大していくという期待がまだあった時期にあたる。すなわち、日本経済が拡大を続けることを前提として企業が採用意欲にあふれていた当時の状況と同程度の水準まで、需給は逼迫しているということである。
また、コロナ禍での景気後退局面においても、失業率の上昇が抑制されていたことにも注目される。景況感を表す指標である景気動向指数(CI)との連動を見ると、CIが77.9まで落ち込んだ2020年半ばにおいても、失業率は3.0%にまでしか上昇しなかった。これには、雇用調整助成金の活用や政府が行ったコロナ対策のための財政出動などがうまく機能したという側面もあるだろうが、より本質的には目下の構造的な人手不足が背景にあるのだと見られる。リーマンショックで景気が落ち込んだ2009年から2010年頃の動きと比較しても、現在の労働市場の構造変化がはっきりと浮かび上がってくる。
これは企業の人手不足感の状況を示す日銀短観の雇用人員判断DIで見ても同様である。雇用人員判断DIは、人手が過剰であると答えた企業の割合から不足であると答えた企業の割合を引くことで算出される指数であるが、これも概ね失業率と同じ傾向を示しており、企業は未曽有の人手不足に見舞われていることが理解される。ここ最近は景況感が悪化してもなお労働需給が逼迫したままの状態にあるほど、構造的な人手不足社会に突入しているのである。
図表3 人手不足と景況感 出典:内閣府「景気動向指数」、日本銀行「日銀短観」、総務省「労働力調査」
出典:内閣府「景気動向指数」、日本銀行「日銀短観」、総務省「労働力調査」
需給双方の要因によって、労働需給は逼迫している
コロナ禍前後で状況は変わっているものの、近年、特に人手不足感が強い業種には運輸・郵便、建設、介護(対個人サービス)、小売などの業種があげられる(図表4)。こうした生活に密着したサービスについては、人手不足により十分なサービスの提供が難しくなっている。
日本経済において人手不足がここまで深刻化しているのはなぜだろうか。それはまず第一に、日本社会が生産年齢人口減少局面に入っているからだろう。少子高齢化が進む日本社会において、多くの業界で体力と気力あふれる若手や中堅の労働者への採用ニーズが急速に高まっているが、需要に対して供給が追い付かず、人員が充足しない状況が続いている。これに対応して高齢者や女性の労働参加が急速に拡大しているが、こうした労働力を活用してもなお、人手が足りないほどの人手不足局面に入っているのである。
第二に、労働を需要する側である消費者側の要因もある。日本経済を語るとき、失われた数十年という言い方はすっかり定着した感もあるが、実はこの数十年間においても日本経済はゆっくりとではあるが着実に豊かになっている。
実際に、日々の生活を振り返ってみても、以前と比べて人々の生活の質が改善していることは確認される。例えば、現代において、コンビニエンスストアが全国に配店されたことで、質の高い製品をいつでもどこでも買えるようになった。また、全国に張り巡らされた物流網によって、インターネット上でボタン1つ押すだけで、日本中どこに暮らしていても自身が望む商品が即座に自宅まで届くようになった。介護保険法が施行された2000年以降、介護サービスは着実に広まっており、安価で高い質の介護サービスを誰でも受けることができるようにもなっている。
こうした質の高いサービスを維持、向上させていくには多くの人手が必要となる。消費者のもっと豊かな生活を送りたいという欲望が、労働へのニーズを着実に高めているのである。そして、このような状況があるからこそ、多くの業界で構造的な人手不足が発生している。
図表4 雇用人員判断DI(業種別) 出典:日本銀行「日銀短観」
出典:日本銀行「日銀短観」
最低賃金はもっと大胆に引き上げてよいのではないか
労働市場が完全に競争的であれば、最低賃金のような政府の介入を伴う施策は必要としない。労働者が自由に労働移動できて、完全競争下で企業が財やサービスの価格などを完全に決めることができるのであれば、自然と賃金が高い仕事に労働力が移動し、全体としての賃金も上昇していくからである。
しかし、現在の日本の労働市場は、経済学者が前提とするような完全競争の環境下にあるとはとても考えられない。
実際の労働者の行動原理を見ていれば、すぐ近くの場所に労働条件が良好で、かつ時給がもっと高い仕事があるにもかかわらず、働き慣れた仕事で実直に働き続ける「非合理的な個人」はどこにでもいることに気付かされる。また、働き方改革の流れによってだいぶ潮目が変わってきているものの、日本の労働市場において、従業員の処遇や待遇面で大きな問題を抱える企業が存在し続けてしまう状況もある。
例えば、本来であれば中小企業の成長を促すためのいくつかの施策が、生産性が低い企業を温存させることにつながってはいないか。また、技能実習生といった外国人の技能の習得を目的としている施策について、企業が外国人を単に安価な労働力とみなして活用している現状はないか。こうした一つひとつの施策について、本来の目的と実態とのねじれが、市場メカニズムの機能不全の原因の1つになっているのかもしれない。
日本の労働市場の競争環境の不完全性や足元の深刻な人手不足の状況を振り返ってみれば、こうした日本の労働市場の現状を抜本的に変えていかなければならない。
そうした観点からも、最低賃金の引き上げはもっと大胆に行ってもよいのではないか。こうした政策によって、市場メカニズムを健全に発露させることが必要だと考えるのである。
高い労働コストは技術革新の原動力
そして、今日本の労働市場が積極的に最低賃金の引き上げを行うべきと考える最も大きな理由は、多くの産業でいよいよ先進技術による機械化や自動化が実装段階に入りつつあるからである。
近年、情報技術の発展などによって、あらゆる産業で機械化・自動化の波が起ころうとしている。例えば、運輸業界であれば、技術の進歩によって高速道路における無人走行や隊列走行が社会で実装されれば、トラックドライバーは長年苦しめられてきた長時間労働から解放されることになるだろう。また、荷役の機械化によって、重い荷物を手作業で上げ下げする作業からも解放することができる。
介護の仕事においても同様である。ロボットによる介助が可能になれば、人手不足が深刻な介護業界を持続可能なものとすることができる。介護士が重労働である入浴介助の仕事に従事せずに済むようになれば、要介護者とのコミュニケーションにより多くの時間をさけるようになる。
経営者がこうした新しい技術の導入の可否を決める際に考慮するのは、当然、その投資が人件費との見合いで実際に回収できるかどうかである。つまり、これからの技術革新如何は労働コストの多寡が決定的に左右するのである。
少子高齢化によって深刻な人手不足社会を迎えている日本において、新しい技術を労働者の脅威とみなすことは誤りである。あらゆる産業で仕事の機械化・自動化を進展させ、人々を単純労働から解放することで、人はもっと人間らしい仕事に従事することができる。AIやロボティクスの発展による社会変革は、課題先進国である日本にこそ最も必要とされている。そして、実際にこうした技術を開発し、実装するだけの高い技術力を日本の企業は持っているのである。
今日本の技術発展の最も大きなネックとなっているのは、労働市場における安い労働コストだ。この問題さえ解決することができれば、世界最先端の技術領域で日本は世界をリードできる。高い最低賃金は、日本経済の高度化を促す原動力なのである。
坂本 貴志
※本稿は筆者の個人的な見解であり、所属する組織・研究会の見解を示すものではありません。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ