著者と読み直す
『妻に稼がれる夫のジレンマ』 小西一禎
夫も妻も『男は稼いでナンボ』の呪縛から逃れればお互いもっとラクに生きられる
本日の1冊
『妻に稼がれる夫のジレンマ』 小西一禎
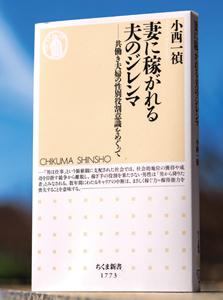 共同通信社の記者だった著者は2017年、妻のアメリカ赴任に同行するため休職し、2人の子どもを連れて渡米。仕事漬けの日々から扶養される立場に変わったことで、アイデンティティーの危機に直面した。その経験から、駐在員の夫や自分より高収入の妻を持つ夫たちを調査。稼ぐ力と「男らしさ」をめぐる葛藤と、彼らが苦悩の末に見出した新たな価値観・生き方を明らかにし、夫も妻も共に活躍できる社会に向けた処方箋を提示する。(筑摩書房刊)
共同通信社の記者だった著者は2017年、妻のアメリカ赴任に同行するため休職し、2人の子どもを連れて渡米。仕事漬けの日々から扶養される立場に変わったことで、アイデンティティーの危機に直面した。その経験から、駐在員の夫や自分より高収入の妻を持つ夫たちを調査。稼ぐ力と「男らしさ」をめぐる葛藤と、彼らが苦悩の末に見出した新たな価値観・生き方を明らかにし、夫も妻も共に活躍できる社会に向けた処方箋を提示する。(筑摩書房刊)
駐妻ならぬ駐夫=海外駐在員の夫が、増えている。フェイスブック上の「世界に広がる駐夫・主夫友の会」のメンバーは2018年の発足時の4人から現在160人に。著者の小西一禎さんは同会を主宰する元共同通信社の政治部記者だ。
小西さんが休職し駐夫になったのは45歳のとき。逡巡しながらも「家族一緒がいちばんだから」と決心した。だが、いざアメリカでの生活が始まると深刻なアイデンティティー・クライシスに陥った。
「妻や子ども2人を送り出したあと、自分には行くところがない。働く身でなくなった現実を突きつけられ、『俺は何やってるんだろう』と。決定的だったのは、親しくしていた他社の記者がワシントンに赴任し、家族で遊びに行ったとき。政治談義のあと、『ところで小西さんは毎日どんな生活を?』と聞かれ、屈辱感に打ちのめされたんです。一切の家事ができなくなって10日間寝込みました」
男としてのプライドが傷つき、キャリアへの不安を募らせる自分とは対照的に、妻は海外赴任の夢を叶え、生き生きと働いている。見下されているような気がして、ことあるごとに「俺はついてきてやった感」を振りかざした。
しかしその後、小西さんは立ち直る。かけがえのない数年間を楽しもうと気持ちを切り替え、「駐夫」として自らをブランディングし、各メディアに寄稿した。最終的には退職して独立。
帰国後は大学院で、自身やほかの駐夫の経験を学問的に捉え直し、社会に問題提起したいと修士論文に取り組んだ。本著はその修論がベースになっている。書籍化の際には、経済力や社会的地位が妻より劣っていると自認する夫たちにもインタビューし、その心の内を分析した。
稼げないのは男らしくない? 呪縛に苦しんだ夫たち
見えてきたのは、日本社会に根強く残る「男は稼いでナンボ」という、稼得能力と男らしさを結びつける考え方に、男性自身が縛られている姿だった。ある駐夫は、妻が稼いだお金での買い物を躊躇していた。別の駐夫は、夫婦喧嘩で言われた「今こうやって(海外に)住めているのは、私のおかげじゃん」という一言が頭から離れないと語った。妻の収入が自分を上回る夫は、自身も相応の収入を稼いでいるのに「ヒモみたいに感じることもある」と打ち明けた。
「私自身、駐夫時代は男が主たる稼ぎ手であるべきという意識に最後まで囚われ、モヤモヤが晴れることはなかった。インタビューした12人には20、30代もいましたが、若い世代も本音はそれほど変わっていないと感じました」
本書で出色なのは、男性たちが葛藤の末に価値観を転換させていく過程を鮮やかに捉えている点だ。駐夫たちは異国の地で、柔軟にキャリアを変えたり、効率的に働いて家族との時間を大切にする人々を間近に見て、日本にいたときとは異なる働き方、生き方を模索し始める。
「男は稼がなくてはならないのだから長時間労働は致し方ないし、家事育児の負担が妻に偏るのも仕方ないと考えていた過去の自分を、彼らは相対化し、違う道があると気づいたんです」
しかし、価値観が変わった彼らの前に、変わろうとしない日本企業の壁が立ちはだかった。
「日本企業はキャリア中断する男性に極めて不寛容で、『競争から降りた人』と捉えてしまう。本人たちは新しい価値観やスキルを身に付けパワーアップしているのに、復職組は飼い殺しにされ、転職にチャレンジした人たちも面接までなかなか漕ぎ着けず、辛酸を嘗めていました」
生き方を変えた夫たちに「希望」 男性がジェンダーを語る意義
しかし奮闘の結果、インタビューした駐夫全員が渡航前より働きやすい職場や望むキャリアを手にした。その事実に小西さんは「希望を感じた」。収入や社会的地位が格上の妻を持つ夫たちも、妻を心から応援し、旧来の性別役割意識から自由になっていた。彼らを「令和の時代の新たな男性像を体現した存在」と見る小西さんは、「今までは女性も男性に稼ぎ手役割を期待し、お互いに『男らしさ』『女らしさ』を押し付けあっていた。そこから解き放たれれば、男女ともに生きやすくなるはず」と力を込める。
だが、そんな小西さんも、男らしさの呪縛から逃れるのは容易ではなかった。政治部時代に親しかった議員や官僚、記者と再会すると、かつてのマッチョな自分が顔を出し、駐夫だった過去を隠したくなった。修論の内容を変えようとすら思ったところを、指導教授に「あなたにしか書けない」と言われ、我に返った。
「ジェンダー問題というだけで聞く耳を持たない男性があまりにも多い。かつての私もそうでした。だからこそ、男性である自分が語りかけることで、これまでと違った聞き方をしてもらえるのではないか。それが男性一人ひとりの意識改革に繋がればと願っています」
 Konishi Kazuyoshi
Konishi Kazuyoshi
ジャーナリスト。慶應義塾大学卒業後、共同通信社に入社。長く政治部記者を務めたあと、ニューヨーク転勤が決まった妻と家族で渡米。「世界に広がる駐夫・主夫友の会」代表。在米中、3年間の休職期間満期につき退社。専門はジェンダーやキャリア形成、政治など。修士(政策学)。
Text =石臥薫子 Photo=今村拓馬


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ