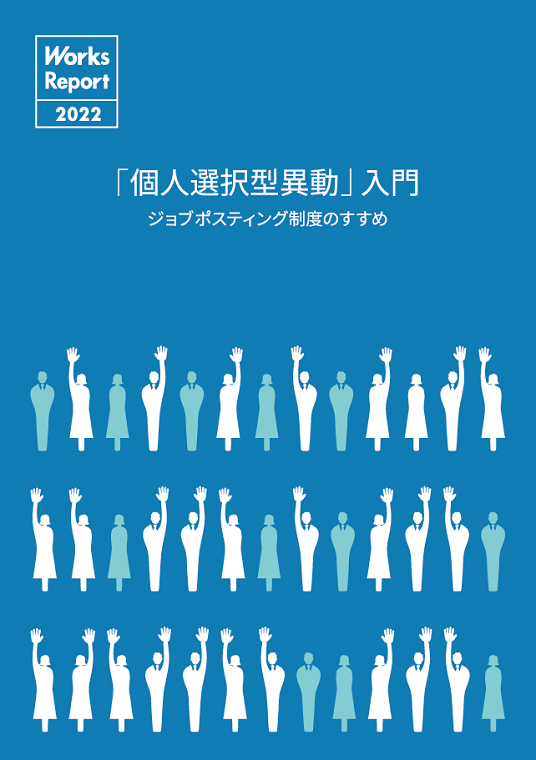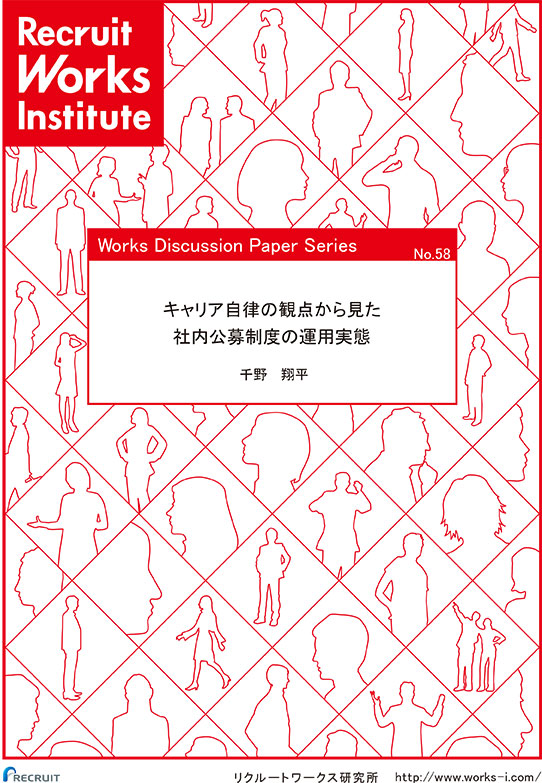企業で働く人の「育ち」 育ちの責任は誰が持つとよいのか
社員の価値観や目指すキャリアが多様化し、企業による一律的な人材育成には限界が生じつつある。ただ労働人口減少の中で、企業がより高い価値を生み出すには、働き手が成長し能力を発揮することが不可欠である。働き手の育成責任を誰が担うのか、神戸大学経済経営研究所の江夏幾多郎氏と、リクルートワークス研究所の千野翔平が話し合った。
ゆれる雇用下での社員育成 関係性の定義が不明確
千野:これまでの日本企業では、メンバーシップ型雇用のもとで新卒学生を中心に採用し、企業が用意したOJTやOff-JT、ジョブローテーションなどで人材の育ちを促していくという仕組みが主流でした。こうした企業主導の取り組みは、社員本人の幅広い職種、職能への対応力を高めましたが、各社員のキャリアを企業側が決めてきたとも言えます。つまり、個人による選択の余地は少なかったのではないでしょうか。こうした中での社員の「学び」について、どのように考えていますか。
江夏:学びの責任は、一義的には社員本人が担うべきでしょう。しかしご指摘の通り、日本企業は、社員のキャリア形成を主導していたがゆえに何をなぜ学ぶかを主体的に考え、会社に提起することを求めてこなかったし、社員の側も、自律的に学ぶ意識は希薄だったと思います。それをよしとする暗黙の合意も、組織と個人の間にあったようです。
千野:近年は、伝統的な日本企業が集団を一律に管理する上意下達の関係から脱し、個々の能力を発揮してもらうことを企業成長のエンジンにしようとする動きが表れてきました。私が企業のCHRO(最高人事責任者)に実施したインタビューでも、組織と個人が上下の関係ではなく、今までよりも個々が活きる関係、すなわち対等な横の関係へと変貌しようとする声が聞かれました。
江夏:その一方で、旧来の考え方から抜けきれていない企業や労働者も少なくありません。そこでは組織と個人の関係を再定義しきれないまま、組織の競争力も個人の働きがいも低迷しています。一般的に組織に参加する人々は、彼らの人格の一部、労働力という側面を組織に提供し、組織はその労働力に対応したインセンティブや役割を付与することで、労働力を組み合わせ、活用します。ただし日本企業の多くでは、組織が雇用や生活の保障と引き換えに「いつでも、どこでも、なんでも」という働き方を個人に求めてきました。包括的な査定ルールの適用もあって、個人が労働力以外の人格の広い側面を組織に提供する、という組織化が行われてきたのです。
しかし働くニーズが多様化する中、企業との一体化を行えない、行いたくない労働者が増加した上、強い一体感が企業の競争力の足を引っ張ることも増えてきました。組織と個人が別人格として関わり合いながらも双方が目的を達成するため、企業が経営のビジョンを、労働者がキャリアのビジョンを示しながら、相互に共感や合意ができる範囲で互いのリソースを提供する、という雇用関係も現実的になろうとしています。
もちろんメンバーシップ雇用を是とする労働者も減りつつあるとはいえ依然いるので、彼らをうまく引きつけ、力を引き出し、活かすことも不可能ではありません。ただ、そのハードルは上がっているし、そのことにうまく対応できなかった結果、上司が若手の育成や動機づけに悩む、若手が仕事に意義を見出せず社外ばかりに目を向けたりする、といったことが起きるのです。
社員への「成長」の丸投げは禁物 企業も責任を負う
千野:ここからは具体例を用いながら、企業で働く人の育成責任の所在について議論したいと思います。
近年は会社主導の異動を残しながらも、手挙げの割合を増やす企業が出てくるなど、個人選択型の異動が増えており、特に、社内公募制度が脚光を浴びています。多様化した個人がこれまで以上に能力を発揮し活躍するためには、ジョブローテーションによる育成ではなく、個々が自発的にキャリアを描ける環境が大事だとの認識が広まっていると考えられます。こうした取り組みは、一人ひとりのモチベーションを向上させ、企業にもメリットとして返ってきます。
江夏:社内公募制度が導入され始めたのは、企業成長が鈍化して新規事業展開も停滞し、新しいポストが生まれにくくなった時期でした。既存のポストも上がつかえて空かず、公募の枠を思うように用意できなかった。
今、個人選択型の異動が増えているのは、社内外の競争力のある人材の能力を活かしきりたい、という企業ニーズの高まりを示しています。手挙げの異動が広がることで、企業と労働者の合意形成の選択肢が増えるのは、組織にとってポジティブな変化だと評価しています。ただ、定期異動を中心とした会社主導の配置転換がメインとなっている構図は、そうすぐには変わらないと思います。
千野:会社主導の配置転換は、必要な時に必要な人材を、必要なタイミングで調達できるという、企業にとって好都合な仕組みです。こうしたメリットを一部犠牲にしてでも手挙げの異動を導入する企業は、社員が自分のタイミングで挑戦できる環境を整えることで、個々の能力を活かすと同時に組織の力も強めたいという思惑があるのでしょう。
ただこうした狙いのままでは、個人選択型の異動は、働き手の成長を本人の自己責任に帰する仕組みだ、という誤解を生みかねません。
江夏:そう思います。企業が社員に「成長」を求めるなら、前提としてどういう社員を全般的に、あるいはポストごとに求めているのか、どういう活躍をしてほしいのかを定義し、示す必要があります。そうすることで、より適切な対象が公募に応じるようになるし、選考を通過した社員にもそうでない社員にも、彼らの現状についてのフィードバックが行いやすくなります。しかし多くの企業はその責任を果たさず、漫然と「成長」を社員に丸投げしています。それでは社員もどのスキルを伸ばせばいいのかと、途方に暮れてしまいます。
企業側の求める人材像があいまいなままでは、たとえ社員が自分なりに研さんし、強みを身につけたとしても、その力を事業の中に位置づけることができず、成果に活かしきれなくなってしまうでしょう。企業は求める人材像を明確にした上で、空きポストとして用意して、社員に期待を示していくことが大事です。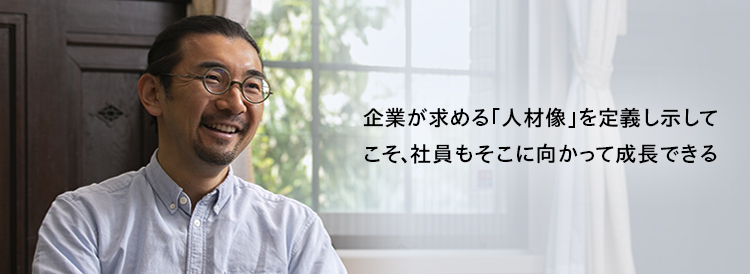
千野:社内公募制度をうまく運用できている企業は、人材要件定義を開示し、通年で求人の閲覧、応募をすることができます。また、結果が出た後に応募者全員と面談するなど、フィードバックも充実しています。こうした企業では、成長を社員に丸投げせず、必要な責任を果たそうとしているように見えます。
上司、募集する側の責任者、人事で育成責任を分担
千野:社内公募制度のフローには、社員の育ちに対する企業の考え方が表れていると思います。応募→書類選考→応募先との面接→合否結果の通知/フィードバック→最終意思確認→異動が一般的なフローですが、運用に成功している企業のインタビュー結果からは、人事も面接に同席したり、フィードバックのコメントを確認したりしていることが明らかになりました。「書類選考」や「応募先との面接」「フィードバック」には、募集する側も人事も関わります。したがって、応募者本人が育ちの責任をすべて負うのではなく、募集する側の管理職、応募者本人の上司や人事も育ちの責任を分担していくべきだと考えます。
江夏:おっしゃる通り、それぞれに役割や責任があると思います。社内公募制度への応募を決断したり、必要なスキルを身につけたりするのは社員本人ですが、上司も面談などを通じて、部下に「このポストを目指すならこういったスキルを身につけた方がいい」といったアドバイスをする必要があります。上司には、部下を囲い込もうとせず、挑戦を促すという大きな役割もあります。人事は、部下を囲い込むインセンティブを管理職が持たないよう、役割定義や評価制度の設計をしなければなりません。
募集する側の管理職も、評価基準という形でポストに求められる能力や役割、さらに仕事の魅力などを提示する責任があります。その上で応募者が基準に合致するかを判断し、合否にかかわらずフィードバックもすべきです。フィードバックが不十分では、社員が自らの適性や課題を見つけることができず、最終的には公募に挑戦する意欲も失われてしまいます。
千野:人事による社員の育ちへの関与も、求められていると感じます。社員からは「直属の上司には、公募への挑戦を相談しづらい」という声もありますが、人事なら中立的な立場で相談に応じ、キャリア形成をサポートできます。また、社内公募制度の特徴でもありますが、社員が現在所属する部をまたいでまったく異なる職務へ異動することが少なくありません。こうした異動者へのフォローもしていくべきだと考えます。さらに、人材を募集する職場にも、募集要項が会社の方向性と合致するよう助言したり、求人の打ち出し方をアドバイスしたりといったコンサルティング機能を果たせると思います。
実際に、私がある会社で実施したインタビュー結果では、公募に合格した人が、異動先で募集要項にない仕事を命じられ、働く意欲や組織への満足度が低下するケースが見られました。したがって、公募による異動者については、社内異動だからと受け入れを疎かにするのではなく、中途採用者と同レベルの受け入れ態勢を設計する必要があると考えます。人事と募集した職場によるオンボーディングが必要です。
江夏:従来の日本的な雇用慣行や仕事のルールを変えず、アドホック的に手挙げの仕組みだけ整えてもうまく機能しないということにも、注意が必要です。「社員は会社命令で何でもやる」という意識が抜けないと、「これもやって」と募集要項で示した範囲外の仕事を命じる、といったことが起きてしまうのです。
個人選択型を導入するなら、社員の責任範囲をあいまいにしたまま、業務が発生するたびに場当たり的に仕事を振り分ける、といったやり方は改めるべきです。要件定義にない仕事を命じる場合は説明し承諾を得るなど、合意を大事にする雇用関係に変わる必要もあります。
千野:社内公募制度は、企業主導の異動では見えなかった個人の才能や想いを実現できる仕組みであり、労働者のポテンシャルを高めることにつながると期待しています。一方で、個人だけに育成の責任を負わせるのではなく、上司や人事、募集した側の担当者なども分担して責任を引き受ける必要があることが、よくわかりました。こうした観点を起点に、企業で働く人の育ちについて引き続き考えていきたいと思います。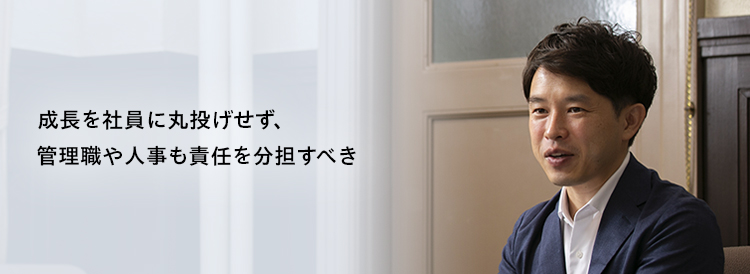
執筆:有馬知子
撮影:MIKIKO


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ