
構造的な人手不足と日本の今後 ―デービッド・アトキンソン氏との対話
 日本社会が直面する「労働供給制約」という構造的な人手不足の局面において、持続可能な経済基盤や生活維持サービスを再構築するには、どのような現状認識と課題の共有、そして変革が求められているのか。日本の産業構造が抱える本質的課題を直言してきた小西美術工藝社社長のデービッド・アトキンソン氏と、「労働供給制約社会」を提唱するリクルートワークス研究所の古屋星斗主任研究員が議論した。
日本社会が直面する「労働供給制約」という構造的な人手不足の局面において、持続可能な経済基盤や生活維持サービスを再構築するには、どのような現状認識と課題の共有、そして変革が求められているのか。日本の産業構造が抱える本質的課題を直言してきた小西美術工藝社社長のデービッド・アトキンソン氏と、「労働供給制約社会」を提唱するリクルートワークス研究所の古屋星斗主任研究員が議論した。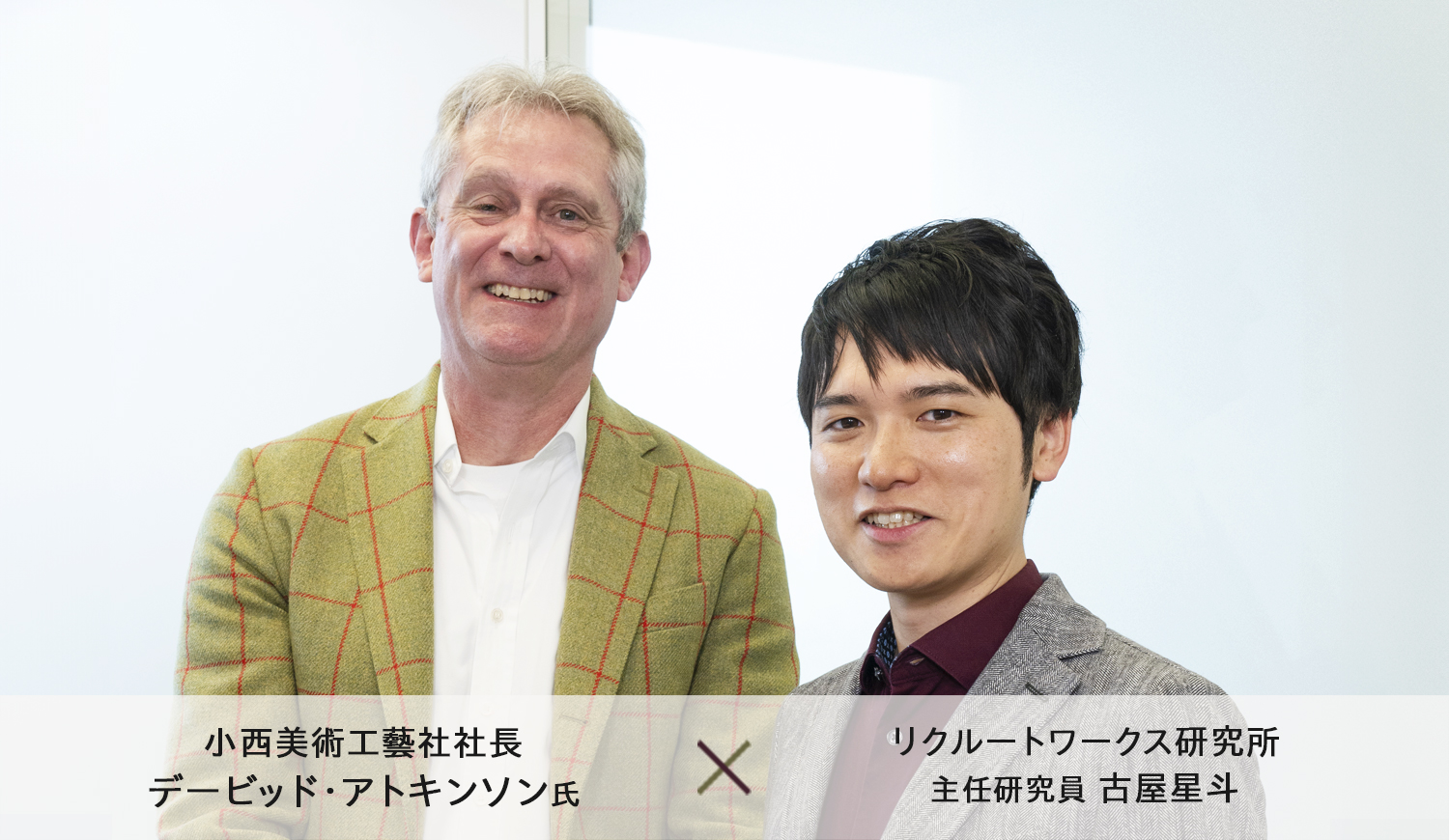
労働供給制約がはじまった
古屋:今起きている人手不足には、一過性ではない、人口動態に起因する構造的な背景があると考えています。特に高齢者人口の割合が高まることで医療、介護、物流など生活維持サービスを中心とする労働需要が高止まりする一方、労働供給は減少していく。私たちはそれを「労働供給制約」と呼んでいますが、この構造的な労働力不足についてどのようにお考えですか。
アトキンソン:今後より顕在化していくと見ています。高齢者を含めた労働参加率がほぼ上限に達する中、生産年齢人口が減り、さらに高齢化が進むと、私の計算ではあと数年で就業者数の純減が始まります。そうなると、大企業と一部の中堅企業しか新卒採用ができなくなるのも時間の問題です。高齢化によって介護・医療サービス分野のウェートがさらに増すことも問題です。生産性の低いこれらの分野に人材が集中すればGDP全体を押し下げます。
古屋:医療・介護を含む生活維持サービスの生産性の改善は喫緊の課題です。今後、日本で唯一増えるのは85歳以上で、2040年には人口構成の10%近くを占めます。著しく増大する医療・介護などの生活維持サービス需要に対応するため、現役世代の働き手が労働集約的な仕事に吸収されていく一方、イノベーションや設備投資に人材や資金が回せなくなる悪循環が懸念されます。こうなる前に、テクノロジーの力で効率を上げていくことも重要です。
アトキンソン:しかしそれも、分散型の経済だと効果は限定的です。日本の農家の耕地面積は平均3.4ヘクタール。この規模では機械化で採算が取れず、安価に雇用できる外国人就労者に依存せざるを得ません。日本企業の99.7%を占める中小企業には平均9人の従業員しかいません。85%は3.4人です。この規模で個別にDXを導入しても全体の生産性は大して上がりません。ベッド数が世界一の水準を誇る日本で、コロナ禍に 医療崩壊寸前の状況に見舞われたのも施設の分散が原因です。あらゆる分野で集約化は必須の課題です。
古屋:企業規模だけで語ることができないこともありますが、企業や労働者の分散が招くのは過当競争です。小規模事業者がひしめく物流業界では過当競争によって取引単価が不当に抑えられ、恒常的な労働分配率の低迷を引き起こしています。また、例えば若手の離職率も企業の規模によって大きな開きがあります。従業員30人未満の企業では採用後3年間で約60%が辞めていますが、300人以上の大企業だと約25%にとどまります。
アトキンソン:有給休暇の取得率や婚姻率、育休取得率なども規模が大きいほど高いですね。零細企業の多くは、存続の目的が「経費を使うこと」になっている面も否めません。資本金1億円以下の企業は年間800万円までの交際費を経費として処理できますから、経営者は公私混同して出費を経費として賄うことが可能です。コロナ禍の「ゼロゼロ融資」が顕著ですが、国の補助金は規模比例ではなくて、少ない金額で一律に上限設定することによって、小さな会社ほど恩恵のある仕組みになっています。こうした政策が経済の分散化を後押ししてきました。価格競争が唯一の生き残りの手段になっている会社を助けるのは、人口減少時代には悪循環を招く弊害でしかありません。
新たな”競争”
古屋:これはある種のチキンレースだと感じています。日本社会が悪循環に突入する方が早いのか、労働生産性を高める努力をしない企業が賃金上昇圧力によって退出を迫られる一方で、人に投資できる企業に働き手が集まるプロセスが先に進むのか。行政は後者のプロセスをより加速しなければならない。そうしないと、どこかのタイミングで生活維持サービスに必要な労働力を賄いきれなくなります。2024年現在、日本は34年ぶりの賃金アップの水準になっていますが、これも労働供給制約が背景にある以上、中長期的に継続すると見ています。大手を中心に、労働分配率もまだほとんど上がっていませんので余力はあります。
アトキンソン:継続すればいいんですけど……。実際はインフレに対応せざるを得なくなって賃金アップしている面はないですか。つまり、事後対応です。日本では、将来予想に基づいて先回りして対応する、というケースはあまり聞いたことがありません。物価が上がったから賃金を上げた、というのは日本らしい事後対応だなと感じています。
古屋:確かにそうした面も否めませんね。中小企業の経営者に今回賃金アップに踏み切った理由を尋ねると、「周りの会社や取引先も上げたから」と。つまり、横並びです。でも私はこうも思うのです、横並びでよいではないか、と。それは外部環境が変化した際に一気に変わることができるということでもあります。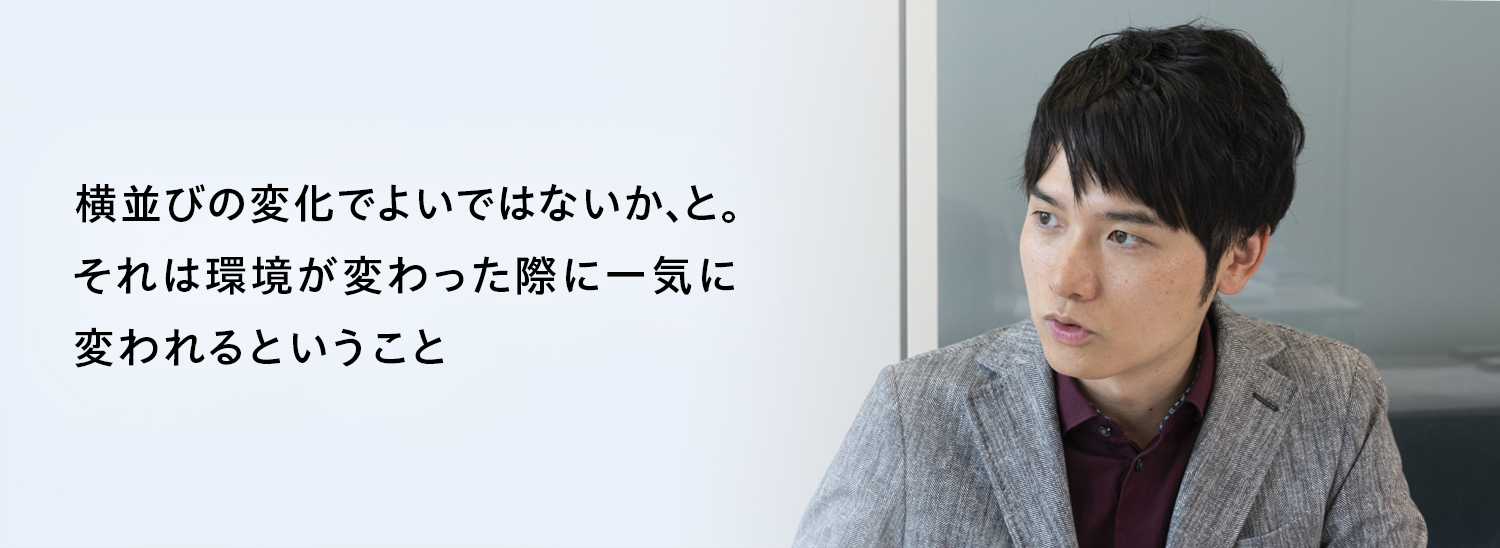 とはいえ、地方の経営者は人手不足をより深刻に実感しています。今年初めて女性ドライバー5人を採用した山形県の中堅物流会社の社長は、取引先に申し入れをする機会が増えたそうです。というのも、トラックドライバーが女性だと、重い荷物の積み下ろしを取引先の人に手伝ってもらう必要が生じます。しかし、ほんの数分の補助を拒む取引先がいるため、社長自らが協力要請する必要が生じたと。この社長は「お客さんに仕事を手伝わせるのはおかしい、という思い込みが女性やシニアの活躍を阻む壁になっていたのかもしれない」という気づきを得られたようです。
とはいえ、地方の経営者は人手不足をより深刻に実感しています。今年初めて女性ドライバー5人を採用した山形県の中堅物流会社の社長は、取引先に申し入れをする機会が増えたそうです。というのも、トラックドライバーが女性だと、重い荷物の積み下ろしを取引先の人に手伝ってもらう必要が生じます。しかし、ほんの数分の補助を拒む取引先がいるため、社長自らが協力要請する必要が生じたと。この社長は「お客さんに仕事を手伝わせるのはおかしい、という思い込みが女性やシニアの活躍を阻む壁になっていたのかもしれない」という気づきを得られたようです。
アトキンソン:「女性活躍」と言いますが、要は安い労働者として女性に目をつけた、ということではないですか。外国人就労者に関しても同じことが言えます。農家にどういう外国人材が欲しいのか尋ねると、できるだけ安く雇用できる人だと答えます。つまり、奴隷のように使える人が欲しい、というわけです。廉価な人材をこき使うのが経営能力だと勘違いしている経営者の悪しき体質が踏襲されています。
古屋:日本の経営者は、若者、女性、高齢者、外国人就労者に安価な 労働力の供給を頼ってきました。高齢者は再雇用制度により再雇用前と比べて約4割減の給与で同じ仕事をさせられますが、この仕組みを改変する企業も出ており、私は安い労働力で利益を上げるビジネスモデルは限界だと感じています。
アトキンソン:高齢者が働くと年金を差し引かれる制度もありますね。なぜ、そんなことをするのかと思います。
古屋:在職老齢年金制度ですね。他にも、パート労働者らの「年収の壁」など労働力の供給にゆがみを生んでいる制度はたくさんあります。人手が余っていた時代の名残です。
人に投資ができる企業を育てる
アトキンソン:高齢化や人口減少はとうに予測されていたのに、なぜ対応してこなかったのか不思議です。強調したいのは、労働者はなぜ、賃金水準が低い企業を存続させることしか頭にない経営者の犠牲にならなければいけないのか、ということです。経済合理性とは無関係に存続している企業で働く労働者は、そのビジネスモデルを維持するために低賃金労働を強いられています。
古屋:「労働者よ、声を上げろ」とおっしゃっているわけですね。ただ、日本の労働者が経営者と1対1で交渉するのはハードルが高いのが現実です。私が提案したいのは、労働条件の交渉に際して労働者をサポートする機能の充実です。とりわけ、中小企業や非正規の労働者の交渉を公的に支援する必要があります。本当は労働組合の機能だと思いますが……。
日本は総力戦の対応が求められています。私たちは昨年、2040年に1100万人の働き手不足が生じるという労働需給シミュレーションを発表しました。
アトキンソン:1100万人という数字は現在の産業構造を維持した場合だと思いますが、産業構造が変わればどうなるのかが気になります。
古屋:産業構造の転換は必須です。スタートアップの経営者に労働供給制約の話をする機会がありましたが、想像していたものとまったく違う反応でした。スタートアップの経営者たちは、今の状況である「人手がまったく足りない」ことを「人手を省いて生産性を上げる」という社会課題解決のビジネスチャンスと捉えていました。
アトキンソン:経営者の反応の違いは、年齢の違いも作用していませんか。日本の社長の平均年齢は数年前、史上初めて60歳を超えました。私自身、振り返っても20代で考えていたことと60歳に近づく今と では大きく変化しています。新しいことに挑戦するのではなく、これまで築いてきたものを守ろうとします。日本は諸外国に比べて政治家の高齢化も目立ちますが、政策立案にも影響しているのではないですか。
古屋:私もその可能性はあると思います。とはいえ、健康寿命が延びて長生きする高齢者が増えることは本来、歓迎すべきことです。私は日本に住むさまざまな人が、寿命が長くなることを喜び満喫することができる国にしたいと思っているのですが、そのためには何が必要とアトキンソンさんはお考えですか。
アトキンソン:若い人の給料を上げるのが一番のポイントではないでしょうか。世界中でデジタルネイティブ世代の存在価値が増しています。小西美術は高卒の初任給を17万円から21万円に引き上げました。もともとの額が少ないため大幅アップしても経営に大した影響はありません。若い人たちの消費は旺盛ですから経済の循環にも寄与します。あと、利益を上げている中堅企業にどこまで労働者を集められるかも今後の注目点です。日本の最大の問題点は分散構造によって優良な中堅企業が育っていないことだと思います。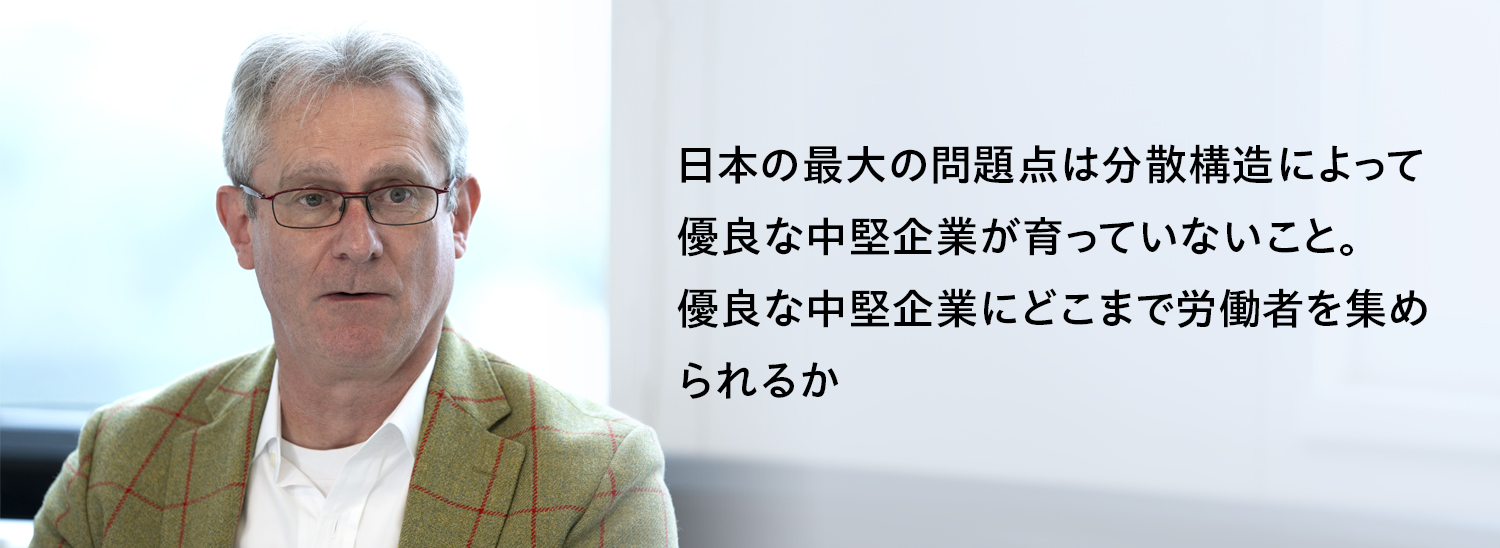 古屋:経済の分散もさることながら、労働者一人ひとりが意思決定主体になり得ていないことも問題ですね。構造的な人手不足をどう乗り越えていくかは、日本に暮らすあらゆる人が向き合わなければいけない課題です。残された時間は限られています。
古屋:経済の分散もさることながら、労働者一人ひとりが意思決定主体になり得ていないことも問題ですね。構造的な人手不足をどう乗り越えていくかは、日本に暮らすあらゆる人が向き合わなければいけない課題です。残された時間は限られています。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

