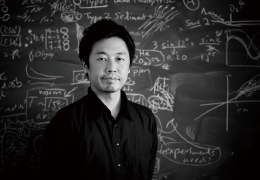Macro Scope
恐竜は、絶滅していない

 恐竜学者 真鍋 真氏
恐竜学者 真鍋 真氏
Manabe Makoto 横浜国立大学卒業後、米国イェール大学で修士号を、英国ブリストル大学で博士号取得。現在、国立科学博物館標本資料センターおよび分子生物多様性研究資料センターセンター長。恐竜など、中生代の爬虫類、鳥類の進化を研究しながら、特別展の企画や図鑑の監修などを数多く手がける。『大人のための恐竜教室』(ウェッジ、山田五郎氏と共著)などの著書がある。
多くの人が子ども時代に、一度は胸をときめかせたことがある“恐竜”という古代の巨大生物。近年、研究が進み、実は大人世代の知る恐竜の常識はもはや過去のものになりつつある。特に驚かされるのは、「恐竜は絶滅していない」という事実だ。日本を代表する恐竜学者、真鍋真氏に、恐竜研究の今と、その成果が私たちに教えてくれることを聞いた。
― 子どもが読む恐竜図鑑を見て、多くの親が「自分が知っているのと違う」と驚きます。どんな新しい発見があったのでしょうか。
恐竜が生きた時代は、中生代といわれるおよそ2億5000万年前から6600万年前です。従来は、恐竜は6600万年前に絶滅したといわれてきました。しかし、現在では「多くの種(しゅ)は滅んだが、一部は鳥に進化して生き残っている」と考えられるようになった。これが最大の変化です。
鳥に進化したことの兆候を示す記念碑的恐竜は、1969年に命名されたデイノニクスです。米国のジョン・オストロム博士が、その手首の形状を見て、鳥に近いと考えたのです。
足の爪を武器として使っていたようなのですが、それを使って何度も相手に飛び蹴りするには持久力がないと難しいため、鳥と同様に、スタミナのある恒温動物だったのではないかと仮説を立てたのです。
もう1つの新発見は、恐竜に羽毛が生えていたということです。かつてはすべての恐竜はワニやトカゲなどと同様に鱗で覆われていたと考えられていましたが、1996年に中国で羽毛が生えた恐竜の化石が発見されたのです。従来は、爬虫類には鱗があり、羽毛があれば鳥だと決めつけていたのですが、そうとは言えなくなってしまいました。では恐竜と鳥を分けるのは翼の有無か、とも思われたのですが、そうでもないのです。ミクロラプトルという立派な翼を持つ恐竜に関する論文が2003年に発表されて、どこまでが恐竜でどこからが鳥類か、その境界線が引けないくらい連続的な進化があったことが明らかになりました。
色がわかり“生き物”としての恐竜が見えてきた
― 2010年に駆け巡った「恐竜の色がわかった」というニュースは、一般の人々にも衝撃を与えました。
重要な発見をしたのは米国の大学院生です。恐竜の羽毛を電子顕微鏡で拡大して見たところ、表面に細長いツブツブと、丸いツブツブがあることに気づきました。その大学院生は現代に生きる鳥の羽毛の表面にも、同じものがあることを確認したのです。そのツブツブはメラノソーム(メラニン色素を含む小胞)で、現代の鳥の2種のツブツブの割合を恐竜の羽毛に適用すれば、色がわかるというわけです。
色がわかったのは、アンキオルニスという頭のてっぺんが赤い恐竜でした。現代のクマゲラも頭のてっぺんが赤いのですが、成熟したオスはそれが額から後頭部にかけた広い範囲に及ぶという特徴を持ちます。その赤が鮮やかで派手なほうが、メスに見つけてもらいやすい。同じ特徴が、恐竜にも備わっていたと考えられています。
また、背中は濃い色、腹は薄い色をした恐竜も発見されています。これは天敵に襲われないためのカムフラージュと考えられます。このような恐竜は森林地帯ではなく平原に棲んでいた可能性が高い。色がわかると、そこから恐竜の生態がわかるようになります。“化石”としてではなく、“生き物”としての恐竜の姿が露わになってきているのです。
― 先生ご自身も、ティラノサウルスに関する重要な発見をされていらっしゃいますね。
ティラノサウルスは、およそ6800万年前から6600万年前という中生代の最末期に、主に北米大陸で隆盛を極めた肉食恐竜です。ところが福井県や岐阜県での調査で、もっと古い地層からティラノサウルス類の特徴を持つ歯の化石が見つかったのです。しかし、1億3000万年前のアジアにティラノサウルス類が生息していたはずはない、となかなか受け入れられませんでした。そんな折、学会で会った中国の著名な研究者、徐星教授が、「君が正しかったことを証明してやる」と言うのです。彼は、中国の1億2000万年前の地層から体長1メートル80センチくらいの小柄なティラノサウルス類の化石を発見しました。その歯は私が発見したものと同じ形状だったのです。
北米のティラノサウルスは全長12メートルを超える巨大恐竜です。約1億年前にユーラシア大陸と北米大陸が地続きとなり、アジアで大型化したものが、北米にわたってさらに大型化したのではないかと考えられています。
賢ければ生き残れるというわけではない
― 鳥として一部の遺伝子は残ったとはいえ、なぜそれほどまでに隆盛を極めた巨大生物が絶滅したのでしょう。隕石衝突説は、今も原因として有力なのですか。
私自身、最も関心のある領域は“絶滅の時代の地層”です。6600万年前の、多くの恐竜が絶滅した時期を、“第5の大量絶滅”と呼びますが、これが隕石衝突によって起こったということは否定されていません。
隕石が浅い海に落ち、地球の表面に大きなクレーターができたのと同時に、隕石と地表の破片が水蒸気と一緒に大気圏に巻き上げられて厚い層ができました。これによって寒冷化が進み、同時に太陽光線が届かないために植物が光合成できなくなりました。このとき、恐竜を含めて動植物の75%以上の種が絶滅したといわれています。ただし、地球上の食物が激減したために小さな生き物にとって有利で、巨大な恐竜は生き残れなかったというだけの話ではないともわかってきました。
たとえば鳥類では、歯のある鳥が絶滅し、クチバシを持つ鳥は生き残っています。クチバシを持った鳥は木の実のタネまで割って食べることができたし、歯よりもクチバシのほうが形成が早く、卵からより早く孵化することができました。いろんな意味で生存確率が高かったといえるでしょう。
多くの恐竜が滅んでいくなか、なぜ、歯のない鳥が生き残っていったのか。いろんな研究者がいろんな仮説を唱える。その繰り返しを経て、何が有利で、何が不利になったのかが徐々に明らかになってきたのです。恐竜の絶滅を考えるなかで、私たちは大切なことを教わっていると思っています。
― どんなことでしょうか。
今、私たちが生きているこの時代は、“第6の大量絶滅”の時代だといわれています。絶滅させている犯人は、私たち人間です。
従来は、恐竜は変温動物でそれほど知能が発達していなかったために、寒冷期にみんな絶滅してしまったと考えられていました。種として生き抜くには“賢さ”が必要だと。
ところが生き物の栄枯盛衰をつぶさに見ると、決してそんな単純なことではないのだとじわじわと気づいてきます。ホモ・サピエンスは賢さを武器にたくさんの道具を作って繁栄してきましたが、その裏で、多くの種を絶滅の危機に追いやっている。つまり、繁栄しすぎた結果、生物の多様性を失わせ、自身の存続自体を危うくしている可能性があるのです。
合意形成のためではない言葉のキャッチボール
― 既知のことをそのまま受け入れるだけでなく、本当にそうなのかという問いを立てられるかどうかが重要ですね。
恐竜の分野の伝統的な研究方法は、積み重ねられた研究論文を読み、そのなかで誰も気づいていない事実を見つけ、仮説を立て、検証して、論文を書くというもの。一人で完結する世界です。しかし、そのやり方だけで新しい事実を見つけるのは困難だと英国留学時代に気づきました。
当時、午前11時と午後4時に研究者が集まるティータイムがありました。週に1回届く「Nature」「Science」といった科学雑誌をみんなで回し読みしながら、議論するのです。
ほとんどは「こんな研究はつまらない」とか「間違っている」とか、“因縁”をつけているようなもので、最初は「人の悪口を言い合うのはいかがなものか」と思っていたのですが、実は、そこで行われる言葉のキャッチボールによって、思いもよらない新しい視点を得ることが多く、議論をすることの効果に気づいたのです。
帰国後、私はここ、国立科学博物館に就職しました。当時はまだ、多くの大学では恐竜を研究する環境など整っていませんでしたが、ここは化石や標本の多いとても恵まれた場所です。そこで、休館日に修士や博士課程の学生を集めた勉強会を始め、みんなで恐竜学の基礎を学び、議論できる場を作りました。
 恐竜が鳥類に進化したという発見のきっかけとなったデイノニクスの化石。国立科学博物館では、その手や足のカギツメの形まではっきり見えるように、自分で好きな角度に回転させて観察できるようにしている。2019年7月に始まる恐竜博でも、恐竜の“新発見”の理解を促すために、展示にさまざまな工夫をしているという。
恐竜が鳥類に進化したという発見のきっかけとなったデイノニクスの化石。国立科学博物館では、その手や足のカギツメの形まではっきり見えるように、自分で好きな角度に回転させて観察できるようにしている。2019年7月に始まる恐竜博でも、恐竜の“新発見”の理解を促すために、展示にさまざまな工夫をしているという。
― その勉強会から多くの若手の恐竜研究者が巣立ち、多様な研究で成果を出し始めていると聞いています。
会話のおもな役割は、企業組織では合意形成なのでしょうが、研究では合意形成の優先順位は低いかもしれません。自分で知りたいこと、もやもやしていることをみんなでひたすら議論して、そこから刺激を受ければいいのです。若い研究者が意見交換できる場の重要性をあらためて今、感じています。
Text=入倉由理子 Photo=刑部友康 Illustration=内田文武
After Interview
取材チームの驚嘆の声一つひとつに反応して、喜んで解説を加えてくれる真鍋氏は、博物館職員の方によれば“子どもたちのアイドル”なのだそうだ。「最近は、女の子の恐竜ファンも増えています。多くの男の子と視点が違って、恐竜の子育てや生活に興味を持ってくれるんです」と嬉しそうに話してくれる。
科学は進歩し続けている。これまでの定説を覆す新しい発見と仮説の登場で、私たちの子どものころからの常識の一部はいつの間にか塗り替えられている。その背後に、若い研究者を見守り、鼓舞し、対話を促してくれた“おとな”の存在がある。会社組織も、そうでありたいものだ。
聞き手=石原直子(本誌編集長)


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ